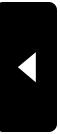2017年06月07日
2017 第14節 : 大宮アルディージャ VS サガン鳥栖
今節は、リーグ戦アウェー未勝利と言う重荷を背負い、前の試合のルヴァンカップ甲府戦(アウェー)の勝利を勢いとして、勝ち点3を奪いに乗り込んだNACK5スタジアムでの試合でした。フリーキックからのチョドンゴンのヘディングで幸先よく先制したものの、監督が変わって攻撃サッカーを標榜した大宮の圧力に耐え切れず同点ゴールを喫し、ホームでの定番となった「ウノゼロ」をアウェーでもという鳥栖サポーターの思いは届かず、同点のまま試合終了のホイッスルが鳴ってしまいました。鳥栖としては、リスクを取って得点を取りにいくような攻めはしなかったので、ひとまず最低限の勝ち点は得られたのかなというところです。
■ 上下の連動・左右の連動によるディフェンスの操作
この試合の大宮の動きとして非常に特徴的だと感じたのは、縦への速さです。ボールを持って攻撃のチャンスと見ると、全体が一気呵成に押し上げる動きを見せていました。これに対して鳥栖はどのような動きを見せたかと言うと、裏へと抜けていく大宮の選手をキャッチアップするために、ディフェンスラインの全体が一斉にリトリートして対応します。本来、1人や2人の裏へと抜ける動きであれば、捨てておけば勝手にオフサイドになるため気にしすぎる必要もなく、ディフェンスライン全体を下げる事自体が逆にリスクとなってしまうのですが、大宮のこの動きのタイミングの良さとかける人数の圧力によって、決して鳥栖のディフェンスラインが無視できない状況を作り出していました。特に、1列目・2列目のプレスが交わされてしまった状態になるとボールに対するプレッシャーがなくなるので、そこからのボール保持者へのアタックと裏へ抜ける動きへのケアと言う、非常に難しい選択を迫られていました。
大宮とすれば、もちろん、ファーストプランとして前線へ飛び出す選手たちが良い状態を作り出せばそこにパスを出せば良いのですが、実はセカンドプランの方が大事でありまして、裏への飛び出しで押し下がったディフェンスラインの前のスペースを利用することが影の狙いとなります。サイドからのドリブルの切り込みや、抜け出そうとした選手の内の一人が下がって受けることによって、ゴール前での基点を作ることができます。鳥栖も中央は非常に堅く守っていたため、ミドルシュートを許すまでには至らなかったのですが、逆サイドは大きく空いている状態ですので、中央から外へ展開されるシーンは数多く作られてしまいました。




■ 1と1の動き
大宮の攻撃の生命線は、やはり4-1-4-1のアンカーとフォワードです。鳥栖のプレスを交わして人がいないところをフォローする役割であったり、攻撃のスイッチを入れるための展開を生む役割であったり、様々なタスクをこなしていました。
前半は長谷川、後半は大山がその役割を担っていましたが、長谷川はどちらかというとディフェンスラインのフォローをする形が多く、起点の位置が低い状態でした。伊藤監督はそれを良しとせず、より前での裁きを求めていた模様で、後半からは大山がそのポジションを担います。
大山が意識していたのは、鳥栖の第1列を交わした状態でボールを受ける事です。豊田・チョドンゴン・鎌田の壁が目の前に立ったままで攻撃を仕掛けるのではなく、アンカーの動きを工夫させて少しでも前で(鳥栖の第1列の守備を抜けた状態で)ボールを受けることを要求していました。大山がボールを受ける位置(対峙する相手)が義希であれば、大宮のビルドアップのファーストステップとしては成功でした。
その動きと攻撃が上手くいったシーンがこちらです。






大宮は、ボールを受ける前の縦に抜ける動き、引いて受ける動きのみならず、横に広がる動きも活用してスペースを作り出すことによって、さらに味方が動ける範囲が広がりました。縦へスピードを上げられない時は、横の動きによって鳥栖の選手を揺さぶり、鳥栖の選手の疲労度はかなり蓄積して行きました。後半になってマテウスが入ってサイドの裏に抜ける動きが目立ちましたが、彼のスピードは非常に脅威でした。


■ 攻撃の再現性
相手の守備が組織的であればあるほど、一定のアルゴリズムによってスペースが空く瞬間を作ることができます。そのアルゴリズムをチームの中で全員が察知・共有することによって、再現性のある攻撃が生まれます。これが相手を崩す「パターン」をつくるということです。この試合では、右サイドバックの小林が、再現性のある攻撃を何度も作っていました。残念ながら、最後の崩しのところが上手くいかずにゴールという結果までは生まれませんでしたが、ゴールエリア内への侵入と言うチャンスまでは確実に作り出していました。




最終的には引き分けに終わってしまいましたが、攻撃の芽というものは、鳥栖も大宮も非常に数多く作っていました。その芽を目に見えるシュートという形に作ったのは大宮の方がシュート12本と多かったですが、鳥栖もシュート数5本という数字以上に惜しいところまで切り込むシーンも多く、非常に見ごたえのある試合ではありました。ただ、試合全体で見ると大宮の方が、攻撃のダイナミクスさというのを感じるシーンは多く、鳥栖の選手にボールを奪われてからのネガティブトランジションの場面でも積極的にボールにアプローチして奪い反すという気迫が見て取れました。


試合全体を通じた大宮のアグレッシブさに呼応するように、鳥栖としては試合終盤では最終ラインの人数を増やして守りきるという選択をしたことによって、勝利に対して消極的であるという風に眼に映った人もいたかもしれません。また、ボールを奪いに行く、もしくはしっかりと引いて構えるという、共通の意思をしっかり持って局面を乗りきるという形がもう少し欲しかった気がします。
アンカーを捕まえきれなかったシーンが多くなった時に、チームの中でどうやってカバーするのかという守備のポイントの共有をもっと図ることができていれば、少し展開は変わっていたかもしれません。それは、積極的に前に出るという選択ではなく、フォワードと鎌田が少し引いてスペースを消して大山と江坂を動けなくするという選択もあり得たのではないかと。何となく前からボールを奪いに行った時に逆にピンチになっているシーンが見受けられました。
また、選手を替えなかったことに対する批判はありますが、彼らを交替することによる失点のリスクと得点のチャンスを天秤にかけた結果が、交代をしないという選択だったのでしょう。豊田、鎌田の体力面に関するところはありますが、チームのエースを替えるというモチベーションの変化も秤の重りのひとつでありますから、非常に難しい所です。いずれにしても、ホームで大宮を迎える際には、伊藤監督の戦術が更に浸透している状態であることが考えられるので、今回よりも更に守備の集中力を上げてよい試合をしてほしいなと思います。
<画像引用元:DAZN>
■ 上下の連動・左右の連動によるディフェンスの操作
この試合の大宮の動きとして非常に特徴的だと感じたのは、縦への速さです。ボールを持って攻撃のチャンスと見ると、全体が一気呵成に押し上げる動きを見せていました。これに対して鳥栖はどのような動きを見せたかと言うと、裏へと抜けていく大宮の選手をキャッチアップするために、ディフェンスラインの全体が一斉にリトリートして対応します。本来、1人や2人の裏へと抜ける動きであれば、捨てておけば勝手にオフサイドになるため気にしすぎる必要もなく、ディフェンスライン全体を下げる事自体が逆にリスクとなってしまうのですが、大宮のこの動きのタイミングの良さとかける人数の圧力によって、決して鳥栖のディフェンスラインが無視できない状況を作り出していました。特に、1列目・2列目のプレスが交わされてしまった状態になるとボールに対するプレッシャーがなくなるので、そこからのボール保持者へのアタックと裏へ抜ける動きへのケアと言う、非常に難しい選択を迫られていました。
大宮とすれば、もちろん、ファーストプランとして前線へ飛び出す選手たちが良い状態を作り出せばそこにパスを出せば良いのですが、実はセカンドプランの方が大事でありまして、裏への飛び出しで押し下がったディフェンスラインの前のスペースを利用することが影の狙いとなります。サイドからのドリブルの切り込みや、抜け出そうとした選手の内の一人が下がって受けることによって、ゴール前での基点を作ることができます。鳥栖も中央は非常に堅く守っていたため、ミドルシュートを許すまでには至らなかったのですが、逆サイドは大きく空いている状態ですので、中央から外へ展開されるシーンは数多く作られてしまいました。




■ 1と1の動き
大宮の攻撃の生命線は、やはり4-1-4-1のアンカーとフォワードです。鳥栖のプレスを交わして人がいないところをフォローする役割であったり、攻撃のスイッチを入れるための展開を生む役割であったり、様々なタスクをこなしていました。
前半は長谷川、後半は大山がその役割を担っていましたが、長谷川はどちらかというとディフェンスラインのフォローをする形が多く、起点の位置が低い状態でした。伊藤監督はそれを良しとせず、より前での裁きを求めていた模様で、後半からは大山がそのポジションを担います。
大山が意識していたのは、鳥栖の第1列を交わした状態でボールを受ける事です。豊田・チョドンゴン・鎌田の壁が目の前に立ったままで攻撃を仕掛けるのではなく、アンカーの動きを工夫させて少しでも前で(鳥栖の第1列の守備を抜けた状態で)ボールを受けることを要求していました。大山がボールを受ける位置(対峙する相手)が義希であれば、大宮のビルドアップのファーストステップとしては成功でした。
その動きと攻撃が上手くいったシーンがこちらです。






大宮は、ボールを受ける前の縦に抜ける動き、引いて受ける動きのみならず、横に広がる動きも活用してスペースを作り出すことによって、さらに味方が動ける範囲が広がりました。縦へスピードを上げられない時は、横の動きによって鳥栖の選手を揺さぶり、鳥栖の選手の疲労度はかなり蓄積して行きました。後半になってマテウスが入ってサイドの裏に抜ける動きが目立ちましたが、彼のスピードは非常に脅威でした。


■ 攻撃の再現性
相手の守備が組織的であればあるほど、一定のアルゴリズムによってスペースが空く瞬間を作ることができます。そのアルゴリズムをチームの中で全員が察知・共有することによって、再現性のある攻撃が生まれます。これが相手を崩す「パターン」をつくるということです。この試合では、右サイドバックの小林が、再現性のある攻撃を何度も作っていました。残念ながら、最後の崩しのところが上手くいかずにゴールという結果までは生まれませんでしたが、ゴールエリア内への侵入と言うチャンスまでは確実に作り出していました。




最終的には引き分けに終わってしまいましたが、攻撃の芽というものは、鳥栖も大宮も非常に数多く作っていました。その芽を目に見えるシュートという形に作ったのは大宮の方がシュート12本と多かったですが、鳥栖もシュート数5本という数字以上に惜しいところまで切り込むシーンも多く、非常に見ごたえのある試合ではありました。ただ、試合全体で見ると大宮の方が、攻撃のダイナミクスさというのを感じるシーンは多く、鳥栖の選手にボールを奪われてからのネガティブトランジションの場面でも積極的にボールにアプローチして奪い反すという気迫が見て取れました。


試合全体を通じた大宮のアグレッシブさに呼応するように、鳥栖としては試合終盤では最終ラインの人数を増やして守りきるという選択をしたことによって、勝利に対して消極的であるという風に眼に映った人もいたかもしれません。また、ボールを奪いに行く、もしくはしっかりと引いて構えるという、共通の意思をしっかり持って局面を乗りきるという形がもう少し欲しかった気がします。
アンカーを捕まえきれなかったシーンが多くなった時に、チームの中でどうやってカバーするのかという守備のポイントの共有をもっと図ることができていれば、少し展開は変わっていたかもしれません。それは、積極的に前に出るという選択ではなく、フォワードと鎌田が少し引いてスペースを消して大山と江坂を動けなくするという選択もあり得たのではないかと。何となく前からボールを奪いに行った時に逆にピンチになっているシーンが見受けられました。
また、選手を替えなかったことに対する批判はありますが、彼らを交替することによる失点のリスクと得点のチャンスを天秤にかけた結果が、交代をしないという選択だったのでしょう。豊田、鎌田の体力面に関するところはありますが、チームのエースを替えるというモチベーションの変化も秤の重りのひとつでありますから、非常に難しい所です。いずれにしても、ホームで大宮を迎える際には、伊藤監督の戦術が更に浸透している状態であることが考えられるので、今回よりも更に守備の集中力を上げてよい試合をしてほしいなと思います。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
20:54
│Match Impression (2017)
2017年06月04日
2017 第13節 : サガン鳥栖 VS コンサドーレ札幌
『値段のないスタジアム』という企画で注目を集めた札幌戦。初めてスタジアムを訪れた方も多かったかと思いますが、互いにスペースをつぶしあって相手のミス待ちによってシュートチャンスを狙い、そして最後は猛攻を耐えて守りきるという、なかなかしぶめの展開となりましたので、この試合にどのくらいの面白さを感じ、どのくらい集金できたかはわかりませんが、この企画の要点は集金額ではなく、「また試合に来ようかな」と一人でも多くの人に思って頂けることですので、将来的な観客増につながることを期待しています。
さて、試合から1週間も経っているので簡単にこの試合のポイントを整理しました。
鳥栖も札幌も守り方は整理されているので、自分たちのストロングポイントだけを用いた攻め方だけではなかなか得点できず、
① 守備が整理されているからこそ相手の動きのパターンを読んで攻め側主導でスペースを作りだす
② 整理されている守備にミスやほころびが生じたときに、そこにチーム全体が気づいて一気にシュートまで持っていく
という、より多くの工夫が必要です。
まず①について。
私が思う、前半のキーポイントは福田でした。鳥栖のセンターバック2名に対して札幌の2トップがプレスに入ります。そこからサイドに流した時には札幌のハーフが寄せてくる。寄せられたときにそのままセンターバックに戻すと金園、戸倉の更なるプレスの餌食になるのでサイドバックからのつなぎが重要なのですが、そこを鳥栖のセンターハーフ3人がうまくポジショニングを取ってボールを受けていました。
ちょっと動きが変わったなと思ったのは、義希が中央で受けて相手のハーフをひきつけたスペースに福田がうまく中央に流れ込んでつないでいた場面があったのですが、15分頃だったか、ベンチのマッシモさんが直接福田を呼んで
「サイドに流れなさい」
という指示。
これにより、福田はサイドに幅をとる動きに変わります。右サイドは純然たる、小林が手前で福田が前という縦の関係が築かれます。
ただ、左サイドはその縦の関係が少し違っていて、原川がサイドに幅を取ることもあれば、吉田と原川が入れ替わって、吉田が幅を取ることもあり。
おそらく、ボールを持って縦に勝負するに当たっては、「吉田>原川」「福田>小林」という序列があるのでしょう。スピードを生かすならばこの並びにするのもうなずけます。
そして、マッシモさんが指示したこの福田に幅を取らせるという利点は、小林、義希に対して札幌のセントラルハーフをひきつけ、そこで福田を大外につけておくことによって、相手のウイングバック(菅)を引き出すこと。(左サイドでは、吉田が早川を引っ張り出すこと)これにより、札幌のセンターバックはサイドのスペースも気にしなければならないし、豊田の高さも気にしなければならないという、数多くの「タスク」を考えなければならなくなります。
鳥栖は、ロングボールで何回か豊田のシュートまでつながったシーンがありましたが、この双方のパターンを考えなければならないという状況が、長いボールに対する処理の一歩が出遅れ、うまく裏を取れたということにつながります。
鳥栖として、もう一つ惜しかったのは、せっかくウイングバックを引き出したのに、そのスペースを使うタイミングが前線の3人とあっていなかったこと。特に、チョドンゴンがサイドに流れて受ける動きをもっと多く見せてくれるとそこが起点になって、最後は豊田が中央でズドンという構図が作れたのですが、どうもチョドンゴンは中央で受けたいプレイヤーの模様。そういう意味では、すぐにサイドに流れるイバルボの方が、札幌戦でははまっていたかもしれません。
もしくは、カウンターの場面も含め、せっかくウイングバックの裏にスペースを作ってそこに鎌田やチョドンゴンなどが走りこんだときには、そこに鳥栖の選手が気づかずに(もしくはおとりとして利用して)、中央にドリブルで切り込んで玉砕するシーンとかもあり(特に福田が多かった)。サイドの深いところで鎌田にボールを預けたら、相手につかれてもクロスまで持って行けるスキルがあるので、考えすぎずに簡単に使っても良いのですけどね。
そして、得点シーンは②の動きでした。
フリーキックで長いボールをゴール前に送り込むと見せかけて、つなぎ始めることによって、札幌の陣形が大きく崩れます。長いボールに備えて、都倉や金園がゴール前にはっていたため、センターバックからのつなぎに対して札幌のハーフの選手が大きく前にひっぱりだされます。そこからはひとつひとつ持ち場がずれている札幌のスペースをしっかりつくだけでよく、原川⇒義希⇒吉田というパスの流れは非常に見事でした。鎌田のゴールが決まった時に、一番ゴールに近い位置を守っていたのが都倉というのがこのゴール(通常状態ではない札幌の陣形)を物語っています。
札幌とすれば、鳥栖が原川に対して繋いだときに大きくプレスで前進した選手がいたのですが、それが果たして必要だったのかというところが反省点でしょう。味方が連動して押し上げできていないときだったので、どこまで人を気にするかというのはありましたが、結果的に、原川に対するあのプレスによって義希のスペースをつくり、義希に対して横山がつかなければならなくなって横山が後手を踏んで前にプレスに入ったときに、吉田が侵入するスペースを作ることになってしまいました。
後半は、鳥栖が引き気味に構え、前半からよく動いていた鳥栖のセンターハーフの前への推進力が弱まった点、豊田が(気を利かせて)2列目や3列目に戻って守備をしたことによってセカンドボールを拾うエリアに人が少なくなってしまった点、札幌が都倉というストロングを生かすために長いボールが多くなってしまった点、などによって押し込まれてしまうような状態になっていたのですが、崩された形でのクロスを上げられることもなく、最後はフランコも投入してしっかりと中央を固めて勝利をもぎ取りました。
互いにつぶしあって、攻撃もうまくいきそうだけども最後の詰めが甘くてシュートまで行けないところも多くあり、最後は完全にリトリートしきってしまって猛攻を食らうという、ハラハラドキドキというか…なかなかストレスのたまる試合でした(笑)
勝ち点を重ねて混戦となっている上位を少しでも覗きこむか、それとも残留争いに引きづり込まれる序曲となってしまうかという試合でしたので、ホント勝ってよかったです。
さて、試合から1週間も経っているので簡単にこの試合のポイントを整理しました。
鳥栖も札幌も守り方は整理されているので、自分たちのストロングポイントだけを用いた攻め方だけではなかなか得点できず、
① 守備が整理されているからこそ相手の動きのパターンを読んで攻め側主導でスペースを作りだす
② 整理されている守備にミスやほころびが生じたときに、そこにチーム全体が気づいて一気にシュートまで持っていく
という、より多くの工夫が必要です。
まず①について。
私が思う、前半のキーポイントは福田でした。鳥栖のセンターバック2名に対して札幌の2トップがプレスに入ります。そこからサイドに流した時には札幌のハーフが寄せてくる。寄せられたときにそのままセンターバックに戻すと金園、戸倉の更なるプレスの餌食になるのでサイドバックからのつなぎが重要なのですが、そこを鳥栖のセンターハーフ3人がうまくポジショニングを取ってボールを受けていました。
ちょっと動きが変わったなと思ったのは、義希が中央で受けて相手のハーフをひきつけたスペースに福田がうまく中央に流れ込んでつないでいた場面があったのですが、15分頃だったか、ベンチのマッシモさんが直接福田を呼んで
「サイドに流れなさい」
という指示。
これにより、福田はサイドに幅をとる動きに変わります。右サイドは純然たる、小林が手前で福田が前という縦の関係が築かれます。
ただ、左サイドはその縦の関係が少し違っていて、原川がサイドに幅を取ることもあれば、吉田と原川が入れ替わって、吉田が幅を取ることもあり。
おそらく、ボールを持って縦に勝負するに当たっては、「吉田>原川」「福田>小林」という序列があるのでしょう。スピードを生かすならばこの並びにするのもうなずけます。
そして、マッシモさんが指示したこの福田に幅を取らせるという利点は、小林、義希に対して札幌のセントラルハーフをひきつけ、そこで福田を大外につけておくことによって、相手のウイングバック(菅)を引き出すこと。(左サイドでは、吉田が早川を引っ張り出すこと)これにより、札幌のセンターバックはサイドのスペースも気にしなければならないし、豊田の高さも気にしなければならないという、数多くの「タスク」を考えなければならなくなります。
鳥栖は、ロングボールで何回か豊田のシュートまでつながったシーンがありましたが、この双方のパターンを考えなければならないという状況が、長いボールに対する処理の一歩が出遅れ、うまく裏を取れたということにつながります。
鳥栖として、もう一つ惜しかったのは、せっかくウイングバックを引き出したのに、そのスペースを使うタイミングが前線の3人とあっていなかったこと。特に、チョドンゴンがサイドに流れて受ける動きをもっと多く見せてくれるとそこが起点になって、最後は豊田が中央でズドンという構図が作れたのですが、どうもチョドンゴンは中央で受けたいプレイヤーの模様。そういう意味では、すぐにサイドに流れるイバルボの方が、札幌戦でははまっていたかもしれません。
もしくは、カウンターの場面も含め、せっかくウイングバックの裏にスペースを作ってそこに鎌田やチョドンゴンなどが走りこんだときには、そこに鳥栖の選手が気づかずに(もしくはおとりとして利用して)、中央にドリブルで切り込んで玉砕するシーンとかもあり(特に福田が多かった)。サイドの深いところで鎌田にボールを預けたら、相手につかれてもクロスまで持って行けるスキルがあるので、考えすぎずに簡単に使っても良いのですけどね。
そして、得点シーンは②の動きでした。
フリーキックで長いボールをゴール前に送り込むと見せかけて、つなぎ始めることによって、札幌の陣形が大きく崩れます。長いボールに備えて、都倉や金園がゴール前にはっていたため、センターバックからのつなぎに対して札幌のハーフの選手が大きく前にひっぱりだされます。そこからはひとつひとつ持ち場がずれている札幌のスペースをしっかりつくだけでよく、原川⇒義希⇒吉田というパスの流れは非常に見事でした。鎌田のゴールが決まった時に、一番ゴールに近い位置を守っていたのが都倉というのがこのゴール(通常状態ではない札幌の陣形)を物語っています。
札幌とすれば、鳥栖が原川に対して繋いだときに大きくプレスで前進した選手がいたのですが、それが果たして必要だったのかというところが反省点でしょう。味方が連動して押し上げできていないときだったので、どこまで人を気にするかというのはありましたが、結果的に、原川に対するあのプレスによって義希のスペースをつくり、義希に対して横山がつかなければならなくなって横山が後手を踏んで前にプレスに入ったときに、吉田が侵入するスペースを作ることになってしまいました。
後半は、鳥栖が引き気味に構え、前半からよく動いていた鳥栖のセンターハーフの前への推進力が弱まった点、豊田が(気を利かせて)2列目や3列目に戻って守備をしたことによってセカンドボールを拾うエリアに人が少なくなってしまった点、札幌が都倉というストロングを生かすために長いボールが多くなってしまった点、などによって押し込まれてしまうような状態になっていたのですが、崩された形でのクロスを上げられることもなく、最後はフランコも投入してしっかりと中央を固めて勝利をもぎ取りました。
互いにつぶしあって、攻撃もうまくいきそうだけども最後の詰めが甘くてシュートまで行けないところも多くあり、最後は完全にリトリートしきってしまって猛攻を食らうという、ハラハラドキドキというか…なかなかストレスのたまる試合でした(笑)
勝ち点を重ねて混戦となっている上位を少しでも覗きこむか、それとも残留争いに引きづり込まれる序曲となってしまうかという試合でしたので、ホント勝ってよかったです。
Posted by オオタニ at
11:02
│Match Impression (2017)
2017年05月25日
2017ルヴァン:サガン鳥栖 VS 横浜F・マリノス
マリノス戦の振り返りです。
頭の中の記憶が頼りなので、合ってないところがあるかもしれないのはご容赦ください。
この試合のポイントは、鳥栖のセットアップの変更。前半から状況に応じてめまぐるしくシステムが変わり、4-3-1-2 ⇒ 4-4-2 ⇒ 4-3-1-2 ⇒ 4-3-3 と、何度も変更していました。試合の最後の方は、攻めたいけどカウンターは食らいたくないという感じで、4-3-3なのか4-5-1なのか、もはやそんな数字での組み合わせはどうでも良いって感じで両サイドのイバルボと富山が攻撃にも守備にも走りきっていました。
試合は、互いに前から激しく奪い合う状態から、段々とマリノスのペースになって進みます。マリノスは、扇原が組み立てに降りてきて3人でビルドアップ。センターバックに豊田と富山がつきます。この時、扇原が下がって受けることによって、マリノスの両サイドバックが大きく横に幅を取っています。扇原がサイドに展開して、鳥栖全体をそのサイドに寄せたところで、逆サイドへの展開を図ったところがマリノスの攻撃のポイント。
水野は扇原につき、小川のスライドも遅れ、藤田や三丸の押し上げもなく、孤立無援の石川(太田)。特に、バブンスキーが下がってボールを受けるので、周りに何人もいるが、果たして僕は誰を見たらよいのだろうかという状態。そこで、ちょっとまずかったのが、割り切って中央に絞っていけばよかったのですが、外への展開を嫌がってか外の選手に付こうとしたところに、中央の縦パスを入れられてしまったので、非常に苦しい状態でした。
そこで、マッシモさんは、水野を右サイド、太田をボランチに据えてフラットな4-4-2に変更します。マリノスのビルドアップ隊の3人は豊田と富山に任せて、中央でもサイドでもボールが入ったところで迎え撃つという形。これによって、前からボールを奪いに行くという機会は減ったものの、スペース管理がうまくいくようになって、ボールを奪えるようになってきます。左サイドに張り出された石川ですが、狭い所でもボールを保持できる能力が生き、縦へのドリブルやカットインしてからのスルーパスなど、ゲームをコントロールできるようになりました。
前半、いい感じで終わったなと思っていたら、また4-3-1-2に戻すマッシモさん。水野の位置をコントロールして、太田と石川が孤立しないように、サイドにでてきた選手たちへのつけ方を変えるなどの対策を打ってきたものの、やっぱり前に行きたがる3人と中盤の3人、そしてスペースを空けたくないサイドバックの意思が合わずにマリノスにポゼションされてしまう状態。マッシモさん、Mか!(笑)…という冗談はさておき、サテライトリーグも廃止されてしまったいま、チーム戦術を試合の中で学ぶ機会は少ないので、どうしてもこの配置でやりたかったのでしょう。
後半はこれでやろうと思ったのでしょうが、結局、マリノスのポゼション状態が続いてしまって、前半の悪い時間帯と変わらないようになってきてしまったので、後半始まってから10分も待つことができずにイバルボと池田を投入して4-3-3に変更。相手のサイドバックを富山とイバルボが見て、ビルドアップ隊を池田一人で見させるというこれまたMっぷりを見せましたが、元気いっぱいの池田はこれに応えてしっかりと動いていました。サイドバックの上下に合わせて、イバルボと富山もリトリートしていたので、ハーフのメンバーは中盤を見れば良いようになり、中盤の数的不利もこれで解消。
そうなると、マリノスはビルドアップで3人も使う事をしなくてもよく、ちょうど扇原も疲れてきたということで、中町を投入。中町はビルドアップで最終ラインに戻る回数は扇原に比べて格段に減って、鳥栖の池田の目の効かない位置(小川の前)にポジションするようになり、マリノスボランチの2人が中盤の薄い所を狙ってきました。
マリノスの対策をものともせず、鳥栖は運動量を発揮して、決して状態は悪くはなりませんでしたが、バブンスキーのパワードリブルにて、マリノスが先制。決まるときはこんなもんです。
先制してからか、中町が入った時か、高野が入った時かよくわかりませんが、鳥栖の3トップに備えるためか、最終ラインに5枚据えていたっぽいマリノス。山中亮輔をウイングバック気味に据えていました。これにより、マリノスの攻撃力はややダウン。そのうえ、最終ラインに5枚そろえたものの、その最終ラインの前のスペースを3人で守っていたので、鳥栖が大外でボールを保持して基点を作り、そこに寄せたところでサイドバックの選手が中に入ってきたところに落とすと、ペナルティエリア前の45度付近でいい感じでフリーに。そこからはクロス練習会のようにクロスがあがっていました。フリックしてからの池田のシュートなど、惜しいシーンもたくさんありました。
家の都合もあり、吉尾が入ったあたりからは帰り支度をしながら歩いていきながら、ゴール裏の近くで観戦。試合終了かなと思ったら、遠いところでPKの笛が。無念。
互いのシステムの変更とか、やり方の変更とか、監督の工夫が見れました。完全にポゼションを取られて苦しい時間帯もありましたが、やり方変えることで息を吹き返して押し込む時間帯もありました。お互いに自分たちの持ち味を発揮しようという積極的な試合展開だったので楽しかったです。
4-3-3によってイバルボが生きることも発見できましたし、石川の積極的なプレイはよかったし、三丸の素晴らしいクロスも見れましたし、カップ戦ならではの試合であったと思います。
もちろん、勝つことが一番ですが、選手たちの経験と言う意味では、非常に意味のあった試合だと思いました。
頭の中の記憶が頼りなので、合ってないところがあるかもしれないのはご容赦ください。
この試合のポイントは、鳥栖のセットアップの変更。前半から状況に応じてめまぐるしくシステムが変わり、4-3-1-2 ⇒ 4-4-2 ⇒ 4-3-1-2 ⇒ 4-3-3 と、何度も変更していました。試合の最後の方は、攻めたいけどカウンターは食らいたくないという感じで、4-3-3なのか4-5-1なのか、もはやそんな数字での組み合わせはどうでも良いって感じで両サイドのイバルボと富山が攻撃にも守備にも走りきっていました。
試合は、互いに前から激しく奪い合う状態から、段々とマリノスのペースになって進みます。マリノスは、扇原が組み立てに降りてきて3人でビルドアップ。センターバックに豊田と富山がつきます。この時、扇原が下がって受けることによって、マリノスの両サイドバックが大きく横に幅を取っています。扇原がサイドに展開して、鳥栖全体をそのサイドに寄せたところで、逆サイドへの展開を図ったところがマリノスの攻撃のポイント。
水野は扇原につき、小川のスライドも遅れ、藤田や三丸の押し上げもなく、孤立無援の石川(太田)。特に、バブンスキーが下がってボールを受けるので、周りに何人もいるが、果たして僕は誰を見たらよいのだろうかという状態。そこで、ちょっとまずかったのが、割り切って中央に絞っていけばよかったのですが、外への展開を嫌がってか外の選手に付こうとしたところに、中央の縦パスを入れられてしまったので、非常に苦しい状態でした。
そこで、マッシモさんは、水野を右サイド、太田をボランチに据えてフラットな4-4-2に変更します。マリノスのビルドアップ隊の3人は豊田と富山に任せて、中央でもサイドでもボールが入ったところで迎え撃つという形。これによって、前からボールを奪いに行くという機会は減ったものの、スペース管理がうまくいくようになって、ボールを奪えるようになってきます。左サイドに張り出された石川ですが、狭い所でもボールを保持できる能力が生き、縦へのドリブルやカットインしてからのスルーパスなど、ゲームをコントロールできるようになりました。
前半、いい感じで終わったなと思っていたら、また4-3-1-2に戻すマッシモさん。水野の位置をコントロールして、太田と石川が孤立しないように、サイドにでてきた選手たちへのつけ方を変えるなどの対策を打ってきたものの、やっぱり前に行きたがる3人と中盤の3人、そしてスペースを空けたくないサイドバックの意思が合わずにマリノスにポゼションされてしまう状態。マッシモさん、Mか!(笑)…という冗談はさておき、サテライトリーグも廃止されてしまったいま、チーム戦術を試合の中で学ぶ機会は少ないので、どうしてもこの配置でやりたかったのでしょう。
後半はこれでやろうと思ったのでしょうが、結局、マリノスのポゼション状態が続いてしまって、前半の悪い時間帯と変わらないようになってきてしまったので、後半始まってから10分も待つことができずにイバルボと池田を投入して4-3-3に変更。相手のサイドバックを富山とイバルボが見て、ビルドアップ隊を池田一人で見させるというこれまたMっぷりを見せましたが、元気いっぱいの池田はこれに応えてしっかりと動いていました。サイドバックの上下に合わせて、イバルボと富山もリトリートしていたので、ハーフのメンバーは中盤を見れば良いようになり、中盤の数的不利もこれで解消。
そうなると、マリノスはビルドアップで3人も使う事をしなくてもよく、ちょうど扇原も疲れてきたということで、中町を投入。中町はビルドアップで最終ラインに戻る回数は扇原に比べて格段に減って、鳥栖の池田の目の効かない位置(小川の前)にポジションするようになり、マリノスボランチの2人が中盤の薄い所を狙ってきました。
マリノスの対策をものともせず、鳥栖は運動量を発揮して、決して状態は悪くはなりませんでしたが、バブンスキーのパワードリブルにて、マリノスが先制。決まるときはこんなもんです。
先制してからか、中町が入った時か、高野が入った時かよくわかりませんが、鳥栖の3トップに備えるためか、最終ラインに5枚据えていたっぽいマリノス。山中亮輔をウイングバック気味に据えていました。これにより、マリノスの攻撃力はややダウン。そのうえ、最終ラインに5枚そろえたものの、その最終ラインの前のスペースを3人で守っていたので、鳥栖が大外でボールを保持して基点を作り、そこに寄せたところでサイドバックの選手が中に入ってきたところに落とすと、ペナルティエリア前の45度付近でいい感じでフリーに。そこからはクロス練習会のようにクロスがあがっていました。フリックしてからの池田のシュートなど、惜しいシーンもたくさんありました。
家の都合もあり、吉尾が入ったあたりからは帰り支度をしながら歩いていきながら、ゴール裏の近くで観戦。試合終了かなと思ったら、遠いところでPKの笛が。無念。
互いのシステムの変更とか、やり方の変更とか、監督の工夫が見れました。完全にポゼションを取られて苦しい時間帯もありましたが、やり方変えることで息を吹き返して押し込む時間帯もありました。お互いに自分たちの持ち味を発揮しようという積極的な試合展開だったので楽しかったです。
4-3-3によってイバルボが生きることも発見できましたし、石川の積極的なプレイはよかったし、三丸の素晴らしいクロスも見れましたし、カップ戦ならではの試合であったと思います。
もちろん、勝つことが一番ですが、選手たちの経験と言う意味では、非常に意味のあった試合だと思いました。
Posted by オオタニ at
19:22
│Match Impression (2017)
2017年05月23日
2017 第12節 : ガンバ大阪 VS サガン鳥栖
好調のG大阪との試合でしたが、対する鳥栖は怪我人が続出して戦力的には苦しい状態。結果は、お互いの勢いの差がそのまま出てしまった感じとなってしまいました。流れの中でもチャンスはあり、決して歯が立たなかったような試合ではなかっただけに、得点差もさることながら、その戦いっぷりとしても非常に悔しい試合でした。
ガンバのセットアップは4-4-2。とはいっても遠藤は自由に動いてましたが。札幌戦ではダイアモンド型で臨んでいた模様ですが、守備での鎌田への対処、攻撃での義希の対処を考えるとボランチ2人の方が組みやすいと判断したのでしょう。鳥栖は変わらず4-3-1-2で、フォワードには怪我から復帰した小野が入りました。双方共に、プレスがハマる状態が作られていたため、上手く追い込みに成功して相手にロングボールを蹴らせたり、縦パスをカットというシーンはともに多く作ることができていました。小野は上下動を繰り返して献身的に攻守に貢献し、チョドンゴンの決定機を演出するなど非常によい動きをしておりましたが、怪我の再発により離脱。非常に無念です。
鳥栖がボールを持ってからのガンバの圧力は思いのほか強いものでした。前節の清水戦では簡単に相手陣地まで押し上げさせてもらっていた両サイドバックでしたが、ガンバは逆にそこが奪いどころと言わんばかりに倉田と藤本が襲い掛かってきます。立て直そうとボールをセンターバックに戻しても、赤崎、長沢の守備意識の高さも相まって執拗にプレスがやってきます。その結果、ロングボールを蹴らされる羽目になるのですが、目的と狙いを持ったロングボールではなく、行き場を失った上でやむを得なく蹴ったロングボールは自分たちのものにするには五分五分よりも低い確率となり、セカンドボールの行方次第という攻撃が多くなってしまったのは否めません。
ただ、ガンバが前から来たときに、最終ラインと前線・中盤との間にギャップができるため、鳥栖がその間をついて上手くつないだり、セカンドボールを高い位置でうまく拾う事もあり、相手陣地で起点を作ってシュートチャンスを迎えることも多々ありました。小野のクロスからのチョドンゴンのヘディングや、鎌田のミドルシュートなど、入ってもおかしくないようなシーンは多く作っていました。しかし、ゴールを奪う事はできず、結局タイムアップ。
この試合でのガンバとの違いは、崩しのシーンの中での中央の使い方です。ガンバは、いかにして中央から崩そうかという視点でボールを回します。そして、隙があれば中央のドリブルで相手をはがしにかかりますし、それが成功した際には攻撃のスピードがぐんと上がります。対して鳥栖は、リスクを負ってでも中央を攻めるようなチャレンジが少なく、空いている選手を使うとなるとどうしてもサイドの選手経由が多くなってしまいます。
中央へボールを入れることによってボランチやセンターバックを動かす事ができた場合は、ひとつの隙となって攻めるポイントが生まれるのですが、中央へのチャレンジが少ないとそもそも相手のボランチやセンターバックを動かすことが難しくなります。そうなると、相手の中央がしっかりと構えていますので、ピンポイントのクロス(たとえば小野が蹴ったような)が入らないと得点することが難しいということになります。鳥栖が、クロスをあげるものの中央ではじかれるというシーンが続いたのは、センターバックをどのようにして動かすかという工夫の違いであり、これがこの試合で感じたガンバとの大きな違いでした。
■ ファビオの縦パス


■ 遠藤の縦パス




ガンバの特徴とこの試合での鳥栖の動きが集約されていたのが先制の場面です。受けたボールが流れたというのもありましたが、倉田が中央から突破を図って義希を交わしたことによって、センターバックのフランコを引きずり出すことに成功しています。センターバックを引き出した後に、右サイドに展開してからのクロスですので、三浦がクロスをあげるときにはフランコというひとつの高い山がない状態でクロスをあげることができました。
また、この場面で非常に重要なのは、原川の守備での戻りが遅れている点です。カウンターが始まる時点では、クロスを上げた三浦とほぼ同じような位置からのスタートであり、また、途中で赤崎がタメを作った時間もありますので、戻る時間は十分にありました。
鳥栖の他のメンバーの戻りは早く、しっかりと中央をカバーしてラインを整えています。それによって義希が中央で倉田にプレスをかけることができました。(正直、私はこの時点では、義希の寄せによってボールが奪えると思いました。)
しかしながら、義希が個の力で抜かれてしまったことにより、ここから組織としての対応をしなければならなくなります。義希が抜かれたのでフランコが対峙するのですが、倉田のクイックネスが上回り右サイドへの侵入を許してしまいます。仮定にすぎませんが、原川が戻っていればこのスペースはなかったので、フランコ(もしくは原川)が倉田を止めていた可能性は十分にあります。守備の際に、ラインを組むというのは、スペースを守るのはもちろんですが、個の力で破られてしまった際のカバーリングの為に味方との距離を保っておくというのもその意図に含まれているのです。
もしかしたら、戦術的に、攻撃へのトランジションに備えて原川が戻らずに、あえて高い位置を保つようにと待機していたのかもしれませんので、これ以上は深くは追求しませんが、ガンバにスペースを与えてしまうと、得点に結びつける力があるということは承知していたはずなのに、そのスペースをやすやすと与えてしまったのは悔やまれるポイントです。
たまたま、原川のこのシーンが失点に結びついてしまったのですが、前述の遠藤の目の前のスペースがあいたシーンでチョドンゴンの絞りが遅れてしまったシーンのように、守備の中で誰か一人の動きが遅れただけでも、強いチームは一瞬にしてゴール前に迫ってきます。







サッカーの試合において、得点が取れなかった原因がフォワードだけにあるわけでもなく、失点を喫した原因がディフェンダーやゴールキーパーだけにあるわけではありません。結果に対する原因は最終局面だけで決まるわけではなく、その場面に至るまでのすべてのプロセスが結果に影響を及ぼします。ひとつひとつのプロセスの中で、たった一つの小さなミスであっても、それが最終的に致命的なダメージとなってしまうこともあります。ミスは、戦術的なものや個人によるものなど、様々あるのでしょうが、チームの中で振り返り、同じ事象が発生しないように対応してほしいと思います。
<画像引用元:DAZN>
ガンバのセットアップは4-4-2。とはいっても遠藤は自由に動いてましたが。札幌戦ではダイアモンド型で臨んでいた模様ですが、守備での鎌田への対処、攻撃での義希の対処を考えるとボランチ2人の方が組みやすいと判断したのでしょう。鳥栖は変わらず4-3-1-2で、フォワードには怪我から復帰した小野が入りました。双方共に、プレスがハマる状態が作られていたため、上手く追い込みに成功して相手にロングボールを蹴らせたり、縦パスをカットというシーンはともに多く作ることができていました。小野は上下動を繰り返して献身的に攻守に貢献し、チョドンゴンの決定機を演出するなど非常によい動きをしておりましたが、怪我の再発により離脱。非常に無念です。
鳥栖がボールを持ってからのガンバの圧力は思いのほか強いものでした。前節の清水戦では簡単に相手陣地まで押し上げさせてもらっていた両サイドバックでしたが、ガンバは逆にそこが奪いどころと言わんばかりに倉田と藤本が襲い掛かってきます。立て直そうとボールをセンターバックに戻しても、赤崎、長沢の守備意識の高さも相まって執拗にプレスがやってきます。その結果、ロングボールを蹴らされる羽目になるのですが、目的と狙いを持ったロングボールではなく、行き場を失った上でやむを得なく蹴ったロングボールは自分たちのものにするには五分五分よりも低い確率となり、セカンドボールの行方次第という攻撃が多くなってしまったのは否めません。
ただ、ガンバが前から来たときに、最終ラインと前線・中盤との間にギャップができるため、鳥栖がその間をついて上手くつないだり、セカンドボールを高い位置でうまく拾う事もあり、相手陣地で起点を作ってシュートチャンスを迎えることも多々ありました。小野のクロスからのチョドンゴンのヘディングや、鎌田のミドルシュートなど、入ってもおかしくないようなシーンは多く作っていました。しかし、ゴールを奪う事はできず、結局タイムアップ。
この試合でのガンバとの違いは、崩しのシーンの中での中央の使い方です。ガンバは、いかにして中央から崩そうかという視点でボールを回します。そして、隙があれば中央のドリブルで相手をはがしにかかりますし、それが成功した際には攻撃のスピードがぐんと上がります。対して鳥栖は、リスクを負ってでも中央を攻めるようなチャレンジが少なく、空いている選手を使うとなるとどうしてもサイドの選手経由が多くなってしまいます。
中央へボールを入れることによってボランチやセンターバックを動かす事ができた場合は、ひとつの隙となって攻めるポイントが生まれるのですが、中央へのチャレンジが少ないとそもそも相手のボランチやセンターバックを動かすことが難しくなります。そうなると、相手の中央がしっかりと構えていますので、ピンポイントのクロス(たとえば小野が蹴ったような)が入らないと得点することが難しいということになります。鳥栖が、クロスをあげるものの中央ではじかれるというシーンが続いたのは、センターバックをどのようにして動かすかという工夫の違いであり、これがこの試合で感じたガンバとの大きな違いでした。
■ ファビオの縦パス


■ 遠藤の縦パス




ガンバの特徴とこの試合での鳥栖の動きが集約されていたのが先制の場面です。受けたボールが流れたというのもありましたが、倉田が中央から突破を図って義希を交わしたことによって、センターバックのフランコを引きずり出すことに成功しています。センターバックを引き出した後に、右サイドに展開してからのクロスですので、三浦がクロスをあげるときにはフランコというひとつの高い山がない状態でクロスをあげることができました。
また、この場面で非常に重要なのは、原川の守備での戻りが遅れている点です。カウンターが始まる時点では、クロスを上げた三浦とほぼ同じような位置からのスタートであり、また、途中で赤崎がタメを作った時間もありますので、戻る時間は十分にありました。
鳥栖の他のメンバーの戻りは早く、しっかりと中央をカバーしてラインを整えています。それによって義希が中央で倉田にプレスをかけることができました。(正直、私はこの時点では、義希の寄せによってボールが奪えると思いました。)
しかしながら、義希が個の力で抜かれてしまったことにより、ここから組織としての対応をしなければならなくなります。義希が抜かれたのでフランコが対峙するのですが、倉田のクイックネスが上回り右サイドへの侵入を許してしまいます。仮定にすぎませんが、原川が戻っていればこのスペースはなかったので、フランコ(もしくは原川)が倉田を止めていた可能性は十分にあります。守備の際に、ラインを組むというのは、スペースを守るのはもちろんですが、個の力で破られてしまった際のカバーリングの為に味方との距離を保っておくというのもその意図に含まれているのです。
もしかしたら、戦術的に、攻撃へのトランジションに備えて原川が戻らずに、あえて高い位置を保つようにと待機していたのかもしれませんので、これ以上は深くは追求しませんが、ガンバにスペースを与えてしまうと、得点に結びつける力があるということは承知していたはずなのに、そのスペースをやすやすと与えてしまったのは悔やまれるポイントです。
たまたま、原川のこのシーンが失点に結びついてしまったのですが、前述の遠藤の目の前のスペースがあいたシーンでチョドンゴンの絞りが遅れてしまったシーンのように、守備の中で誰か一人の動きが遅れただけでも、強いチームは一瞬にしてゴール前に迫ってきます。







サッカーの試合において、得点が取れなかった原因がフォワードだけにあるわけでもなく、失点を喫した原因がディフェンダーやゴールキーパーだけにあるわけではありません。結果に対する原因は最終局面だけで決まるわけではなく、その場面に至るまでのすべてのプロセスが結果に影響を及ぼします。ひとつひとつのプロセスの中で、たった一つの小さなミスであっても、それが最終的に致命的なダメージとなってしまうこともあります。ミスは、戦術的なものや個人によるものなど、様々あるのでしょうが、チームの中で振り返り、同じ事象が発生しないように対応してほしいと思います。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
18:04
│Match Impression (2017)
2017年05月18日
2017 第11節 : 清水エスパルス VS サガン鳥栖
開幕から決して順風満帆とは言えない両チームの戦い。ホームの清水エスパルスは今シーズンホームでの勝利がなく、アウェーのサガン鳥栖は今シーズンアウェーでの勝利がない状態で、どちらが先にジンクスを抜け出せるかという戦いでありましたが、結果は、試合終了間際にサガン鳥栖が追い付いて引き分け。どちらも待望の1勝はお預けとなってしまいました。清水エスパルスは落胆が大きく、追いついたサガン鳥栖の方が歓喜に沸いた形であったのですが、試合の経過がそうさせただけで、試合内容からすると、もしかしたら、その感情は逆になっていてもおかしくはないのかもしれません。
サガン鳥栖は、豊田、谷口の負傷により、イバルボ、青木がスタメンに入りますが、4-3-1-2のスタイルには変わりありません。豊田の持ち味は当然ロングボールへの強さと決定力の高さなのですが、実は、守備時のプレスバック、スペースのカバーリング、コーナーキックにおけるニアサイドのケアもチームへの貢献ポイント。イバルボが守備に対してどの程度貢献できるのかという心配をしていましたが、先制点を奪われ、清水が自陣に撤退してしまったことによって守備に対する心配は杞憂となってしまいました。
それでは、攻撃でどの程度貢献できるかという所ですが、イバルボに豊田という絶対的ターゲットの替わりを務めさせることを躊躇したのか、ロングボールを蹴り込む回数は少なく、また、清水のプレッシャーが前から来なかったので、最終ラインからのボールのつなぎには苦労しなかったことも、ロングボールの少なさに影響を与えました。
最終ラインにプレッシャーに来るのがほぼチョンテセ1人だけだったので、センターバック2人でボールを交換する事が容易となり、そこから義希への繋ぎや小林、吉田への繋ぎも比較的自由にさばくことができていました。(ただし、その、センターバックが容易にボールを持てていたことから、余裕を持ちすぎて、チョンテセにひっかけられて決定的なピンチを迎えるという大ミスというのもありましたが)
清水は、比較的前からプレッシャーにくる鳥栖に対して前進と後退を繰り返して、左右に展開して糸口を探していましたが、セカンドボールを拾ってからの両サイドバックの前進によって、形は綺麗でないながらもシュートまで結びつけることができ、コーナーキックのチャンスを得るようになります。
ただし、その清水も、いい形でボールを展開していたり、奪ってからトランジションという肝心な時に、パスミス、トラップミスによって鳥栖にボールをさわられるケースが多く、逆に言うと、サガン鳥栖は前から(主に相手のミスによって)ボールを奪った時が最大の攻撃のチャンスでしたが、フリーでのシュートもなかなか決められず。
余談ですが、六反がこんなに上手になるとわかっていたのならば、アビスパも放出しなかっただろうなと(笑)
このように、互いに積極的に押し込みたいところなのですが、崩しのきっかけを失って、ボールを持ってじっくり攻めるフェーズに入ってしまうと、相手がしっかりと引いて構えることにより、途端に突破口を失ってしまう状態が続いていました。
事故なのか、事故でなかったのか
そのような展開の中で、22分にチアゴアウベスが強烈なミドルシュートで先制点を叩き込みます。果たして、このシュートは事故だったのでしょうか、事故ではなかったのでしょうか。
ヒントは、11分に隠されていました。左サイドでビルドアップして、チアゴアウベスのいる右サイドへ大きく展開します。チアゴアウベスはチョンテセに当ててダイレクトで落としたボールを受取り、そこから前を向いてボールを受ける形(シュートを打つ形)を作ろうとしますが、ここはイバルボのプレスバックによって阻まれます。
先制点の場面も崩しとしては同じような形でした。左サイドから右サイドに展開してワイドに構えていたチアゴアウベスがボールを受け、そこからチョンテセに当ててダイレクトに落としたボールを受け取ってそのまま豪快なシュートという形です。鳥栖として振り返るべきは、
① チョンテセに対するくさびのボールを許してしまった
② チョンテセに対して2人で囲みに行ったが、ボールをチアゴアウベスに落とされてしまった
③ チアゴアウベスの中央への突進をフリーにしてしまった
の3点でしょうか。②に関しては、しっかりと対処しに行った結果なので、取れなかったのは仕方がないこと(ミスはミスですが)と割り切ってよいのかなと。ただし、①と③に関しては、もっとやれることがあったのではないかという印象です。清水がチョンテセにあてるというひとつの「形」として作ろうとしていた場面は何度かあったので、鳥栖としては、相手の次の動きの「予測」と言う点、そして、ボールに対する「プレッシャー」と言う点から考えても、この失点を事故として片づけてしまうとまた同じような手痛いゴラッソをくらうかもしれないなという所です。
閉塞していく攻撃
早い時間帯で先制したということもあり、この試合の清水の守備の選択肢はまさに文字通り「リトリート」
リトリートとは言うものの、どこかの位置では鳥栖に対するプレッシャーをかけなければならないのですが、鳥栖のサイドバックにボールが渡ってからもなかなかプレッシャーはかからず。
鳥栖のサイドバック、サイドハーフにプレッシャーをかけると、どうしても自分たちのサイドバックの裏が空いてしまい、そこを鎌田が狙っているのは自明の理であるため、なかなか圧力をかける事ができないという状態で、清水として、前から奪いに行くよりは、自陣のサイドバックの裏に穴を開けない事を選択していたのでしょう。
清水のこの選択によって、鳥栖は簡単にハーフまでボールを渡すことができましたが、では、そこからサイドバックと協力して崩してクロスなのか、フォワードと連係して崩してクロスなのか、それともカットインで切り込んでシュートなのか。
左サイドでは、イバルボがサイドに加担してきても、個人の力での突破がはまらずにシュート(クロス)にすらつながらず、右サイドでは、フォワードのサポートが手薄でカットインなどを試みるものの、清水の厚い壁に阻まれてミドルシュートすら打てず。
中盤の選手ひとりひとりが何かをしようと試みるもその動きが単発で終わり、また、せっかくゴール前にフォワードが構えている状態であっても、どうやっていい形でクロスを上げようかと模索しているうちに、清水に押し上げられ、プレッシャーによって撤退を余儀なくされ、効果的なシュートチャンスが作れませんでした。
結局狙いどころとしては、鳥栖も清水もトランジションの場面ということになり、攻撃の手数は繰り広げるものの、最終的には相手のミス待ちのような様相を呈しておりました。
では、リトリートした清水に守備の穴がなかったかというと、決してそうではなく、特に鎌田を意識しているからか、彼らの動きに対して、ディフェンス陣がついていくことによって大きなスペースが空いているケースもありました。
また、清水が「ここで奪う」という共通意識がなく、鳥栖のボールの繋ぎに対して後追いで人がついてくるため、ワンタッチでのパス回しなどにはついていけない状態でした。こういうところをうまくついていくことができれば、早い時間帯での得点も可能だっただけに、もったいないなというシーンは多かったです。
■清水のプレスが後追いでプレッシャーとならず、義希からのダイレクトパスで裏を取ったシーン





■鎌田が作るスペースをうまく活用できないシーン


サガン鳥栖とは池田圭である
このままでは埒が明かないと判断したマッシモ監督は池田、水野、富山を投入。それから徐々に、閉塞感が漂っていた前線が活性化します。
イバルボ、チョドンゴンのゴール前に張るような動きと異なり、相手の中盤と最終ラインとの間や、裏への抜け出しなど、池田圭が池田圭であることを証明する動きで清水の守備陣を翻弄します。また、その動きによって相手ディフェンスを引き付けることが出来、鎌田、水野もうまく中盤にスペースを見つけ出して侵入する回数が増えてきます。
水野はサイドで張っていた福田と異なり、外から中へという動きでボールを引き出していたので、マッシモ監督から何か指示が出ていたのかもしれません。

そして、歓喜のゴールシーンが訪れました。まず、清水の動きですが、勝っている状態でしかも勝利のホイッスル寸前というところで、鳥栖のゴール前に対して4人が急襲して戻りが遅れてしまったのは後悔したことでしょう。それは、小林監督のコメントからも伺えます。ボールキープできないにしても、相手が攻めたいことはわかっているので、これまで通りリトリートして前線は最小の人数に対応させるということを継続するべきでした。
さて、最後のトランジションの場面で、鳥栖は非常に連動性の高い動きを見せました。池田がセンターバックをひっぱって中央に大きなスペースを作り、そのスペースに富山が飛び込んで、近くに寄っていたチョドンゴンがつぶれ、フリーの水野がシュート。誰一人としてさぼることなく、味方の動きに応じたプレイをみることができ、非常に素晴らしいゴールだったのですが、もう少し、早い時間で欲しいゴールでした。



正直、清水の守備がそこまで良かったとは思えないので、崩せるチャンスは何度もあったと思います。それ以上に、鳥栖の前線に効果的な動きが少なくサイドバックの2人はボールの出しどころに苦労していました。マッシモさんのサイドからという指示はあったでしょうが、サイドからサイドと単純にボールを送りこむだけではなく、サイドを崩すために中盤でどのような動きをしたらよいのか、どうやってスペースを作ろうかという一工夫が欲しかったところです。
最後のゴールの場面は、全員の動きが連動してお見事だったのですが、やはり、鎌田があのスペースを見つけてパスを送り込んでくれたおかげでもあり、非凡なところを垣間見たシーンでもありました。
<画像引用元:DAZN>
サガン鳥栖は、豊田、谷口の負傷により、イバルボ、青木がスタメンに入りますが、4-3-1-2のスタイルには変わりありません。豊田の持ち味は当然ロングボールへの強さと決定力の高さなのですが、実は、守備時のプレスバック、スペースのカバーリング、コーナーキックにおけるニアサイドのケアもチームへの貢献ポイント。イバルボが守備に対してどの程度貢献できるのかという心配をしていましたが、先制点を奪われ、清水が自陣に撤退してしまったことによって守備に対する心配は杞憂となってしまいました。
それでは、攻撃でどの程度貢献できるかという所ですが、イバルボに豊田という絶対的ターゲットの替わりを務めさせることを躊躇したのか、ロングボールを蹴り込む回数は少なく、また、清水のプレッシャーが前から来なかったので、最終ラインからのボールのつなぎには苦労しなかったことも、ロングボールの少なさに影響を与えました。
最終ラインにプレッシャーに来るのがほぼチョンテセ1人だけだったので、センターバック2人でボールを交換する事が容易となり、そこから義希への繋ぎや小林、吉田への繋ぎも比較的自由にさばくことができていました。(ただし、その、センターバックが容易にボールを持てていたことから、余裕を持ちすぎて、チョンテセにひっかけられて決定的なピンチを迎えるという大ミスというのもありましたが)
清水は、比較的前からプレッシャーにくる鳥栖に対して前進と後退を繰り返して、左右に展開して糸口を探していましたが、セカンドボールを拾ってからの両サイドバックの前進によって、形は綺麗でないながらもシュートまで結びつけることができ、コーナーキックのチャンスを得るようになります。
ただし、その清水も、いい形でボールを展開していたり、奪ってからトランジションという肝心な時に、パスミス、トラップミスによって鳥栖にボールをさわられるケースが多く、逆に言うと、サガン鳥栖は前から(主に相手のミスによって)ボールを奪った時が最大の攻撃のチャンスでしたが、フリーでのシュートもなかなか決められず。
余談ですが、六反がこんなに上手になるとわかっていたのならば、アビスパも放出しなかっただろうなと(笑)
このように、互いに積極的に押し込みたいところなのですが、崩しのきっかけを失って、ボールを持ってじっくり攻めるフェーズに入ってしまうと、相手がしっかりと引いて構えることにより、途端に突破口を失ってしまう状態が続いていました。
事故なのか、事故でなかったのか
そのような展開の中で、22分にチアゴアウベスが強烈なミドルシュートで先制点を叩き込みます。果たして、このシュートは事故だったのでしょうか、事故ではなかったのでしょうか。
ヒントは、11分に隠されていました。左サイドでビルドアップして、チアゴアウベスのいる右サイドへ大きく展開します。チアゴアウベスはチョンテセに当ててダイレクトで落としたボールを受取り、そこから前を向いてボールを受ける形(シュートを打つ形)を作ろうとしますが、ここはイバルボのプレスバックによって阻まれます。
先制点の場面も崩しとしては同じような形でした。左サイドから右サイドに展開してワイドに構えていたチアゴアウベスがボールを受け、そこからチョンテセに当ててダイレクトに落としたボールを受け取ってそのまま豪快なシュートという形です。鳥栖として振り返るべきは、
① チョンテセに対するくさびのボールを許してしまった
② チョンテセに対して2人で囲みに行ったが、ボールをチアゴアウベスに落とされてしまった
③ チアゴアウベスの中央への突進をフリーにしてしまった
の3点でしょうか。②に関しては、しっかりと対処しに行った結果なので、取れなかったのは仕方がないこと(ミスはミスですが)と割り切ってよいのかなと。ただし、①と③に関しては、もっとやれることがあったのではないかという印象です。清水がチョンテセにあてるというひとつの「形」として作ろうとしていた場面は何度かあったので、鳥栖としては、相手の次の動きの「予測」と言う点、そして、ボールに対する「プレッシャー」と言う点から考えても、この失点を事故として片づけてしまうとまた同じような手痛いゴラッソをくらうかもしれないなという所です。
閉塞していく攻撃
早い時間帯で先制したということもあり、この試合の清水の守備の選択肢はまさに文字通り「リトリート」
リトリートとは言うものの、どこかの位置では鳥栖に対するプレッシャーをかけなければならないのですが、鳥栖のサイドバックにボールが渡ってからもなかなかプレッシャーはかからず。
鳥栖のサイドバック、サイドハーフにプレッシャーをかけると、どうしても自分たちのサイドバックの裏が空いてしまい、そこを鎌田が狙っているのは自明の理であるため、なかなか圧力をかける事ができないという状態で、清水として、前から奪いに行くよりは、自陣のサイドバックの裏に穴を開けない事を選択していたのでしょう。
清水のこの選択によって、鳥栖は簡単にハーフまでボールを渡すことができましたが、では、そこからサイドバックと協力して崩してクロスなのか、フォワードと連係して崩してクロスなのか、それともカットインで切り込んでシュートなのか。
左サイドでは、イバルボがサイドに加担してきても、個人の力での突破がはまらずにシュート(クロス)にすらつながらず、右サイドでは、フォワードのサポートが手薄でカットインなどを試みるものの、清水の厚い壁に阻まれてミドルシュートすら打てず。
中盤の選手ひとりひとりが何かをしようと試みるもその動きが単発で終わり、また、せっかくゴール前にフォワードが構えている状態であっても、どうやっていい形でクロスを上げようかと模索しているうちに、清水に押し上げられ、プレッシャーによって撤退を余儀なくされ、効果的なシュートチャンスが作れませんでした。
結局狙いどころとしては、鳥栖も清水もトランジションの場面ということになり、攻撃の手数は繰り広げるものの、最終的には相手のミス待ちのような様相を呈しておりました。
では、リトリートした清水に守備の穴がなかったかというと、決してそうではなく、特に鎌田を意識しているからか、彼らの動きに対して、ディフェンス陣がついていくことによって大きなスペースが空いているケースもありました。
また、清水が「ここで奪う」という共通意識がなく、鳥栖のボールの繋ぎに対して後追いで人がついてくるため、ワンタッチでのパス回しなどにはついていけない状態でした。こういうところをうまくついていくことができれば、早い時間帯での得点も可能だっただけに、もったいないなというシーンは多かったです。
■清水のプレスが後追いでプレッシャーとならず、義希からのダイレクトパスで裏を取ったシーン





■鎌田が作るスペースをうまく活用できないシーン


サガン鳥栖とは池田圭である
このままでは埒が明かないと判断したマッシモ監督は池田、水野、富山を投入。それから徐々に、閉塞感が漂っていた前線が活性化します。
イバルボ、チョドンゴンのゴール前に張るような動きと異なり、相手の中盤と最終ラインとの間や、裏への抜け出しなど、池田圭が池田圭であることを証明する動きで清水の守備陣を翻弄します。また、その動きによって相手ディフェンスを引き付けることが出来、鎌田、水野もうまく中盤にスペースを見つけ出して侵入する回数が増えてきます。
水野はサイドで張っていた福田と異なり、外から中へという動きでボールを引き出していたので、マッシモ監督から何か指示が出ていたのかもしれません。

そして、歓喜のゴールシーンが訪れました。まず、清水の動きですが、勝っている状態でしかも勝利のホイッスル寸前というところで、鳥栖のゴール前に対して4人が急襲して戻りが遅れてしまったのは後悔したことでしょう。それは、小林監督のコメントからも伺えます。ボールキープできないにしても、相手が攻めたいことはわかっているので、これまで通りリトリートして前線は最小の人数に対応させるということを継続するべきでした。
さて、最後のトランジションの場面で、鳥栖は非常に連動性の高い動きを見せました。池田がセンターバックをひっぱって中央に大きなスペースを作り、そのスペースに富山が飛び込んで、近くに寄っていたチョドンゴンがつぶれ、フリーの水野がシュート。誰一人としてさぼることなく、味方の動きに応じたプレイをみることができ、非常に素晴らしいゴールだったのですが、もう少し、早い時間で欲しいゴールでした。



正直、清水の守備がそこまで良かったとは思えないので、崩せるチャンスは何度もあったと思います。それ以上に、鳥栖の前線に効果的な動きが少なくサイドバックの2人はボールの出しどころに苦労していました。マッシモさんのサイドからという指示はあったでしょうが、サイドからサイドと単純にボールを送りこむだけではなく、サイドを崩すために中盤でどのような動きをしたらよいのか、どうやってスペースを作ろうかという一工夫が欲しかったところです。
最後のゴールの場面は、全員の動きが連動してお見事だったのですが、やはり、鎌田があのスペースを見つけてパスを送り込んでくれたおかげでもあり、非凡なところを垣間見たシーンでもありました。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
20:56
│Match Impression (2017)
2017年05月09日
2017 第10節 : サガン鳥栖 VS 横浜F・マリノス
今節はレディースDayと銘打ち、21,245人もの大観衆を集め、ユニフォームプレゼント企画にてピンク一色に染まったベストアメニティスタジアムでの試合でした。鮮やかなピンク色に染まったスタジアムを見て鳥栖フューチャーズ時代に描いていた思いを馳せた方もいたことでしょう。しかし、そこにあるチームはタレントを集めて個の力で勝負を挑んだ「鳥栖フューチャーズ」と決別するかのよう、全員のハードワークで勝利をつかみ取るまさに「サガン鳥栖」の試合であり、鳥栖フューチャーズが実現できなかったトップリーグでの試合を、サガン鳥栖が着実に歩み続けていることを再認識させられる試合でした。
サガン鳥栖がこの試合で選択したスタイルはまさに「アグレッシブ」でした。中澤、デゲネクには鳥栖のフォワード2名がプレスをかけた時に個人で交わしきる力は持ち合わせておらず、その組み立て能力の弱さによって、マリノスは必ず一人が最終ライン近くに下がってくることになります。扇原を組み立ての中継地点としていましたが、豊田・チョドンゴンに加えて鎌田が前線のプレスにはいることによって、マリノス最終ラインは自分たちのポジションを押し上げることができず、組み立ての分断に成功していました。(鎌田の得点は思わぬ副産物でした。)
マリノスとしては中央から繋げないのならば、長いボールを蹴るかサイドバックに展開するしか道は残されておらず、攻撃の生命線はロングボールの競り合いではないため、必然的にサイドバック経由でのつなぎが多くなります。事実、中澤が松原へ展開して、松原から縦のマルティノスへの繋ぎ(もしくは松原から伊藤翔を経由したマルティノスへの繋ぎ)は比較的スムーズに行われていました。
鳥栖としては相手をサイドに追いやることが守備の目的であり、センターハーフは相手を外へ追い出すようなポジショニングをとっています。マリノスとしては齋藤もしくはマルティノスの突破によって打開を図りたいので、結果、ボールはサイドに押しやられることになり、マルティノスと吉田のマッチアップは必然的に発生することになります。そのマッチアップが発生した際に大事なのは、互いにどれだけの援軍を得られるかということです。伊藤翔や天野がいち早くサポートに入った時にはマリノス側の崩しが生まれ、吉田・原川や義希がうまく挟み込むことができれば鳥栖のカウンターのチャンスに繋がっていました。
ただし、逆サイドでは事情が異なります。齋藤が少しでもフリーでボールを受けたいために様々なところにポジショニングを取っており、金井がサイドでボールを受けても齋藤との距離が空いていることによりつなぎもままならない状態でした。また、前半も中盤に差し掛かると思うようにボールを受けることができないバブンスキーが下がるシーンが多くなり、サイドがジャムってしまって密集地帯となっていました。マリノスの選手が集まるという事は、そこに鳥栖の選手が集まるということであり、そこにボールが出ても必然とプレスの餌食になります。
このままでは良くないと、前半30分過ぎ頃からは齋藤がサイドで待ち構えるようになります。齋藤のポジションが中央から離れたことにより、マリノスはシンプルに直接齋藤目がけてボールを蹴るシーンがでてきます。しかし、これも長いボールが齋藤に渡る頃には体力の余りある小林・福田・義希が即座に囲い込みを始め、齋藤へボールを渡すことは許しても、そこからの中央へのドリブル突破までは許しませんでした。
いずれにしても、前半は鳥栖が相手の最終ラインを押し込んで分断することに成功していたため、マルティノスも齋藤もやや引いてからしかボールを受けることができず、ゴールから遠い位置からの崩しとなってしまい、マリノスの攻撃で脅威を感じるシーンはほぼありませんでした。
こういう状況であるからこそ、鳥栖としては追加点が欲しいところでした。正直言ってマルティノスの守備は緩いです。攻撃へ寄与することが免罪符となっているのか、突破を許した後のトランジションが極端に遅く、また、鳥栖のサイドバックやセントラルハーフのオーバーラップに釣られて自分の持場を簡単に空けてしまうシーンが目につきます。吉田・原川・鎌田が幾度となく左サイドを崩していたのですが、マリノスはそれが織り込み済みであるかのように中央に屈強なセンターバックが立ちはだかり、これ以上の得点を許しませんでした。左サイドからの再三のクロスやカウンターからの抜けだしが悉く不発に終わったことがこの試合のクロージングを難しくしてしまった要因となってしまいます。
後半も中盤に差し掛かるころから、少しずつ鳥栖の運動量が落ちていきます。特に前線の運動量の低下は顕著であり、これまで低い位置に押し込んでいたマリノスのセンターバック陣がじりじりとそのポジションを高めていくことになります。ポジションが高くなるにつれマリノスの前線との距離が近づき、ボランチが前線に飛び出せる回数も多く増えていくことによって、パスの選択肢が徐々に多くなっていきます。
鳥栖としては、この展開でポジションを高めていくサイドバックの存在がやっかいになってしまいました。前半は、彼らを低い位置に押し込めていたため、齋藤やマルティノスにボールを配球することが主な役割であったのですが、齋藤やマルティノスとの距離が近くなってくると、彼らがボールを受けてからフォローに入ることができるようになります。そうすると、鳥栖もサイドバックを完全に無視はできず、プレスとマークが分散して緩くなってしまいます。マルティノスはサイドバックのあがりという援軍が来たために、緩くなった鳥栖のプレスを個人技で交わして中にカットインして中央へボールを運ぶプレイも出てきます。これらの動きにより中央と外を交互に利用して崩すシーンが増え、徐々にマリノスが鳥栖陣地の深い所に入るようになっていきました。
後半も終了が近付いてくるとマッシモ監督は守りきるという選択を取ります。後手を踏んでいたサイドの攻防で再び主導権を握るため、藤田を投入し5ー4ー1へと陣形を変更しました。マルティノスと齋藤学が高い位置を取ってくるので、鳥栖はセンターハーフとサイドバックで彼ら2人を対処し、中央の3人でウーゴヴィエイラ・伊藤翔を抑えるという形を取りました。ただし、この変更により、ただでさえプレスのかかりきってなかった前線から1枚剥ぎ取ることによって、なおさらマリノスの最終ラインの押し上げを許すことになってしまいます。
比重を後ろに置くことによって、ある程度の押し込みを受けることは想定していたでしょうが、少しでもその押し込みを防ぐために、5バックにすると同時に前線の選手の活性化を図らなければなりません。特に豊田と鎌田は足がとまっており、前半、あれだけにらみを利かせていたデゲネクの上りをただ茫然と見守るだけになってしまい、カウンターのチャンスでも余力は残っておらず、前線で時間を稼ぐことすらできず、戦うにはあまりにも体力的に厳しい状態でした。
5-4-1のシステムをとった時に重要なのは後ろの選手ではなく、肝心なのは前線の動きであり、味方を支える全体の運動量です。豊田の交替はセットプレイの弾き返し役と前線の運動量のトレードオフと考えていたのでしょうが、結局、鳥栖の2人目の交替はアディショナルタイムに入ってからでした。
試合のクロージングは難しく、選手交代が裏目に出ることもあります。今回の試合は結果として勝利を挙げましたが、そのプロセスを振り返るともう少し試合運びを上手にやれたのではないかと感じる点が多かったです。
■ MVP義希、MIP福田
この熱い試合を観戦した方はそれぞれ自分の中で選手たちの活躍に対する感想(評価)を持ったことでしょう。サッカーを観戦して、各々が自分なりの解釈で試合を振り返るというのは、サッカー文化の醸成のためにも非常に良いことです。
この試合での評価は、福田に対する賛辞が多く聞こえてきました。攻撃に守備にまさに八面六臂の活躍で、特に後半終了間際のカウンターの場面でのシュートは決まらなかったものの、足が動いていない鳥栖の前線をカバーして余りある働きをしていました。味方のシュートに繋がるパスも何本も供給でき、今シーズンの不振を払しょくするような出色の出来でした。
このように、鮮烈に印象に残るプレイはありましたが、その反面、表面に現れないインシデントを発生させていたことも見逃せません。ゴール前で不用意にボールを持ちすぎて、相手のファールを取ってくれたから助かったものの失点につながるミスが発生しそうになったシーンや、プレスしなければならないところで躊躇してしまい(ゾーンの意識?体力切れ?)その結果相手の前進を許してしまったシーンなど。また、攻撃面でもパスの丁寧さに欠けてチャンスにつながりそうなところがうまく組み立てできなかったシーンもありました。
スタメンで試合に出始めてからそろそろ丸一年と言う頃でしょうか。彼のプレースタイルも認知され、泥臭くハードワークで走りきるという鳥栖のスタイルにぴったりと合っており、人気も期待も大きく背負っている選手です。彼こそ、次の世代の鳥栖のリーダーとして将来はチームを先頭に立って率いて欲しいのですが、まだまだ技術的にも成長する余地はありますし、もっともっとプレイの精度を上げて試合によって発生する好不調の波を少なくしてほしいですね。
対して、私はこの試合のMVPは義希を推します。先ほどインシデント(事故につながりかねない事象)という言葉を使いましたが、マリノスのチャンスを生みだしそうなインシデントを悉くつぶしていました。スペースに対するカバーリング、ボールに対するアクション、特にこの試合ではマリノスの攻撃の次の一手に対する予知が素晴らしく、ここにボールが出るだろうというエリア・選手をいち早く察知してマリノスのやりたい事を素早くつぶしていました。ボールの繋ぎに関してもチャンスと見るやダイレクトで前に送り、絶対にボールを奪われてはいけない位置ではセーフティファーストを心掛け、終盤では、足が止まってしまった前線の守備不足への対処も彼が行っていましたし、TPOに応じた動きでチーム全体の屋台骨として支えていました。義希の動きがあったからこそ掴めた勝利と言っても過言ではありません。
このことから、最も印象に残ったプレイヤーは福田、最も価値のあるプレイヤーは義希という私なりの思いです。みなさんの中のMIPとMVPは誰だったでしょうか。得点を取った鎌田という方もいらっしゃると思いますし、決定的なシーンを防いだ権田と言う方や齋藤を完璧に抑えこんだ小林という方もいらっしゃると思います。それぞれの思いでこの試合を解釈して振り返ってみると、サッカーがより面白くなるかなと思います。
■義希ベストプレイセレクション(その1)



■義希ベストプレイセレクション(その2)

■義希ベストプレイセレクション(その3)


■義希ベストプレイセレクション(その4)


<画像引用元:DAZN>
サガン鳥栖がこの試合で選択したスタイルはまさに「アグレッシブ」でした。中澤、デゲネクには鳥栖のフォワード2名がプレスをかけた時に個人で交わしきる力は持ち合わせておらず、その組み立て能力の弱さによって、マリノスは必ず一人が最終ライン近くに下がってくることになります。扇原を組み立ての中継地点としていましたが、豊田・チョドンゴンに加えて鎌田が前線のプレスにはいることによって、マリノス最終ラインは自分たちのポジションを押し上げることができず、組み立ての分断に成功していました。(鎌田の得点は思わぬ副産物でした。)
マリノスとしては中央から繋げないのならば、長いボールを蹴るかサイドバックに展開するしか道は残されておらず、攻撃の生命線はロングボールの競り合いではないため、必然的にサイドバック経由でのつなぎが多くなります。事実、中澤が松原へ展開して、松原から縦のマルティノスへの繋ぎ(もしくは松原から伊藤翔を経由したマルティノスへの繋ぎ)は比較的スムーズに行われていました。
鳥栖としては相手をサイドに追いやることが守備の目的であり、センターハーフは相手を外へ追い出すようなポジショニングをとっています。マリノスとしては齋藤もしくはマルティノスの突破によって打開を図りたいので、結果、ボールはサイドに押しやられることになり、マルティノスと吉田のマッチアップは必然的に発生することになります。そのマッチアップが発生した際に大事なのは、互いにどれだけの援軍を得られるかということです。伊藤翔や天野がいち早くサポートに入った時にはマリノス側の崩しが生まれ、吉田・原川や義希がうまく挟み込むことができれば鳥栖のカウンターのチャンスに繋がっていました。
ただし、逆サイドでは事情が異なります。齋藤が少しでもフリーでボールを受けたいために様々なところにポジショニングを取っており、金井がサイドでボールを受けても齋藤との距離が空いていることによりつなぎもままならない状態でした。また、前半も中盤に差し掛かると思うようにボールを受けることができないバブンスキーが下がるシーンが多くなり、サイドがジャムってしまって密集地帯となっていました。マリノスの選手が集まるという事は、そこに鳥栖の選手が集まるということであり、そこにボールが出ても必然とプレスの餌食になります。
このままでは良くないと、前半30分過ぎ頃からは齋藤がサイドで待ち構えるようになります。齋藤のポジションが中央から離れたことにより、マリノスはシンプルに直接齋藤目がけてボールを蹴るシーンがでてきます。しかし、これも長いボールが齋藤に渡る頃には体力の余りある小林・福田・義希が即座に囲い込みを始め、齋藤へボールを渡すことは許しても、そこからの中央へのドリブル突破までは許しませんでした。
いずれにしても、前半は鳥栖が相手の最終ラインを押し込んで分断することに成功していたため、マルティノスも齋藤もやや引いてからしかボールを受けることができず、ゴールから遠い位置からの崩しとなってしまい、マリノスの攻撃で脅威を感じるシーンはほぼありませんでした。
こういう状況であるからこそ、鳥栖としては追加点が欲しいところでした。正直言ってマルティノスの守備は緩いです。攻撃へ寄与することが免罪符となっているのか、突破を許した後のトランジションが極端に遅く、また、鳥栖のサイドバックやセントラルハーフのオーバーラップに釣られて自分の持場を簡単に空けてしまうシーンが目につきます。吉田・原川・鎌田が幾度となく左サイドを崩していたのですが、マリノスはそれが織り込み済みであるかのように中央に屈強なセンターバックが立ちはだかり、これ以上の得点を許しませんでした。左サイドからの再三のクロスやカウンターからの抜けだしが悉く不発に終わったことがこの試合のクロージングを難しくしてしまった要因となってしまいます。
後半も中盤に差し掛かるころから、少しずつ鳥栖の運動量が落ちていきます。特に前線の運動量の低下は顕著であり、これまで低い位置に押し込んでいたマリノスのセンターバック陣がじりじりとそのポジションを高めていくことになります。ポジションが高くなるにつれマリノスの前線との距離が近づき、ボランチが前線に飛び出せる回数も多く増えていくことによって、パスの選択肢が徐々に多くなっていきます。
鳥栖としては、この展開でポジションを高めていくサイドバックの存在がやっかいになってしまいました。前半は、彼らを低い位置に押し込めていたため、齋藤やマルティノスにボールを配球することが主な役割であったのですが、齋藤やマルティノスとの距離が近くなってくると、彼らがボールを受けてからフォローに入ることができるようになります。そうすると、鳥栖もサイドバックを完全に無視はできず、プレスとマークが分散して緩くなってしまいます。マルティノスはサイドバックのあがりという援軍が来たために、緩くなった鳥栖のプレスを個人技で交わして中にカットインして中央へボールを運ぶプレイも出てきます。これらの動きにより中央と外を交互に利用して崩すシーンが増え、徐々にマリノスが鳥栖陣地の深い所に入るようになっていきました。
後半も終了が近付いてくるとマッシモ監督は守りきるという選択を取ります。後手を踏んでいたサイドの攻防で再び主導権を握るため、藤田を投入し5ー4ー1へと陣形を変更しました。マルティノスと齋藤学が高い位置を取ってくるので、鳥栖はセンターハーフとサイドバックで彼ら2人を対処し、中央の3人でウーゴヴィエイラ・伊藤翔を抑えるという形を取りました。ただし、この変更により、ただでさえプレスのかかりきってなかった前線から1枚剥ぎ取ることによって、なおさらマリノスの最終ラインの押し上げを許すことになってしまいます。
比重を後ろに置くことによって、ある程度の押し込みを受けることは想定していたでしょうが、少しでもその押し込みを防ぐために、5バックにすると同時に前線の選手の活性化を図らなければなりません。特に豊田と鎌田は足がとまっており、前半、あれだけにらみを利かせていたデゲネクの上りをただ茫然と見守るだけになってしまい、カウンターのチャンスでも余力は残っておらず、前線で時間を稼ぐことすらできず、戦うにはあまりにも体力的に厳しい状態でした。
5-4-1のシステムをとった時に重要なのは後ろの選手ではなく、肝心なのは前線の動きであり、味方を支える全体の運動量です。豊田の交替はセットプレイの弾き返し役と前線の運動量のトレードオフと考えていたのでしょうが、結局、鳥栖の2人目の交替はアディショナルタイムに入ってからでした。
試合のクロージングは難しく、選手交代が裏目に出ることもあります。今回の試合は結果として勝利を挙げましたが、そのプロセスを振り返るともう少し試合運びを上手にやれたのではないかと感じる点が多かったです。
■ MVP義希、MIP福田
この熱い試合を観戦した方はそれぞれ自分の中で選手たちの活躍に対する感想(評価)を持ったことでしょう。サッカーを観戦して、各々が自分なりの解釈で試合を振り返るというのは、サッカー文化の醸成のためにも非常に良いことです。
この試合での評価は、福田に対する賛辞が多く聞こえてきました。攻撃に守備にまさに八面六臂の活躍で、特に後半終了間際のカウンターの場面でのシュートは決まらなかったものの、足が動いていない鳥栖の前線をカバーして余りある働きをしていました。味方のシュートに繋がるパスも何本も供給でき、今シーズンの不振を払しょくするような出色の出来でした。
このように、鮮烈に印象に残るプレイはありましたが、その反面、表面に現れないインシデントを発生させていたことも見逃せません。ゴール前で不用意にボールを持ちすぎて、相手のファールを取ってくれたから助かったものの失点につながるミスが発生しそうになったシーンや、プレスしなければならないところで躊躇してしまい(ゾーンの意識?体力切れ?)その結果相手の前進を許してしまったシーンなど。また、攻撃面でもパスの丁寧さに欠けてチャンスにつながりそうなところがうまく組み立てできなかったシーンもありました。
スタメンで試合に出始めてからそろそろ丸一年と言う頃でしょうか。彼のプレースタイルも認知され、泥臭くハードワークで走りきるという鳥栖のスタイルにぴったりと合っており、人気も期待も大きく背負っている選手です。彼こそ、次の世代の鳥栖のリーダーとして将来はチームを先頭に立って率いて欲しいのですが、まだまだ技術的にも成長する余地はありますし、もっともっとプレイの精度を上げて試合によって発生する好不調の波を少なくしてほしいですね。
対して、私はこの試合のMVPは義希を推します。先ほどインシデント(事故につながりかねない事象)という言葉を使いましたが、マリノスのチャンスを生みだしそうなインシデントを悉くつぶしていました。スペースに対するカバーリング、ボールに対するアクション、特にこの試合ではマリノスの攻撃の次の一手に対する予知が素晴らしく、ここにボールが出るだろうというエリア・選手をいち早く察知してマリノスのやりたい事を素早くつぶしていました。ボールの繋ぎに関してもチャンスと見るやダイレクトで前に送り、絶対にボールを奪われてはいけない位置ではセーフティファーストを心掛け、終盤では、足が止まってしまった前線の守備不足への対処も彼が行っていましたし、TPOに応じた動きでチーム全体の屋台骨として支えていました。義希の動きがあったからこそ掴めた勝利と言っても過言ではありません。
このことから、最も印象に残ったプレイヤーは福田、最も価値のあるプレイヤーは義希という私なりの思いです。みなさんの中のMIPとMVPは誰だったでしょうか。得点を取った鎌田という方もいらっしゃると思いますし、決定的なシーンを防いだ権田と言う方や齋藤を完璧に抑えこんだ小林という方もいらっしゃると思います。それぞれの思いでこの試合を解釈して振り返ってみると、サッカーがより面白くなるかなと思います。
■義希ベストプレイセレクション(その1)



■義希ベストプレイセレクション(その2)

■義希ベストプレイセレクション(その3)


■義希ベストプレイセレクション(その4)


<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
20:56
│Match Impression (2017)
2017年05月02日
2017 第9節 : 鹿島アントラーズ VS サガン鳥栖
鹿島戦を簡単に振り返ります。
マッシモさんのコメント、豊田のコメントを見る所に、アウェーということで、中盤でしっかりとした守備ができる小野を先発にしてから臨んだというところでしょうか。守備時の雰囲気的には4-5-1(4-3-2-1)で、前線から激しく最終ラインをチェイスするのではなく、フォワードのどちらかの一人が(神戸戦の後半程ではありませんが)中盤のサポートをするという形だったのですが、先制点もつかの間、鳥栖のミス(あえてミスと言いますが)によって、鹿島の逆転を許し、ビハインドを追う展開となってしまいました。
プランとして前半は堅くということで入りましたが、後半に入るとビハインドの状況なのでどこかのタイミングで攻め始めなければなりません。攻撃のスイッチとしては、そうですね、鎌田に代わってチョドンゴンが入った当たりでしょうか。前線へのボールの配球でひとつ彼がポイントを作ることになるのですが、それでもシュートチャンスを多く迎えるような展開にはならずという所で、更なる攻勢をしかけるために79分にイバルボを投入します。
しかしながら、今回はイバルボの投入が裏目となってしまった感が強く、フォワードが左右に大きく張り出したのは良いのですが、そこまでボールを運ぶことに苦労してしまい、かといってストロングポイントを生かすべくロングボールでしかけるようなアタックもなく、とにかく、試合全体を通じてなかなか攻撃の形が作れず、終わってみればPK1本与えてもらった割に、そしてビハインドの時間が45分以上もあった割には、シュートが6本とはやや寂しい限りの試合でした。
鹿島は、コンパクトな守備陣形なのですが、豊田に植田がしっかりとマーキングしていたように、自分がマークするべき選手に対する意識が強いので、相手選手に引っ張られるシーンも多々あります。前半にそこをうまく活用できたシーンがありましたので、紹介します。
ボールは、キーパーの権田のスローから始まります。ディフェンスラインでボールを回して、左サイドの吉田からミンヒョクにボールが入った時に、うまい具合に小川がアンカーの位置で顔を出します。全体の連動はここからスタートして、ミンヒョク⇒小川⇒小野⇒ミンヒョク⇒鎌田へと、それぞれが味方の空けたスペースを利用するべく上下に顔を出しており、連動した素晴らしいつなぎでした。




実は、この攻撃の良い所は、組み立てに豊田が参加していないことだと考えます。ミンヒョクのパスが良い状態で鎌田に繋がったとしたら、豊田はゴール前にフィニッシャーの役割として顔を出せることになります。私的には、これが一番大事なことだと思うのです。
チームとして、シュートを放つ行為に至るまでの組み立て(青写真)をどう描いているか、また、その青写真がいかに選手間で共有されているかというのは非常に大事なことです。その共通意識がないと、個人個人が攻撃に寄与しようとする動きが単発(悪い言い方をするとムダ)になってしまって、組織として崩すことができません。
例えばチームとして誰をフィニッシャー役とするのか、フィニッシャーが得点の可能性を秘めるシュートを放つためには誰がどのようなラストパスを送るのがベストなのか、そのラストパスを送るシーンを作るために誰を経由してどのような崩しのプロセスを踏めばよいのか、そのためにどの位置でボールを奪って攻撃に転じたいのか。この試合は時間が進むにつれて(選手交代を行うにつれて)共通のイメージを選手たちが段々と持てなくなっていったように目に映りました。
ちなみに、下に示しますが、試合終了も近づいてきた時間帯にこのシーンを見た時に、鹿島によほどのミスがない限り、負けゲームであるということを覚悟しました。ボールの動きに対して、また、原川の動きに対して、回りが何かアクションを取って攻撃を活性化しようとする動きがほとんど発生しておらず、ビハインドの場面で残り時間をどのように有意義につかうかという意図が感じられなかったからです。




鹿島の守備が良かったとはいえ、テレビで見ている限りでも、3人のトップの選手をどのような役割でどのように使いたいのか、ゴールへのプロセス(青写真)を感じ取ることができず、非常にフラストレーションのたまる試合でした。
サッカーの1点は非常に重いものでありまして、その重い1点を取るためには、いろいろと策をめぐらせなければなりません。その策を講じたとしても必ず得点が取れるわけではありませんが、チームとしていろいろな策を講じて共通意識を持って戦う事が「面白いサッカー」ひいては「勝てるサッカー」に繋がると思います。今回は残念な結果でしたが、また、トレーニングして次節はよい試合を見せて欲しいと思います。
<画像引用元:DAZN>
マッシモさんのコメント、豊田のコメントを見る所に、アウェーということで、中盤でしっかりとした守備ができる小野を先発にしてから臨んだというところでしょうか。守備時の雰囲気的には4-5-1(4-3-2-1)で、前線から激しく最終ラインをチェイスするのではなく、フォワードのどちらかの一人が(神戸戦の後半程ではありませんが)中盤のサポートをするという形だったのですが、先制点もつかの間、鳥栖のミス(あえてミスと言いますが)によって、鹿島の逆転を許し、ビハインドを追う展開となってしまいました。
プランとして前半は堅くということで入りましたが、後半に入るとビハインドの状況なのでどこかのタイミングで攻め始めなければなりません。攻撃のスイッチとしては、そうですね、鎌田に代わってチョドンゴンが入った当たりでしょうか。前線へのボールの配球でひとつ彼がポイントを作ることになるのですが、それでもシュートチャンスを多く迎えるような展開にはならずという所で、更なる攻勢をしかけるために79分にイバルボを投入します。
しかしながら、今回はイバルボの投入が裏目となってしまった感が強く、フォワードが左右に大きく張り出したのは良いのですが、そこまでボールを運ぶことに苦労してしまい、かといってストロングポイントを生かすべくロングボールでしかけるようなアタックもなく、とにかく、試合全体を通じてなかなか攻撃の形が作れず、終わってみればPK1本与えてもらった割に、そしてビハインドの時間が45分以上もあった割には、シュートが6本とはやや寂しい限りの試合でした。
鹿島は、コンパクトな守備陣形なのですが、豊田に植田がしっかりとマーキングしていたように、自分がマークするべき選手に対する意識が強いので、相手選手に引っ張られるシーンも多々あります。前半にそこをうまく活用できたシーンがありましたので、紹介します。
ボールは、キーパーの権田のスローから始まります。ディフェンスラインでボールを回して、左サイドの吉田からミンヒョクにボールが入った時に、うまい具合に小川がアンカーの位置で顔を出します。全体の連動はここからスタートして、ミンヒョク⇒小川⇒小野⇒ミンヒョク⇒鎌田へと、それぞれが味方の空けたスペースを利用するべく上下に顔を出しており、連動した素晴らしいつなぎでした。




実は、この攻撃の良い所は、組み立てに豊田が参加していないことだと考えます。ミンヒョクのパスが良い状態で鎌田に繋がったとしたら、豊田はゴール前にフィニッシャーの役割として顔を出せることになります。私的には、これが一番大事なことだと思うのです。
チームとして、シュートを放つ行為に至るまでの組み立て(青写真)をどう描いているか、また、その青写真がいかに選手間で共有されているかというのは非常に大事なことです。その共通意識がないと、個人個人が攻撃に寄与しようとする動きが単発(悪い言い方をするとムダ)になってしまって、組織として崩すことができません。
例えばチームとして誰をフィニッシャー役とするのか、フィニッシャーが得点の可能性を秘めるシュートを放つためには誰がどのようなラストパスを送るのがベストなのか、そのラストパスを送るシーンを作るために誰を経由してどのような崩しのプロセスを踏めばよいのか、そのためにどの位置でボールを奪って攻撃に転じたいのか。この試合は時間が進むにつれて(選手交代を行うにつれて)共通のイメージを選手たちが段々と持てなくなっていったように目に映りました。
ちなみに、下に示しますが、試合終了も近づいてきた時間帯にこのシーンを見た時に、鹿島によほどのミスがない限り、負けゲームであるということを覚悟しました。ボールの動きに対して、また、原川の動きに対して、回りが何かアクションを取って攻撃を活性化しようとする動きがほとんど発生しておらず、ビハインドの場面で残り時間をどのように有意義につかうかという意図が感じられなかったからです。




鹿島の守備が良かったとはいえ、テレビで見ている限りでも、3人のトップの選手をどのような役割でどのように使いたいのか、ゴールへのプロセス(青写真)を感じ取ることができず、非常にフラストレーションのたまる試合でした。
サッカーの1点は非常に重いものでありまして、その重い1点を取るためには、いろいろと策をめぐらせなければなりません。その策を講じたとしても必ず得点が取れるわけではありませんが、チームとしていろいろな策を講じて共通意識を持って戦う事が「面白いサッカー」ひいては「勝てるサッカー」に繋がると思います。今回は残念な結果でしたが、また、トレーニングして次節はよい試合を見せて欲しいと思います。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
17:59
│Match Impression (2017)
2017年04月25日
2017 第8節 : サガン鳥栖 VS ヴィッセル神戸
神戸との試合は、前半早々に上げた1点をしっかりと守りきり、上位相手から貴重な勝ち点3を奪う事ができました。早い時間に先制してしまうと、相手が攻勢を強めてくるので、どうしても受け身の戦いにならざるを得ないのですが、しっかりとした守りを軸にしながらも、追加点の決定的チャンスを数回作ることができ、非常にアグレッシブで楽しい試合でした。
前半開始から30分過ぎくらいまでは、神戸の組織的な攻撃に手を焼くシーンもあったのですが、鳥栖の守備陣が徐々に相手の動きにフィットすることができました。特に後半からは、開始からのフォワードを1列下げた4-4-1-1(ないしは4-5-1)の形や、相手が3トップになってからの5-4-1という、マッシモ監督の指示の下で選手たちがフレキシブルに対応することができ、ベンチワークの戦いと言う意味でも非常に熱い試合でした。
■ 守備陣形
前半途中までは、神戸が左右にボールを振って、鳥栖のゾーンの乱れが発生した時に、うまくサイドバックがそのギャップをついた攻めをするシーンが目立ちました。特に、大森、松下の二人が左右のいろいろなポジションに顔を見せていたたため、そこにサイドバックがオーバーラップしてくると、局面的な不利を迎えてしまって非常に対処に苦労していました。(下図2つ参照)


しかしながら、鳥栖の選手たちも、前半30分頃には徐々に神戸の選手たちの動きに慣れてきて、特に、サイドバックやサイドハーフが相手に食いつく(相手のダイアゴナルや上下の動きに対してマークについていく)べきところと、離すところを選手間で相互理解できてきて、不用意なスペースを作ることが段々と少なくなってきました。また、押し込まれたときに豊田やチョドンゴンが守備に参加することによって、何とか神戸の攻撃をしのぐことができました。

後半になって、マッシモさんが手を打ってきます。鳥栖のフォワードの後ろ(3ボランチのエリア)で面白いようにボールを回されているのを打破すべく、後半に入ってからは、フォワード(主にチョドンゴン)を1枚下げた形で4-4-1-1(4-5-1)の形で構えるようになりました。これが非常に奏功して、神戸のボランチがボールを受けた際に、必ずチョドンゴンが対峙し、ボランチを自由にさせないことによって、展開のスピードを遅らせる事が出来ました。
また、前半は神戸ボランチに対して鳥栖のハーフがマークについたスペース(バイタル)を使われることが多かったのですが、チョドンゴンを下げたことによって、バイタルにスペースを作らずコンパクトさを保つことができ、中央を固めることができました。神戸もボールの展開に成功して、大きなサイドチェンジからチャンスを作ることも度々ありましたが、中央のブロックを崩されたわけではないので、何とかクロスを跳ね返すことに成功していました。





この4-5-1がもたらしたもう一つの効果は、豊田がワントップで張っているため、鳥栖の攻撃へのトランジションで、ボールの出しどころが明確であるという点です。豊田にボールが集まるので、自然と彼のフォローに選手たちが集まってくるので、カウンターの起点が明確になりました。
また、チョドンゴンの攻守の切り替えが早くて、ボールを奪えそうな状態になったら、下がった状態から1列ポジションをあげて、すぐに豊田のフォローができる位置にポジショニングをとっていました。ボールの出しどころが明確になることによって、周りの鳥栖の選手たちがはっきりとプレイできるようになったのは、思わぬ効果だったかなと思います。
最後は、小林を投入して、5バックにして神戸の猛攻を乗り切りましたが、神戸が3トップ気味にして、両サイドをワイドに使って選手を張らせていたため、そのような作戦を取ったのかなと思いました。マッシモさんがこれまで5バックを取ってこなかったので、ついついいろいろと考えてしまうのですが、確かに、相手が2トップのままで人数を集めて中央をついてくるならば、5バックにしてサイドのスペースを埋めても、今回ほど大きな効果を得ることはできないですしね。

今後、ステレオタイプ的に後半40分過ぎからは5バックで守備を固めて守りきるという形になるのか、それとも相手陣形を見た上で5バックは選択肢のひとつとして用いるのかわかりませんが、今回は相手の陣形への対処という意味でも、選手たちへの守りきるという意思表示と言う意味でも、小林の投入は非常に大きな采配でした。
最後に、手前味噌ですが、チョドンゴンを3月のルヴァンカップ新潟戦で初めて見た時の印象をBlogに書いていました。自分が気に入ったプレイヤーが活躍してくれるのは、やっぱり気持ちいいものですよね。
----------
個人的に、良いプレイヤーだなと思ったのは、チョドンゴンです。ワンタッチでのプレイや裏へのダイレクトパス、ポストプレイなど、ゲームの組み立てに寄与しようとする動きがよく見えました。彼自身ではなく、彼の周りのいるプレイヤーのレベルが上がると、彼自身が更に生きてくるのではないかと感じました。
----------
この試合では、チョドンゴンは得点の方が目立ちますが、私は後半の彼の攻守に貢献する動き、特に、守備時のファーストディフェンダーとして相手のボランチを封じた動きが鳥栖に勝利をもたらせたと思います。守備に関しては、豊田も時折ハーフの位置や最終ラインに戻って守備をこなしていましたし、まさに全員でつかんだ勝利ですね。
イバルボは彼のいいところがあるし、また新たにチョドンゴンのいいところも発見できましたし、今後のマッシモさんの選手起用が楽しみです。
<画像引用元:DAZN>
前半開始から30分過ぎくらいまでは、神戸の組織的な攻撃に手を焼くシーンもあったのですが、鳥栖の守備陣が徐々に相手の動きにフィットすることができました。特に後半からは、開始からのフォワードを1列下げた4-4-1-1(ないしは4-5-1)の形や、相手が3トップになってからの5-4-1という、マッシモ監督の指示の下で選手たちがフレキシブルに対応することができ、ベンチワークの戦いと言う意味でも非常に熱い試合でした。
■ 守備陣形
前半途中までは、神戸が左右にボールを振って、鳥栖のゾーンの乱れが発生した時に、うまくサイドバックがそのギャップをついた攻めをするシーンが目立ちました。特に、大森、松下の二人が左右のいろいろなポジションに顔を見せていたたため、そこにサイドバックがオーバーラップしてくると、局面的な不利を迎えてしまって非常に対処に苦労していました。(下図2つ参照)


しかしながら、鳥栖の選手たちも、前半30分頃には徐々に神戸の選手たちの動きに慣れてきて、特に、サイドバックやサイドハーフが相手に食いつく(相手のダイアゴナルや上下の動きに対してマークについていく)べきところと、離すところを選手間で相互理解できてきて、不用意なスペースを作ることが段々と少なくなってきました。また、押し込まれたときに豊田やチョドンゴンが守備に参加することによって、何とか神戸の攻撃をしのぐことができました。

後半になって、マッシモさんが手を打ってきます。鳥栖のフォワードの後ろ(3ボランチのエリア)で面白いようにボールを回されているのを打破すべく、後半に入ってからは、フォワード(主にチョドンゴン)を1枚下げた形で4-4-1-1(4-5-1)の形で構えるようになりました。これが非常に奏功して、神戸のボランチがボールを受けた際に、必ずチョドンゴンが対峙し、ボランチを自由にさせないことによって、展開のスピードを遅らせる事が出来ました。
また、前半は神戸ボランチに対して鳥栖のハーフがマークについたスペース(バイタル)を使われることが多かったのですが、チョドンゴンを下げたことによって、バイタルにスペースを作らずコンパクトさを保つことができ、中央を固めることができました。神戸もボールの展開に成功して、大きなサイドチェンジからチャンスを作ることも度々ありましたが、中央のブロックを崩されたわけではないので、何とかクロスを跳ね返すことに成功していました。





この4-5-1がもたらしたもう一つの効果は、豊田がワントップで張っているため、鳥栖の攻撃へのトランジションで、ボールの出しどころが明確であるという点です。豊田にボールが集まるので、自然と彼のフォローに選手たちが集まってくるので、カウンターの起点が明確になりました。
また、チョドンゴンの攻守の切り替えが早くて、ボールを奪えそうな状態になったら、下がった状態から1列ポジションをあげて、すぐに豊田のフォローができる位置にポジショニングをとっていました。ボールの出しどころが明確になることによって、周りの鳥栖の選手たちがはっきりとプレイできるようになったのは、思わぬ効果だったかなと思います。
最後は、小林を投入して、5バックにして神戸の猛攻を乗り切りましたが、神戸が3トップ気味にして、両サイドをワイドに使って選手を張らせていたため、そのような作戦を取ったのかなと思いました。マッシモさんがこれまで5バックを取ってこなかったので、ついついいろいろと考えてしまうのですが、確かに、相手が2トップのままで人数を集めて中央をついてくるならば、5バックにしてサイドのスペースを埋めても、今回ほど大きな効果を得ることはできないですしね。

今後、ステレオタイプ的に後半40分過ぎからは5バックで守備を固めて守りきるという形になるのか、それとも相手陣形を見た上で5バックは選択肢のひとつとして用いるのかわかりませんが、今回は相手の陣形への対処という意味でも、選手たちへの守りきるという意思表示と言う意味でも、小林の投入は非常に大きな采配でした。
最後に、手前味噌ですが、チョドンゴンを3月のルヴァンカップ新潟戦で初めて見た時の印象をBlogに書いていました。自分が気に入ったプレイヤーが活躍してくれるのは、やっぱり気持ちいいものですよね。
----------
個人的に、良いプレイヤーだなと思ったのは、チョドンゴンです。ワンタッチでのプレイや裏へのダイレクトパス、ポストプレイなど、ゲームの組み立てに寄与しようとする動きがよく見えました。彼自身ではなく、彼の周りのいるプレイヤーのレベルが上がると、彼自身が更に生きてくるのではないかと感じました。
----------
この試合では、チョドンゴンは得点の方が目立ちますが、私は後半の彼の攻守に貢献する動き、特に、守備時のファーストディフェンダーとして相手のボランチを封じた動きが鳥栖に勝利をもたらせたと思います。守備に関しては、豊田も時折ハーフの位置や最終ラインに戻って守備をこなしていましたし、まさに全員でつかんだ勝利ですね。
イバルボは彼のいいところがあるし、また新たにチョドンゴンのいいところも発見できましたし、今後のマッシモさんの選手起用が楽しみです。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
21:23
│Match Impression (2017)
2017年04月19日
2017 第7節 : ジュビロ磐田 VS サガン鳥栖
磐田との戦いは、試合終了間際に上げたエース豊田のゴールで幕を閉じるかと思いきや、思いもよらぬ展開で逆転負けを喫してしまいました。悔やむに悔やみきれない逆転負けですが、試合全体を通じて見ると、鳥栖よりも磐田の方がやりたかった事を実現できていたのかなという感じです。
磐田は昨年度にトップを張っていたジェイから川又に代わったものの、チームのやり方としては大きく変わったわけではなく、中央で起点を作って最後はサイドからのクロスでフィニッシュの形を迎えるという、非常にシンプルな形の攻撃でした。ただ、やはり、中村俊の加入は非常に大きく、攻撃のタクトをふるうに当たって非常に大きな補強だったかと思います。
鳥栖はボールサイドの選手を寄せて、コンパクトな陣形の中でボールを奪いとる戦術であるので、相手が鳥栖の寄せに対応できなかった場合は、よい形でボールを奪えるのですが、相手がプレスを潜り抜けて逆サイドへ早い展開をしかけた場合、スライドに時間を要してしまって、相手の縦へのスピードへの対応が遅くなるという所です。
この日の磐田は、そのあたりの出し入れがうまくハマる展開が多く、鳥栖の守備としては、相手がクロスを上げるところまで迫ってくるので思いのほかボールを奪う位置が低くて攻撃に転じるチャンスが少なかったかなと思います。実際、クロスは磐田の17本に対して鳥栖は13本、シュートは磐田の13本に対して鳥栖は5本と、数値だけ見ても、磐田の方が攻勢に立っていたのかなという感じです。
■ パターンその1


■ パターンその2


鳥栖の狙いとしては、両サイドのスペースですが、磐田の3バックのストッパーは、鳥栖のハーフ(鎌田、福田、小野)がそのスペースを突くことが分かっていたので、予めスペースを埋める動きで抑制していました。センターバックやボランチの位置から縦へのパスが入らないことが分かっている(縦に入っても効果的な攻撃に繋がらない確率が高い)ので、そのあたりはある程度自由に持たせて、サイドの裏のスペースをケアすることを第一優先として対応していました。
鳥栖としては、サイド攻撃が封じられている状況と言う所で、手をこまねいているだけでは点が取れず、バリエーションを出して行かなければなりません。そこで二の矢、三の矢を打つ必要があるのですが、そのヒントとなった良いシーンがあったので紹介します。サイドに流れた鎌田を囮として利用した、連動性のある攻撃でした。




私は、このシーンを見て、義希から原川への交替の意図としては、サイドのスペースが消されて思うように使えないということは、逆にいうとこのシーンのように、サイドが封じられている分いつもよりもセンターの位置でボールを持つことができ、中央のスペースを使える確率が上がるという事で、得点を取るために、ドリブルでボールを運ぶことが出来て、パスをうまく回すことができる原川を起用したのかなと思いました。この手自体は決して悪かったとは思わず、試合の流れ・動きを見た的確な采配だと感じます。
実際、試合終了間際まで粘る展開ながらも先制点を奪い、実質勝利を手中に納めかけました。ただし、得点を奪った後には相手が同点に追いつくため(逆転を狙うため)に攻勢に出ることが分かっているわけでありまして、そのあたりの試合のクロージングに失敗したかなという感じです。監督はミスと言っていましたが、同点のシーンは確かに、ミスが連鎖したので仕方ないにしても、同点に追い付かれてからの戦い方に関しては、監督の采配も含めたチーム全体のミスとも言えるかもしれません。
ちょっと、同点のシーンをおさらいしてみますが、一番大きいのはセンターバック二人が跳ね返すことができなかったこと、二番目は福田がプレスに行ってしまったので戻りきれなかったこと、三番目は吉田が中村にクロスを上げさせてしまったこと、四番目は田川がセンターハーフの位置から最終ラインのカバーができなったこと(これはちょっと考え方次第)かなと思います。全員、責められるものではなく、プレイとしてはやむを得ない事なのですが、それが重なると失点と言う形に現れてしまいますよね。




鳥栖は、同点に追い付かれてからも攻めの姿勢を崩さず、攻める事を優先しました。アディショナルタイムだけ見ると、チャンスを作ったけれども決めきることが出来なかった鳥栖と、チャンスをしっかりと決めることができた磐田という違いだけだと思いますが、試合全体を通じて見たときには、思い通りの展開に引きづり込むことが出来た磐田と、義希を変えてでもリズムを変えなければならなかった鳥栖という事で、それがこの試合結果に繋がったのかなと思います。
最後に、一つだけ気になったことは、磐田のように川又にボールを納めさせてそこから中村俊に展開というように、決まりきったパターンや優先ごとを持つことが、実は今の鳥栖に必要なことではないかと考えました。この試合だけではなく、今シーズンのこれまでの試合でもそうなのですが、鳥栖全体として鎌田にボールを集めるという意識が昨年度よりは薄いのかなと感じてしまいます。当然、状況や相手との関係によって、パスが出せないというのもあるのですが、鎌田がよい動きをしてフリーでいても、なかなかそこにボールが出ないことがあります。
イバルボ・小野・原川などボールを持てて強い選手も入ってきてパスの選択肢が多くなったのですが、あまりにも単純に蹴りすぎて次の攻撃に繋がらないシーンも多く見えます。私は、タメを作れるという意味でも、鎌田が良いポジションにいるならば、一旦彼を経由した方が、試合全体が潤滑油のように回っていくのではないかと感じました。あまりにもゴールへ向かうスピードをあげてしまうと、自分たちのリズムに落とし切れない間にトランジションが発生してしまっているのかなと。
周りから見るのと選手たちが感じることは当然異なるので、一概にそうとは言えないのかもしれませんが、鎌田に大きな可能性を感じている一人としては、せっかくフリーでいるならば、彼を使って欲しいという思いがあります。

<画像引用元:DAZN>
磐田は昨年度にトップを張っていたジェイから川又に代わったものの、チームのやり方としては大きく変わったわけではなく、中央で起点を作って最後はサイドからのクロスでフィニッシュの形を迎えるという、非常にシンプルな形の攻撃でした。ただ、やはり、中村俊の加入は非常に大きく、攻撃のタクトをふるうに当たって非常に大きな補強だったかと思います。
鳥栖はボールサイドの選手を寄せて、コンパクトな陣形の中でボールを奪いとる戦術であるので、相手が鳥栖の寄せに対応できなかった場合は、よい形でボールを奪えるのですが、相手がプレスを潜り抜けて逆サイドへ早い展開をしかけた場合、スライドに時間を要してしまって、相手の縦へのスピードへの対応が遅くなるという所です。
この日の磐田は、そのあたりの出し入れがうまくハマる展開が多く、鳥栖の守備としては、相手がクロスを上げるところまで迫ってくるので思いのほかボールを奪う位置が低くて攻撃に転じるチャンスが少なかったかなと思います。実際、クロスは磐田の17本に対して鳥栖は13本、シュートは磐田の13本に対して鳥栖は5本と、数値だけ見ても、磐田の方が攻勢に立っていたのかなという感じです。
■ パターンその1


■ パターンその2


鳥栖の狙いとしては、両サイドのスペースですが、磐田の3バックのストッパーは、鳥栖のハーフ(鎌田、福田、小野)がそのスペースを突くことが分かっていたので、予めスペースを埋める動きで抑制していました。センターバックやボランチの位置から縦へのパスが入らないことが分かっている(縦に入っても効果的な攻撃に繋がらない確率が高い)ので、そのあたりはある程度自由に持たせて、サイドの裏のスペースをケアすることを第一優先として対応していました。
鳥栖としては、サイド攻撃が封じられている状況と言う所で、手をこまねいているだけでは点が取れず、バリエーションを出して行かなければなりません。そこで二の矢、三の矢を打つ必要があるのですが、そのヒントとなった良いシーンがあったので紹介します。サイドに流れた鎌田を囮として利用した、連動性のある攻撃でした。




私は、このシーンを見て、義希から原川への交替の意図としては、サイドのスペースが消されて思うように使えないということは、逆にいうとこのシーンのように、サイドが封じられている分いつもよりもセンターの位置でボールを持つことができ、中央のスペースを使える確率が上がるという事で、得点を取るために、ドリブルでボールを運ぶことが出来て、パスをうまく回すことができる原川を起用したのかなと思いました。この手自体は決して悪かったとは思わず、試合の流れ・動きを見た的確な采配だと感じます。
実際、試合終了間際まで粘る展開ながらも先制点を奪い、実質勝利を手中に納めかけました。ただし、得点を奪った後には相手が同点に追いつくため(逆転を狙うため)に攻勢に出ることが分かっているわけでありまして、そのあたりの試合のクロージングに失敗したかなという感じです。監督はミスと言っていましたが、同点のシーンは確かに、ミスが連鎖したので仕方ないにしても、同点に追い付かれてからの戦い方に関しては、監督の采配も含めたチーム全体のミスとも言えるかもしれません。
ちょっと、同点のシーンをおさらいしてみますが、一番大きいのはセンターバック二人が跳ね返すことができなかったこと、二番目は福田がプレスに行ってしまったので戻りきれなかったこと、三番目は吉田が中村にクロスを上げさせてしまったこと、四番目は田川がセンターハーフの位置から最終ラインのカバーができなったこと(これはちょっと考え方次第)かなと思います。全員、責められるものではなく、プレイとしてはやむを得ない事なのですが、それが重なると失点と言う形に現れてしまいますよね。




鳥栖は、同点に追い付かれてからも攻めの姿勢を崩さず、攻める事を優先しました。アディショナルタイムだけ見ると、チャンスを作ったけれども決めきることが出来なかった鳥栖と、チャンスをしっかりと決めることができた磐田という違いだけだと思いますが、試合全体を通じて見たときには、思い通りの展開に引きづり込むことが出来た磐田と、義希を変えてでもリズムを変えなければならなかった鳥栖という事で、それがこの試合結果に繋がったのかなと思います。
最後に、一つだけ気になったことは、磐田のように川又にボールを納めさせてそこから中村俊に展開というように、決まりきったパターンや優先ごとを持つことが、実は今の鳥栖に必要なことではないかと考えました。この試合だけではなく、今シーズンのこれまでの試合でもそうなのですが、鳥栖全体として鎌田にボールを集めるという意識が昨年度よりは薄いのかなと感じてしまいます。当然、状況や相手との関係によって、パスが出せないというのもあるのですが、鎌田がよい動きをしてフリーでいても、なかなかそこにボールが出ないことがあります。
イバルボ・小野・原川などボールを持てて強い選手も入ってきてパスの選択肢が多くなったのですが、あまりにも単純に蹴りすぎて次の攻撃に繋がらないシーンも多く見えます。私は、タメを作れるという意味でも、鎌田が良いポジションにいるならば、一旦彼を経由した方が、試合全体が潤滑油のように回っていくのではないかと感じました。あまりにもゴールへ向かうスピードをあげてしまうと、自分たちのリズムに落とし切れない間にトランジションが発生してしまっているのかなと。
周りから見るのと選手たちが感じることは当然異なるので、一概にそうとは言えないのかもしれませんが、鎌田に大きな可能性を感じている一人としては、せっかくフリーでいるならば、彼を使って欲しいという思いがあります。

<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
17:42
│Match Impression (2017)
2017年04月12日
2017 第6節 : サガン鳥栖 VS アルビレックス新潟
■ 雑感
先日行われたアルビレックス新潟との試合の雑感です。簡単に振り返ります。
スコアこそ、3-0という試合ですが、一歩間違ったらその結果は逆転していた可能性はあったかもしれないという試合でした。
新潟の攻撃のセットアップとして、サイドハーフの端山と山崎を鳥栖のサイドバックくらいまでの高い位置に上げていました。狙いとしては、端山と山崎が引いてボールを受ける動きに対してサイドバックがついてきたときに、そのスペースをフォワードに狙わせるというのが見て取れました。
このやり方の弊害としては、新潟としてはダブルボランチ2人が組み立てようとするところに、鳥栖の中盤の3人が対峙することになり、中盤のつなぎとしては数的不利が生まれます。新潟が思いのほか長いボールが多かったのは、戦術によるところもあるでしょうが、鳥栖のプレッシャーに対しての逃げ場がなかったというのもあるでしょう。

ただ、新潟の狙いもハマらなかったわけではなく、何度となくスペースを空ける動きが成功していました。前半16分のシーンは、見事にそのスペースをついてからのホニのシュートでしたが、わずかにゴールを外れました。パスの精度が悪かったり、味方が気づいていなかったりなどによって、ゴールという結果までは生まれなかったのですが、これからこの形に対する連動性を向上させることができれば一つの形として確立できそうな気がします。


今回の新潟のストロングポイントとして、戦術云々よりもガリャルドとホニの動きが洗練しすぎており、前半10分の中央のスルーパスのシーンに代表されるように、トランジションの場面でうまく最終ラインの前でガリャルドがボールを受けると、最終ラインの人数がそろっていてもそれをはがして割り切るドリブル能力そしてパス能力の高さを発揮しておりました。最終ラインから飛び出すホニに対するガリャルドのパスというコンビネーションは非常に脅威でして、決定的なピンチを何度も招いていましたが、天の恵みと言いますか、雨が降っていて「すべるゾーン」がホニの動きを止める攻撃ストッパーになってくれていたのは、(例え運であっても)この試合のひとつのポイントだったかと思います。助かった~というシーンは非常に多かったです。
対して、鳥栖は、4-3-1-2から4-4-2にしてから上手く回ったという監督のコメントがありましたが、この類のコメントはもはや鳥栖の恒例行事になっているような気がしますね(笑) もちろん、ポジショニングは相手次第というところもありますので、試合の中で対応していかなければならないことは確かです。
ただ、チームの成長のため、そして鎌田の成長のためには、4-3-1-2を模索して組織として作り上げきってほしいなと思っています。4-4-2だと、自分の動けるエリアも役割も明確になって動きやすいでしょうが、明確なだけに、展開や戦況を大きく変えるような動きが取りづらいです。その点、4-3-1-2だと、トップ下の鎌田をフリーマン的に攻守に活用することによって、数的不利なエリアへのサポートや、相手が作ったギャップへの切り込みなど、鎌田の判断だけでその試合を有利な状況に持ってくることができる可能性を秘めています。
ただ、そのためには、セントラルハーフの3人だけで、攻撃・守備をある程度賄えるようになることも必要ですし、当然のことながら運動量が求められますし、何よりもチーム全体として戦況を見極められる広い戦術眼が求められます。これらを、試合を通じて高めていくことによって、中盤の4人が躍動する更に高いレベルのサッカーをサガン鳥栖が見せてくれることを大きく期待しています。
さて、新潟戦に戻りますが、確かに、前半の最初は、イバルボと鎌田が非常にちぐはぐな感じでポジショニングを取っていたシーンもありましたが、鎌田の動きによっては、サイドの数的有利の状況を作り出してよい攻撃を仕掛けていたシーンもありました。
前半に、イバルボに長いボールを当てて彼がキープして、イバルボの頭を超える素晴らしいパスで鎌田が前を向いてボールを受けて、シュートを放つ(逆サイドの豊田がつめていて惜しかったですが)と言うシーンは、一つのポイントだと思います。両サイドハーフとイバルボがサイドで組み立ててからの展開と言うのは、ひとつの形になっていたのかなと思いました。
気になったのは新潟の右サイドでありまして、端山・矢野・加藤のコンビネーションが悪くて(端山は今期初出場だったんですね)、吉田が追い越して上がってくるとマークの付き方がメンバー間で整理されておらず、ボール保持者へのプレッシャーが弱くなって、鳥栖が余裕を持ってパスコースを選択できる場面が見受けられました。
あと、PKの前のシーンもですが、前からボールを奪いたい前線と、しっかりとブロックを組みたい2列目・最終ラインとの息が合わずに、中盤に大きなスペースを空けることも多々ありました。新潟は、守備面では非常に課題の大きかった試合だったのかなと思います。


鳥栖も、攻撃が機能するシーンも見られましたが、逆サイド側に展開することを見越してか、イバルボがボールサイドと逆側のスペースを狙える位置にポジショニングしており、そのおかげでせっかく豊田がロングボールの処理に競り勝っても、イバルボはまったくその近辺にいないというシーンもありましたし、鎌田がサイドに張り出したおかげで、逆にパスコースがなくなって中央に戻さざるをえず、キープレイヤーであるはずの鎌田が逆に囮となって彼にボールが渡らないシステムになってしまっていたりなど、もっともっと洗練するべきポイントはたくさんありました。
この試合、スコア的には快勝でしたが、危ないシーンも作られましたし、もっともっと向上させるべきところがある試合だったように思えます。次節に期待ですね。
■ 権田について
最後に、前節の試合の振り返りができなかったので、あえて書きますが、権田はこの試合、非常によいパフォーマンスで安定したプレイを見せてくれました。これまでの鳥栖の中でも安定感はピカイチでしょう。(一瞬のきらめきはやはり高嵜理貴押しですw)
前節のミスも、決してメンタル面が大きな原因ではなく、選手間のコミュニケーションやプレイスタイルの理解不足によって生じたものであり、今後は改善できるものでありますから、大きく捉える必要はないと考えています。
前節の次の試合だったからこそ、無失点の勝利を挙げることができたのは非常によかったと思います。
これからも権田のプレイには大きく期待しています。
■ メモ
<画像引用元:DAZN>
先日行われたアルビレックス新潟との試合の雑感です。簡単に振り返ります。
スコアこそ、3-0という試合ですが、一歩間違ったらその結果は逆転していた可能性はあったかもしれないという試合でした。
新潟の攻撃のセットアップとして、サイドハーフの端山と山崎を鳥栖のサイドバックくらいまでの高い位置に上げていました。狙いとしては、端山と山崎が引いてボールを受ける動きに対してサイドバックがついてきたときに、そのスペースをフォワードに狙わせるというのが見て取れました。
このやり方の弊害としては、新潟としてはダブルボランチ2人が組み立てようとするところに、鳥栖の中盤の3人が対峙することになり、中盤のつなぎとしては数的不利が生まれます。新潟が思いのほか長いボールが多かったのは、戦術によるところもあるでしょうが、鳥栖のプレッシャーに対しての逃げ場がなかったというのもあるでしょう。

ただ、新潟の狙いもハマらなかったわけではなく、何度となくスペースを空ける動きが成功していました。前半16分のシーンは、見事にそのスペースをついてからのホニのシュートでしたが、わずかにゴールを外れました。パスの精度が悪かったり、味方が気づいていなかったりなどによって、ゴールという結果までは生まれなかったのですが、これからこの形に対する連動性を向上させることができれば一つの形として確立できそうな気がします。


今回の新潟のストロングポイントとして、戦術云々よりもガリャルドとホニの動きが洗練しすぎており、前半10分の中央のスルーパスのシーンに代表されるように、トランジションの場面でうまく最終ラインの前でガリャルドがボールを受けると、最終ラインの人数がそろっていてもそれをはがして割り切るドリブル能力そしてパス能力の高さを発揮しておりました。最終ラインから飛び出すホニに対するガリャルドのパスというコンビネーションは非常に脅威でして、決定的なピンチを何度も招いていましたが、天の恵みと言いますか、雨が降っていて「すべるゾーン」がホニの動きを止める攻撃ストッパーになってくれていたのは、(例え運であっても)この試合のひとつのポイントだったかと思います。助かった~というシーンは非常に多かったです。
対して、鳥栖は、4-3-1-2から4-4-2にしてから上手く回ったという監督のコメントがありましたが、この類のコメントはもはや鳥栖の恒例行事になっているような気がしますね(笑) もちろん、ポジショニングは相手次第というところもありますので、試合の中で対応していかなければならないことは確かです。
ただ、チームの成長のため、そして鎌田の成長のためには、4-3-1-2を模索して組織として作り上げきってほしいなと思っています。4-4-2だと、自分の動けるエリアも役割も明確になって動きやすいでしょうが、明確なだけに、展開や戦況を大きく変えるような動きが取りづらいです。その点、4-3-1-2だと、トップ下の鎌田をフリーマン的に攻守に活用することによって、数的不利なエリアへのサポートや、相手が作ったギャップへの切り込みなど、鎌田の判断だけでその試合を有利な状況に持ってくることができる可能性を秘めています。
ただ、そのためには、セントラルハーフの3人だけで、攻撃・守備をある程度賄えるようになることも必要ですし、当然のことながら運動量が求められますし、何よりもチーム全体として戦況を見極められる広い戦術眼が求められます。これらを、試合を通じて高めていくことによって、中盤の4人が躍動する更に高いレベルのサッカーをサガン鳥栖が見せてくれることを大きく期待しています。
さて、新潟戦に戻りますが、確かに、前半の最初は、イバルボと鎌田が非常にちぐはぐな感じでポジショニングを取っていたシーンもありましたが、鎌田の動きによっては、サイドの数的有利の状況を作り出してよい攻撃を仕掛けていたシーンもありました。
前半に、イバルボに長いボールを当てて彼がキープして、イバルボの頭を超える素晴らしいパスで鎌田が前を向いてボールを受けて、シュートを放つ(逆サイドの豊田がつめていて惜しかったですが)と言うシーンは、一つのポイントだと思います。両サイドハーフとイバルボがサイドで組み立ててからの展開と言うのは、ひとつの形になっていたのかなと思いました。
気になったのは新潟の右サイドでありまして、端山・矢野・加藤のコンビネーションが悪くて(端山は今期初出場だったんですね)、吉田が追い越して上がってくるとマークの付き方がメンバー間で整理されておらず、ボール保持者へのプレッシャーが弱くなって、鳥栖が余裕を持ってパスコースを選択できる場面が見受けられました。
あと、PKの前のシーンもですが、前からボールを奪いたい前線と、しっかりとブロックを組みたい2列目・最終ラインとの息が合わずに、中盤に大きなスペースを空けることも多々ありました。新潟は、守備面では非常に課題の大きかった試合だったのかなと思います。


鳥栖も、攻撃が機能するシーンも見られましたが、逆サイド側に展開することを見越してか、イバルボがボールサイドと逆側のスペースを狙える位置にポジショニングしており、そのおかげでせっかく豊田がロングボールの処理に競り勝っても、イバルボはまったくその近辺にいないというシーンもありましたし、鎌田がサイドに張り出したおかげで、逆にパスコースがなくなって中央に戻さざるをえず、キープレイヤーであるはずの鎌田が逆に囮となって彼にボールが渡らないシステムになってしまっていたりなど、もっともっと洗練するべきポイントはたくさんありました。
この試合、スコア的には快勝でしたが、危ないシーンも作られましたし、もっともっと向上させるべきところがある試合だったように思えます。次節に期待ですね。
■ 権田について
最後に、前節の試合の振り返りができなかったので、あえて書きますが、権田はこの試合、非常によいパフォーマンスで安定したプレイを見せてくれました。これまでの鳥栖の中でも安定感はピカイチでしょう。(一瞬のきらめきはやはり高嵜理貴押しですw)
前節のミスも、決してメンタル面が大きな原因ではなく、選手間のコミュニケーションやプレイスタイルの理解不足によって生じたものであり、今後は改善できるものでありますから、大きく捉える必要はないと考えています。
前節の次の試合だったからこそ、無失点の勝利を挙げることができたのは非常によかったと思います。
これからも権田のプレイには大きく期待しています。
■ メモ
新潟の20番の所は狙い目かも。
— オオタニ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2017年4月8日
左サイドから崩せそうなんだけどな。
新潟は、両サイドのハーフを高い位置にセットアップして、サイドでボールを受けようと引いた時に鳥栖のサイドバックがついてきたら、その空けたスペースをツートップが狙う……と。
— オオタニ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2017年4月8日
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
20:25
│Match Impression (2017)
2017年03月23日
2017 第4節 : セレッソ大阪 VS サガン鳥栖
前節広島戦で初勝利を挙げ、今節はアウェー大阪に乗り込んで連勝を目論んだセレッソ戦。昨日の友は今日の敵、かつての盟友と袂を分かち、敵となって立ちはだかる尹さん率いるセレッソだっただけにどうしても勝ちたい一戦でしたが、なかなか思うような戦いができず、惜しくも苦杯をなめてしまいました。今回は、新加入のイバルボの起用などによってチームとして手探り状態での戦いであったので、次のホームでのセレッソとの戦いではよりチーム戦術を向上してリベンジマッチを臨みたい所です。
■ 試合の流れ
試合の攻防としては、互いにブロックを引いて、確かな守備を軸として相手のミスを誘発し、なるべく良い位置でボールを奪ってから攻撃へのトランジションに転ずる戦術で、見ていて非常に堅い試合でありました。
ただ、全体的にはセレッソがボールを保持して攻撃を仕掛け、鳥栖がそれを受けるという事が多く、どちらかというと鳥栖の方がより多くのリアクションを取らざるをえず、リアクションを取ることによって体力も徐々に摩耗していき、それが後半のコーナーキックのこぼれ球に対するアクションがとれずに失点してしまったことに繋がったかもしれません。
セレッソは、ボールを保持してつなぐだけでなく、長いボールも効果的に使ってきておりまして、プレスでボールを取りに行ったときに鳥栖の選手を越されるボールを簡単に使われて、そこは鳥栖が苦労したところかなと言う所です。鳥栖が前からプレスをかけると簡単に杉本に向けた長いボールを送ったり、鳥栖のフォワード2人のプレスが甘いところではソウザを飛び越して山村に当てたりと、一度センターを経由してキープできたときにはそこから、サイドに張っている清武や柿谷にボールを送り、最後は個の力で勝負をさせるという攻撃が目につきました。個の力として、各自特徴がはっきりしているので、長いボールは杉本、中央でつなぐ時はソウザ、サイドで勝負をさせたいときは柿谷・清武と、攻撃のコンセプトが明確でありました。
それに対して鳥栖は、清武や柿谷への応対の為に中盤の選手がリトリートして(最終ラインに入ったりなど)対応していたため、ボールの奪いどころが敵陣よりも遠いエリアであることが多く、また、奪ってからの預けどころがなかなか定まらずに、効果的な速攻に繋げる事ができていませんでした。原川が守備に忙殺せざるを得なかったのは、攻撃へのトランジションで後手を踏む要因にもなりました。
ボールを持っている場面でも、セレッソの速攻(カウンター)をケアするためか、なかなか攻撃に人数をかけることができず、うまく個の力で抜け出せたときくらいしか決定的なシュートチャンスが作れることができず、組織としての崩しのパターンがなかなか見られませんでした。
特に、今シーズンはかなり有効であった、フォーワードとハーフの動き、そして最終ラインからのボールの展開によって、相手のサイドバックの裏にスペースを作り、そこに鎌田が飛び出して起点を作るという鳥栖のパターンがなかなか発揮できず、攻撃の起点作りに苦労していた印象です。仕方のないことですが、イバルボがフォワードに入ったことによって、セレッソ陣内での追い出しがあまり機能せず、高い位置でボールが奪えなかったので、守備側に回った時に、イニシアチブをとってショートカウンターをしかける場面が少なかったです。
負けている状況というのはありましたが、試合終了間際に豊田や田川、チョドンゴンをめがけて長いボールを蹴っている方が、チーム全体として、攻撃のコンセプトが一致していて得点の期待が持てたかなと思いました。最後はミンヒョクの決定的なシュートが無情にも外れてゲームセットとなりましたが、(新加入の選手をいきなり使うという事も含めた)ゲームプランニングの差がこの1点の差だったようにも思えます。
■ イバルボを使った攻撃の形
25分の最終ラインからのロングボールから原川のシュートに至るまでの攻撃は、イバルボが起点となってから非常によい展開での攻撃でした。長いボールをイバルボが受けて、左サイドの原川に展開します。イバルボに対してはセンターバックがつきましたので、そのスペースを狙って鎌田が飛び出します。原川はタイミングよく鎌田に預け、鎌田が前線でためを作ってから吉田のサポートを受け、原川に戻してシュートを放ちます。この時、中央を使ってシュートまで繋げましたが、ボールを受けたイバルボは、左サイドにポジションを取っています。彼をもう一度使う事によって、彼の個人技による縦に抜けてからのクロスやカットインしてからのシュートなどのプレイも期待できます。この一連のシーンが、今後、イバルボを使う上での良いヒントでしょうね。





イバルボは、鳥栖の最終ラインがボールを出しあぐねているときには、引いてボールを受けに来てくれます。鳥栖の選手がなかなかイバルボに預けなかったのですが、彼がここでボールを受けて、キープして展開できるような強さを発揮してくれるならば、攻撃の幅が広がるはずです。

また、37分の藤田からのロングボールを相手と競りながらも胸トラップでボールを抑えたシーンは流石のフィジカルだなと思いました。イバルボ経由で原川や鎌田(出場していませんが小野も)が前を向いてボールを受けるシーンを作ることができると、鳥栖の攻撃のバリエーションが増えることになりそうです。
この試合では、彼の使い方どころか、まだプレイスタイルや特徴が明確でなかったので、周りとのコンビネーションがうまく行かず、イバルボ自身も動くに動けずという状態だったかと思いますが、この2週間で鳥栖の攻撃を整備できれば、劇的に変わる可能性は秘めていると感じました。
あとは、守備の面です。フォワードがプレスに行くに当たって、パスコースやスペースを埋める動きや、周りと連動してボールを奪いに行く2つの動きをこなさなければなりませんが、合流して間もないので、当然ながらなかなか連動した動きができずという状態でした。時には中盤に戻って守備をこなしているシーンもありましたから、守備に対する意識がないわけではないので、しっかりと役割を伝えることによって、徐々にフィットしてくると思います。
■ まとめ
リーグ戦を戦う上で、先を見据えてスタイルにこだわったり様々な選手を試すのも必要ですし、勝ち点を得るためにその試合だけに特化した戦い方でやりきるというのも必要です。そのバランスをどのポイントでとるかと言うのは非常に難しい所ですが、この試合においては、最後の場面ではチョドンゴン、田川と言う高さのあるプレイヤーを前線に入れてきたので、早めにロングボールを使うという攻撃にシフトしてもよかったかなと思いました。実際、ラストシーンでキムミンヒョクの決定的なシュートシーンも演出できましたしね。
失点のシーンでは、コーナーキックの跳ね返りに対して皆がゴール前でウォッチャーになってしまい、清武に対するプレッシャーをかけられなかったことで失点する羽目になってしまいましたが、その他の場面では、非常に高い集中力で、柿谷や清武の個の力をうまく抑えることが出来ていたと思います。
チームの方針をぶらさず、継続して戦っていくことが一番大事ですので、今回は負けてしまいましたが、気持ちを切り替えて次の試合に向けてより良い準備を行って欲しいと思います。
■ 試合の流れ
試合の攻防としては、互いにブロックを引いて、確かな守備を軸として相手のミスを誘発し、なるべく良い位置でボールを奪ってから攻撃へのトランジションに転ずる戦術で、見ていて非常に堅い試合でありました。
ただ、全体的にはセレッソがボールを保持して攻撃を仕掛け、鳥栖がそれを受けるという事が多く、どちらかというと鳥栖の方がより多くのリアクションを取らざるをえず、リアクションを取ることによって体力も徐々に摩耗していき、それが後半のコーナーキックのこぼれ球に対するアクションがとれずに失点してしまったことに繋がったかもしれません。
セレッソは、ボールを保持してつなぐだけでなく、長いボールも効果的に使ってきておりまして、プレスでボールを取りに行ったときに鳥栖の選手を越されるボールを簡単に使われて、そこは鳥栖が苦労したところかなと言う所です。鳥栖が前からプレスをかけると簡単に杉本に向けた長いボールを送ったり、鳥栖のフォワード2人のプレスが甘いところではソウザを飛び越して山村に当てたりと、一度センターを経由してキープできたときにはそこから、サイドに張っている清武や柿谷にボールを送り、最後は個の力で勝負をさせるという攻撃が目につきました。個の力として、各自特徴がはっきりしているので、長いボールは杉本、中央でつなぐ時はソウザ、サイドで勝負をさせたいときは柿谷・清武と、攻撃のコンセプトが明確でありました。
それに対して鳥栖は、清武や柿谷への応対の為に中盤の選手がリトリートして(最終ラインに入ったりなど)対応していたため、ボールの奪いどころが敵陣よりも遠いエリアであることが多く、また、奪ってからの預けどころがなかなか定まらずに、効果的な速攻に繋げる事ができていませんでした。原川が守備に忙殺せざるを得なかったのは、攻撃へのトランジションで後手を踏む要因にもなりました。
ボールを持っている場面でも、セレッソの速攻(カウンター)をケアするためか、なかなか攻撃に人数をかけることができず、うまく個の力で抜け出せたときくらいしか決定的なシュートチャンスが作れることができず、組織としての崩しのパターンがなかなか見られませんでした。
特に、今シーズンはかなり有効であった、フォーワードとハーフの動き、そして最終ラインからのボールの展開によって、相手のサイドバックの裏にスペースを作り、そこに鎌田が飛び出して起点を作るという鳥栖のパターンがなかなか発揮できず、攻撃の起点作りに苦労していた印象です。仕方のないことですが、イバルボがフォワードに入ったことによって、セレッソ陣内での追い出しがあまり機能せず、高い位置でボールが奪えなかったので、守備側に回った時に、イニシアチブをとってショートカウンターをしかける場面が少なかったです。
負けている状況というのはありましたが、試合終了間際に豊田や田川、チョドンゴンをめがけて長いボールを蹴っている方が、チーム全体として、攻撃のコンセプトが一致していて得点の期待が持てたかなと思いました。最後はミンヒョクの決定的なシュートが無情にも外れてゲームセットとなりましたが、(新加入の選手をいきなり使うという事も含めた)ゲームプランニングの差がこの1点の差だったようにも思えます。
■ イバルボを使った攻撃の形
25分の最終ラインからのロングボールから原川のシュートに至るまでの攻撃は、イバルボが起点となってから非常によい展開での攻撃でした。長いボールをイバルボが受けて、左サイドの原川に展開します。イバルボに対してはセンターバックがつきましたので、そのスペースを狙って鎌田が飛び出します。原川はタイミングよく鎌田に預け、鎌田が前線でためを作ってから吉田のサポートを受け、原川に戻してシュートを放ちます。この時、中央を使ってシュートまで繋げましたが、ボールを受けたイバルボは、左サイドにポジションを取っています。彼をもう一度使う事によって、彼の個人技による縦に抜けてからのクロスやカットインしてからのシュートなどのプレイも期待できます。この一連のシーンが、今後、イバルボを使う上での良いヒントでしょうね。





イバルボは、鳥栖の最終ラインがボールを出しあぐねているときには、引いてボールを受けに来てくれます。鳥栖の選手がなかなかイバルボに預けなかったのですが、彼がここでボールを受けて、キープして展開できるような強さを発揮してくれるならば、攻撃の幅が広がるはずです。

また、37分の藤田からのロングボールを相手と競りながらも胸トラップでボールを抑えたシーンは流石のフィジカルだなと思いました。イバルボ経由で原川や鎌田(出場していませんが小野も)が前を向いてボールを受けるシーンを作ることができると、鳥栖の攻撃のバリエーションが増えることになりそうです。
この試合では、彼の使い方どころか、まだプレイスタイルや特徴が明確でなかったので、周りとのコンビネーションがうまく行かず、イバルボ自身も動くに動けずという状態だったかと思いますが、この2週間で鳥栖の攻撃を整備できれば、劇的に変わる可能性は秘めていると感じました。
あとは、守備の面です。フォワードがプレスに行くに当たって、パスコースやスペースを埋める動きや、周りと連動してボールを奪いに行く2つの動きをこなさなければなりませんが、合流して間もないので、当然ながらなかなか連動した動きができずという状態でした。時には中盤に戻って守備をこなしているシーンもありましたから、守備に対する意識がないわけではないので、しっかりと役割を伝えることによって、徐々にフィットしてくると思います。
■ まとめ
リーグ戦を戦う上で、先を見据えてスタイルにこだわったり様々な選手を試すのも必要ですし、勝ち点を得るためにその試合だけに特化した戦い方でやりきるというのも必要です。そのバランスをどのポイントでとるかと言うのは非常に難しい所ですが、この試合においては、最後の場面ではチョドンゴン、田川と言う高さのあるプレイヤーを前線に入れてきたので、早めにロングボールを使うという攻撃にシフトしてもよかったかなと思いました。実際、ラストシーンでキムミンヒョクの決定的なシュートシーンも演出できましたしね。
失点のシーンでは、コーナーキックの跳ね返りに対して皆がゴール前でウォッチャーになってしまい、清武に対するプレッシャーをかけられなかったことで失点する羽目になってしまいましたが、その他の場面では、非常に高い集中力で、柿谷や清武の個の力をうまく抑えることが出来ていたと思います。
チームの方針をぶらさず、継続して戦っていくことが一番大事ですので、今回は負けてしまいましたが、気持ちを切り替えて次の試合に向けてより良い準備を行って欲しいと思います。
Posted by オオタニ at
19:26
│Match Impression (2017)
2017年03月17日
2017ルヴァン:サガン鳥栖 VS アルビレックス新潟
水曜日に行われたルヴァンカップ新潟戦の雑感です。ただし、後半からしか見ることができていないので、その前提で感想を述べます。
まず攻撃面ですが、ビルドアップに苦戦した印象で、こちらのセンターバック2人に対して相手のツートップが張り付き、寄せられてサイドに流して最後は詰まって長いボールを蹴るしかないという状況が多く、もう少し展開を工夫出来たらよいなと思いました。鳥栖のツートップの動きがよく、長いボールを入れるタイミングを作ってくれていたので、アンカーで入った小川がうまく使えたらよかったのになという所です。
小川が、センターバック2人の前で構えている事が多かったので、たまには、自分が引いて最終ラインに入って、相手のツートップをセンターバック2人と合わせた3人でゆったりかわしつつ、組み立ての中でフォワードに直接ボールを入れるなど、少しアクセントをいれると面白かったかもしれません。
中央でボールをうけようとしても、相手も小川に入ったところを狙おうとしているので、センターバックもそれがわかっている状態ではなかなか預けられませんし、ワンタッチで抜けられるほどのコンビネーションもありません。
チーム全体として動きの上下が足りず、相手のブロックに対してそのまま挑んでしまうだけで、最終的にはそのままはまって詰まってしまうという悪循環を繰り返していました。そのあたりの全体のコントロールという点が、小川の動きとして少し物足りなかったです。
石川が入ってからは、サイドで預けても一人ではがすことができるので、その点はやや助けられたかなというのはあります。義希が入ってからも引いて自分にマークを付かせてから、藤田を上がらせるなどの動きも見えました。交替して入った選手たちがリズムを作ろうとしたことによって、少しずつ攻撃に幅が出てきたのは感じました。
個人的に、良いプレイヤーだなと思ったのは、チョドンゴンです。ワンタッチでのプレイや裏へのダイレクトパス、ポストプレイなど、ゲームの組み立てに寄与しようとする動きがよく見えました。彼自身ではなく、彼の周りのいるプレイヤーのレベルが上がると、彼自身が更に生きてくるのではないかと感じました。
守備に関しては、試合を共にやっているメンバーではなかったので、プレスのタイミングなど難しかったのでしょう。
個々のプレスが新潟のボールの動きに対してわずかに間に合っておらず、プレイヤーはチーム戦術としての動きを見せようとしていましたが、ボールの行先に応じて後から動いているようになってしまい、積極的に奪いに行っても、簡単にパスではがされるような場面が多くありました。
コンパクトな状態でのプレスであれば、それでも相手のちょっとしたトラップミスなどで奪う事ができるのですが、疲れてきた後半では、間延びしているので、積極的なプレスが逆に仇となって、逆に相手にスペースを与えてしまっていました。
気になっていたフランコですが、少しクイックネスが足りないかなという印象です。大柄なせいでそのように見えてしまうのかもしれませんが、相手の一瞬の動きに対して遅れを取ることがありました。自分のスピードに自信がないと相手との間合いも空いてしまい、その結果、ブロックできるはずのボールがブロックできずにクロスやシュートを許してしまう原因になります。もう少し、Jリーグのスピードに慣れる必要があるかなという所です。
後半から見て、様々なゴールが見られたのは良かったです。田中達也はさすがですね。シュートはゴールへのパスというのを見せてもらいました。ふかさず、力まず、コースをしっかり狙ってチャンスに確実に決める。田川君にとっては、よいお手本を目の前で見せてもらったのではないでしょうか。
まず攻撃面ですが、ビルドアップに苦戦した印象で、こちらのセンターバック2人に対して相手のツートップが張り付き、寄せられてサイドに流して最後は詰まって長いボールを蹴るしかないという状況が多く、もう少し展開を工夫出来たらよいなと思いました。鳥栖のツートップの動きがよく、長いボールを入れるタイミングを作ってくれていたので、アンカーで入った小川がうまく使えたらよかったのになという所です。
小川が、センターバック2人の前で構えている事が多かったので、たまには、自分が引いて最終ラインに入って、相手のツートップをセンターバック2人と合わせた3人でゆったりかわしつつ、組み立ての中でフォワードに直接ボールを入れるなど、少しアクセントをいれると面白かったかもしれません。
中央でボールをうけようとしても、相手も小川に入ったところを狙おうとしているので、センターバックもそれがわかっている状態ではなかなか預けられませんし、ワンタッチで抜けられるほどのコンビネーションもありません。
チーム全体として動きの上下が足りず、相手のブロックに対してそのまま挑んでしまうだけで、最終的にはそのままはまって詰まってしまうという悪循環を繰り返していました。そのあたりの全体のコントロールという点が、小川の動きとして少し物足りなかったです。
石川が入ってからは、サイドで預けても一人ではがすことができるので、その点はやや助けられたかなというのはあります。義希が入ってからも引いて自分にマークを付かせてから、藤田を上がらせるなどの動きも見えました。交替して入った選手たちがリズムを作ろうとしたことによって、少しずつ攻撃に幅が出てきたのは感じました。
個人的に、良いプレイヤーだなと思ったのは、チョドンゴンです。ワンタッチでのプレイや裏へのダイレクトパス、ポストプレイなど、ゲームの組み立てに寄与しようとする動きがよく見えました。彼自身ではなく、彼の周りのいるプレイヤーのレベルが上がると、彼自身が更に生きてくるのではないかと感じました。
守備に関しては、試合を共にやっているメンバーではなかったので、プレスのタイミングなど難しかったのでしょう。
個々のプレスが新潟のボールの動きに対してわずかに間に合っておらず、プレイヤーはチーム戦術としての動きを見せようとしていましたが、ボールの行先に応じて後から動いているようになってしまい、積極的に奪いに行っても、簡単にパスではがされるような場面が多くありました。
コンパクトな状態でのプレスであれば、それでも相手のちょっとしたトラップミスなどで奪う事ができるのですが、疲れてきた後半では、間延びしているので、積極的なプレスが逆に仇となって、逆に相手にスペースを与えてしまっていました。
気になっていたフランコですが、少しクイックネスが足りないかなという印象です。大柄なせいでそのように見えてしまうのかもしれませんが、相手の一瞬の動きに対して遅れを取ることがありました。自分のスピードに自信がないと相手との間合いも空いてしまい、その結果、ブロックできるはずのボールがブロックできずにクロスやシュートを許してしまう原因になります。もう少し、Jリーグのスピードに慣れる必要があるかなという所です。
後半から見て、様々なゴールが見られたのは良かったです。田中達也はさすがですね。シュートはゴールへのパスというのを見せてもらいました。ふかさず、力まず、コースをしっかり狙ってチャンスに確実に決める。田川君にとっては、よいお手本を目の前で見せてもらったのではないでしょうか。
Posted by オオタニ at
20:58
│Match Impression (2017)
2017年03月14日
2017 第3節 : サガン鳥栖 VS サンフレッチェ広島
互いに勝利のないまま第3節を迎えてしまったサガン鳥栖とサンフレッチェ広島。思い描いていたようなスタートダッシュを切ることができませんでしたが、まだまだシーズンも始まったばかりですし、取り返すには十分の猶予があります。そのためにも、一刻も早く初勝利を挙げたい両チームでしたが、ホームのサガン鳥栖が虎の子の1点を守りきり、必死の思いで今季初勝利を納めました。
■ 試合の流れ
試合開始当初から、互いにアグレッシブにボールに対するアクションを取っていました。鳥栖としては、広島のミキッチ、清水という両ワイドを生かした攻撃は非常に脅威で、それに加えて中盤の底には青山、セカンドトップにはフェリペ・柴崎という、センスのあるメンバーが攻撃の手綱を握っており、対応に一瞬の油断も許されない相手でしたが、前線からの守備、リトリートしてからの守備、どちらも相手の動きにうまく対応し、ボールを奪った時には、攻撃に人数をかけて攻めきるという、非常にバランスの良い戦いを繰り広げました。先制点は、この良い流れの中でフリーキックを得て、開幕戦と同じような位置から原川が蹴ったボールは、同じような軌跡を辿り見事にゴールに吸い込まれていきました。
後半に入ると、広島が攻勢を強めます。前半に比べると、塩谷、水本が攻撃に参加する場面が増えてきました。ワイドの選手とセカンドトップの選手のちょうど中間にポジションを取り、ボールの配給役を担っていたのですが、鳥栖の中盤がややそこに引きずられて押し込まれる状態になってきました。ただ、それに対して鳥栖はフォワードが完全にリトリートするという選択をせずに、前からボールを奪いに行っていましたし、セットプレイの場面以外では豊田、富山(田川)をトップに残す選択をしていました。
試合も終盤になると、攻めたい広島のテンポに合わせるように、空いたスペースめがけて走りこんで、ボールを蹴って…という消耗戦のような戦いになってしまったので、なかなか試合が落ち着かずに逆にあわやというシーンも作られてしまいました。チャンスはいくつかあったのですが、そこで決めきることができなかったですね。
結果として、勝利を得ることができましたが、数的有利を得ながらもそれを生かせない戦いとなってしまい、課題が残る試合となってしまいました。とはいえ、今シーズン初勝利を強敵広島から上げて勝ち点3をゲットできたのは、次節のセレッソ大阪戦に向けて非常に大きな弾みとなりました。
■ 前半の柴崎への対応
前半5分過ぎくらいに、マッシモさんの指示で、福田と原川を入れ替えます。立ち上がりから、前目からプレスに入っていく原川に対して、清水、柴崎の2人の対応に追われていた藤田。奪ってからの攻撃へのトランジションや、押し込まれたときのポジション取りなど総合的に考えて、富山・原川を下げるという選択肢を取らず、福田を右サイドに移して、藤田と連係して柴崎と清水を止めることを優先しました。この結果、藤田に柴崎を応対させたときの福田の動き(最終ラインのカバー)が非常にオーガナイズされていて、右サイドの守備を行う上では良い環境となりました。
また、左サイドは、フェリペがフォローにはいる動きが少なく、ミキッチ単独での攻撃が多かったので、これも吉田をぶつけることによって、応対が可能となり全体的にバランスがよくなりました。(前半は)
試合を見ていて、サガン鳥栖は柴崎の動きを自由にさせたくないのだなという意思を感じました。入れ替わり入ってくる広島の選手に備えてマークの受け渡しは当然発生するのですが、柴崎だけは一瞬の隙も作ることなく、マンマークかのようについていくシーンが多かったです。特に、藤田が一旦捕まえてからは、広島の組み立てに惑わされず、柴崎を離さない動きをとっていました。そのスペースは福田がしっかりとカバーリングしており、2人の連係は見ていて安心感がありました。
また、工藤がワントップで張っており、柴崎が動いて作ったスペースに対して、フェリペや丸谷が飛び込んで来たら怖かったのですが、彼らがうまくそのスペースを利用できなかったため、(丸谷は最終ラインでの組み立てに入っていた)、谷口とミンヒョクの2人で工藤ひとりを見ることができたのは大きかったと思います。サイドからの攻撃は迫力あったものの中央を縦に崩すシーンは広島としては、思ったほど作れなかったのかなという印象です。


…とはいうものの、たとえマークがついていても、例えセンターの人数が少なくても、攻撃の形を作ってしまうのが広島でして、柴崎の裏への動きにいち早く反応した青山のスルーパスによって、あっというまに工藤のシュートチャンスを演出したのは、流石の攻撃でした。



■ 後半の守勢について
後半に入ってくると、負けている広島が明らかに攻勢にでてきました。広島が流れをつかんだ一つの要因としては、フェリペがポイントとして鳥栖の最終ライン近くでボールを受けてそこからサイドへ散らす役割を果たしたこと。これによって、吉田が中央に絞らざるを得ず、サイドのミキッチをフリーにすることが多くなってきました。ミキッチにボールが入ると、吉田がサイドに飛びでていき、サイドからのクロスに備えて義希や福田が最終ラインに入ってクロスを待ち構えることが多くなります。最終ラインを厚くすることによって、跳ね返したセカンドボールを拾える回数が少なくなりました。
それに加えて、後半は、丸谷を組立で最終ラインに下げ、センターバックの水本もしくは塩谷が、リスクを冒して非常に高い位置でボールを受けて配給役をこなしていました。特に、フェリペが上がったスペースを塩谷がオーバーラップして埋めてからその位置でゲームメイクを務めていたのは非常に脅威でした。この2つのポイントによって、鳥栖は思うようにラインを上げられず、広島に押し込まれてしまう時間帯を作ってしまいました。後半63分のシーンは、見どころのあるシーンで、広島がやりたかった攻撃を表していると思います。






鳥栖としては、広島が組み立てている時に、上がってきた塩谷(水本)を、誰が見るのかというところが、曖昧だったかのように思えます。鎌田、富山、豊田がそれぞれのポジションからどのタイミングでリトリートするのか、塩谷に対する対処をしっかりと決めきれずに、フリーにしてしまうシーンが多かったかなという感じです。
フェリペや柴崎が最終ライン近くにポジションを取って、鳥栖の中盤の選手が最終ラインに吸収している状況だったので、守備だけを考えるならば、丸谷&千葉への応対を豊田1人にして、鎌田と富山は水本と塩谷を見る形にしても良かったのかなと言う所です。後半も終盤になって中盤のスペースが空いていたので、その2人が自由に上がってくるのは中盤の選手がちょっときつかったかなと。
もし、マッシモさんの指示でカウンターの攻撃を重視するため、鎌田や富山は必要以上にマークに戻らずに、攻撃に備えて前線に残っていたとしたらならば、もっともっとボールを奪った時の攻撃の起点にならなければならなかったし、より多くのチャンスを作らなければならなかったでしょう。広島がリスクを冒しているにも関わらず、その隙を鳥栖の攻撃陣がついて追加点を挙げることができなかったことが、最後に苦戦した要因ですよね。
丸谷が退場し、柴崎がロペスに変わってからは、更に右サイドが攻撃の主戦場となりました。ロペスが前線にはることによって、最終ラインがなかなか押し上げできず、右サイドのミキッチとの二人のコンビネーションで何度も崩されていました。鳥栖は、相手が退場して数的不利というのもあって、完全に引いて守っていたわけではなく、前から追いかけボールを奪いに行っていましたが、広島の選手の個人技の高さがボールロストせずに、うまくプレスをいなしてボールを回し、トップまでくさびのボールを入れることに成功していました。特に、塩谷が鳥栖の選手をいとも簡単にはがしていたので、彼1人の活躍で数的不利は実質あまり関係ないものになってしまっていました。
そして、体力の消耗からか、ボールを奪っても前に上がる体力が残っておらず、判断力も鈍って繋げられるような場面でもボールを前に蹴るだけになってしまい、思うようにボールを保持することができなくなってしまっていました。試合終了間際は防戦一方で、最終的には15本ものコーナーキックを浴びる猛攻を受けてしまいました。
■ まとめ
相手が退場したことによって、当初のゲームプランが崩れたことはありますが、広島が一人少ない状況でも鳥栖は押し込まれるという、改めて力のあるチームという事を思い知らされました。それだけに、原川のフリーキックは値千金のゴールで、この先制点があったからこそ、全員で一致団結して守れたのだと思います。
また、この試合は、権田のスーパーセーブなしではありえなかった勝利です。86分の塩谷のシュートは、ちょうどシュートを放つ真後ろから見ていたのですが、打った瞬間は正直、「あ、入った」と思ってしまいました。ディフェンスと若干かぶって見えにくかったでしょうが、ボールが見えた瞬間に権田が左に大きく飛んでフィスティングした瞬間には、思わず大きな声で叫んでしまいました。(この試合唯一の叫び(笑))
田川も川崎戦に続いて大きな可能性を見せてくれました。ひとりで持ち込めるスピード、テクニックは十分にJ1で通用すると思いますし、何よりも戦おうとするメンタルが素晴らしいです。大型で左利きというのも非常にメリットがありまして、右サイドに張ってからカットインして左足でシュートが打てるプレイヤーというのは、フォワードの選択肢として昨年の鳥栖にはなかったものです。彼ならば、焦らなくても、すぐにゴールという結果は訪れるでしょう。もっともっと自信を持って戦って欲しいと思います。
様々な課題があった試合ですが、まずは今シーズン初勝利というものを素直に喜びたいと思います。
<画像引用元:DAZN>
■ 試合の流れ
試合開始当初から、互いにアグレッシブにボールに対するアクションを取っていました。鳥栖としては、広島のミキッチ、清水という両ワイドを生かした攻撃は非常に脅威で、それに加えて中盤の底には青山、セカンドトップにはフェリペ・柴崎という、センスのあるメンバーが攻撃の手綱を握っており、対応に一瞬の油断も許されない相手でしたが、前線からの守備、リトリートしてからの守備、どちらも相手の動きにうまく対応し、ボールを奪った時には、攻撃に人数をかけて攻めきるという、非常にバランスの良い戦いを繰り広げました。先制点は、この良い流れの中でフリーキックを得て、開幕戦と同じような位置から原川が蹴ったボールは、同じような軌跡を辿り見事にゴールに吸い込まれていきました。
後半に入ると、広島が攻勢を強めます。前半に比べると、塩谷、水本が攻撃に参加する場面が増えてきました。ワイドの選手とセカンドトップの選手のちょうど中間にポジションを取り、ボールの配給役を担っていたのですが、鳥栖の中盤がややそこに引きずられて押し込まれる状態になってきました。ただ、それに対して鳥栖はフォワードが完全にリトリートするという選択をせずに、前からボールを奪いに行っていましたし、セットプレイの場面以外では豊田、富山(田川)をトップに残す選択をしていました。
試合も終盤になると、攻めたい広島のテンポに合わせるように、空いたスペースめがけて走りこんで、ボールを蹴って…という消耗戦のような戦いになってしまったので、なかなか試合が落ち着かずに逆にあわやというシーンも作られてしまいました。チャンスはいくつかあったのですが、そこで決めきることができなかったですね。
結果として、勝利を得ることができましたが、数的有利を得ながらもそれを生かせない戦いとなってしまい、課題が残る試合となってしまいました。とはいえ、今シーズン初勝利を強敵広島から上げて勝ち点3をゲットできたのは、次節のセレッソ大阪戦に向けて非常に大きな弾みとなりました。
■ 前半の柴崎への対応
前半5分過ぎくらいに、マッシモさんの指示で、福田と原川を入れ替えます。立ち上がりから、前目からプレスに入っていく原川に対して、清水、柴崎の2人の対応に追われていた藤田。奪ってからの攻撃へのトランジションや、押し込まれたときのポジション取りなど総合的に考えて、富山・原川を下げるという選択肢を取らず、福田を右サイドに移して、藤田と連係して柴崎と清水を止めることを優先しました。この結果、藤田に柴崎を応対させたときの福田の動き(最終ラインのカバー)が非常にオーガナイズされていて、右サイドの守備を行う上では良い環境となりました。
また、左サイドは、フェリペがフォローにはいる動きが少なく、ミキッチ単独での攻撃が多かったので、これも吉田をぶつけることによって、応対が可能となり全体的にバランスがよくなりました。(前半は)
試合を見ていて、サガン鳥栖は柴崎の動きを自由にさせたくないのだなという意思を感じました。入れ替わり入ってくる広島の選手に備えてマークの受け渡しは当然発生するのですが、柴崎だけは一瞬の隙も作ることなく、マンマークかのようについていくシーンが多かったです。特に、藤田が一旦捕まえてからは、広島の組み立てに惑わされず、柴崎を離さない動きをとっていました。そのスペースは福田がしっかりとカバーリングしており、2人の連係は見ていて安心感がありました。
また、工藤がワントップで張っており、柴崎が動いて作ったスペースに対して、フェリペや丸谷が飛び込んで来たら怖かったのですが、彼らがうまくそのスペースを利用できなかったため、(丸谷は最終ラインでの組み立てに入っていた)、谷口とミンヒョクの2人で工藤ひとりを見ることができたのは大きかったと思います。サイドからの攻撃は迫力あったものの中央を縦に崩すシーンは広島としては、思ったほど作れなかったのかなという印象です。


…とはいうものの、たとえマークがついていても、例えセンターの人数が少なくても、攻撃の形を作ってしまうのが広島でして、柴崎の裏への動きにいち早く反応した青山のスルーパスによって、あっというまに工藤のシュートチャンスを演出したのは、流石の攻撃でした。



■ 後半の守勢について
後半に入ってくると、負けている広島が明らかに攻勢にでてきました。広島が流れをつかんだ一つの要因としては、フェリペがポイントとして鳥栖の最終ライン近くでボールを受けてそこからサイドへ散らす役割を果たしたこと。これによって、吉田が中央に絞らざるを得ず、サイドのミキッチをフリーにすることが多くなってきました。ミキッチにボールが入ると、吉田がサイドに飛びでていき、サイドからのクロスに備えて義希や福田が最終ラインに入ってクロスを待ち構えることが多くなります。最終ラインを厚くすることによって、跳ね返したセカンドボールを拾える回数が少なくなりました。
それに加えて、後半は、丸谷を組立で最終ラインに下げ、センターバックの水本もしくは塩谷が、リスクを冒して非常に高い位置でボールを受けて配給役をこなしていました。特に、フェリペが上がったスペースを塩谷がオーバーラップして埋めてからその位置でゲームメイクを務めていたのは非常に脅威でした。この2つのポイントによって、鳥栖は思うようにラインを上げられず、広島に押し込まれてしまう時間帯を作ってしまいました。後半63分のシーンは、見どころのあるシーンで、広島がやりたかった攻撃を表していると思います。






鳥栖としては、広島が組み立てている時に、上がってきた塩谷(水本)を、誰が見るのかというところが、曖昧だったかのように思えます。鎌田、富山、豊田がそれぞれのポジションからどのタイミングでリトリートするのか、塩谷に対する対処をしっかりと決めきれずに、フリーにしてしまうシーンが多かったかなという感じです。
フェリペや柴崎が最終ライン近くにポジションを取って、鳥栖の中盤の選手が最終ラインに吸収している状況だったので、守備だけを考えるならば、丸谷&千葉への応対を豊田1人にして、鎌田と富山は水本と塩谷を見る形にしても良かったのかなと言う所です。後半も終盤になって中盤のスペースが空いていたので、その2人が自由に上がってくるのは中盤の選手がちょっときつかったかなと。
もし、マッシモさんの指示でカウンターの攻撃を重視するため、鎌田や富山は必要以上にマークに戻らずに、攻撃に備えて前線に残っていたとしたらならば、もっともっとボールを奪った時の攻撃の起点にならなければならなかったし、より多くのチャンスを作らなければならなかったでしょう。広島がリスクを冒しているにも関わらず、その隙を鳥栖の攻撃陣がついて追加点を挙げることができなかったことが、最後に苦戦した要因ですよね。
丸谷が退場し、柴崎がロペスに変わってからは、更に右サイドが攻撃の主戦場となりました。ロペスが前線にはることによって、最終ラインがなかなか押し上げできず、右サイドのミキッチとの二人のコンビネーションで何度も崩されていました。鳥栖は、相手が退場して数的不利というのもあって、完全に引いて守っていたわけではなく、前から追いかけボールを奪いに行っていましたが、広島の選手の個人技の高さがボールロストせずに、うまくプレスをいなしてボールを回し、トップまでくさびのボールを入れることに成功していました。特に、塩谷が鳥栖の選手をいとも簡単にはがしていたので、彼1人の活躍で数的不利は実質あまり関係ないものになってしまっていました。
そして、体力の消耗からか、ボールを奪っても前に上がる体力が残っておらず、判断力も鈍って繋げられるような場面でもボールを前に蹴るだけになってしまい、思うようにボールを保持することができなくなってしまっていました。試合終了間際は防戦一方で、最終的には15本ものコーナーキックを浴びる猛攻を受けてしまいました。
■ まとめ
相手が退場したことによって、当初のゲームプランが崩れたことはありますが、広島が一人少ない状況でも鳥栖は押し込まれるという、改めて力のあるチームという事を思い知らされました。それだけに、原川のフリーキックは値千金のゴールで、この先制点があったからこそ、全員で一致団結して守れたのだと思います。
また、この試合は、権田のスーパーセーブなしではありえなかった勝利です。86分の塩谷のシュートは、ちょうどシュートを放つ真後ろから見ていたのですが、打った瞬間は正直、「あ、入った」と思ってしまいました。ディフェンスと若干かぶって見えにくかったでしょうが、ボールが見えた瞬間に権田が左に大きく飛んでフィスティングした瞬間には、思わず大きな声で叫んでしまいました。(この試合唯一の叫び(笑))
田川も川崎戦に続いて大きな可能性を見せてくれました。ひとりで持ち込めるスピード、テクニックは十分にJ1で通用すると思いますし、何よりも戦おうとするメンタルが素晴らしいです。大型で左利きというのも非常にメリットがありまして、右サイドに張ってからカットインして左足でシュートが打てるプレイヤーというのは、フォワードの選択肢として昨年の鳥栖にはなかったものです。彼ならば、焦らなくても、すぐにゴールという結果は訪れるでしょう。もっともっと自信を持って戦って欲しいと思います。
様々な課題があった試合ですが、まずは今シーズン初勝利というものを素直に喜びたいと思います。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
19:49
│Match Impression (2017)
2017年03月09日
2017 第2節 : 川崎フロンターレVSサガン鳥栖
開幕戦を黒星スタートとなってしまったサガン鳥栖。第2節はアウェーで強敵川崎フロンターレとの対戦でした。まだまだお互いにチームとして成熟していない中での戦いで、勝利がどちらに転んでもおかしくない試合でしたが、互いに攻め合った結果、決定打を放つことが出来ずに試合終了となりました。鳥栖としては、アウェー川崎での勝ち点1は、良い結果だったと思います。
■ 試合の流れ
試合開始当初から、両チームとも相手の守備がずれているポイントをついて攻撃を繰り出すような状況でした。川崎の先制点は、鳥栖のミスから生まれたものでありましたが、やはり、小林の動きは突出していて、裏へ抜ける動き出し(ゴールに直結するための動き出し)は、両チームの中でも一番際立っていました。
しかしながら、大塚や阿部のところを使って、いいところまでボールが入るのですが、トラップミスや判断ミスによって、うまく好機を演出することができないシーンも多く、後半にハイネルが入ってから、ボールロストの回数が減ってリズムがでてきたのですが、ポジションの取り方としてやや後ろで受けることが多く、小林とのコンビネーションで決定的チャンスを何度も演出……というシーンを作り出せませんでした。
鳥栖の攻撃は、長短のパスを織り交ぜながら、何回か良いシーンを作ることができていました。思いのほか簡単に川崎のディフェンスラインの裏をつけることができていたと思います。同点ゴールも、きっかけは鎌田が最終ラインの裏に侵入したところからスタートしていますし、左サイドの裏に抜けた豊田の左足のシュートというシーンもありましたし、惜しいシーンは何度もありましたが、2点目を取るまでには至りませんでした。
全体的に、新チームになったばかりということで、攻撃も守備もコンビネーションにちらほらとずれが見え隠れしている状態であり、また、選手個々のコンディションも完全に上がっていない選手がいる状況の試合(特に川崎はACLもあり)でしたので、引き分けと言う結果は妥当なのかなと思いました。
■ 発展途上の守備構築
選手が入れ替わったことによる守備組織の再構築というのはよく聞く話です。選手が入れ替わるという事は、当然ながら能力が異なるメンバーが試合に入るということであり、その個性に合わせた組織の見直しというのが必要になります。チームというものは、組織戦術だけ変えれば…、選手だけ変えれば…という簡単ものではないので、構築には一定の期間がかかる覚悟が必要です。
今回は、23分によいシーンがあったので振り返ります。図は、川崎が、左サイドのスローインから始まって、サイドチェンジで右サイドまでボールを持ってきたところです。右サイドにいる田坂と阿部で組み立てているのですが、ボールが一旦中央に戻ったところで、義希がプレスを始めます。鳥栖としては、そこでハメていこうという合図です。義希がボール保持者にプレスすることによって、次のプレイの選択肢を狭めることができるのですが、それを察知した動きを原川ができていません。本来は、義希の動きに連動して、右サイドにいる田坂へのプレッシャーをかけたいところですが、タイミングがずれたことにより、相手との間が空きすぎて、慌ててプレスにいってもかわされてしまい、小林への縦パスを狙われてしまいます。鳥栖のディフェンスラインが整っており、全体を押し上げてオフサイドを取れたことによって、事なきを得たのですが、田坂が持ち替えなければ動き出し、パスのタイミングによっては決定的ピンチを迎えるようなシーンでしたので、なるべくならばパスの出所を抑えたいシーンでありますし、抑えることが可能であったシーンだと思います。





また、同じように、プレスをするタイミングとスペースを埋めるタイミングの意識がずれたことによって、生じてしまった縦パスのシーンがあったのですが、27分を例に出しますと、これも川崎が左サイドから右サイドに展開している場面です。原川は、しきりに、阿部のことを気にしながら自分のポジションを取っています。しかしながら、阿部に関しては、吉田が応対できる状況であり、また、原川のスペースに入られた際のケアも義希が埋める準備はあるので、自分に対峙している田坂に対するアクションを取って、チーム全体としてハメにいこうというスイッチを入れてもよいかなという状況です。
しかしながら、原川は、ポジショニングを取ることに一生懸命で、自ら能動的にアクションを取ることができておらず、ボールの動き、相手の動きに対応するアクションがとれなかった結果、相手に対するプレッシャーもかからず、パスコースを消すこともできずに、大塚への縦パスを許してしまうことになります。これも、大塚のトラップミスによって事なきを得ましたが、トラップで反転して前を向かれたり、フリックで流されたりすると決定的ピンチを迎えかねない状況でした。

今回は、たまたま原川の動きを例に使いましたが、チームとしてこのような動きのずれによってラストパスを狙われるようなシーンは極力減らさなければなりません。昨年度は、鳥栖の守備構築に半年かかりましたので、新しく入った選手がチームとしての動きをすぐに理解できるわけではないのですが、前線からの組織的な守備というのは、鳥栖が上位に進出するにあたっての絶対条件であるので、少しでも早く全体の戦術理解度を向上してほしいですね。
■ 鎌田のスペースを狙う動き
攻撃面では、この試合で光ったのは、鎌田のディフェンスラインの裏を狙う動きでした。
24分のシーンは連動して崩せた良いシーンでした。左サイドを縦パスで前線までボールを送り込み、空いたスペースを狙って起点を作って裏のスペースに抜けるという、チームとしての動きが統率された非常に良い攻撃だったと思います。




31分のシーンでは、左サイドの富山がボールを受け、田坂がマークについたところのスペースを狙って鎌田が走り込みを見せます。ちなみに、このシーンは、富山のパスが遅れ、その後豊田も同じスペースを狙ってパスを要求しますが、富山はバックパスを選択。開幕戦でのレポートでも指摘しましたが、ゲームメイクするフォワードとしては、ここは前への展開でチャンスを作ってほしかったところです。状況の気づき・判断・そしてパスの技術力という事を考えると、小野がこのポジションに入るという選択肢も見てみたい気もします。


そして、33分の同点ゴールの前のシーンでも、川崎の中盤(エドゥアルド・ネット?)がリスタートからの早い展開で右サイドに起点を作る鳥栖のパスに対して寄せきれず、登里がボール保持者に寄せていったスペースに対して鎌田が狙って走りこんでいます。そして、縦パスを受けた鎌田のクロスをキーパーがはじいたところで、義希のビューティフルゴールが生まれました。


■ まとめ
正直、川崎の守備は緩い場面が多く、スペースを空けてくれる機会も多かったので、チャンスメイキングには苦労していなかった感じです。でも、川崎も最後の中央のところはしっかりしていましたので、鳥栖も勝ち越し点を挙げるところまでには行きませんでした。
また、川崎も攻撃に選手をさいているので、鳥栖としても全体を押し上げて攻撃でイケイケとまではなりきれませんでした。
川崎も、鳥栖も、良いところまでは侵入して行くのですが、最後のシュートシーンまではなかなか繋げることができず、フィニッシュをどのような形で迎えるかというのは、互いに大きな課題が残った試合だと思います。
<画像引用元:DAZN>
■ 試合の流れ
試合開始当初から、両チームとも相手の守備がずれているポイントをついて攻撃を繰り出すような状況でした。川崎の先制点は、鳥栖のミスから生まれたものでありましたが、やはり、小林の動きは突出していて、裏へ抜ける動き出し(ゴールに直結するための動き出し)は、両チームの中でも一番際立っていました。
しかしながら、大塚や阿部のところを使って、いいところまでボールが入るのですが、トラップミスや判断ミスによって、うまく好機を演出することができないシーンも多く、後半にハイネルが入ってから、ボールロストの回数が減ってリズムがでてきたのですが、ポジションの取り方としてやや後ろで受けることが多く、小林とのコンビネーションで決定的チャンスを何度も演出……というシーンを作り出せませんでした。
鳥栖の攻撃は、長短のパスを織り交ぜながら、何回か良いシーンを作ることができていました。思いのほか簡単に川崎のディフェンスラインの裏をつけることができていたと思います。同点ゴールも、きっかけは鎌田が最終ラインの裏に侵入したところからスタートしていますし、左サイドの裏に抜けた豊田の左足のシュートというシーンもありましたし、惜しいシーンは何度もありましたが、2点目を取るまでには至りませんでした。
全体的に、新チームになったばかりということで、攻撃も守備もコンビネーションにちらほらとずれが見え隠れしている状態であり、また、選手個々のコンディションも完全に上がっていない選手がいる状況の試合(特に川崎はACLもあり)でしたので、引き分けと言う結果は妥当なのかなと思いました。
■ 発展途上の守備構築
選手が入れ替わったことによる守備組織の再構築というのはよく聞く話です。選手が入れ替わるという事は、当然ながら能力が異なるメンバーが試合に入るということであり、その個性に合わせた組織の見直しというのが必要になります。チームというものは、組織戦術だけ変えれば…、選手だけ変えれば…という簡単ものではないので、構築には一定の期間がかかる覚悟が必要です。
今回は、23分によいシーンがあったので振り返ります。図は、川崎が、左サイドのスローインから始まって、サイドチェンジで右サイドまでボールを持ってきたところです。右サイドにいる田坂と阿部で組み立てているのですが、ボールが一旦中央に戻ったところで、義希がプレスを始めます。鳥栖としては、そこでハメていこうという合図です。義希がボール保持者にプレスすることによって、次のプレイの選択肢を狭めることができるのですが、それを察知した動きを原川ができていません。本来は、義希の動きに連動して、右サイドにいる田坂へのプレッシャーをかけたいところですが、タイミングがずれたことにより、相手との間が空きすぎて、慌ててプレスにいってもかわされてしまい、小林への縦パスを狙われてしまいます。鳥栖のディフェンスラインが整っており、全体を押し上げてオフサイドを取れたことによって、事なきを得たのですが、田坂が持ち替えなければ動き出し、パスのタイミングによっては決定的ピンチを迎えるようなシーンでしたので、なるべくならばパスの出所を抑えたいシーンでありますし、抑えることが可能であったシーンだと思います。





また、同じように、プレスをするタイミングとスペースを埋めるタイミングの意識がずれたことによって、生じてしまった縦パスのシーンがあったのですが、27分を例に出しますと、これも川崎が左サイドから右サイドに展開している場面です。原川は、しきりに、阿部のことを気にしながら自分のポジションを取っています。しかしながら、阿部に関しては、吉田が応対できる状況であり、また、原川のスペースに入られた際のケアも義希が埋める準備はあるので、自分に対峙している田坂に対するアクションを取って、チーム全体としてハメにいこうというスイッチを入れてもよいかなという状況です。
しかしながら、原川は、ポジショニングを取ることに一生懸命で、自ら能動的にアクションを取ることができておらず、ボールの動き、相手の動きに対応するアクションがとれなかった結果、相手に対するプレッシャーもかからず、パスコースを消すこともできずに、大塚への縦パスを許してしまうことになります。これも、大塚のトラップミスによって事なきを得ましたが、トラップで反転して前を向かれたり、フリックで流されたりすると決定的ピンチを迎えかねない状況でした。

今回は、たまたま原川の動きを例に使いましたが、チームとしてこのような動きのずれによってラストパスを狙われるようなシーンは極力減らさなければなりません。昨年度は、鳥栖の守備構築に半年かかりましたので、新しく入った選手がチームとしての動きをすぐに理解できるわけではないのですが、前線からの組織的な守備というのは、鳥栖が上位に進出するにあたっての絶対条件であるので、少しでも早く全体の戦術理解度を向上してほしいですね。
■ 鎌田のスペースを狙う動き
攻撃面では、この試合で光ったのは、鎌田のディフェンスラインの裏を狙う動きでした。
24分のシーンは連動して崩せた良いシーンでした。左サイドを縦パスで前線までボールを送り込み、空いたスペースを狙って起点を作って裏のスペースに抜けるという、チームとしての動きが統率された非常に良い攻撃だったと思います。




31分のシーンでは、左サイドの富山がボールを受け、田坂がマークについたところのスペースを狙って鎌田が走り込みを見せます。ちなみに、このシーンは、富山のパスが遅れ、その後豊田も同じスペースを狙ってパスを要求しますが、富山はバックパスを選択。開幕戦でのレポートでも指摘しましたが、ゲームメイクするフォワードとしては、ここは前への展開でチャンスを作ってほしかったところです。状況の気づき・判断・そしてパスの技術力という事を考えると、小野がこのポジションに入るという選択肢も見てみたい気もします。


そして、33分の同点ゴールの前のシーンでも、川崎の中盤(エドゥアルド・ネット?)がリスタートからの早い展開で右サイドに起点を作る鳥栖のパスに対して寄せきれず、登里がボール保持者に寄せていったスペースに対して鎌田が狙って走りこんでいます。そして、縦パスを受けた鎌田のクロスをキーパーがはじいたところで、義希のビューティフルゴールが生まれました。


■ まとめ
正直、川崎の守備は緩い場面が多く、スペースを空けてくれる機会も多かったので、チャンスメイキングには苦労していなかった感じです。でも、川崎も最後の中央のところはしっかりしていましたので、鳥栖も勝ち越し点を挙げるところまでには行きませんでした。
また、川崎も攻撃に選手をさいているので、鳥栖としても全体を押し上げて攻撃でイケイケとまではなりきれませんでした。
川崎も、鳥栖も、良いところまでは侵入して行くのですが、最後のシュートシーンまではなかなか繋げることができず、フィニッシュをどのような形で迎えるかというのは、互いに大きな課題が残った試合だと思います。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
20:25
│Match Impression (2017)
2017年03月01日
2017 第1節 : サガン鳥栖 VS 柏レイソル
いよいよJリーグ2017シーズンが開幕しました。我らがサガン鳥栖は、開幕を迎えるに当たり、これまでの歴史を振り返っても、最高の陣容でシーズンを迎えることになったと言えるでしょう。エースの豊田もタイトルへ向けた意欲を高らかに宣言しており、悲願の優勝へ向けた機運が高まる中での開幕でしたが、結果は思うようなものではありませんでした。
■ 試合の流れ
柏のブラジリアン3トップ+伊東純也の攻撃陣はやはり圧巻でした。ハモン・ロペス、ディエゴ・オリベイラのキープ力に加え、伊東の縦へと突進する推進力は鳥栖にとって大きな脅威となり、特に伊東の前半6分の自陣でボールをカットしてから一人で持ち込んでシュートしたプレイや前半8分の鋭いレスポンスからコーナーキックを取ったプレイは、鳥栖サポーターへの挨拶代わりの一発として十分に印象に刻まれました。
柏に対して、鳥栖の序盤の入り方としては、あまりリスクを取らずに構えていた印象を受けました。サイドバックの上りも自重気味でしたし、相手のセンターバックがボールを保持していても、ブロックを構えている状態で積極的に前から奪いに行くような形ではありませんでした。
柏の守備陣は、攻撃の選手たちもしっかりとブロックに入ってコンパクトに鳥栖を迎え打っていて、前線の2人も、下平監督から徹底的に守備の重要さを叩きこまれたのでしょう。非常に組織的で堅い守備だったと思います。鳥栖がフォワードにくさびのボールを打っても柏の選手がすぐに密集してくるので、なかなかよい展開を作れず、やや柏が押している形で序盤は進みました。
試合も落ち着いてくると、鳥栖も徐々にボールを持てるようになり、昨シーズンと同様に、サイドバックの裏のスペースを有効的に使う攻撃が徐々に見え始めてきました。15分頃、鎌田や小野が積極的に突破を図ることによって、何本か惜しいクロスやシュートを放つまでに至りました。吉田豊のポストに当たったシュートは決まってほしかったですね。



一進一退の攻防の中、先制点は鳥栖が挙げます。ゴール前でフリーキックのチャンスを得て、原川のシュートが見事にサガン鳥栖2017シーズン初ゴールを生み出しました。原川は、セットプレイで数々の好機を演出(特にこの直後の豊田の惜しいヘディングの時に蹴ったコーナーキック)しましたし、今後の活躍に期待が持てます。
後半に入ると、ギアを上げてきた柏があっさりと同点に追いつきます。ルーズボールが柏の選手の足元に収まるという不運もありましたが、全体を押し上げるのか、引き下げるのか、やや曖昧な状態で入ってしまった鳥栖を尻目に、猛然と押し込んできた柏の攻撃を受け止めることができずに吉田がPKを与えてしまいました。
その後、鳥栖も陣形を変え、特に富山、鎌田のポジショニングを変更して、前からボールを奪いに行くことでチャンスを作ろうとしますが、柏の強力な攻撃陣にじわじわと押し込まれ、再びPKを与えてしまって意気消沈。3失点目は反撃の気持ちを削ぎ落すには十分なダメ押し点でした。
■ 鳥栖の守備陣形
試合開始序盤からは、鳥栖は守備の陣形を4-3-2-1で待ち構えました。中央のボランチへのパスをケアするために、富山が1列下がって鎌田と2人でラインを組んでおり、中盤は昨年と同様のスタイルで、小野、義希、原川の3人が互いにスペースを埋めあいながら入ってきたボールに対してプレッシャーに向かっていました。
それに対して、柏は、守備時の4-4-2から、攻撃の際にはサイドバックの輪湖を1列上げて、3-5-2の形で組み立てを行いました。この陣形によって柏にアドバンテージが生まれたのは、柏の最終ラインへのプレッシャーが豊田一人であったため、最終ラインで苦労することなくボールをキープできたことです。鳥栖のプレッシャーがかからない状態であるため、最終ライン間でひとり飛ばせるパスを出す余裕があることになり、左右に振ることによって鳥栖のスライドの遅れを生じさせる確率を高め、輪湖もしくは伊藤をフリーにする機会が生まれました。



鳥栖にとって、もう一つ苦労したのは、柏の前線(ハモン・ロペス、ディエゴ・オリベイラ)のキープ力でした。柏もサイドに拠点を作るよりは、当然中央への縦パス1本の方がゴールに直結するわけでありまして、サイドをおとりに使いながら常に前線の2人への供給を狙っています。もちろん、縦へのパスと言うのは鳥栖としても狙いどころでありまして、入ってきたところをセンターハーフの3人とセカンドトップの2人が素早い寄せでボールを奪おうとアタックを仕掛けていました。ところが、いつもであればボールを奪ってショートカウンターのチャンスを作れるシーンでありながら、前線の選手がボールロストせずにキープし続けていました。いつもの奪いどころで奪えない事が、なかなか鳥栖のリズムにならなかったところです。

後半に入ると、富山、鎌田の位置を変えました。前半は柏の最終ライン3人に対して豊田1人しかプレッシャーにかかりませんでしたが、後半からは富山も前から行くことによって柏の最終ラインにプレッシャーがかからない状態を解消し、それとともに、鎌田の位置を1列下げて、中盤を4人の構成でフラットに構えさせる状態を作りました。マッシモさんがハーフタイムにセカンドボールに対するマネジメントに関して選手たちに忠告した模様ですが、もしかしたら、前から行かせることによって、柏が長いボールを蹴ってくることを想定していたのかもしれません。
68分のシーンは、前半にはあまり見られなかった、相手の陣形にはまったボールの奪い方でして、柏の最終ラインのボール回しを前線から追いかけ、原川が高い位置で奪いとることができました。しかし、ホント、この位置でボールを奪ってからの鎌田が放ったニアへのシュートは惜しかったですね。中村のスーパーファインセーブでした。


ただ、攻撃と守備は表裏一体でありまして、鎌田の位置を下げるという事は、ボールを奪ってから鎌田がゴールから遠い位置にポジショニングを取ってしまうという事であり、奪ってからのショートカウンターを作り出そうとするものの、鎌田のドリブル開始の位置が低いため、豊田や富山との連係もかみ合わず、ひとりで突っかけて行って柏の守備陣にひっかかるシーンも数回ありました。鎌田のポジショニングをどこに取らせたら正解なのかという答えはなかなか見つからないですね。
■ 個々の力の重要さ
失点は、いずれも守備組織が崩壊したわけではなく、柏のクロスが上がるシーンで、2人がマークについているものの、そこでボールを奪う事ができずに、クロスを上げられたのがそもそもの失点の元凶でしょう。
逆転のゴールを生み出すPKの前のシーンでは、ディエゴ・オリベイラが、原川、谷口の両選手にマークにつかれながらも体の向きを変えるフェイントだけで二人をぶち抜いていきました。ダメ押しのゴールのクロスのシーンでもクリスティアーノに2人がついていたものの、プレッシャーが甘く、簡単にクロスを上げられてしまいました。3失点目に関しては、センターバックの2人の間にあのスピードでクロスを蹴られたらなす術がないでしょう。


また、試合のところどころで、誰がプレッシャーをかけるのか、誰がカバーリングの準備をするのか、選手間の整理がうまくついていないシーンが見られました。(吉田&原川や小野&藤田のハーフ&サイドバックの摺合せが少し足りていないかなと感じました。)守備のベースは昨年と同様の形ということで、基礎としてできあがっているので、これからは、ボールの位置や相手選手の位置関係によって、選手間で自然にプレッシャー、カバーリング、そしてスペースを埋める動きができるようにディテールの部分をつめていけば、昨年度よりも早い時期にチームとして好調の波が来るのではないかなと感じました。
それと同時に、柏のように、強力なフォワードがいる時に、守備組織だけではまかないきれない個の部分の向上は必要だと思います。特に、原川がボールを奪うための相手との間合いの詰め方、プレッシャーのかけ方という武器をつけたら、義希をしのぐ素晴らしいアンカーになれる素質があると感じました。
■ 攻撃の形作り・役割分担
この試合の攻撃は、いくつか良いシーンは見られたのですが、攻撃の核となる選手・パターンがなかなか見つけられないまま、90分が過ぎてしまった印象です。ひとりひとりの選手は非常に素質が高い選手が多いです。しかしながら、これらがまだまだかみ合っていません。
一番感じたのは、豊田はストライカーであるので、彼がシュートを打てるシーンをチームとして作り上げる事が大事なのですが、柏戦では、豊田が下がってボールを受けたり、ポストではたくシーンが目立ち、ゴール前で目立つことがほとんどありませんでした。(時には、最終ラインに戻って守備をすることも!)
ゲームメイクの役割は、本来は富山に求めたいところであるのですが、富山はチャンスを作り出す効果的な動きがほとんどできず、正直、ゲームの中では消えてしまっていた印象です。
また、この試合はここぞという場面でオフサイドの笛が良くなっていた気がします。無論、柏のディフェンスラインの高さ・コンパクトさによるものなのですが、今後、選手間の意識が統一されて受け手が欲しいタイミングとパスを出すタイミングが一致しだしたら、オフサイドにかかることなくチャンスを迎えるシーンも増えていくでしょう。
■ スタジアムの雰囲気
2失点目を喫してから、スタジアム全体の雰囲気や矛先がやや審判に向きかけていたのかなというのを感じました。選手たちの気持ちが萎えかけているところでしたので、選手たちが前を向いて気持ちを切り替えるような雰囲気作りをしなければなりませんでした。鳥栖の選手がボールを持った時に相手を圧倒するくらいの声援・雰囲気を作り出すことができれば、ホームスタジアムとして大きく後押しできます。自分の経験ですが、選手としてプレイしている時、良いプレイによって観客席から拍手があがるだけで選手はうれしいものですし、心の励みにもなります。たとえどんな状況でも、失点の後は気持ちを切り替えて、良いプレイやチャンスシーンには、惜しみない拍手と声援を送りたいですね。
■ 今シーズンへの期待
先ほども書きましたが、今年の陣容として、個々の能力が非常に高い選手が多いのを随所に感じました。セットプレイからの好機だけでも、昨年とは比べ物にならないくらいの可能性を感じました。非常に大きな武器だと思います。スコアこそ1-3というものでしたが、監督を信じて、選手たちが怪我することなく、コミュニケーションを取りながら戦う事ができれば、必ず昨年以上の成績を残せると信じています。開幕戦は残念な結果に終わりましたが、気持ちを切り替えて、次の戦いを応援したいと思います。
<画像引用元:DAZN>
■ 試合の流れ
柏のブラジリアン3トップ+伊東純也の攻撃陣はやはり圧巻でした。ハモン・ロペス、ディエゴ・オリベイラのキープ力に加え、伊東の縦へと突進する推進力は鳥栖にとって大きな脅威となり、特に伊東の前半6分の自陣でボールをカットしてから一人で持ち込んでシュートしたプレイや前半8分の鋭いレスポンスからコーナーキックを取ったプレイは、鳥栖サポーターへの挨拶代わりの一発として十分に印象に刻まれました。
柏に対して、鳥栖の序盤の入り方としては、あまりリスクを取らずに構えていた印象を受けました。サイドバックの上りも自重気味でしたし、相手のセンターバックがボールを保持していても、ブロックを構えている状態で積極的に前から奪いに行くような形ではありませんでした。
柏の守備陣は、攻撃の選手たちもしっかりとブロックに入ってコンパクトに鳥栖を迎え打っていて、前線の2人も、下平監督から徹底的に守備の重要さを叩きこまれたのでしょう。非常に組織的で堅い守備だったと思います。鳥栖がフォワードにくさびのボールを打っても柏の選手がすぐに密集してくるので、なかなかよい展開を作れず、やや柏が押している形で序盤は進みました。
試合も落ち着いてくると、鳥栖も徐々にボールを持てるようになり、昨シーズンと同様に、サイドバックの裏のスペースを有効的に使う攻撃が徐々に見え始めてきました。15分頃、鎌田や小野が積極的に突破を図ることによって、何本か惜しいクロスやシュートを放つまでに至りました。吉田豊のポストに当たったシュートは決まってほしかったですね。



一進一退の攻防の中、先制点は鳥栖が挙げます。ゴール前でフリーキックのチャンスを得て、原川のシュートが見事にサガン鳥栖2017シーズン初ゴールを生み出しました。原川は、セットプレイで数々の好機を演出(特にこの直後の豊田の惜しいヘディングの時に蹴ったコーナーキック)しましたし、今後の活躍に期待が持てます。
後半に入ると、ギアを上げてきた柏があっさりと同点に追いつきます。ルーズボールが柏の選手の足元に収まるという不運もありましたが、全体を押し上げるのか、引き下げるのか、やや曖昧な状態で入ってしまった鳥栖を尻目に、猛然と押し込んできた柏の攻撃を受け止めることができずに吉田がPKを与えてしまいました。
その後、鳥栖も陣形を変え、特に富山、鎌田のポジショニングを変更して、前からボールを奪いに行くことでチャンスを作ろうとしますが、柏の強力な攻撃陣にじわじわと押し込まれ、再びPKを与えてしまって意気消沈。3失点目は反撃の気持ちを削ぎ落すには十分なダメ押し点でした。
■ 鳥栖の守備陣形
試合開始序盤からは、鳥栖は守備の陣形を4-3-2-1で待ち構えました。中央のボランチへのパスをケアするために、富山が1列下がって鎌田と2人でラインを組んでおり、中盤は昨年と同様のスタイルで、小野、義希、原川の3人が互いにスペースを埋めあいながら入ってきたボールに対してプレッシャーに向かっていました。
それに対して、柏は、守備時の4-4-2から、攻撃の際にはサイドバックの輪湖を1列上げて、3-5-2の形で組み立てを行いました。この陣形によって柏にアドバンテージが生まれたのは、柏の最終ラインへのプレッシャーが豊田一人であったため、最終ラインで苦労することなくボールをキープできたことです。鳥栖のプレッシャーがかからない状態であるため、最終ライン間でひとり飛ばせるパスを出す余裕があることになり、左右に振ることによって鳥栖のスライドの遅れを生じさせる確率を高め、輪湖もしくは伊藤をフリーにする機会が生まれました。



鳥栖にとって、もう一つ苦労したのは、柏の前線(ハモン・ロペス、ディエゴ・オリベイラ)のキープ力でした。柏もサイドに拠点を作るよりは、当然中央への縦パス1本の方がゴールに直結するわけでありまして、サイドをおとりに使いながら常に前線の2人への供給を狙っています。もちろん、縦へのパスと言うのは鳥栖としても狙いどころでありまして、入ってきたところをセンターハーフの3人とセカンドトップの2人が素早い寄せでボールを奪おうとアタックを仕掛けていました。ところが、いつもであればボールを奪ってショートカウンターのチャンスを作れるシーンでありながら、前線の選手がボールロストせずにキープし続けていました。いつもの奪いどころで奪えない事が、なかなか鳥栖のリズムにならなかったところです。

後半に入ると、富山、鎌田の位置を変えました。前半は柏の最終ライン3人に対して豊田1人しかプレッシャーにかかりませんでしたが、後半からは富山も前から行くことによって柏の最終ラインにプレッシャーがかからない状態を解消し、それとともに、鎌田の位置を1列下げて、中盤を4人の構成でフラットに構えさせる状態を作りました。マッシモさんがハーフタイムにセカンドボールに対するマネジメントに関して選手たちに忠告した模様ですが、もしかしたら、前から行かせることによって、柏が長いボールを蹴ってくることを想定していたのかもしれません。
68分のシーンは、前半にはあまり見られなかった、相手の陣形にはまったボールの奪い方でして、柏の最終ラインのボール回しを前線から追いかけ、原川が高い位置で奪いとることができました。しかし、ホント、この位置でボールを奪ってからの鎌田が放ったニアへのシュートは惜しかったですね。中村のスーパーファインセーブでした。


ただ、攻撃と守備は表裏一体でありまして、鎌田の位置を下げるという事は、ボールを奪ってから鎌田がゴールから遠い位置にポジショニングを取ってしまうという事であり、奪ってからのショートカウンターを作り出そうとするものの、鎌田のドリブル開始の位置が低いため、豊田や富山との連係もかみ合わず、ひとりで突っかけて行って柏の守備陣にひっかかるシーンも数回ありました。鎌田のポジショニングをどこに取らせたら正解なのかという答えはなかなか見つからないですね。
■ 個々の力の重要さ
失点は、いずれも守備組織が崩壊したわけではなく、柏のクロスが上がるシーンで、2人がマークについているものの、そこでボールを奪う事ができずに、クロスを上げられたのがそもそもの失点の元凶でしょう。
逆転のゴールを生み出すPKの前のシーンでは、ディエゴ・オリベイラが、原川、谷口の両選手にマークにつかれながらも体の向きを変えるフェイントだけで二人をぶち抜いていきました。ダメ押しのゴールのクロスのシーンでもクリスティアーノに2人がついていたものの、プレッシャーが甘く、簡単にクロスを上げられてしまいました。3失点目に関しては、センターバックの2人の間にあのスピードでクロスを蹴られたらなす術がないでしょう。


また、試合のところどころで、誰がプレッシャーをかけるのか、誰がカバーリングの準備をするのか、選手間の整理がうまくついていないシーンが見られました。(吉田&原川や小野&藤田のハーフ&サイドバックの摺合せが少し足りていないかなと感じました。)守備のベースは昨年と同様の形ということで、基礎としてできあがっているので、これからは、ボールの位置や相手選手の位置関係によって、選手間で自然にプレッシャー、カバーリング、そしてスペースを埋める動きができるようにディテールの部分をつめていけば、昨年度よりも早い時期にチームとして好調の波が来るのではないかなと感じました。
それと同時に、柏のように、強力なフォワードがいる時に、守備組織だけではまかないきれない個の部分の向上は必要だと思います。特に、原川がボールを奪うための相手との間合いの詰め方、プレッシャーのかけ方という武器をつけたら、義希をしのぐ素晴らしいアンカーになれる素質があると感じました。
■ 攻撃の形作り・役割分担
この試合の攻撃は、いくつか良いシーンは見られたのですが、攻撃の核となる選手・パターンがなかなか見つけられないまま、90分が過ぎてしまった印象です。ひとりひとりの選手は非常に素質が高い選手が多いです。しかしながら、これらがまだまだかみ合っていません。
一番感じたのは、豊田はストライカーであるので、彼がシュートを打てるシーンをチームとして作り上げる事が大事なのですが、柏戦では、豊田が下がってボールを受けたり、ポストではたくシーンが目立ち、ゴール前で目立つことがほとんどありませんでした。(時には、最終ラインに戻って守備をすることも!)
ゲームメイクの役割は、本来は富山に求めたいところであるのですが、富山はチャンスを作り出す効果的な動きがほとんどできず、正直、ゲームの中では消えてしまっていた印象です。
また、この試合はここぞという場面でオフサイドの笛が良くなっていた気がします。無論、柏のディフェンスラインの高さ・コンパクトさによるものなのですが、今後、選手間の意識が統一されて受け手が欲しいタイミングとパスを出すタイミングが一致しだしたら、オフサイドにかかることなくチャンスを迎えるシーンも増えていくでしょう。
■ スタジアムの雰囲気
2失点目を喫してから、スタジアム全体の雰囲気や矛先がやや審判に向きかけていたのかなというのを感じました。選手たちの気持ちが萎えかけているところでしたので、選手たちが前を向いて気持ちを切り替えるような雰囲気作りをしなければなりませんでした。鳥栖の選手がボールを持った時に相手を圧倒するくらいの声援・雰囲気を作り出すことができれば、ホームスタジアムとして大きく後押しできます。自分の経験ですが、選手としてプレイしている時、良いプレイによって観客席から拍手があがるだけで選手はうれしいものですし、心の励みにもなります。たとえどんな状況でも、失点の後は気持ちを切り替えて、良いプレイやチャンスシーンには、惜しみない拍手と声援を送りたいですね。
■ 今シーズンへの期待
先ほども書きましたが、今年の陣容として、個々の能力が非常に高い選手が多いのを随所に感じました。セットプレイからの好機だけでも、昨年とは比べ物にならないくらいの可能性を感じました。非常に大きな武器だと思います。スコアこそ1-3というものでしたが、監督を信じて、選手たちが怪我することなく、コミュニケーションを取りながら戦う事ができれば、必ず昨年以上の成績を残せると信じています。開幕戦は残念な結果に終わりましたが、気持ちを切り替えて、次の戦いを応援したいと思います。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
20:00
│Match Impression (2017)