2018年12月06日
2018 第34節 : 鹿島アントラーズ VS サガン鳥栖
2018年第34節、鹿島アントラーズ戦のレビューです。
鳥栖のセットアップは4-4-2。スタメンはマリノス戦からの変更があり、左サイドバックに三丸を起用しました。ベンチには豊田、池田というサガン鳥栖のレジェンドたちが顔をそろえます。
対する鹿島のセットアップも鳥栖と同様に4-4-2で原則的にはミラーゲームの状態。ただし、鹿島の方がフォワードも含めた流動的なポジションチェンジによって、局所的な数的優位を作るという動きが洗練されており、試合全体を通じて鹿島がボールを握る展開となりました。
この試合で特徴的だったのは、攻撃に出る場面と守備で引く場面がくっきりと明確であった所。どちらかがボールを握るタームとなると、比較的継続してポゼションを取ることが出来ていました。鳥栖は、マリノス戦のように積極的にサイドハーフをあげたプレッシングという形はとらず、相手センターバックには自由は許さないけれども、かといって過度なプレッシャーによって奪い取りにいくわけではないという、非常にインテリジェンスさ(前への推進と後ろへの撤退のタイミングの判断)が要求される守備をとっていました。たとえ、ビルドアップフェーズで網を潜り抜けられるとしても、同時にサイドハーフまで含めたリトリートを開始してブロックをしっかりと構築し、クロスに対しても裏抜けに対しても人っ子一人逃さないという集中した守備を見せていました。
鳥栖はビルドアップにおいては、鹿島を崩しきるためのアイデアには乏しく、攻撃の生命線となったのはカウンター攻撃でした。ボールを引きだす多くのケースとして、サイドバックの裏のスペースにフォワードが入って起点を作り、そこからサイドハーフやボランチ、時にはサイドバックがフォローで追い越していくという形を作っていました。カウンター攻撃にかける人数に関しては、マッシモ時代に比べると非常に多くの人数を割いており、ボールを奪ってから相手陣地にはいっていく人数は単純に増えています。ただし、やみくもに入っていく人数を増やしているわけでもなく、最終ラインは適度な人数を中央に残していて、カウンター攻撃への逆カウンターに対応できるようにしています。カウンター時の攻撃デザインはかなり整理された印象です。



鹿島も鳥栖と同様に、アタッキングサードから積極的な守備を展開していたわけではなく、ミドルサード付近でやや見ている戦いであったので、序盤は鳥栖の運動量を活用した押し込みとセカンドボール奪取に苦労していました。鳥栖がその時間帯に、立て続けにセットプレイのチャンスを得たのですが、このチャンスで得点に繋げることができなかったことによって、リズムが変わっていきます。
序盤の鳥栖の攻勢を乗り切った鹿島は徐々にボールポゼションを高めて、鳥栖を押し込みだしました。鳥栖がブロックを構える守備で対応していたので、鹿島はビルドアップの中で徐々に攻撃方法を確立していきます。攻撃のポイントとしては、ワイドに広がって起点をつくるフォワードと大きなサイドチェンジ。特に右サイドは縦に勝負できる西がいるので、左で作って右に展開し、クロスをあげるというひとつのパターンが確立されていました。


鹿島は、ひとたび押し込む事に成功すると攻撃に人数をかけてきますので、鳥栖も守備に人数をかけざるを得なくなります。今節の戦いで鹿島にイニシアチブを握られていると感じたのは、小野のポジショニング。三丸がワイドに開いて対応しなければならなくなったスペースを小野が埋めなければならない状態を作ってしまいました。こうなってしまうと、一つの問題点として、ポジティブトランジション(ボールを奪って攻撃に転じる場面)において、フォワードへのサポートがどうしても薄くなるという状態が生まれます。鹿島の攻撃に対して、サイドハーフがこのポジションで守備をしなければならなくなったということが、鳥栖がイニシアチブを握れなかった要因ですね。今節の小野は、すごく良い守備をしていたと思います。ゴール前の相手とのデュエルでしっかりとボールをひっかけるシーンもありました。


鳥栖としては、ボールを奪ってからは高い位置を取ってくるサイドバックの裏のスペースを使ってフォワードがボールを受ける動きを見せます。ここで、トーレス、チョドンゴンがキープ出来れば良いのですが、小野や福田のフォローが遅れるため、ボールキープと次への展開をひとりで解決しなければなりません。鹿島は、センターバック+αが抑えにくるので、さすがのトーレスもチョドンゴンもボールキープもままならない時間帯が続きました。これが、ポジティブトランジションによるボールキープが上手くいかずに、ずっと鹿島のターンのような状態になってしまった一つの要因でした。逆に言うと、ここでしっかりとボールキープしていい形で展開できた場合には、鳥栖のターンというのも作れていました。



後半にはいると鳥栖はやや守備のギアを上げて、高い位置からボールを奪いにいく形が見えだしました。相手が鹿島なので、リトリートしてブロックを組んでいるだけだと、押し切られて失点してしまう可能性があったので、まずは積極的な守備でイニシアチブを取りにいったのでしょう。選手交代も、前線の交替からという事だったのですが、メンツ的には、池田、豊田とプレッシングなどしっかりとこなしてくれるメンバーだったので、そのあたりは送り出すに当たっての安心感はあったかと思います。
前線からの守備という観点では、トーレスも非常によく守備を頑張っていました。ボールを奪われた際のネガティブトランジション(攻から守への切り替え)でも、積極的に相手選手にプレッシャーをかけ、例えファールになったとしてもアグレッシブにボールを奪いに行く姿も見えました。しかしながら、実は、トーレスの守備の本当に素晴らしいところは、そのような目に見えやすいプレッシングの場面ではありません。味方選手のポジションのずれが生じて相手が突いてこようとするスペースができても、攻撃される事を未然に防ぐポジショニング、相手のボールを追いこむエリアを決めたらそこに相手を誘導するようなポジショニングこそがトーレス(スペインの選手)の守備の真骨頂なのです。守備の肝は頑張らなくてもよい形を作る事です。スペースを空けるから、人数が足りなくなってしまうから、何人ものメンバーがハードワークして、頑張らなければならなくなってしまうのです。本当に良い守備というのは、最初から適切なポジションを取って相手が攻撃をしづらい形を作り、相手が攻撃をしかけようとする隙を与えない事にあります。


両チームともに、引き分けならば目標達成(鹿島は2位もありましたが)なのですが、負けてしまうと途端に目標到達が厳しくなってしまう状態であり、勝ちに行かなければならないけど、負けたくはないという状況が試合展開を難しくしました。鳥栖にとっても、積極的に前から奪いに行く事は、攻撃の為の守備というよりは、相手をゴール前から出来る限り遠ざけるための守備というものでした。両チームともに、引き分け狙いで消極的というわけではありませんでしたが、当然の事ながら大きなリスクをかけてでも得点を奪いに行くという戦術にはなりませんでした。後半も時間が経つにつれて、スペースができてカウンターの応酬になるものの、守備側がリスクマネジメントで守備要員を残しているので、決定的な状況までは作れないという形になりました。ある意味、両チームとも攻守の比重をバランスよく置き、そしてそのバランス通りにスコアレスで終わったという試合でした。
この結果、鹿島は来期のACL出場を決め、鳥栖は残留を決めるというシーズンとなりました。鳥栖にとっては、春先の7連敗から始まり、ずっと苦しいシーズンを過ごしてきましたが、残留に向けた苦労(投資)が報われる形で終える事ができて本当に良かったです。
竹原社長は、サガン鳥栖サポーターに、「負けを重ねてもブーイングだけはしないでくれ」とおっしゃっていましたが、シーズン終了後の選手コメントを見るに、「負けてもブーイングをせずに声援で後押しをしてくれるサポーターたちに報いたかった」というコメントもちらほら見えました。トーレスもそう語っていましたね。
私は、時にはブーイングは必要なこともあると思います。それは、試合中にフェアじゃないプレイがあった時や、試合に集中していないようなプレイがあった時のような、瞬間、瞬間の場面です。しかしながら、試合が終わった後は、例えその試合が惨敗だったとしても、勝利を目指して全力で戦ってくれた選手たちを労い、そして次の試合に勝つために最高の準備をしようという気持ちになるよう、モチベーションを高めてやることが必要であり重要だと思います。試合後に負けた怒りを選手にぶつけるのではなく、負けて悔しい気持ちを胸にぐっと抑え込んで、選手たちを鼓舞するサポソンを歌うサガン鳥栖サポーターは、今回の残留に大きく貢献したのだと、胸を張って言えます。試合に負けて悔しいのはサポーターだけでなく、何よりもプレイしている選手たちも当然悔しいのですからね。そこで怒りと罵詈雑言の言葉をぶつけたところで、何も産み出すものはありません。
2018シーズンも幕を閉じました。サガン鳥栖に関係するみなさん、本当に残留おめでとうございました。しかしながら、ほっとするのもつかの間、2019シーズンへ向けた戦いは既に始まっています。監督も選手もスポンサーも、サガン鳥栖に関わる全ての事柄において、来シーズンこそはITADAKIを目指すチームを作らなければなりません。そのためにも、我々サポーターはまずはドリームパスポートを購入して、チームを「資金」という形で支援することが必要です。「資金」を支援して作り上げたチームを、開幕してからは再び我々の「声援」で支援しましょう。
最後に、堅固な守備組織構築を目指したマッシモ・フィッカデンティ監督によって得失点差をなんとか抑え込む事ができ、そしてその守備基盤の上に攻撃というエッセンスを加えてくれた金明輝監督によって、残留を果たすことができました。両監督がサガン鳥栖の為に死力を尽くしてくれたからこそ、我々は来年もトップリーグで戦う事ができます。本当にありがとうございました。
サガン鳥栖サポーターのみなさん、苦しいシーズンでしたが、今年1年間、本当におつかれさまでした!
また来シーズンも、時間が許す限り、当Blogのコンセプトである「サガン鳥栖の戦術を分析して分かりやすく説明できるように心がけたい」と思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。
※シーズンオフも、データ分析などでちょくちょくエントリーしたいと思うので、そちらもよろしくお願いします。
<画像引用元:DAZN>
鳥栖のセットアップは4-4-2。スタメンはマリノス戦からの変更があり、左サイドバックに三丸を起用しました。ベンチには豊田、池田というサガン鳥栖のレジェンドたちが顔をそろえます。
対する鹿島のセットアップも鳥栖と同様に4-4-2で原則的にはミラーゲームの状態。ただし、鹿島の方がフォワードも含めた流動的なポジションチェンジによって、局所的な数的優位を作るという動きが洗練されており、試合全体を通じて鹿島がボールを握る展開となりました。
この試合で特徴的だったのは、攻撃に出る場面と守備で引く場面がくっきりと明確であった所。どちらかがボールを握るタームとなると、比較的継続してポゼションを取ることが出来ていました。鳥栖は、マリノス戦のように積極的にサイドハーフをあげたプレッシングという形はとらず、相手センターバックには自由は許さないけれども、かといって過度なプレッシャーによって奪い取りにいくわけではないという、非常にインテリジェンスさ(前への推進と後ろへの撤退のタイミングの判断)が要求される守備をとっていました。たとえ、ビルドアップフェーズで網を潜り抜けられるとしても、同時にサイドハーフまで含めたリトリートを開始してブロックをしっかりと構築し、クロスに対しても裏抜けに対しても人っ子一人逃さないという集中した守備を見せていました。
鳥栖はビルドアップにおいては、鹿島を崩しきるためのアイデアには乏しく、攻撃の生命線となったのはカウンター攻撃でした。ボールを引きだす多くのケースとして、サイドバックの裏のスペースにフォワードが入って起点を作り、そこからサイドハーフやボランチ、時にはサイドバックがフォローで追い越していくという形を作っていました。カウンター攻撃にかける人数に関しては、マッシモ時代に比べると非常に多くの人数を割いており、ボールを奪ってから相手陣地にはいっていく人数は単純に増えています。ただし、やみくもに入っていく人数を増やしているわけでもなく、最終ラインは適度な人数を中央に残していて、カウンター攻撃への逆カウンターに対応できるようにしています。カウンター時の攻撃デザインはかなり整理された印象です。



鹿島も鳥栖と同様に、アタッキングサードから積極的な守備を展開していたわけではなく、ミドルサード付近でやや見ている戦いであったので、序盤は鳥栖の運動量を活用した押し込みとセカンドボール奪取に苦労していました。鳥栖がその時間帯に、立て続けにセットプレイのチャンスを得たのですが、このチャンスで得点に繋げることができなかったことによって、リズムが変わっていきます。
序盤の鳥栖の攻勢を乗り切った鹿島は徐々にボールポゼションを高めて、鳥栖を押し込みだしました。鳥栖がブロックを構える守備で対応していたので、鹿島はビルドアップの中で徐々に攻撃方法を確立していきます。攻撃のポイントとしては、ワイドに広がって起点をつくるフォワードと大きなサイドチェンジ。特に右サイドは縦に勝負できる西がいるので、左で作って右に展開し、クロスをあげるというひとつのパターンが確立されていました。


鹿島は、ひとたび押し込む事に成功すると攻撃に人数をかけてきますので、鳥栖も守備に人数をかけざるを得なくなります。今節の戦いで鹿島にイニシアチブを握られていると感じたのは、小野のポジショニング。三丸がワイドに開いて対応しなければならなくなったスペースを小野が埋めなければならない状態を作ってしまいました。こうなってしまうと、一つの問題点として、ポジティブトランジション(ボールを奪って攻撃に転じる場面)において、フォワードへのサポートがどうしても薄くなるという状態が生まれます。鹿島の攻撃に対して、サイドハーフがこのポジションで守備をしなければならなくなったということが、鳥栖がイニシアチブを握れなかった要因ですね。今節の小野は、すごく良い守備をしていたと思います。ゴール前の相手とのデュエルでしっかりとボールをひっかけるシーンもありました。


鳥栖としては、ボールを奪ってからは高い位置を取ってくるサイドバックの裏のスペースを使ってフォワードがボールを受ける動きを見せます。ここで、トーレス、チョドンゴンがキープ出来れば良いのですが、小野や福田のフォローが遅れるため、ボールキープと次への展開をひとりで解決しなければなりません。鹿島は、センターバック+αが抑えにくるので、さすがのトーレスもチョドンゴンもボールキープもままならない時間帯が続きました。これが、ポジティブトランジションによるボールキープが上手くいかずに、ずっと鹿島のターンのような状態になってしまった一つの要因でした。逆に言うと、ここでしっかりとボールキープしていい形で展開できた場合には、鳥栖のターンというのも作れていました。



後半にはいると鳥栖はやや守備のギアを上げて、高い位置からボールを奪いにいく形が見えだしました。相手が鹿島なので、リトリートしてブロックを組んでいるだけだと、押し切られて失点してしまう可能性があったので、まずは積極的な守備でイニシアチブを取りにいったのでしょう。選手交代も、前線の交替からという事だったのですが、メンツ的には、池田、豊田とプレッシングなどしっかりとこなしてくれるメンバーだったので、そのあたりは送り出すに当たっての安心感はあったかと思います。
前線からの守備という観点では、トーレスも非常によく守備を頑張っていました。ボールを奪われた際のネガティブトランジション(攻から守への切り替え)でも、積極的に相手選手にプレッシャーをかけ、例えファールになったとしてもアグレッシブにボールを奪いに行く姿も見えました。しかしながら、実は、トーレスの守備の本当に素晴らしいところは、そのような目に見えやすいプレッシングの場面ではありません。味方選手のポジションのずれが生じて相手が突いてこようとするスペースができても、攻撃される事を未然に防ぐポジショニング、相手のボールを追いこむエリアを決めたらそこに相手を誘導するようなポジショニングこそがトーレス(スペインの選手)の守備の真骨頂なのです。守備の肝は頑張らなくてもよい形を作る事です。スペースを空けるから、人数が足りなくなってしまうから、何人ものメンバーがハードワークして、頑張らなければならなくなってしまうのです。本当に良い守備というのは、最初から適切なポジションを取って相手が攻撃をしづらい形を作り、相手が攻撃をしかけようとする隙を与えない事にあります。


両チームともに、引き分けならば目標達成(鹿島は2位もありましたが)なのですが、負けてしまうと途端に目標到達が厳しくなってしまう状態であり、勝ちに行かなければならないけど、負けたくはないという状況が試合展開を難しくしました。鳥栖にとっても、積極的に前から奪いに行く事は、攻撃の為の守備というよりは、相手をゴール前から出来る限り遠ざけるための守備というものでした。両チームともに、引き分け狙いで消極的というわけではありませんでしたが、当然の事ながら大きなリスクをかけてでも得点を奪いに行くという戦術にはなりませんでした。後半も時間が経つにつれて、スペースができてカウンターの応酬になるものの、守備側がリスクマネジメントで守備要員を残しているので、決定的な状況までは作れないという形になりました。ある意味、両チームとも攻守の比重をバランスよく置き、そしてそのバランス通りにスコアレスで終わったという試合でした。
この結果、鹿島は来期のACL出場を決め、鳥栖は残留を決めるというシーズンとなりました。鳥栖にとっては、春先の7連敗から始まり、ずっと苦しいシーズンを過ごしてきましたが、残留に向けた苦労(投資)が報われる形で終える事ができて本当に良かったです。
竹原社長は、サガン鳥栖サポーターに、「負けを重ねてもブーイングだけはしないでくれ」とおっしゃっていましたが、シーズン終了後の選手コメントを見るに、「負けてもブーイングをせずに声援で後押しをしてくれるサポーターたちに報いたかった」というコメントもちらほら見えました。トーレスもそう語っていましたね。
私は、時にはブーイングは必要なこともあると思います。それは、試合中にフェアじゃないプレイがあった時や、試合に集中していないようなプレイがあった時のような、瞬間、瞬間の場面です。しかしながら、試合が終わった後は、例えその試合が惨敗だったとしても、勝利を目指して全力で戦ってくれた選手たちを労い、そして次の試合に勝つために最高の準備をしようという気持ちになるよう、モチベーションを高めてやることが必要であり重要だと思います。試合後に負けた怒りを選手にぶつけるのではなく、負けて悔しい気持ちを胸にぐっと抑え込んで、選手たちを鼓舞するサポソンを歌うサガン鳥栖サポーターは、今回の残留に大きく貢献したのだと、胸を張って言えます。試合に負けて悔しいのはサポーターだけでなく、何よりもプレイしている選手たちも当然悔しいのですからね。そこで怒りと罵詈雑言の言葉をぶつけたところで、何も産み出すものはありません。
2018シーズンも幕を閉じました。サガン鳥栖に関係するみなさん、本当に残留おめでとうございました。しかしながら、ほっとするのもつかの間、2019シーズンへ向けた戦いは既に始まっています。監督も選手もスポンサーも、サガン鳥栖に関わる全ての事柄において、来シーズンこそはITADAKIを目指すチームを作らなければなりません。そのためにも、我々サポーターはまずはドリームパスポートを購入して、チームを「資金」という形で支援することが必要です。「資金」を支援して作り上げたチームを、開幕してからは再び我々の「声援」で支援しましょう。
最後に、堅固な守備組織構築を目指したマッシモ・フィッカデンティ監督によって得失点差をなんとか抑え込む事ができ、そしてその守備基盤の上に攻撃というエッセンスを加えてくれた金明輝監督によって、残留を果たすことができました。両監督がサガン鳥栖の為に死力を尽くしてくれたからこそ、我々は来年もトップリーグで戦う事ができます。本当にありがとうございました。
サガン鳥栖サポーターのみなさん、苦しいシーズンでしたが、今年1年間、本当におつかれさまでした!
また来シーズンも、時間が許す限り、当Blogのコンセプトである「サガン鳥栖の戦術を分析して分かりやすく説明できるように心がけたい」と思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。
※シーズンオフも、データ分析などでちょくちょくエントリーしたいと思うので、そちらもよろしくお願いします。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
17:59
│Match Impression (2018)
2018年11月29日
2018 第33節 : サガン鳥栖 VS 横浜F・マリノス
2018年第33節、横浜マリノス戦のレビューです。
鳥栖のセットアップは4-4-2。フォワードにはチョドンゴンが入りトーレスとのツートップ。左サイドハーフに小野、左サイドバックには安在を起用しました。金崎、田川、三丸に関しては、万全ではないという情報もあり、ベンチスタートです。
対するマリノスは攻撃時と守備時で大きく陣形を変えるスタイル。攻撃時が特徴的でして、システム的に言うと2-3-2-3のような形。最終ラインは2センターバック(+時折ゴールキーパー)でビルドアップスタート。サイドバックを中央の高い位置に上げて扇原を含めた3人がセントラルハーフのように振る舞い、パスの受け手となります。トップ下の位置で大津、天野が運動量を発揮してポジションを頻繁に変え、前線は伊藤を中央に、仲川と遠藤が両サイドの幅を取ります。守備時は4-4-2のセットアップです。
鳥栖としては、この特徴的なビルドアップでボールを保持したいマリノスをどのように抑えるかというところがひとつのポイントだったのですが、取った戦略は積極的なプレッシングによるビルドアップ潰しでした。センターバック2名に対してはそのままツートップを当て、3センターに対して(あえてサイドバックとは言いません)は、サイドハーフの小野と福田、そしてボランチが1列上がってプレッシングを行います。
ボール保持を阻止しようという事がよく分かるのは、マリノスのゴールキックの時でありまして、センターバックへの繋ぎを阻止するべくフォワードが高い位置を取ってしっかりとマークし、中盤も連動してマリノスの3センターへのパスコースをつぶしていました。早いキックで両ウイングに合わせてくることも想定して、サイドバックが幅を取るウイングに対してしっかりとマーク。
鳥栖のプレッシャーに飯倉がギブアップしてロングボールを蹴るシーンも見え、マリノスにとっては自分たちがやろうとすることを阻害されている嫌な雰囲気は感じていたと思います。明輝さんの積極的な采配でしたね。


鳥栖が人を明確に意識したプレッシング戦術を図ったことの引き換えとして、マリノスのポジショニングに応じてスペースを与える事となります。マリノスの狙い目としては、サイドバックが中央に入ったことによって空けたスペースでした。スペースの使い方には決まりはなかった模様で、大津と天野が広がってビルドアップの出口となったり、仲川や遠藤が下がってボールを受けて基点となったり。時折サイドバックが侵入することもありました。鳥栖にとってもそのスペースが狙われるのは予見していたらしく、一人余ったボランチや、小野、福田の二度追いによってマリノスに自由にボールを回されるのを阻害していました。
マリノスのビルドアップは、このスペースを使ったワンタッチプレイが成功するかどうか、鳥栖のビルドアップ阻止は、このスペースに入ってきた選手を捕まえきれるかどうか、という事でサイドのスペースはかなり熱いエリアとなっていました。
図で表すと以下のような感じです。



最終的には、マリノスとしてはいかに両ウイングである仲川、遠藤が勝負できる体制に持ち込める状況を作れるかというところがポイントでした。
鳥栖としては、ビルドアップで網を抜けられたとしても、仲川と遠藤が下がらざるを得ない状況を作り出した時にはさほどピンチにはつながっていませんでしたが、フリーでボールを受けて前を向かれると鳥栖にとっては厳しい状況を迎えていました。


仲川と遠藤に対しては、鳥栖のサイドバックが対峙していたのですが、特に小林は獅子奮迅の活躍でしたね。遠藤と多くのデュエルが発生したのですが、裏へ抜けるパス、カットインしてくるドリブル、クロスからの飛び込み、それらの全てに対応して遠藤を封じ込みました。
また、カウンター時に義希が止めきれなくてゴール前で仲川と1VS1になったときのカットは身が奮えるほどのプレイでしたね。
攻撃面でもビルドアップで右サイドでの崩しに参画してカットインで相手をはがすプレイは見事でしたし、私の中では、今回のMVPは小林です。(ちなみに、MIPはトーレス、金崎)

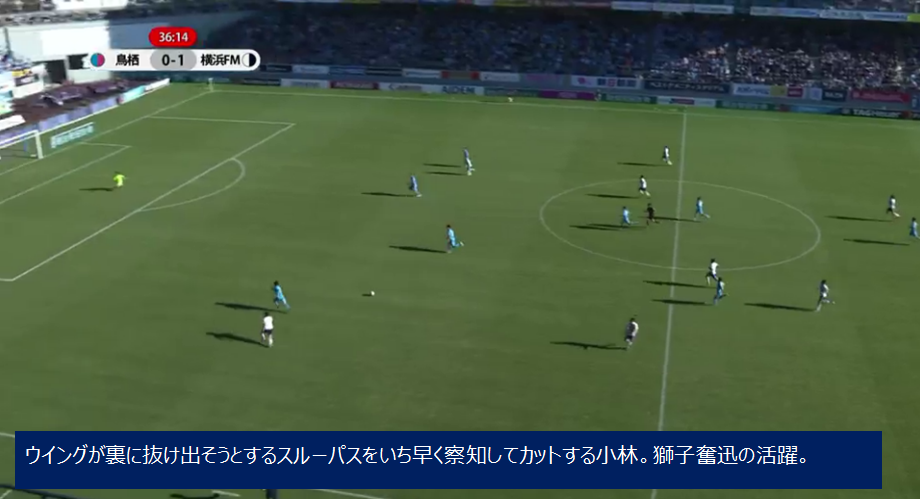
鳥栖としては準備していたプレッシング戦術がしっかりと機能しており、前線でひっかけてショートカウンターというチャンスを多く作っていたのである程度満足行く戦いだったかと思います。
低い位置からのカウンターでも中央に絞っている両サイドバックの裏のスペースを有効活用してボールを前進させたり、ビルドアップの局面でもサイドバック、サイドハーフ、ボランチの3人によるグループの崩しが見られたりと、攻撃に関してもある程度準備していた形は実現できていたと思います。
ただし、いかんせん、ゴール前で手数をかけすぎたり、判断ミスが発生したりなど、決定的なチャンスを作れそうでなかなかシュートにもちこめないというモドカシイ状況ではありました。福田のカットからのショートカウンターはシュートまでは行ってほしかったですね。何度もドキドキして席を思わず立ってしまいました(笑)



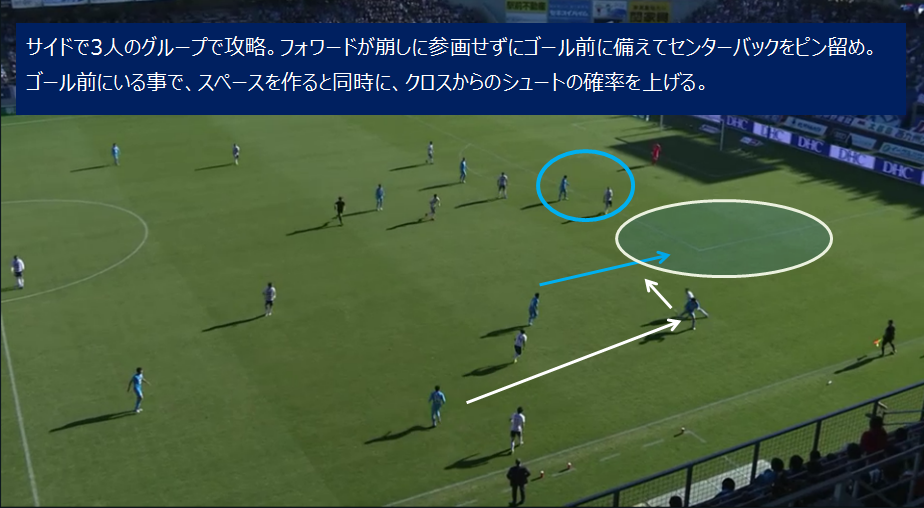
鳥栖が優勢かという状況でしたが、ここがサッカーの怖い所でありまして、先制点はマリノスがあげます。
先制点のシーンでは、ルーズボールを収めたマリノスが、勝負どころであるウイングにボールを渡すことに成功し、仲川が前を向くことができました。
ここで鳥栖の組織にとっては予定外の事が発生しました。仲川がボール保持している状態で、本来の役割である安在が対峙していたのですが、更にアウトサイドをサイドバックの松原がオーバーラップしていきます。サイドバックのセントラルハーフ化がモットーであるマリノスが、ここで人数をかけるべくサイドバックらしい外からの上りを見せたところで、鳥栖の守備の構造が変わります。
松原をケアするべく安在がアウトサイドに下がって仲川のマークを小野が引き受ける事になりました。ここから更に、大津が今度は仲川の内側のスペースを飛び出していきます。仲川のアジリティのある突破に対応するために間を取っていた小野に対し、仲川が小野の足元を抜けるように、スペースに入る大津にパスを送りこむのは難しくない選択でした。ダイレクトの折り返し、そしてダイレクトのシュートで義希、祐治のマークも届かずに先制点を決めます。
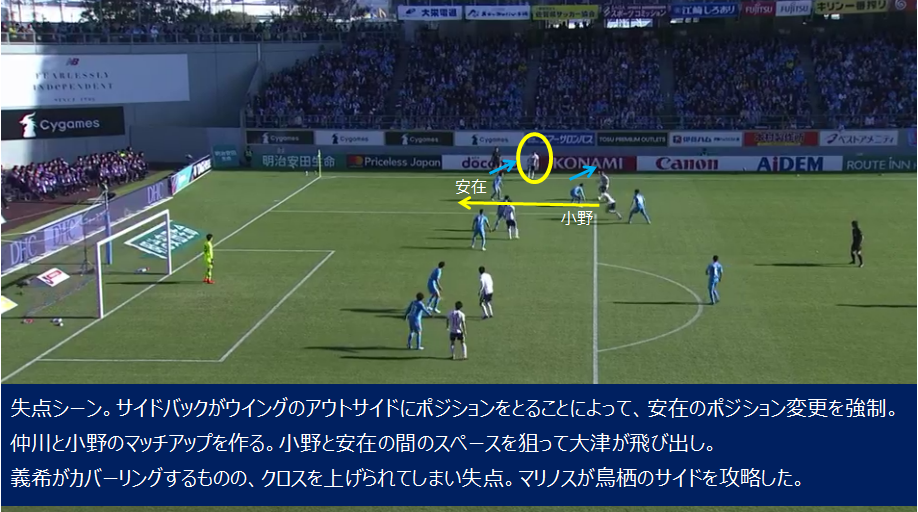
先制点を上げたマリノスは、全体のポジショニングは落ち着いたものの、ボールを保持する戦い方は変わりませんでした。鳥栖としては引き続きひっかけてカウンターという形を取れればよかったのですが、運動量の低下と共にボールを奪うポイントが徐々に低くなっていきます。
ボールを奪ってもセントラルハーフ化したサイドバックがしっかりと中央に鎮座するので、クリティカルなシュートレンジエリアを崩せず、サイドにボールを運ぶ動きになってしまうことで前半は思うようにシュートチャンスを作れませんでした。
後半に入ると、フォワードが積極的に縦パスを受ける体制を作り、時間が経つにつれて、攻勢を強めたい鳥栖が徐々にボールを保持するようにシフトしていきました。
運動量の落ちてきたチョドンゴンに替わって金崎が入って更に潮目が変わります。金崎が激しいプレッシングを始めたので、再び前半のように、ビルドアップの抜け道(セカンドトップへのパス)を狙ってサイドハーフがカットする回数が増え、ショートカウンターの攻撃数も増えてきました。福田が良い位置でボールカットしたシーンは惜しかったですね。これも、シュートに繋げたかったです。

同点ゴールは、その金崎がサイドで基点を作ってからのものでした。安在が金崎を追い越して左サイドからクロスを上げ、逆サイドにいた福田がボールを受けて再びクロスを上げたところでシノヅカのハンドリングを誘い、PKを得る事ができました。明輝体制に替わって、両サイドハーフがゴール前に迫るシーンが増えています。クロスが抜けて逆サイドでボールを拾えるポジションを取るという形を作れたこと(ペナルティエリア内の人数が増えた事)は、明輝監督に代わった一番の効果ですよね。そして、金崎のPKは気迫溢れるシュートでした。シーズン途中から来てくれた彼がこのように強い気持ちでサガン鳥栖の一員として戦ってくれるのは非常に心強いです。
左サイドハーフを田川に代えた直後に逆転ゴールが生まれます。マリノスがカウンター気味にドリブルで中央を上がって行ったところを、祐治がうまくひっかけて金崎にボールを送り込みます。マリノスカウンターに対する逆カウンターを生み出すことができました。
ここでうまかったのは、トーレスがしっかりとオフサイドにならないようにポジションを取ったことです。並のストライカーであれば、ボールを奪われたときにリトリートが遅れてオフサイドとなってしまうのですが、トーレスはしっかりとボールを受ける準備ができていました。前半から、福田や小野がひっかけるシーンが多かったのですが、トーレスもチョドンゴンも、ボールカットに合わせてしっかりとオフサイドにならないようにポジションを取っています。惜しくも彼らにボールが渡らなかったのですが、常に準備をしていた動きがついに報われた瞬間でした。センターバック一人をかわして素早い振りぬけで放ったシュートは本当に素晴らしかったですね。
鳥栖にとってある意味誤算だったのは、田川投入直後に逆転ゴールが生まれた事。今度は守るフェーズになり、田川が左サイドの守備を担うことになりました。
田川が仲川に振り切られたり、右サイドにスライドした時にポジションの絞りが遅れたりと、守備を担うサイドハーフとしては、ちょっと危ないシーンを生んでしまいました。逆にカウンターに入った時のスピードは魅力的でして、中央を持ち込んで、左サイドの金崎に送り込んでからのシュートというシーンを作り出すことができました。やはり、攻撃で特徴を生かせる選手ですよね。
最後は疲れで足に痛みが出た安在を三丸に替えてしっかりとゲームを終了させることができました。三丸が入ってご挨拶とばかりに仲川に鋭いプレッシングをしたり(ファールになってしまいまいたが)、左サイド深く入られたところを久保からしっかりとボールを奪ったり、三丸の守備の安心感は、ここ数試合でのスタメンが自信になってますよね。
さきほど小林を書きましたが、もちろん、安在も素晴らしい出来でした。仲川とのマッチアップが多くて苦労していましたが、四苦八苦しながらもなんとか1失点で抑える事ができて、非常に良い仕事をしたと思います。
さて、ちょっと最後に一言。失点後の小野の振る舞いは、傍から見るとあまり気持ちの良いものではありませんでした。熱くなって安在や義希に激しく言っていたのは気になりました。熱い気持ちとメンタル不安定は別物です。サッカーはチームスポーツですので、得点も失点も良くも悪くもチーム全体が成しえた成果です。自分の責務を放棄したかのようにチームメイトに声を荒げるのはチームビルディングとしては不要なものです。釈迦に説法ですが、サッカーはチームスポーツであることと、試合を優位に進めるためにはメンタルコントロールが重要である事を再認識しなければならないと思います。
ただ、これは外野の意見であって、現場の監督・コーチ・選手たちがどう思っているかが一番大事です。みんなの勇気の原動力になっていればまっまく問題ありません。こればかりは本人たちの世界ですから。
先制点を献上し、そして名古屋も湘南も柏もリードしているという絶体絶命のピンチから、金崎、トーレスのゴールでサガン鳥栖が蘇りました。
鹿島戦は引き分けでも残留確定です。万が一順位を落としても、プレーオフに臨むことができます。ようやくここまでチームを持ってくることが出来ました。泣いても笑っても残り1試合。なんとか残留を勝ち取って、来シーズンこそは是非ともトップリーグでの強いサガン鳥栖を見たいですね。
<画像引用元:DAZN>
鳥栖のセットアップは4-4-2。フォワードにはチョドンゴンが入りトーレスとのツートップ。左サイドハーフに小野、左サイドバックには安在を起用しました。金崎、田川、三丸に関しては、万全ではないという情報もあり、ベンチスタートです。
対するマリノスは攻撃時と守備時で大きく陣形を変えるスタイル。攻撃時が特徴的でして、システム的に言うと2-3-2-3のような形。最終ラインは2センターバック(+時折ゴールキーパー)でビルドアップスタート。サイドバックを中央の高い位置に上げて扇原を含めた3人がセントラルハーフのように振る舞い、パスの受け手となります。トップ下の位置で大津、天野が運動量を発揮してポジションを頻繁に変え、前線は伊藤を中央に、仲川と遠藤が両サイドの幅を取ります。守備時は4-4-2のセットアップです。
鳥栖としては、この特徴的なビルドアップでボールを保持したいマリノスをどのように抑えるかというところがひとつのポイントだったのですが、取った戦略は積極的なプレッシングによるビルドアップ潰しでした。センターバック2名に対してはそのままツートップを当て、3センターに対して(あえてサイドバックとは言いません)は、サイドハーフの小野と福田、そしてボランチが1列上がってプレッシングを行います。
ボール保持を阻止しようという事がよく分かるのは、マリノスのゴールキックの時でありまして、センターバックへの繋ぎを阻止するべくフォワードが高い位置を取ってしっかりとマークし、中盤も連動してマリノスの3センターへのパスコースをつぶしていました。早いキックで両ウイングに合わせてくることも想定して、サイドバックが幅を取るウイングに対してしっかりとマーク。
鳥栖のプレッシャーに飯倉がギブアップしてロングボールを蹴るシーンも見え、マリノスにとっては自分たちがやろうとすることを阻害されている嫌な雰囲気は感じていたと思います。明輝さんの積極的な采配でしたね。


鳥栖が人を明確に意識したプレッシング戦術を図ったことの引き換えとして、マリノスのポジショニングに応じてスペースを与える事となります。マリノスの狙い目としては、サイドバックが中央に入ったことによって空けたスペースでした。スペースの使い方には決まりはなかった模様で、大津と天野が広がってビルドアップの出口となったり、仲川や遠藤が下がってボールを受けて基点となったり。時折サイドバックが侵入することもありました。鳥栖にとってもそのスペースが狙われるのは予見していたらしく、一人余ったボランチや、小野、福田の二度追いによってマリノスに自由にボールを回されるのを阻害していました。
マリノスのビルドアップは、このスペースを使ったワンタッチプレイが成功するかどうか、鳥栖のビルドアップ阻止は、このスペースに入ってきた選手を捕まえきれるかどうか、という事でサイドのスペースはかなり熱いエリアとなっていました。
図で表すと以下のような感じです。



最終的には、マリノスとしてはいかに両ウイングである仲川、遠藤が勝負できる体制に持ち込める状況を作れるかというところがポイントでした。
鳥栖としては、ビルドアップで網を抜けられたとしても、仲川と遠藤が下がらざるを得ない状況を作り出した時にはさほどピンチにはつながっていませんでしたが、フリーでボールを受けて前を向かれると鳥栖にとっては厳しい状況を迎えていました。


仲川と遠藤に対しては、鳥栖のサイドバックが対峙していたのですが、特に小林は獅子奮迅の活躍でしたね。遠藤と多くのデュエルが発生したのですが、裏へ抜けるパス、カットインしてくるドリブル、クロスからの飛び込み、それらの全てに対応して遠藤を封じ込みました。
また、カウンター時に義希が止めきれなくてゴール前で仲川と1VS1になったときのカットは身が奮えるほどのプレイでしたね。
攻撃面でもビルドアップで右サイドでの崩しに参画してカットインで相手をはがすプレイは見事でしたし、私の中では、今回のMVPは小林です。(ちなみに、MIPはトーレス、金崎)

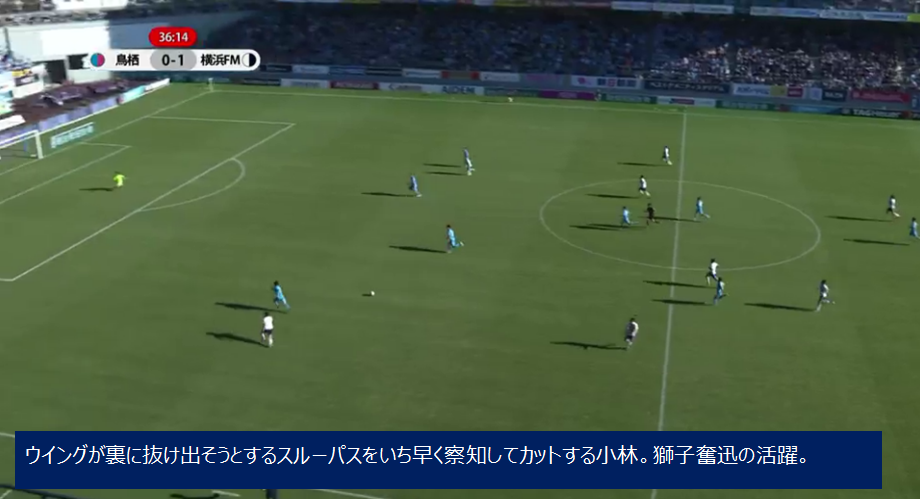
鳥栖としては準備していたプレッシング戦術がしっかりと機能しており、前線でひっかけてショートカウンターというチャンスを多く作っていたのである程度満足行く戦いだったかと思います。
低い位置からのカウンターでも中央に絞っている両サイドバックの裏のスペースを有効活用してボールを前進させたり、ビルドアップの局面でもサイドバック、サイドハーフ、ボランチの3人によるグループの崩しが見られたりと、攻撃に関してもある程度準備していた形は実現できていたと思います。
ただし、いかんせん、ゴール前で手数をかけすぎたり、判断ミスが発生したりなど、決定的なチャンスを作れそうでなかなかシュートにもちこめないというモドカシイ状況ではありました。福田のカットからのショートカウンターはシュートまでは行ってほしかったですね。何度もドキドキして席を思わず立ってしまいました(笑)



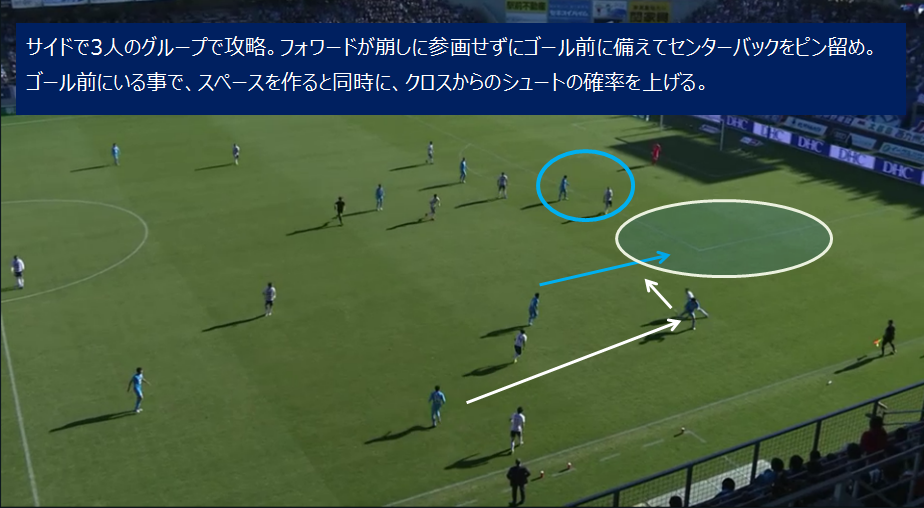
鳥栖が優勢かという状況でしたが、ここがサッカーの怖い所でありまして、先制点はマリノスがあげます。
先制点のシーンでは、ルーズボールを収めたマリノスが、勝負どころであるウイングにボールを渡すことに成功し、仲川が前を向くことができました。
ここで鳥栖の組織にとっては予定外の事が発生しました。仲川がボール保持している状態で、本来の役割である安在が対峙していたのですが、更にアウトサイドをサイドバックの松原がオーバーラップしていきます。サイドバックのセントラルハーフ化がモットーであるマリノスが、ここで人数をかけるべくサイドバックらしい外からの上りを見せたところで、鳥栖の守備の構造が変わります。
松原をケアするべく安在がアウトサイドに下がって仲川のマークを小野が引き受ける事になりました。ここから更に、大津が今度は仲川の内側のスペースを飛び出していきます。仲川のアジリティのある突破に対応するために間を取っていた小野に対し、仲川が小野の足元を抜けるように、スペースに入る大津にパスを送りこむのは難しくない選択でした。ダイレクトの折り返し、そしてダイレクトのシュートで義希、祐治のマークも届かずに先制点を決めます。
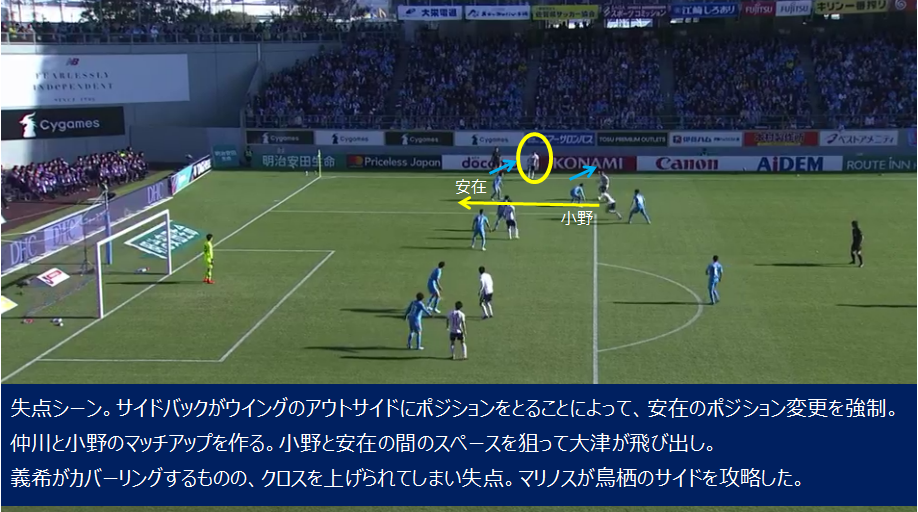
先制点を上げたマリノスは、全体のポジショニングは落ち着いたものの、ボールを保持する戦い方は変わりませんでした。鳥栖としては引き続きひっかけてカウンターという形を取れればよかったのですが、運動量の低下と共にボールを奪うポイントが徐々に低くなっていきます。
ボールを奪ってもセントラルハーフ化したサイドバックがしっかりと中央に鎮座するので、クリティカルなシュートレンジエリアを崩せず、サイドにボールを運ぶ動きになってしまうことで前半は思うようにシュートチャンスを作れませんでした。
後半に入ると、フォワードが積極的に縦パスを受ける体制を作り、時間が経つにつれて、攻勢を強めたい鳥栖が徐々にボールを保持するようにシフトしていきました。
運動量の落ちてきたチョドンゴンに替わって金崎が入って更に潮目が変わります。金崎が激しいプレッシングを始めたので、再び前半のように、ビルドアップの抜け道(セカンドトップへのパス)を狙ってサイドハーフがカットする回数が増え、ショートカウンターの攻撃数も増えてきました。福田が良い位置でボールカットしたシーンは惜しかったですね。これも、シュートに繋げたかったです。

同点ゴールは、その金崎がサイドで基点を作ってからのものでした。安在が金崎を追い越して左サイドからクロスを上げ、逆サイドにいた福田がボールを受けて再びクロスを上げたところでシノヅカのハンドリングを誘い、PKを得る事ができました。明輝体制に替わって、両サイドハーフがゴール前に迫るシーンが増えています。クロスが抜けて逆サイドでボールを拾えるポジションを取るという形を作れたこと(ペナルティエリア内の人数が増えた事)は、明輝監督に代わった一番の効果ですよね。そして、金崎のPKは気迫溢れるシュートでした。シーズン途中から来てくれた彼がこのように強い気持ちでサガン鳥栖の一員として戦ってくれるのは非常に心強いです。
左サイドハーフを田川に代えた直後に逆転ゴールが生まれます。マリノスがカウンター気味にドリブルで中央を上がって行ったところを、祐治がうまくひっかけて金崎にボールを送り込みます。マリノスカウンターに対する逆カウンターを生み出すことができました。
ここでうまかったのは、トーレスがしっかりとオフサイドにならないようにポジションを取ったことです。並のストライカーであれば、ボールを奪われたときにリトリートが遅れてオフサイドとなってしまうのですが、トーレスはしっかりとボールを受ける準備ができていました。前半から、福田や小野がひっかけるシーンが多かったのですが、トーレスもチョドンゴンも、ボールカットに合わせてしっかりとオフサイドにならないようにポジションを取っています。惜しくも彼らにボールが渡らなかったのですが、常に準備をしていた動きがついに報われた瞬間でした。センターバック一人をかわして素早い振りぬけで放ったシュートは本当に素晴らしかったですね。
鳥栖にとってある意味誤算だったのは、田川投入直後に逆転ゴールが生まれた事。今度は守るフェーズになり、田川が左サイドの守備を担うことになりました。
田川が仲川に振り切られたり、右サイドにスライドした時にポジションの絞りが遅れたりと、守備を担うサイドハーフとしては、ちょっと危ないシーンを生んでしまいました。逆にカウンターに入った時のスピードは魅力的でして、中央を持ち込んで、左サイドの金崎に送り込んでからのシュートというシーンを作り出すことができました。やはり、攻撃で特徴を生かせる選手ですよね。
最後は疲れで足に痛みが出た安在を三丸に替えてしっかりとゲームを終了させることができました。三丸が入ってご挨拶とばかりに仲川に鋭いプレッシングをしたり(ファールになってしまいまいたが)、左サイド深く入られたところを久保からしっかりとボールを奪ったり、三丸の守備の安心感は、ここ数試合でのスタメンが自信になってますよね。
さきほど小林を書きましたが、もちろん、安在も素晴らしい出来でした。仲川とのマッチアップが多くて苦労していましたが、四苦八苦しながらもなんとか1失点で抑える事ができて、非常に良い仕事をしたと思います。
さて、ちょっと最後に一言。失点後の小野の振る舞いは、傍から見るとあまり気持ちの良いものではありませんでした。熱くなって安在や義希に激しく言っていたのは気になりました。熱い気持ちとメンタル不安定は別物です。サッカーはチームスポーツですので、得点も失点も良くも悪くもチーム全体が成しえた成果です。自分の責務を放棄したかのようにチームメイトに声を荒げるのはチームビルディングとしては不要なものです。釈迦に説法ですが、サッカーはチームスポーツであることと、試合を優位に進めるためにはメンタルコントロールが重要である事を再認識しなければならないと思います。
ただ、これは外野の意見であって、現場の監督・コーチ・選手たちがどう思っているかが一番大事です。みんなの勇気の原動力になっていればまっまく問題ありません。こればかりは本人たちの世界ですから。
先制点を献上し、そして名古屋も湘南も柏もリードしているという絶体絶命のピンチから、金崎、トーレスのゴールでサガン鳥栖が蘇りました。
鹿島戦は引き分けでも残留確定です。万が一順位を落としても、プレーオフに臨むことができます。ようやくここまでチームを持ってくることが出来ました。泣いても笑っても残り1試合。なんとか残留を勝ち取って、来シーズンこそは是非ともトップリーグでの強いサガン鳥栖を見たいですね。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
12:01
│Match Impression (2018)
2018年11月16日
2018 第32節 : ヴィッセル神戸 VS サガン鳥栖
2018年第32節、ヴィッセル神戸戦のレビューです。今回もポイントだけ。
鳥栖のセットアップは4-4-2。金崎が復帰してフォワードに入った点以外は長崎戦と同じ布陣です。
対する神戸は4-3-3(4-3-2-1)のセットアップ。3人のインサイドハーフが、やや前目にポジショニングを取るイニエスタとポドルスキ―を支える形となりました。
この試合の大きなポイントは、神戸のボール保持戦術でしょう。前半の鳥栖は前線でのボールの奪いどころをサイドに置きましたがなかなか機能せず、かといってイニエスタとポドルスキ―のプレイエリアを捨ててまでというプレスにも行けず、そうこうするうちにフリーとなったティーラトンに幾度もボールが渡ってしまい、その結果、最終的な選択としてはブロックを組んでゴール前で守りきるという、消極的な形でディフェンシブサードでの待機を強いられる戦いとなってしまいました。
神戸のボール保持戦術ですが、神戸は両センターバックが大きくワイドに広がって横幅を作ります。そして、両センターバックをフォローするように2列目から選手が下りてきて(主に藤田)3人での最終ラインを形成します。これにより、鳥栖の2トップに対して常に優位な状態でボールを保持することができました。神戸が巧妙だったのは、苦しい時には簡単にゴールキーパーを使う事でした。キーパーを使って迂回することによって、簡単にボールロストしないように、可能な限りのボール保持を試みます。

ボールキープの仕組みができたので、あとはどうやってゴール前までボールを運ぶかという所ですが、基本的には中央に人数を集めて数的優位を作ってボールを前進します。中央を締められた時(鳥栖の選手が集まって来たとき)に、高い位置を取らせているサイドバックを使うという形を作りました。前半は特にこの形がはまりましたね。ティーラトンにフリーでボールを持たれてしまうシーンを何度も作られてしまいました。

前からプレスに行きたい鳥栖としてはツートップに加えてあと一人入らないとプレッシャーをかける事ができません。プレッシャーに入るエリアと人選をどうしようかという所ですが、サイドハーフの福田、原川が横幅を取るセンターバックまでプレッシャーに出てしまうのはあまり良くない形でした。インサイドハーフが横幅を取るセンターバックに出ていく事により、神戸のサイドバックに対して、鳥栖もサイドバックが出ていかなければならなくなります。秀人と義希はイニエスタ、ポドルスキを放すわけにはいかないので、中央に鎮座する事になり、これで神戸のインサイドハーフは誰が見るのか問題が勃発しました。
三田、伊野波が比較的フリーになるので、サイドバックの裏に抜けたり、中央の藤田を経由して縦位置でボールを受けたりできます。彼らを気にしすぎると、直接イニエスタやポドルスキにボールが出されるケースが増え、徐々に鳥栖のプレッシングが無効化してしまいました。
横幅を取るセンターバックに対してツートップがプレスに行き、そこから出てくるボールに対してサイドハーフが行っているときはボールが奪えるチャンスもあって問題なかったのですが、その形を取れない時が、鳥栖の守備がビルドアップで破壊される時でした。



今回、厄介だったのは、セットアップでは、鳥栖の最終ラインと2列目の間にポジションを取っているポドルスキやイニエスタが、ビルドアップで義希、秀人の前でボールを受けるために下がってくることです。彼らが下がってボールを受ける事によって、最終ラインからのパスコースが、サイドバック、インサイドハーフ、セカンドトップと種類が増える事になります。また、中央に鳥栖の選手を引き付ける事ができます。鳥栖のボランチの前でボールを受けたポドルスキやイニエスタにとっては、ひとり剥がして前を向くことなど造作でもない事でした。イニエスタとポドルスキの2人のコンビネーションは本当に脅威で、確実にプレイエリアを前進していく事ができました。


こうして、鳥栖としては、前から行ってもはがされて徒労に終わる時間が増えてくると、最後の手段としてはいかにして良い状態でシュートを打たれないかという形でブロックを作る事しかなくなります。サイドハーフが出ていくとそこがスペースになってイニエスタに使われてしまうので、出来る限りミドルサードまで我慢して、中央へのパスコースを防ぎつつ、タイミングを見計らってプレッシングに行くように切り替えました。こうして、鳥栖が前に出ていく回数が減ったので、神戸は苦労せずにボールを握れるようになりました。
鳥栖にとって助かっていたのは、神戸のコントロールミス(トラップミス)によって、攻撃がストップしてしまう事でした。ボールコントロールがしっかりとしていれば、瞬く間にピンチになったシーンが幾度もありました。戦術も大事ですが、最後はやはり、止める、蹴るの技術も大事だと思うシーンが多々ありました。図は、原川と三丸がプレッシングにはいることによって伊野波が裏のスペースでボールを受けるシーンです。トラップミスによって助かったのですが、オマリも引き出されていてなかなか危ないシーンではあります。

後半に入ると鳥栖は、少し守備のやり方を変えてきます。ボール保持されているままでは攻撃の打つ手がなくなるので、やはり前から奪える仕組みを作らなければなりません。ポイントは2つありました。ひとつめはビルドアップを行う最終ラインへのプレッシャーのかけ方。前半は、サイドにボールを回させて、センターバック、もしくはサイドバックに対するプレッシャーが多かったのですが、後半に入ると最終ラインでボール保持を形成する藤田に対して鳥栖のボランチがボールを奪いに出ていき、ポドルスキやイニエスタにボールが入る前のタイミングでプレッシングをかけます。中央の人数をひとり削るという勇気のいるプレイでしたが、かわされてもすぐに戻る献身さを見せる事が出来る秀人と義希だからこそできた形かもしれません。藤田の所に秀人が出ていく事により、横幅を取るセンターバックに対してフォワードがプレッシングにいく事ができました。これによって鳥栖のサイドハーフが神戸のインサイドハーフを捕まえる事ができるようになったので、前半のようには簡単にボール保持される機会が減りました。


もうひとつ、ポジショニングを変えたのはサイドバックの位置です。前半は、中央を固めるというコンセプトだったので、4-4のラインを中央に寄せるためにどうしてもサイド(特にティーラトン)のところがフリーになってしまい、何度も中央からサイドのティーラトンへ展開されてフリーでクロスを上げられるシーンを作られてしまいました。後半は、ティーラトンに自由を与えないために、小林が少しワイドの位置に構えるような形になりました。これによって、ティーラトンにボールが入ってもスピードに乗る前にプレッシングに行けるので、時おり彼にボールが入る前にカットすることもありました。

この守備ができたのは、ボール保持して前進を図る神戸に取っても痛しかゆしの部分でありまして、本来は小林がサイドを気にするポジションを取ることによって、サイドバックとセンターバックの間のスペースが空くのですが、神戸はこのスペースを有効活用して侵入してくるプレイヤーがいません。セカンドトップ(と言うよりは、オフェンシブハーフかな)のポドルスキもイニエスタもどちらかと言えば、このエリアにパスを出す側の選手であって入る側の選手ではなく、そうなると古橋一人が頑張ってポジションを移してボールを受ける事になります。神戸はフィニッシュにも問題を抱えていて、前線が古橋ひとりであるためクロスが上がっても古橋一人であるためにオマリ、祐治がことごとくクロスを跳ね返していました。スルーパスに対しても、古橋が追い付けていないシーンもありました。このあたりのボールは保持できてもなかなか決定的シュートまで結びつけられないという点は神戸としての課題でもありますね。
鳥栖は、前半にボール保持されて奪いきれなかったので、最後は中央を固めてゴール前で鍵をかけるという守備を行いましたが、神戸が多少ゴール前にスペースを空けても入ってくる選手がいないという事で、サイドバックのポジションを外寄りにするという変更は正解だったということですね。


チーム作りと言うのは難しいなというのがありまして、もし、柏の瀬川であったり、札幌の三好であったりすると、そういったゴール前のスペースをしっかり使ってくる動きをするでしょう。そこにイニエスタが絡むと鳥栖も2失点は必至だったかもしれません(笑) しかしながら、ポドルスキという大きな武器を持っているので使わないわけにはいきません。ビルドアップやミドルシュートのシーンでは、類まれなる活躍をしてくれます。そう考えると鳥栖の金崎とトーレスも同じですよね。使わないわけにはいかないし、なんとか機能させないといけない。豊田が怪我しているので何ともいえませんが、本来は豊田も使いたい選手ですし、チームビルディングの難しさを感じます。
ということで、おさらいです。
前半は、横幅を取るセンターバックと、最終ラインで数的優位を作る藤田、2列目と3列目の間にポジションを取るイニエスタとポドルスキという色々と対応しなければならない事項があり、最終的にはリトリートして守備ブロックを組んでゴールを固めるという、明輝監督としては不本意であろう守備を強いられました。後半からは、勇気をもって秀人を前に上げてプレッシングでの数的不利を解消し、サイドバックのポジションを変える事によってサイドの深い位置への侵入を未然に防ぎました。ポジショニングを変える事で、戦局の優位性を変える事ができるという、良い例となる試合だったかなと思います。明輝監督は守備に関する修正力を見せてくれましたしね。


この試合、ボールポゼション、決定的チャンスの数、ピンチの数を考えると完全に神戸が優勢でした。それだけに、この勝ち点1は決して悪くはありません。この勝ち点1によって、鳥栖は降格圏から脱出する事ができました。肝は次のマリノス戦ですね。ホーム最終戦をどのような形で終える事ができるか。シーズン最終戦に向け、ひとときも目を放すことができない戦いが続きます。
<画像引用元:DAZN>
鳥栖のセットアップは4-4-2。金崎が復帰してフォワードに入った点以外は長崎戦と同じ布陣です。
対する神戸は4-3-3(4-3-2-1)のセットアップ。3人のインサイドハーフが、やや前目にポジショニングを取るイニエスタとポドルスキ―を支える形となりました。
この試合の大きなポイントは、神戸のボール保持戦術でしょう。前半の鳥栖は前線でのボールの奪いどころをサイドに置きましたがなかなか機能せず、かといってイニエスタとポドルスキ―のプレイエリアを捨ててまでというプレスにも行けず、そうこうするうちにフリーとなったティーラトンに幾度もボールが渡ってしまい、その結果、最終的な選択としてはブロックを組んでゴール前で守りきるという、消極的な形でディフェンシブサードでの待機を強いられる戦いとなってしまいました。
神戸のボール保持戦術ですが、神戸は両センターバックが大きくワイドに広がって横幅を作ります。そして、両センターバックをフォローするように2列目から選手が下りてきて(主に藤田)3人での最終ラインを形成します。これにより、鳥栖の2トップに対して常に優位な状態でボールを保持することができました。神戸が巧妙だったのは、苦しい時には簡単にゴールキーパーを使う事でした。キーパーを使って迂回することによって、簡単にボールロストしないように、可能な限りのボール保持を試みます。

ボールキープの仕組みができたので、あとはどうやってゴール前までボールを運ぶかという所ですが、基本的には中央に人数を集めて数的優位を作ってボールを前進します。中央を締められた時(鳥栖の選手が集まって来たとき)に、高い位置を取らせているサイドバックを使うという形を作りました。前半は特にこの形がはまりましたね。ティーラトンにフリーでボールを持たれてしまうシーンを何度も作られてしまいました。

前からプレスに行きたい鳥栖としてはツートップに加えてあと一人入らないとプレッシャーをかける事ができません。プレッシャーに入るエリアと人選をどうしようかという所ですが、サイドハーフの福田、原川が横幅を取るセンターバックまでプレッシャーに出てしまうのはあまり良くない形でした。インサイドハーフが横幅を取るセンターバックに出ていく事により、神戸のサイドバックに対して、鳥栖もサイドバックが出ていかなければならなくなります。秀人と義希はイニエスタ、ポドルスキを放すわけにはいかないので、中央に鎮座する事になり、これで神戸のインサイドハーフは誰が見るのか問題が勃発しました。
三田、伊野波が比較的フリーになるので、サイドバックの裏に抜けたり、中央の藤田を経由して縦位置でボールを受けたりできます。彼らを気にしすぎると、直接イニエスタやポドルスキにボールが出されるケースが増え、徐々に鳥栖のプレッシングが無効化してしまいました。
横幅を取るセンターバックに対してツートップがプレスに行き、そこから出てくるボールに対してサイドハーフが行っているときはボールが奪えるチャンスもあって問題なかったのですが、その形を取れない時が、鳥栖の守備がビルドアップで破壊される時でした。



今回、厄介だったのは、セットアップでは、鳥栖の最終ラインと2列目の間にポジションを取っているポドルスキやイニエスタが、ビルドアップで義希、秀人の前でボールを受けるために下がってくることです。彼らが下がってボールを受ける事によって、最終ラインからのパスコースが、サイドバック、インサイドハーフ、セカンドトップと種類が増える事になります。また、中央に鳥栖の選手を引き付ける事ができます。鳥栖のボランチの前でボールを受けたポドルスキやイニエスタにとっては、ひとり剥がして前を向くことなど造作でもない事でした。イニエスタとポドルスキの2人のコンビネーションは本当に脅威で、確実にプレイエリアを前進していく事ができました。


こうして、鳥栖としては、前から行ってもはがされて徒労に終わる時間が増えてくると、最後の手段としてはいかにして良い状態でシュートを打たれないかという形でブロックを作る事しかなくなります。サイドハーフが出ていくとそこがスペースになってイニエスタに使われてしまうので、出来る限りミドルサードまで我慢して、中央へのパスコースを防ぎつつ、タイミングを見計らってプレッシングに行くように切り替えました。こうして、鳥栖が前に出ていく回数が減ったので、神戸は苦労せずにボールを握れるようになりました。
鳥栖にとって助かっていたのは、神戸のコントロールミス(トラップミス)によって、攻撃がストップしてしまう事でした。ボールコントロールがしっかりとしていれば、瞬く間にピンチになったシーンが幾度もありました。戦術も大事ですが、最後はやはり、止める、蹴るの技術も大事だと思うシーンが多々ありました。図は、原川と三丸がプレッシングにはいることによって伊野波が裏のスペースでボールを受けるシーンです。トラップミスによって助かったのですが、オマリも引き出されていてなかなか危ないシーンではあります。

後半に入ると鳥栖は、少し守備のやり方を変えてきます。ボール保持されているままでは攻撃の打つ手がなくなるので、やはり前から奪える仕組みを作らなければなりません。ポイントは2つありました。ひとつめはビルドアップを行う最終ラインへのプレッシャーのかけ方。前半は、サイドにボールを回させて、センターバック、もしくはサイドバックに対するプレッシャーが多かったのですが、後半に入ると最終ラインでボール保持を形成する藤田に対して鳥栖のボランチがボールを奪いに出ていき、ポドルスキやイニエスタにボールが入る前のタイミングでプレッシングをかけます。中央の人数をひとり削るという勇気のいるプレイでしたが、かわされてもすぐに戻る献身さを見せる事が出来る秀人と義希だからこそできた形かもしれません。藤田の所に秀人が出ていく事により、横幅を取るセンターバックに対してフォワードがプレッシングにいく事ができました。これによって鳥栖のサイドハーフが神戸のインサイドハーフを捕まえる事ができるようになったので、前半のようには簡単にボール保持される機会が減りました。


もうひとつ、ポジショニングを変えたのはサイドバックの位置です。前半は、中央を固めるというコンセプトだったので、4-4のラインを中央に寄せるためにどうしてもサイド(特にティーラトン)のところがフリーになってしまい、何度も中央からサイドのティーラトンへ展開されてフリーでクロスを上げられるシーンを作られてしまいました。後半は、ティーラトンに自由を与えないために、小林が少しワイドの位置に構えるような形になりました。これによって、ティーラトンにボールが入ってもスピードに乗る前にプレッシングに行けるので、時おり彼にボールが入る前にカットすることもありました。

この守備ができたのは、ボール保持して前進を図る神戸に取っても痛しかゆしの部分でありまして、本来は小林がサイドを気にするポジションを取ることによって、サイドバックとセンターバックの間のスペースが空くのですが、神戸はこのスペースを有効活用して侵入してくるプレイヤーがいません。セカンドトップ(と言うよりは、オフェンシブハーフかな)のポドルスキもイニエスタもどちらかと言えば、このエリアにパスを出す側の選手であって入る側の選手ではなく、そうなると古橋一人が頑張ってポジションを移してボールを受ける事になります。神戸はフィニッシュにも問題を抱えていて、前線が古橋ひとりであるためクロスが上がっても古橋一人であるためにオマリ、祐治がことごとくクロスを跳ね返していました。スルーパスに対しても、古橋が追い付けていないシーンもありました。このあたりのボールは保持できてもなかなか決定的シュートまで結びつけられないという点は神戸としての課題でもありますね。
鳥栖は、前半にボール保持されて奪いきれなかったので、最後は中央を固めてゴール前で鍵をかけるという守備を行いましたが、神戸が多少ゴール前にスペースを空けても入ってくる選手がいないという事で、サイドバックのポジションを外寄りにするという変更は正解だったということですね。


チーム作りと言うのは難しいなというのがありまして、もし、柏の瀬川であったり、札幌の三好であったりすると、そういったゴール前のスペースをしっかり使ってくる動きをするでしょう。そこにイニエスタが絡むと鳥栖も2失点は必至だったかもしれません(笑) しかしながら、ポドルスキという大きな武器を持っているので使わないわけにはいきません。ビルドアップやミドルシュートのシーンでは、類まれなる活躍をしてくれます。そう考えると鳥栖の金崎とトーレスも同じですよね。使わないわけにはいかないし、なんとか機能させないといけない。豊田が怪我しているので何ともいえませんが、本来は豊田も使いたい選手ですし、チームビルディングの難しさを感じます。
ということで、おさらいです。
前半は、横幅を取るセンターバックと、最終ラインで数的優位を作る藤田、2列目と3列目の間にポジションを取るイニエスタとポドルスキという色々と対応しなければならない事項があり、最終的にはリトリートして守備ブロックを組んでゴールを固めるという、明輝監督としては不本意であろう守備を強いられました。後半からは、勇気をもって秀人を前に上げてプレッシングでの数的不利を解消し、サイドバックのポジションを変える事によってサイドの深い位置への侵入を未然に防ぎました。ポジショニングを変える事で、戦局の優位性を変える事ができるという、良い例となる試合だったかなと思います。明輝監督は守備に関する修正力を見せてくれましたしね。


この試合、ボールポゼション、決定的チャンスの数、ピンチの数を考えると完全に神戸が優勢でした。それだけに、この勝ち点1は決して悪くはありません。この勝ち点1によって、鳥栖は降格圏から脱出する事ができました。肝は次のマリノス戦ですね。ホーム最終戦をどのような形で終える事ができるか。シーズン最終戦に向け、ひとときも目を放すことができない戦いが続きます。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
17:34
│Match Impression (2018)
2018年11月08日
2018 第31節 : サガン鳥栖 VS V・ファーレン長崎
2018年第31節、V・ファーレン長崎戦のレビューです。もう少し掘り下げたかったのですが、時間が足りなかったのでポイントだけ振り返ります。(それでも十分長くなりましたけど(笑))
鳥栖のセットアップは4-4-2。戦前から別メニューとなっている選手の情報がネットニュースに上がっていましたが、その情報が正しかったみたいで、金崎、小野、豊田がベンチ外でした。ツートップはチョドンゴンとトーレス、中盤は原川、秀人、義希、福田のラインナップ。最終ラインは変更ありません。
一方の長崎はいつもの3-4-1-2システムではなく、4-4-2システムによる序盤の戦いとなりました。狙いとしてはミラーゲームにすることによってマーキングを明確にすること。3-4-2-1システムでは、鳥栖2センターバックに対して前線はファンマ一人になるので、前から行くためにはセカンドトップのうちの一人がプレスに入らなければなりません。最終ラインに自由な時間を与えないように、また、マーキングの乱れによるスペースを使われないように、予め明確にプレッシングの相手を決めてしまおうという事だと思われます。その戦術に呼応するように、前線から平松とファンマが運動量激しく最終ラインに対してプレッシングを行い、鳥栖の自由に繋ぐプレイを阻害し、単純にボールを蹴らざるをえない状況を作り出していました。

対する長崎はファンマを狙うというコンセプトが統一されていました。鳥栖も比較的高い位置からプレッシングに来ており、トランジションの場面においてボランチ経由でつなごうとすると、積極的に秀人と義希がつぶしに来ていたので、ドイスボランチのプレッシングをかわすために早めにボールを蹴ってしまう方が得策という形になります。この試合の秀人と義希のトランジションでのプレスは非常に素晴らしく、長崎が攻撃に入ろうとしたところで素早くチェックしてショートカウンターに繋げる場面が多くありました。長崎としては、それを防ぐ手立てとしての早めのロングボールというのは悪い選択ではなかったかと思います。鳥栖としては、秀人と義希が前から行くものの彼らの頭上を超えるボールをファンマに送られることによって、セカンドボールに対するアクションが少し遅れるという状況を生み、また、長崎の前半20分過頃のシステム変更によって明確にセカンドトップとドイスボランチがこぼれ球を拾う形を作り出し、徐々に長崎がセカンドボールを奪取できるという状況につながりました。
このように、前半から互いに守備アクションが激しく、繋ぐ余裕を与えてもらえなかったので、トランジションの応酬(ロングボールの応酬)というやや落ち着かない形での序盤となりました。つぶし合いの状況は一つのミスによって大きなピンチを生み出すことになります。一時も気を抜けないという状況が、更にチャージが激しくなる戦いを演出しました。退場者が出てもおかしくなかった状況ですが、木村主審はスタジアムの雰囲気に圧倒されることなく冷静に笛を吹いていたと思います。イエローカード乱発で荒れはててもおかしくない試合をぎりぎりのコントロールで対応して頂けたのではないかなという感想です。
さて、トランジション合戦も少し落ち着きを見せると、鳥栖が少しずつビルドアップを試みるようになりました。特徴的なのは福田のポジショニングでありまして、ボールを保持するとポジションを非常に高い位置にとって相手のサイドバック(ウイングバック)が前に出てきづらい状況を作っていました。福田がサイドバック(ウイングバック)を引き連れてスペースを作ってフォワードが入ってくるきっかけを作ったり、福田が引いて空けたスペースにトーレスやチョドンゴンが入ってボールを受ける形を作ったり、時折、福田自身が小林から縦パスを受けてサイドでのポストプレイを行ったり、いろいろな工夫を見せてボールを前進する仕組みを試みていました。ロングボールもツートップ一辺倒ではなく、逆サイドの高い位置にポジションを取る福田に対しても送られていましたし、ある意味4-3-3の3トップの一角のような働きを見せてくれました。



福田のポジショニングに呼応するように、チョドンゴンは両サイドのスペースに入ってボールを受け、トーレスは中央をベースとしてポストプレイ、そしてフィニッシュの役割をこなしていました。特にトーレスはビルドアップの場面やカウンターの場面で、いち早く顔を見せて縦へのボールを引きだすプレイをチョイスしていました。彼からのサイドチェンジも何回かあり、チョドンゴンがサイドに流れて、中央で待ちかまえるトーレスにクロスという形も複数回トライできていました。互いの役割が整理されていた証拠だと思います。


長崎にとってはミラーシステムで相手の良さを消すと同時に、当然、その形だと反対にボール保持時は鳥栖のプレッシングを受ける事になるので、攻撃面ではあまりメリットがありません。序盤から激しく見せたプレッシングも体力の低下と共に少しずつ鳥栖にスペースを使われる事にもなってきました。このままつぶし合いで試合が終わってしまうのは勝ち点3が欲しい長崎としても得策ではないということ、また、序盤に鳥栖にイニシアチブを持たれないという目的は果たしたという事でいつもの3-4-2-1に戻したのではないかと思われます。
長崎がいつもの形に戻したことによって、セカンドボールの奪取とサイドからの攻撃が明確になります。まずはトップのファンマに当てて、セカンドトップがボールを受け、鳥栖を中央に密集(義希と秀人を中央に集めさせる)させたタイミングで素早くサイドの翁長や飯尾に展開してチャンスを作ります。飯尾も翁長がサイドでボールを受けると一人はがしてクロスを上げる事ができるので、鳥栖はサイドからのクロスで何度かピンチを迎えていました。飯尾や翁長がサイドバックのマークを受けて動けなくなった時には、セカンドトップの2人がウイングバックの裏のスペースに入り込んでいましたし、そのあたりは長崎の攻撃がこの一年で洗練されているなというのを感じました。

鳥栖も、プレッシングにずれが生じる事によって、ビルドアップの工夫ができるようになります。原川がサイドバックとセンターバックの間のスペースにポジションを取り、そこに義希が絡むことによって数的優位を作る攻撃を見せていました。そこでボールキープができると三丸が裏へのスペースにオーバーラップする出番もできますし、三丸が引き付けることによって、原川がハーフスペースでボールを受けたり、相手のウイングバックの裏でボールを受けることもできます。



長崎の4-4-2システムでのスタートは互いにつぶしあう形でトランジション合戦を生み出し、長崎が3-4-1-2システムに変更することによって、ミスマッチによって生まれるスペースを利用したビルドアップ攻撃を生み出すという、試合展開のキーは長崎が握っていたという展開でした。
どちらが得点してもおかしくないという状況のなか、後半になって長崎の運動量が落ち、プレッシングの強度が低くなってきたところで鳥栖がボールを保持できる状況を生みます。得点は、押し込んでボールキープしてからの崩しによるものでした。福田がハーフスペースの高い位置へ入ってウイングバックを引き寄せている状況ですが、ボールを左右に回しながらチョドンゴンとトーレスが中央で基点を作ると、自らが空けたスペースを利用するべくややワイドにポジションを構えます。トーレスからの展開を受けると中央に入ってくるチョドンゴンにピンポイントクロス。クロスが上がるときには逆サイドハーフの原川がしっかりとペナルティエリアに入っています。トーレスのポストプレイ、福田の動きとクロスの質、チョドンゴンのシュート精度、原川のポジショニング、それらがしっかりとかみ合ったナイスゴールでした。




鳥栖が先制したことによって、長崎が攻勢に出ます。鳥栖としてはその分裏のスペースもあるわけでありまして、カウンター攻撃をしかけますが、なかなかよい形を作れません。時間が過ぎていき長崎がセンターバックの一角を攻撃参加に出すシーンも多くなってきた頃に明輝監督が動きます。小林を吉田に代えて5-4-1システムに変更します。長崎の3フォワード+両ウイングバックが前線にポジションを取るので彼らに対するマークを明確にする事、そしてドイスボランチとセンターバックのオーバーラップを中盤の4人で見る事というタスクが与えられました。
5-4-1システムはマッシモ時代にもあまり記憶がありません。そのあたりは明輝監督の色が出たとも言えるでしょう。システム変更時には、チョドンゴンに代えてトップの位置に入っていた田川を右サイドハーフに据えました。このあたりは考え処ですよね。カウンターの場面でトーレスに預けるボールを送り込むよりは、裏に蹴っ飛ばすことが多くなったので、田川をトップに置いて右サイドハーフは安在という選択肢もあったかなとは思います。ただし、ボールキープに関してはトーレスの方が何枚も上なので、5-4-1にした上でボール奪ってから彼に預けるという形を作りたかったのかもしれません。どのような形で時間を進めるかという所の意思統一が必要ですよね。そのあたりはこれからまだまだ成熟が必要な所でしょう。監督が変わったばっかりなので、これからですね。
さて、システムを5-4-1にしてからすぐにこの試合最大のピンチを迎えるのですが、チャンスの後にピンチありとでも言いましょうか、原川のクロスが相手にカットされてからのカウンター攻撃によるものでした。中央でボールを受けた中村慶が鳥栖の左サイドに向かってドリブルで前進します。その時にマークについていた吉田が中村慶に着いていく決断をして逆サイドまで引っ張られます。これによって、鳥栖の右サイドに大きなスペースをあけることになるので、ボランチの位置に入った吉田と入れ替わりで秀人が右ウイングの位置に入ります。中村慶は、秀人が戻りきる前にスペースに入ってくる選手に対してパスを送り込みました。ここからがポイントなのですが、吉田は中村慶がパスを送った後に、右ウイングバックのポジションに戻ろうとします。本来、秀人がボランチの位置にポジションをとっていたならば中央へのクロスに備えて中央のスペースを守る動きをしていたはずなのですが、ポジションチェンジした吉田は秀人が右ウイングのポジションをカバーリングしているにも関わらず、右ウイングの位置に戻ろうとしてしまいました。これによって中央が薄くなり、サイドに展開した中村慶にクロスが入ってボレーシュートを放たれてしまいました。権田のスーパーセーブによって救われたのですが、5-4-1システムにおけるポジショニングはもう少し習熟が必要かもしれません。


大事な大事なシックスポイントマッチを勝点3という最高の結果で終える事ができました。これによって、鳥栖は、残り試合を3連勝することによって自動で降格圏を脱出できるという権利を得る事ができました。(マリノスと勝ち点差2なので上回ることが出来ます)
最大の目標である残留まであと一息ですね。予断を許さない状況ですが、チーム全体で一丸となって残留を勝ち取りたいですね。
<画像引用元:DAZN>
鳥栖のセットアップは4-4-2。戦前から別メニューとなっている選手の情報がネットニュースに上がっていましたが、その情報が正しかったみたいで、金崎、小野、豊田がベンチ外でした。ツートップはチョドンゴンとトーレス、中盤は原川、秀人、義希、福田のラインナップ。最終ラインは変更ありません。
一方の長崎はいつもの3-4-1-2システムではなく、4-4-2システムによる序盤の戦いとなりました。狙いとしてはミラーゲームにすることによってマーキングを明確にすること。3-4-2-1システムでは、鳥栖2センターバックに対して前線はファンマ一人になるので、前から行くためにはセカンドトップのうちの一人がプレスに入らなければなりません。最終ラインに自由な時間を与えないように、また、マーキングの乱れによるスペースを使われないように、予め明確にプレッシングの相手を決めてしまおうという事だと思われます。その戦術に呼応するように、前線から平松とファンマが運動量激しく最終ラインに対してプレッシングを行い、鳥栖の自由に繋ぐプレイを阻害し、単純にボールを蹴らざるをえない状況を作り出していました。

対する長崎はファンマを狙うというコンセプトが統一されていました。鳥栖も比較的高い位置からプレッシングに来ており、トランジションの場面においてボランチ経由でつなごうとすると、積極的に秀人と義希がつぶしに来ていたので、ドイスボランチのプレッシングをかわすために早めにボールを蹴ってしまう方が得策という形になります。この試合の秀人と義希のトランジションでのプレスは非常に素晴らしく、長崎が攻撃に入ろうとしたところで素早くチェックしてショートカウンターに繋げる場面が多くありました。長崎としては、それを防ぐ手立てとしての早めのロングボールというのは悪い選択ではなかったかと思います。鳥栖としては、秀人と義希が前から行くものの彼らの頭上を超えるボールをファンマに送られることによって、セカンドボールに対するアクションが少し遅れるという状況を生み、また、長崎の前半20分過頃のシステム変更によって明確にセカンドトップとドイスボランチがこぼれ球を拾う形を作り出し、徐々に長崎がセカンドボールを奪取できるという状況につながりました。
このように、前半から互いに守備アクションが激しく、繋ぐ余裕を与えてもらえなかったので、トランジションの応酬(ロングボールの応酬)というやや落ち着かない形での序盤となりました。つぶし合いの状況は一つのミスによって大きなピンチを生み出すことになります。一時も気を抜けないという状況が、更にチャージが激しくなる戦いを演出しました。退場者が出てもおかしくなかった状況ですが、木村主審はスタジアムの雰囲気に圧倒されることなく冷静に笛を吹いていたと思います。イエローカード乱発で荒れはててもおかしくない試合をぎりぎりのコントロールで対応して頂けたのではないかなという感想です。
さて、トランジション合戦も少し落ち着きを見せると、鳥栖が少しずつビルドアップを試みるようになりました。特徴的なのは福田のポジショニングでありまして、ボールを保持するとポジションを非常に高い位置にとって相手のサイドバック(ウイングバック)が前に出てきづらい状況を作っていました。福田がサイドバック(ウイングバック)を引き連れてスペースを作ってフォワードが入ってくるきっかけを作ったり、福田が引いて空けたスペースにトーレスやチョドンゴンが入ってボールを受ける形を作ったり、時折、福田自身が小林から縦パスを受けてサイドでのポストプレイを行ったり、いろいろな工夫を見せてボールを前進する仕組みを試みていました。ロングボールもツートップ一辺倒ではなく、逆サイドの高い位置にポジションを取る福田に対しても送られていましたし、ある意味4-3-3の3トップの一角のような働きを見せてくれました。



福田のポジショニングに呼応するように、チョドンゴンは両サイドのスペースに入ってボールを受け、トーレスは中央をベースとしてポストプレイ、そしてフィニッシュの役割をこなしていました。特にトーレスはビルドアップの場面やカウンターの場面で、いち早く顔を見せて縦へのボールを引きだすプレイをチョイスしていました。彼からのサイドチェンジも何回かあり、チョドンゴンがサイドに流れて、中央で待ちかまえるトーレスにクロスという形も複数回トライできていました。互いの役割が整理されていた証拠だと思います。


長崎にとってはミラーシステムで相手の良さを消すと同時に、当然、その形だと反対にボール保持時は鳥栖のプレッシングを受ける事になるので、攻撃面ではあまりメリットがありません。序盤から激しく見せたプレッシングも体力の低下と共に少しずつ鳥栖にスペースを使われる事にもなってきました。このままつぶし合いで試合が終わってしまうのは勝ち点3が欲しい長崎としても得策ではないということ、また、序盤に鳥栖にイニシアチブを持たれないという目的は果たしたという事でいつもの3-4-2-1に戻したのではないかと思われます。
長崎がいつもの形に戻したことによって、セカンドボールの奪取とサイドからの攻撃が明確になります。まずはトップのファンマに当てて、セカンドトップがボールを受け、鳥栖を中央に密集(義希と秀人を中央に集めさせる)させたタイミングで素早くサイドの翁長や飯尾に展開してチャンスを作ります。飯尾も翁長がサイドでボールを受けると一人はがしてクロスを上げる事ができるので、鳥栖はサイドからのクロスで何度かピンチを迎えていました。飯尾や翁長がサイドバックのマークを受けて動けなくなった時には、セカンドトップの2人がウイングバックの裏のスペースに入り込んでいましたし、そのあたりは長崎の攻撃がこの一年で洗練されているなというのを感じました。

鳥栖も、プレッシングにずれが生じる事によって、ビルドアップの工夫ができるようになります。原川がサイドバックとセンターバックの間のスペースにポジションを取り、そこに義希が絡むことによって数的優位を作る攻撃を見せていました。そこでボールキープができると三丸が裏へのスペースにオーバーラップする出番もできますし、三丸が引き付けることによって、原川がハーフスペースでボールを受けたり、相手のウイングバックの裏でボールを受けることもできます。



長崎の4-4-2システムでのスタートは互いにつぶしあう形でトランジション合戦を生み出し、長崎が3-4-1-2システムに変更することによって、ミスマッチによって生まれるスペースを利用したビルドアップ攻撃を生み出すという、試合展開のキーは長崎が握っていたという展開でした。
どちらが得点してもおかしくないという状況のなか、後半になって長崎の運動量が落ち、プレッシングの強度が低くなってきたところで鳥栖がボールを保持できる状況を生みます。得点は、押し込んでボールキープしてからの崩しによるものでした。福田がハーフスペースの高い位置へ入ってウイングバックを引き寄せている状況ですが、ボールを左右に回しながらチョドンゴンとトーレスが中央で基点を作ると、自らが空けたスペースを利用するべくややワイドにポジションを構えます。トーレスからの展開を受けると中央に入ってくるチョドンゴンにピンポイントクロス。クロスが上がるときには逆サイドハーフの原川がしっかりとペナルティエリアに入っています。トーレスのポストプレイ、福田の動きとクロスの質、チョドンゴンのシュート精度、原川のポジショニング、それらがしっかりとかみ合ったナイスゴールでした。




鳥栖が先制したことによって、長崎が攻勢に出ます。鳥栖としてはその分裏のスペースもあるわけでありまして、カウンター攻撃をしかけますが、なかなかよい形を作れません。時間が過ぎていき長崎がセンターバックの一角を攻撃参加に出すシーンも多くなってきた頃に明輝監督が動きます。小林を吉田に代えて5-4-1システムに変更します。長崎の3フォワード+両ウイングバックが前線にポジションを取るので彼らに対するマークを明確にする事、そしてドイスボランチとセンターバックのオーバーラップを中盤の4人で見る事というタスクが与えられました。
5-4-1システムはマッシモ時代にもあまり記憶がありません。そのあたりは明輝監督の色が出たとも言えるでしょう。システム変更時には、チョドンゴンに代えてトップの位置に入っていた田川を右サイドハーフに据えました。このあたりは考え処ですよね。カウンターの場面でトーレスに預けるボールを送り込むよりは、裏に蹴っ飛ばすことが多くなったので、田川をトップに置いて右サイドハーフは安在という選択肢もあったかなとは思います。ただし、ボールキープに関してはトーレスの方が何枚も上なので、5-4-1にした上でボール奪ってから彼に預けるという形を作りたかったのかもしれません。どのような形で時間を進めるかという所の意思統一が必要ですよね。そのあたりはこれからまだまだ成熟が必要な所でしょう。監督が変わったばっかりなので、これからですね。
さて、システムを5-4-1にしてからすぐにこの試合最大のピンチを迎えるのですが、チャンスの後にピンチありとでも言いましょうか、原川のクロスが相手にカットされてからのカウンター攻撃によるものでした。中央でボールを受けた中村慶が鳥栖の左サイドに向かってドリブルで前進します。その時にマークについていた吉田が中村慶に着いていく決断をして逆サイドまで引っ張られます。これによって、鳥栖の右サイドに大きなスペースをあけることになるので、ボランチの位置に入った吉田と入れ替わりで秀人が右ウイングの位置に入ります。中村慶は、秀人が戻りきる前にスペースに入ってくる選手に対してパスを送り込みました。ここからがポイントなのですが、吉田は中村慶がパスを送った後に、右ウイングバックのポジションに戻ろうとします。本来、秀人がボランチの位置にポジションをとっていたならば中央へのクロスに備えて中央のスペースを守る動きをしていたはずなのですが、ポジションチェンジした吉田は秀人が右ウイングのポジションをカバーリングしているにも関わらず、右ウイングの位置に戻ろうとしてしまいました。これによって中央が薄くなり、サイドに展開した中村慶にクロスが入ってボレーシュートを放たれてしまいました。権田のスーパーセーブによって救われたのですが、5-4-1システムにおけるポジショニングはもう少し習熟が必要かもしれません。


大事な大事なシックスポイントマッチを勝点3という最高の結果で終える事ができました。これによって、鳥栖は、残り試合を3連勝することによって自動で降格圏を脱出できるという権利を得る事ができました。(マリノスと勝ち点差2なので上回ることが出来ます)
最大の目標である残留まであと一息ですね。予断を許さない状況ですが、チーム全体で一丸となって残留を勝ち取りたいですね。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
12:25
│Match Impression (2018)
2018年10月24日
2018 第30節 : ベガルタ仙台 VS サガン鳥栖
2018年第30節、ベガルタ仙台戦のレビューです。
鳥栖のセットアップは4-4-2。最終ライン4人の内、スタメンが3人入れ替わりました。左サイドバックには三丸が入り、祐治が出場停止明けでスタメン復帰、右サイドバックは小林が藤田に替わってスタメンに入りました。セントラルハーフは右から福田、義希、秀人、小野のラインナップ。ツートップはトーレスがスタメンに復帰して金崎とのコンビです。
仙台のセットアップは3-4-2-1だったので、鳥栖のシステムとはミスマッチが生じる事になります。特に、ビルドアップの場面では両チームともに守備側のフォワードよりも攻撃側の最終ラインの方が人数多いため、前線からプレッシングをかけるためにはセットアップのシステムから誰がどのタイミングで前にプレスに入るのかという決め事が重要になります。
鳥栖も仙台も積極的に前からのプレッシングを行っていましたが、どちらかというと鳥栖の方がより前からという意識は高かったかと思います。鳥栖のプレッシングは、フォワード2人がサイドへの誘導を行い(フォワードの内のひとりはボランチへのパスコースを遮断し)、誘導した側のストッパーに対してサイドハーフが出ていく形を取りました。また、ウイングバックに対してサイドバックが出ていく形を取り、仙台のドイスボランチに対しては、鳥栖もドイスボランチをぶつけます。特に福田がアグレッシブに前にでてきており、サイドバックも連動してウイングバックへのプレッシングを果たしていたため、前方でひっかけてショートカウンターというシーンを何回か見る事ができました。後半の福田が高い位置でひっかけてカットインして左足でシュートしたシーンは惜しかったですね。良いプレイでしたが、シュートが枠に行ってほしい所です。

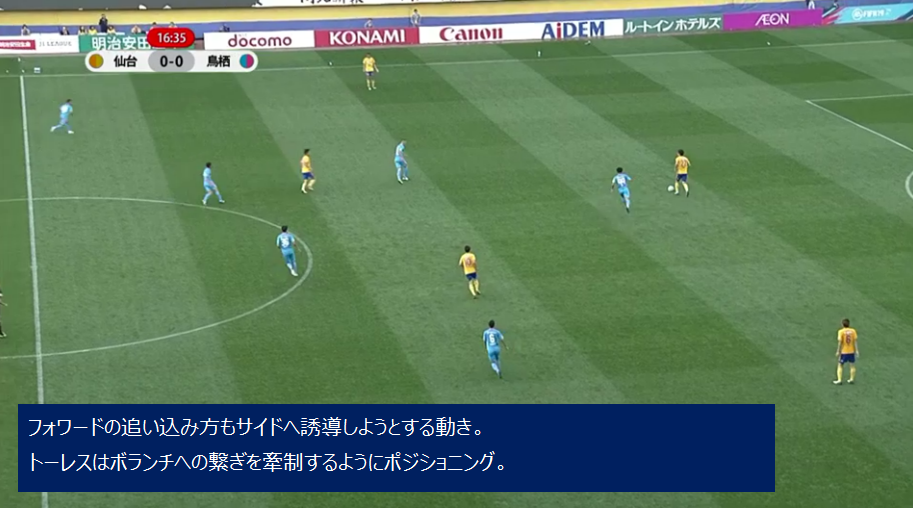

高い位置からいく事による弊害ももちろんありまして、特に、サイドバックがウイングバックにつくので、裏のスペースを与える事になります。前線からのプレッシングがずれたり遅れたりした場合には、サイドのスペースに入るセカンドトップに繋がれて攻撃の基点をつくられていました。基点を作られると、蜂須賀、関口(永戸)がフォローに入って裏に抜けだす攻撃を見せます。彼らは個人で打開する力もスピードもあり、クロスも正確ですので非常に怖い存在でした。
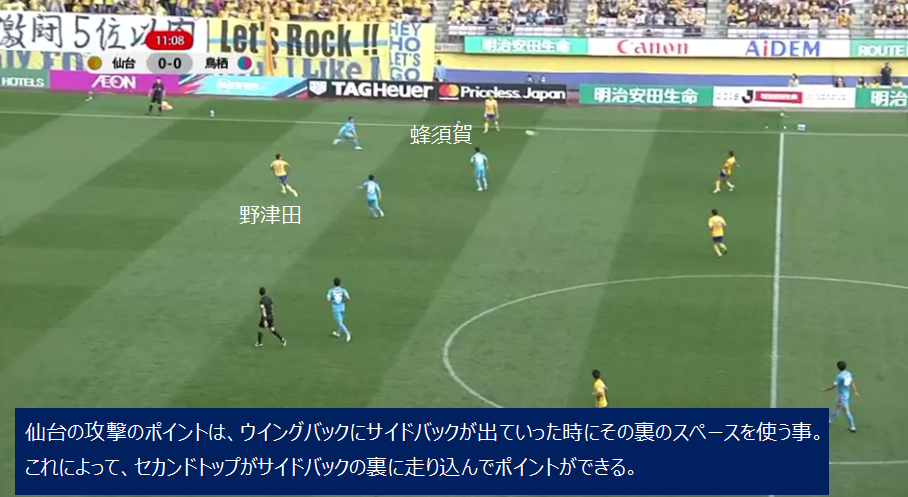
仙台にとっては鳥栖のプレッシングに詰まってしまって、「困った時のロングボール」の狙いどころが石原だったので、ちょっとオマリや祐治に対して分が悪かったかなと思います。ここが、札幌と仙台の違いではありますよね。札幌は困った時のロングボールにジェイというのは脅威でしかありませんでしたから。
仙台のプレッシングは鳥栖のセンターバック2名に対しては石原がサイドを限定させる役割。サイドバックにボールが入ってからが仙台のプレッシングのスタートです。セカンドトップ(阿部、野津田)がサイドバックに対してアプローチをかけると共に、ボールの出先になるサイドハーフにはウイングバックを当て、鳥栖のドイスボランチには仙台もドイスボランチを当ててきます。仙台がアンカーシステムとドイスボランチシステムを使い分けているみたいですが、鳥栖戦はドイスボランチで来ました。秀人と義希に対するマーキングを明確にするためでしょう。鳥栖は、仙台ボランチからのマーキングから解放のために、ビルドアップで秀人が下がるケースが多かったのですが、そうなってくるとパスの出先が一つ失われてしまうので、秀人からは長いサイドチェンジやフォワードへのロングボールを蹴るケースが多くなりました。



仙台がシステムミスマッチに対する解決策をしっかりと果たして、中盤がマーキングにあっていために鳥栖は直接フォワードにボールを当てる解決策を試みます。金崎がハーフスペース(ざっくりいうと、仙台5バックのストッパーの位置)でボールを受けるポジションをとり、サイドバックから直接のボール配球を受ける準備をします。これによって仙台ストッパーが釣り出されるので、ウイングバックはストッパーのカバーをしなければならず、大外のレーンががら空きになるという仕組みです。福田や小野がサイドでフリーとなってボールを受けるシーンを多く作ることができました。



鳥栖は、明輝監督になって、選手たちのポジショニングの修正を施しました。単純にいうと交通渋滞が発生しないように交通整理を行った感じです。ルールは、端的に言うと、「縦位置には2名以上かぶって入らない」という感じでしょうか。フォワードは極力中央からは動かず、ボールを受ける時にはハーフスペースにポジションをとりポストプレイを行います。サイドハーフは大外にポジションを取り、サイドバックはサイドハーフの動きを見てからレーンがかぶらないように前進していく感じです。小林と三丸のインナーラップとオーバーラップの使い分けは統率された動きであると感じました。
マッシモ時代は、金崎が大外まで開いてボールを受けるケースが多かったのですが、金崎のポジショニングがやや中央寄り(ハーフスペース)に陣取るようになりました。これにより、サイドハーフの小野や福田が、トーレスや金崎がボールを受けたエリアの外側のスペースを活用してオーバーラップをしかけるようになりました。交通整理が整って選手が均等に配置されるので、フォワード、サイドハーフ、サイドバックによる交通渋滞が発生することがなくなり、スムーズな攻撃が展開できました。





ビルドアップも方式を変えまして、マッシモ監督時代は、サイドハーフやインサイドハーフをビルドアップで下げてサイドバックを前に押し出す形を取っていましたが、明輝監督になってその形はほとんどなくなりました。サイドバックがボールを持ったら、縦位置前方にサイドハーフはボールを受ける準備をします。これによる最大の利点は、カウンター攻撃を受けた時にサイドバックが後方に控えているために、無駄なスペースを相手に与えずにいち早く守備に備えられることです。マッシモ監督時代は、原川が引いて吉田が前方にポジションを取っており、ネガティブトランジション時(攻から守への切り替え時)に、二人ともボールにつっかかってしまうというポジショニングミスで気がつけば後ろのスペースががら空きという状況による失点が多発しておりました。攻撃は小野、後方支援は三丸という役割を明確にすることによって、カウンター時の守備不在を防いでおります。不意にボールを奪われてもサイドバックが低い位置にいるので裏のスペースを使われるというケースも格段に減っております。
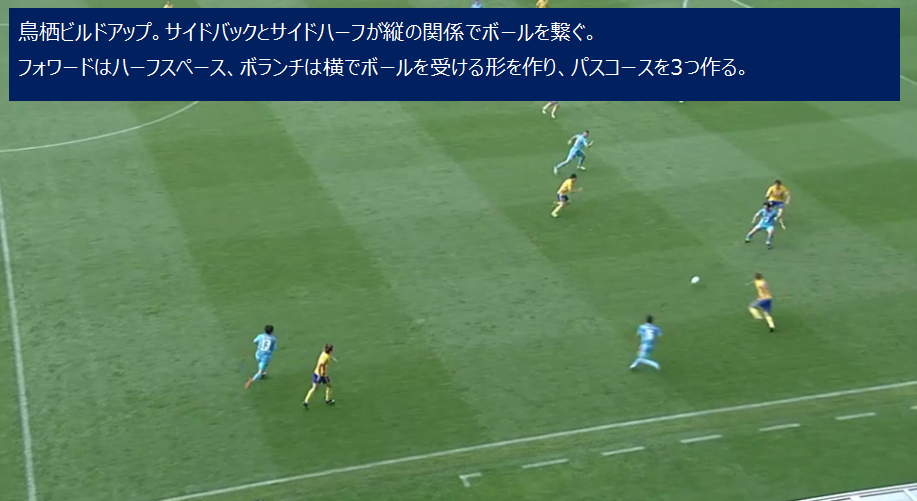
鳥栖が監督交代の変化は守備ブロック時のサイドハーフの位置取りにも現れていました。マッシモ時代は相手に押し込まれた場合はサイドハーフ(特に福田)が最終ラインを下げて5バックで構えるケースが多かったのですが、仙台戦では、サイドバックがアウトサイドのケアに入って、ボランチが最終ラインに下がる形が多くなっていました。これによって、カウンター攻撃をしかけるときに、小野と福田が高い位置からの始動となるので、金崎やトーレスにボールを預けてからのフォローや抜けだしにかかる時間が少なくなり、カウンター攻撃のスピードが上がりました。
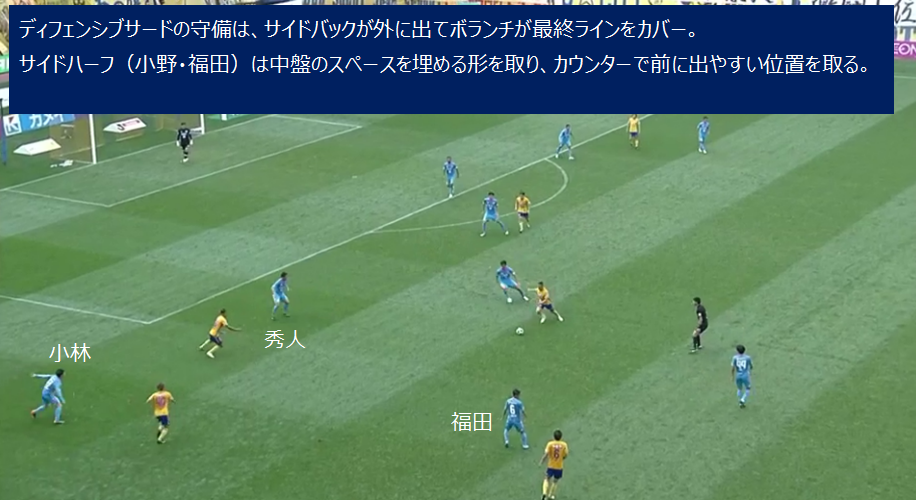
全体的に、4-4-2システムの中でポジションを前後させるような複雑さもないので、それぞれの役割がある意味単純で明確になり、これまで縦横無尽に動いていた金崎と小野がバッティングするようなシーンもなく、どこかのエリアに特化して強いという状況はなくなったものの、全体的にバランスよく選手を配置するような形になりました。また、クロスが上がる際にもペナルティエリア内に3人が入る形ができていたため、クロスに対する可能性も増えました。流れの中でトーレスが得点をとれたのはその集大成でしょう。小野が今回の持場である大外レーンに開いてボールを引出し、中央に構えるトーレスへ完璧なクロスを供給してくれました。
やりかた自体は大きくはかわっていないでしょうが、少しポジションを整理するだけで勝利につなげることができたのは、ユースでも高い勝率をほこる采配を振っていた明輝監督への交替の効果だと思います。降格圏を彷徨う崖っぷちの状態で仙台から勝ち点3を奪えたのは、今後の事を考えると非常に大きいですよね。長崎もこの試合を基に研究してくるでしょうから、更に明輝監督がどのような戦術を持っているのか、長崎のウイークポイントに対する策はあるのか、着目してみたいと思います。シーズン開始頃の長崎とのアウェー戦では、半年後にこのような事態になるとは思ってもいませんでした。まだ残留できるチャンスは両チームともにあるので、死闘を演じる事になるでしょうが、しっかりと勝って勝ち点3をゲットしてほしいと思います。
<画像引用元:DAZN>
鳥栖のセットアップは4-4-2。最終ライン4人の内、スタメンが3人入れ替わりました。左サイドバックには三丸が入り、祐治が出場停止明けでスタメン復帰、右サイドバックは小林が藤田に替わってスタメンに入りました。セントラルハーフは右から福田、義希、秀人、小野のラインナップ。ツートップはトーレスがスタメンに復帰して金崎とのコンビです。
仙台のセットアップは3-4-2-1だったので、鳥栖のシステムとはミスマッチが生じる事になります。特に、ビルドアップの場面では両チームともに守備側のフォワードよりも攻撃側の最終ラインの方が人数多いため、前線からプレッシングをかけるためにはセットアップのシステムから誰がどのタイミングで前にプレスに入るのかという決め事が重要になります。
鳥栖も仙台も積極的に前からのプレッシングを行っていましたが、どちらかというと鳥栖の方がより前からという意識は高かったかと思います。鳥栖のプレッシングは、フォワード2人がサイドへの誘導を行い(フォワードの内のひとりはボランチへのパスコースを遮断し)、誘導した側のストッパーに対してサイドハーフが出ていく形を取りました。また、ウイングバックに対してサイドバックが出ていく形を取り、仙台のドイスボランチに対しては、鳥栖もドイスボランチをぶつけます。特に福田がアグレッシブに前にでてきており、サイドバックも連動してウイングバックへのプレッシングを果たしていたため、前方でひっかけてショートカウンターというシーンを何回か見る事ができました。後半の福田が高い位置でひっかけてカットインして左足でシュートしたシーンは惜しかったですね。良いプレイでしたが、シュートが枠に行ってほしい所です。

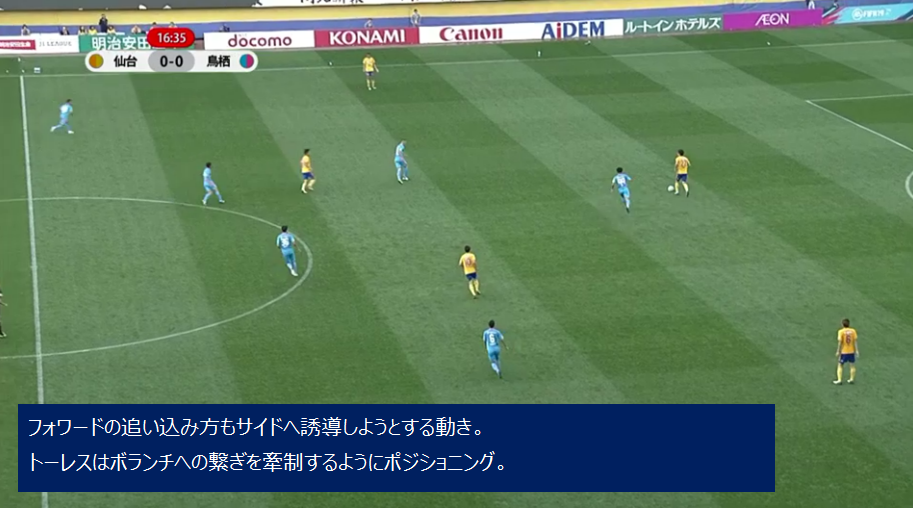

高い位置からいく事による弊害ももちろんありまして、特に、サイドバックがウイングバックにつくので、裏のスペースを与える事になります。前線からのプレッシングがずれたり遅れたりした場合には、サイドのスペースに入るセカンドトップに繋がれて攻撃の基点をつくられていました。基点を作られると、蜂須賀、関口(永戸)がフォローに入って裏に抜けだす攻撃を見せます。彼らは個人で打開する力もスピードもあり、クロスも正確ですので非常に怖い存在でした。
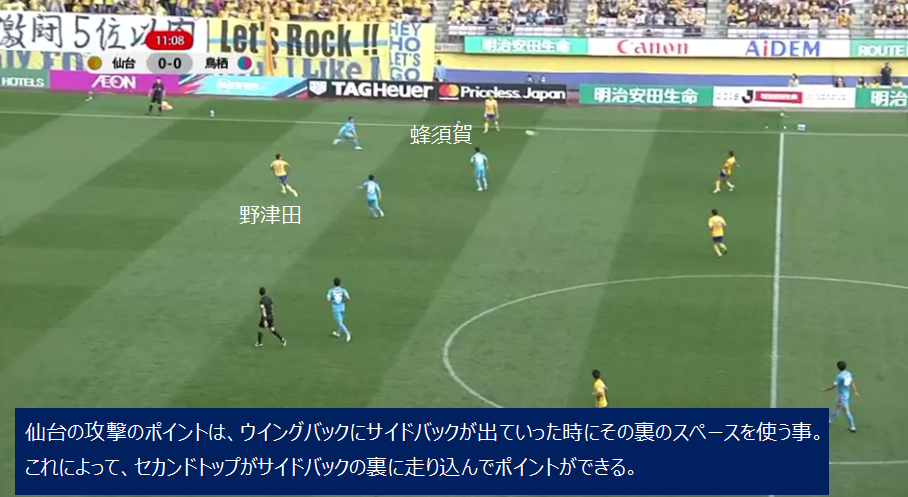
仙台にとっては鳥栖のプレッシングに詰まってしまって、「困った時のロングボール」の狙いどころが石原だったので、ちょっとオマリや祐治に対して分が悪かったかなと思います。ここが、札幌と仙台の違いではありますよね。札幌は困った時のロングボールにジェイというのは脅威でしかありませんでしたから。
仙台のプレッシングは鳥栖のセンターバック2名に対しては石原がサイドを限定させる役割。サイドバックにボールが入ってからが仙台のプレッシングのスタートです。セカンドトップ(阿部、野津田)がサイドバックに対してアプローチをかけると共に、ボールの出先になるサイドハーフにはウイングバックを当て、鳥栖のドイスボランチには仙台もドイスボランチを当ててきます。仙台がアンカーシステムとドイスボランチシステムを使い分けているみたいですが、鳥栖戦はドイスボランチで来ました。秀人と義希に対するマーキングを明確にするためでしょう。鳥栖は、仙台ボランチからのマーキングから解放のために、ビルドアップで秀人が下がるケースが多かったのですが、そうなってくるとパスの出先が一つ失われてしまうので、秀人からは長いサイドチェンジやフォワードへのロングボールを蹴るケースが多くなりました。



仙台がシステムミスマッチに対する解決策をしっかりと果たして、中盤がマーキングにあっていために鳥栖は直接フォワードにボールを当てる解決策を試みます。金崎がハーフスペース(ざっくりいうと、仙台5バックのストッパーの位置)でボールを受けるポジションをとり、サイドバックから直接のボール配球を受ける準備をします。これによって仙台ストッパーが釣り出されるので、ウイングバックはストッパーのカバーをしなければならず、大外のレーンががら空きになるという仕組みです。福田や小野がサイドでフリーとなってボールを受けるシーンを多く作ることができました。



鳥栖は、明輝監督になって、選手たちのポジショニングの修正を施しました。単純にいうと交通渋滞が発生しないように交通整理を行った感じです。ルールは、端的に言うと、「縦位置には2名以上かぶって入らない」という感じでしょうか。フォワードは極力中央からは動かず、ボールを受ける時にはハーフスペースにポジションをとりポストプレイを行います。サイドハーフは大外にポジションを取り、サイドバックはサイドハーフの動きを見てからレーンがかぶらないように前進していく感じです。小林と三丸のインナーラップとオーバーラップの使い分けは統率された動きであると感じました。
マッシモ時代は、金崎が大外まで開いてボールを受けるケースが多かったのですが、金崎のポジショニングがやや中央寄り(ハーフスペース)に陣取るようになりました。これにより、サイドハーフの小野や福田が、トーレスや金崎がボールを受けたエリアの外側のスペースを活用してオーバーラップをしかけるようになりました。交通整理が整って選手が均等に配置されるので、フォワード、サイドハーフ、サイドバックによる交通渋滞が発生することがなくなり、スムーズな攻撃が展開できました。





ビルドアップも方式を変えまして、マッシモ監督時代は、サイドハーフやインサイドハーフをビルドアップで下げてサイドバックを前に押し出す形を取っていましたが、明輝監督になってその形はほとんどなくなりました。サイドバックがボールを持ったら、縦位置前方にサイドハーフはボールを受ける準備をします。これによる最大の利点は、カウンター攻撃を受けた時にサイドバックが後方に控えているために、無駄なスペースを相手に与えずにいち早く守備に備えられることです。マッシモ監督時代は、原川が引いて吉田が前方にポジションを取っており、ネガティブトランジション時(攻から守への切り替え時)に、二人ともボールにつっかかってしまうというポジショニングミスで気がつけば後ろのスペースががら空きという状況による失点が多発しておりました。攻撃は小野、後方支援は三丸という役割を明確にすることによって、カウンター時の守備不在を防いでおります。不意にボールを奪われてもサイドバックが低い位置にいるので裏のスペースを使われるというケースも格段に減っております。
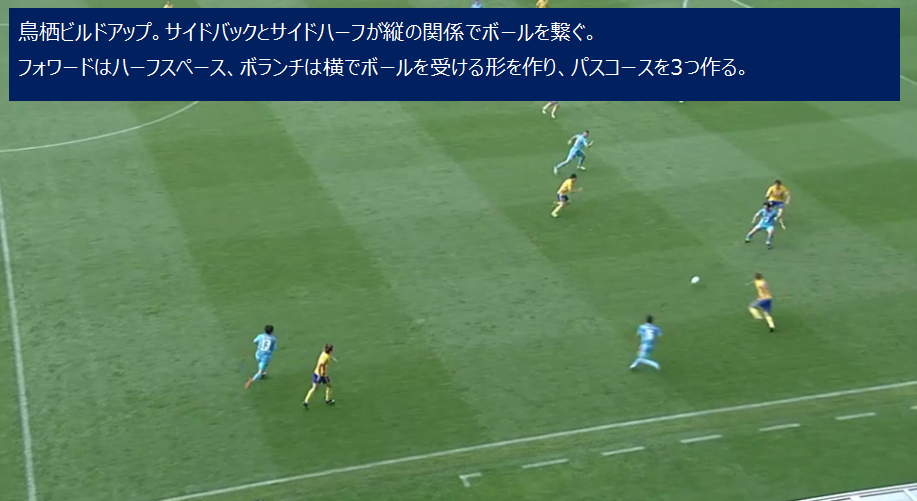
鳥栖が監督交代の変化は守備ブロック時のサイドハーフの位置取りにも現れていました。マッシモ時代は相手に押し込まれた場合はサイドハーフ(特に福田)が最終ラインを下げて5バックで構えるケースが多かったのですが、仙台戦では、サイドバックがアウトサイドのケアに入って、ボランチが最終ラインに下がる形が多くなっていました。これによって、カウンター攻撃をしかけるときに、小野と福田が高い位置からの始動となるので、金崎やトーレスにボールを預けてからのフォローや抜けだしにかかる時間が少なくなり、カウンター攻撃のスピードが上がりました。
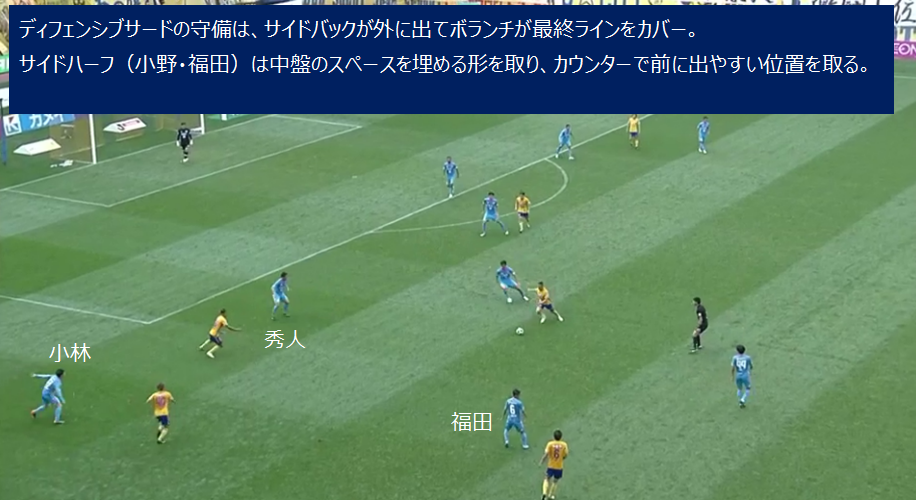
全体的に、4-4-2システムの中でポジションを前後させるような複雑さもないので、それぞれの役割がある意味単純で明確になり、これまで縦横無尽に動いていた金崎と小野がバッティングするようなシーンもなく、どこかのエリアに特化して強いという状況はなくなったものの、全体的にバランスよく選手を配置するような形になりました。また、クロスが上がる際にもペナルティエリア内に3人が入る形ができていたため、クロスに対する可能性も増えました。流れの中でトーレスが得点をとれたのはその集大成でしょう。小野が今回の持場である大外レーンに開いてボールを引出し、中央に構えるトーレスへ完璧なクロスを供給してくれました。
やりかた自体は大きくはかわっていないでしょうが、少しポジションを整理するだけで勝利につなげることができたのは、ユースでも高い勝率をほこる采配を振っていた明輝監督への交替の効果だと思います。降格圏を彷徨う崖っぷちの状態で仙台から勝ち点3を奪えたのは、今後の事を考えると非常に大きいですよね。長崎もこの試合を基に研究してくるでしょうから、更に明輝監督がどのような戦術を持っているのか、長崎のウイークポイントに対する策はあるのか、着目してみたいと思います。シーズン開始頃の長崎とのアウェー戦では、半年後にこのような事態になるとは思ってもいませんでした。まだ残留できるチャンスは両チームともにあるので、死闘を演じる事になるでしょうが、しっかりと勝って勝ち点3をゲットしてほしいと思います。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
15:52
│Match Impression (2018)
2018年10月11日
2018 第29節 : サガン鳥栖 VS 湘南ベルマーレ
2018年第29節、湘南ベルマーレ戦のレビューです。
鳥栖のセットアップは4-3-1-2。小野をトップ下に起用して湘南の3バックに対して前線からプレッシングをかける守備方式を採用しました。フォワードはチョドンゴンが久しぶりのスタメン復帰。ポストプレイとセンターバック脇のスペースに流れる役割ということで、度々攻撃の基点を作っていました。湘南のセットアップは3-4-1-2。両サイドの岡本、杉岡の上下動によってバランスをコントロールするのですが、攻撃時にはストッパーの大野や山根が前線まで顔を出すというまさに全員攻撃、全員守備のハードワークサッカーを展開していました。
鳥栖も湘南も序盤から相手の陣地まで押し込んでプレッシングをかけていました。鳥栖は小野も含めた前線の3人が湘南の3バックに対してプレッシングをかけ、サイドに追い込んだ上でセントラルハーフが湘南のビルドアップの出口を封鎖しました。秀人が湘南ボランチに対して積極的に追い込みをかけて、相手が最終ラインに下がってまでも執拗に追い込んで前を向かせない対応を取りにいく形もあり、この試合にかけるアグレッシブさを十分に感じさせてくれました。
対する湘南も、セカンドトップが1名前に出て山崎と共に鳥栖の両センターバックを捕まえることで、3-5-2の形に変化でき、高い位置をとろうとするサイドバックを中盤で捕まえて簡単にマッチアップの相手を作ることができたので、前からのプレッシングでキーパーまで戻させてロングボールを蹴らせることに成功していました。


湘南と鳥栖とどちらがイニシアチブを握るのかというポイントは、ロングボールに対する強さとセカンドボールの拾い方でした。互いにプレッシングが強烈でキーパーからのロングボールも多くなり、最後は空中戦という形になるのですが、山崎がミンヒョクやオマリに勝てる確率よりは、チョドンゴンが坂、大野、山根に勝てる確率の方が高く。また、湘南はトップの山崎に対してセカンドトップがセカンドボールを回収する形に対して、鳥栖はチョドンゴンに対して、金崎、小野+セントラルハーフがボールを回収する形になり、セカンドボールがこぼれる地点の数的密集度も鳥栖の方が回収しやすい形になっていました。ロングボールが軸でしたが、鳥栖がボールを握って押し込むことに成功し、湘南を完全リトリートさせることに成功させていたので、ボールを奪われてもトランジションでのプレスで奪い返したり、相手にクリアさせるだけの形を作れ、波状攻撃に繋げていました。
このタイミングで先制できれば良かったのですが、度重なるクロスでも、セットプレイでのチャンスでも得点できず。そうすると徐々に体力が落ちてきて、序盤は湘南がボールを握れない程に(前を向けない程に)強いプレスをかけていましたが、徐々に湘南がボールを回せるほどにプレッシングの強度が弱まってきます。
そうすると、湘南はボールロスト(ショートカウンター)のリスクが少しずつ下がってくるので、攻撃に手数をかけてきます。一番大きな特徴は、ストッパーの大野や山根をサイド攻撃に参画させたことでした。サイドで数的優位を作って、局面でのグループ単位の動きによって鳥栖の守備陣を翻弄します。特に、鳥栖の左サイドでは、原川と吉田のコンビネーションが合わないタイミング(ボール保持者に二人で寄せてしまったり、誰もボール保持者にプレッシャーをかけられなかったり)を見つけると、一気呵成に崩しにかかります。誰かが動いて作ったスペースを次の人間が使う。そこでまた鳥栖の人間が動いてできたスペースを他のメンバーが使うという、三段論法のような形で鳥栖のスペースに次々と人が入りこんでいました。




一方、鳥栖の攻撃は、グループ戦術という点では、やはり個人のアイデアに依存している形でした。下記のシーンを見て欲しいのですが、秀人が中央でボールを持って、中央に吉田が入ってくるのですが湘南守備陣を動かすこともできず、ボールは出てこず。金崎にボールを預けて秀人が縦のスペースを狙うがボールは出てこず。福田がサイドから中央に入って湘南のディフェンスを1人動かしますが、金崎は突破できず、そして福田にもボールは出らず。ポジショニングを守るならば、吉田は大外にいた方がフリーで受けられるチャンスもありますし、湘南のディフェンスを一人引き付けることもできます。みんなが中央に集まってくるので、湘南のディフェンスも中央に集まってきて交通渋滞が発生し、シュートを打てるスペースもできません。




個人のアイデアはあって、いろいろと動かそうとするのですが、それがアイデアを共有した上でのグループとしての動きになっていないので、ひらめきの意思がたまたまあった時にしか、有効な攻撃に繋がりません。その時々で、出す人、受ける人、犠牲になる人が変わるので、どう動いて良いのか分からずに気が付けば動き出しが遅れます。せっかく藤田が縦のパスに抜けてクロスを上げようとしたら、そこに金崎まで来てしまってボールに触ってオフサイドになったシーンは、役割が整理できていないという典型的な現象です。
スペースを見つけて動くのは、大事なことですが、そのスペースを使う事を周りが理解していなければ意味がありません。クロスをあげるときも、縦に突破してあげたり、一旦足を持ち替えてあげたりして、中央で待ち構える人間とタイミングがずれるため、なかなかピンポイントで味方に合いません。押し込んでいるようで、決定的なシュートに繋がらないもどかしさは常々感じました。
失点シーンは、これまでも当Blogで指摘してきた崩され方であり、マッシモがどうしても修正できなかった部分です。鳥栖の守備陣は個に強い反面、その個の力がありすぎるが上に、ボールや相手選手へのプレッシャーに寄ってしまう傾向にあります。スペースを守らなければならないところでも相手選手に引きずられて奪いに行ってしまうので、気が付けば相手がフリーになったり、すっぽり空いてしまったりするケースがあります。ボール、スペース、そして人というバランスが崩れた時、失点のピンチが訪れます。
湘南のスローインからでした。スローインよりも後ろ側の受け手に対して鳥栖は3人が上がってマーキングについています。更に、鳥栖は逆サイドのスペースを捨ててでも右サイドに人を寄せてスローインからのボールを奪おうとする体制をとっています。この状況でこのようなリスクを取る必要があったのかというのは一つの論点であるかと思います。あくまでスローインは相手ボールであるので、コントロールは湘南の配下にあるからここまで極端なシフトでボールを奪いに行く必要があるかという所です。案の定、スローインで投げられたボールに対してプレッシングをかけますが、奪う事が出来ずに逆サイドのスペースに展開されてしまいます。
そこからは、湘南の動きに翻弄されます。吉田一人で見なければならないのですが、ひとまずラインを下げて、ペナルティエリア付近に来たのでボール保持者に対してプレッシングに入ります。吉田が空けたスペースに対して湘南の選手が入ってくるので、オマリがカバーリングでサイドバックの裏をケアします。問題はここからです。サイドバック、センターバックと動かされたのですが、それを誰がどうやってケアするのかというところにミスが発生しています。もちろん、カウンターという場面で非常に難しい状況なのですが、マッシモがこのチームを率いて3年目でもありますし、ましてや、吉田、原川、ミンヒョクはその指導を十分に受けてきたメンバーです。オマリが決して突拍子もない動きを見せたのではありません。こういう大事な状況で、マンマークでもない、ゾーン守備でもない、中途半端な守り方しかできない事が、不用意な失点を招き、その結果このような順位となっているのでしょう。失点の理由やミスの傾向にて同じような事を繰り返している事が、マッシモの指導者としての限界だったのかもしれません。無論、それはマッシモだけの責任ではなく、彼のやり方を選手が習熟できなかったのかもしれません。





この試合の後に、マッシモ解任の報が流れました。残りは5試合です。明輝さんもプレッシャーのかかる場面で重要な任務をよく引き受けてくれました。監督交代によって戦術的に急に改善することはないでしょうが、マンネリの打破、メンタル面の向上は期待できます。残り試合、選手もサポーターも共に前を向いて戦い、『全力に悔いなし』でシーズンを終えたいですね。
<画像引用元:DAZN>
鳥栖のセットアップは4-3-1-2。小野をトップ下に起用して湘南の3バックに対して前線からプレッシングをかける守備方式を採用しました。フォワードはチョドンゴンが久しぶりのスタメン復帰。ポストプレイとセンターバック脇のスペースに流れる役割ということで、度々攻撃の基点を作っていました。湘南のセットアップは3-4-1-2。両サイドの岡本、杉岡の上下動によってバランスをコントロールするのですが、攻撃時にはストッパーの大野や山根が前線まで顔を出すというまさに全員攻撃、全員守備のハードワークサッカーを展開していました。
鳥栖も湘南も序盤から相手の陣地まで押し込んでプレッシングをかけていました。鳥栖は小野も含めた前線の3人が湘南の3バックに対してプレッシングをかけ、サイドに追い込んだ上でセントラルハーフが湘南のビルドアップの出口を封鎖しました。秀人が湘南ボランチに対して積極的に追い込みをかけて、相手が最終ラインに下がってまでも執拗に追い込んで前を向かせない対応を取りにいく形もあり、この試合にかけるアグレッシブさを十分に感じさせてくれました。
対する湘南も、セカンドトップが1名前に出て山崎と共に鳥栖の両センターバックを捕まえることで、3-5-2の形に変化でき、高い位置をとろうとするサイドバックを中盤で捕まえて簡単にマッチアップの相手を作ることができたので、前からのプレッシングでキーパーまで戻させてロングボールを蹴らせることに成功していました。


湘南と鳥栖とどちらがイニシアチブを握るのかというポイントは、ロングボールに対する強さとセカンドボールの拾い方でした。互いにプレッシングが強烈でキーパーからのロングボールも多くなり、最後は空中戦という形になるのですが、山崎がミンヒョクやオマリに勝てる確率よりは、チョドンゴンが坂、大野、山根に勝てる確率の方が高く。また、湘南はトップの山崎に対してセカンドトップがセカンドボールを回収する形に対して、鳥栖はチョドンゴンに対して、金崎、小野+セントラルハーフがボールを回収する形になり、セカンドボールがこぼれる地点の数的密集度も鳥栖の方が回収しやすい形になっていました。ロングボールが軸でしたが、鳥栖がボールを握って押し込むことに成功し、湘南を完全リトリートさせることに成功させていたので、ボールを奪われてもトランジションでのプレスで奪い返したり、相手にクリアさせるだけの形を作れ、波状攻撃に繋げていました。
このタイミングで先制できれば良かったのですが、度重なるクロスでも、セットプレイでのチャンスでも得点できず。そうすると徐々に体力が落ちてきて、序盤は湘南がボールを握れない程に(前を向けない程に)強いプレスをかけていましたが、徐々に湘南がボールを回せるほどにプレッシングの強度が弱まってきます。
そうすると、湘南はボールロスト(ショートカウンター)のリスクが少しずつ下がってくるので、攻撃に手数をかけてきます。一番大きな特徴は、ストッパーの大野や山根をサイド攻撃に参画させたことでした。サイドで数的優位を作って、局面でのグループ単位の動きによって鳥栖の守備陣を翻弄します。特に、鳥栖の左サイドでは、原川と吉田のコンビネーションが合わないタイミング(ボール保持者に二人で寄せてしまったり、誰もボール保持者にプレッシャーをかけられなかったり)を見つけると、一気呵成に崩しにかかります。誰かが動いて作ったスペースを次の人間が使う。そこでまた鳥栖の人間が動いてできたスペースを他のメンバーが使うという、三段論法のような形で鳥栖のスペースに次々と人が入りこんでいました。




一方、鳥栖の攻撃は、グループ戦術という点では、やはり個人のアイデアに依存している形でした。下記のシーンを見て欲しいのですが、秀人が中央でボールを持って、中央に吉田が入ってくるのですが湘南守備陣を動かすこともできず、ボールは出てこず。金崎にボールを預けて秀人が縦のスペースを狙うがボールは出てこず。福田がサイドから中央に入って湘南のディフェンスを1人動かしますが、金崎は突破できず、そして福田にもボールは出らず。ポジショニングを守るならば、吉田は大外にいた方がフリーで受けられるチャンスもありますし、湘南のディフェンスを一人引き付けることもできます。みんなが中央に集まってくるので、湘南のディフェンスも中央に集まってきて交通渋滞が発生し、シュートを打てるスペースもできません。




個人のアイデアはあって、いろいろと動かそうとするのですが、それがアイデアを共有した上でのグループとしての動きになっていないので、ひらめきの意思がたまたまあった時にしか、有効な攻撃に繋がりません。その時々で、出す人、受ける人、犠牲になる人が変わるので、どう動いて良いのか分からずに気が付けば動き出しが遅れます。せっかく藤田が縦のパスに抜けてクロスを上げようとしたら、そこに金崎まで来てしまってボールに触ってオフサイドになったシーンは、役割が整理できていないという典型的な現象です。
スペースを見つけて動くのは、大事なことですが、そのスペースを使う事を周りが理解していなければ意味がありません。クロスをあげるときも、縦に突破してあげたり、一旦足を持ち替えてあげたりして、中央で待ち構える人間とタイミングがずれるため、なかなかピンポイントで味方に合いません。押し込んでいるようで、決定的なシュートに繋がらないもどかしさは常々感じました。
失点シーンは、これまでも当Blogで指摘してきた崩され方であり、マッシモがどうしても修正できなかった部分です。鳥栖の守備陣は個に強い反面、その個の力がありすぎるが上に、ボールや相手選手へのプレッシャーに寄ってしまう傾向にあります。スペースを守らなければならないところでも相手選手に引きずられて奪いに行ってしまうので、気が付けば相手がフリーになったり、すっぽり空いてしまったりするケースがあります。ボール、スペース、そして人というバランスが崩れた時、失点のピンチが訪れます。
湘南のスローインからでした。スローインよりも後ろ側の受け手に対して鳥栖は3人が上がってマーキングについています。更に、鳥栖は逆サイドのスペースを捨ててでも右サイドに人を寄せてスローインからのボールを奪おうとする体制をとっています。この状況でこのようなリスクを取る必要があったのかというのは一つの論点であるかと思います。あくまでスローインは相手ボールであるので、コントロールは湘南の配下にあるからここまで極端なシフトでボールを奪いに行く必要があるかという所です。案の定、スローインで投げられたボールに対してプレッシングをかけますが、奪う事が出来ずに逆サイドのスペースに展開されてしまいます。
そこからは、湘南の動きに翻弄されます。吉田一人で見なければならないのですが、ひとまずラインを下げて、ペナルティエリア付近に来たのでボール保持者に対してプレッシングに入ります。吉田が空けたスペースに対して湘南の選手が入ってくるので、オマリがカバーリングでサイドバックの裏をケアします。問題はここからです。サイドバック、センターバックと動かされたのですが、それを誰がどうやってケアするのかというところにミスが発生しています。もちろん、カウンターという場面で非常に難しい状況なのですが、マッシモがこのチームを率いて3年目でもありますし、ましてや、吉田、原川、ミンヒョクはその指導を十分に受けてきたメンバーです。オマリが決して突拍子もない動きを見せたのではありません。こういう大事な状況で、マンマークでもない、ゾーン守備でもない、中途半端な守り方しかできない事が、不用意な失点を招き、その結果このような順位となっているのでしょう。失点の理由やミスの傾向にて同じような事を繰り返している事が、マッシモの指導者としての限界だったのかもしれません。無論、それはマッシモだけの責任ではなく、彼のやり方を選手が習熟できなかったのかもしれません。





この試合の後に、マッシモ解任の報が流れました。残りは5試合です。明輝さんもプレッシャーのかかる場面で重要な任務をよく引き受けてくれました。監督交代によって戦術的に急に改善することはないでしょうが、マンネリの打破、メンタル面の向上は期待できます。残り試合、選手もサポーターも共に前を向いて戦い、『全力に悔いなし』でシーズンを終えたいですね。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
12:41
│Match Impression (2018)
2018年10月03日
2018 第28節 : コンサドーレ札幌 VS サガン鳥栖
2018年第28節、コンサドーレ札幌戦のレビューです。
鳥栖のセットアップは攻撃時に4-4-2、守備時に5-3-2をベースとした戦い。ミドルサードでは、前にプレスをかけられるタイミングで安在が出ていきます。プレッシングがはがされてディフェンシブサードに入られると安在を藤田の外側にリトリートさせて5-3-2ブロックという形です。
最終ラインを5名でセットアップしているので、1人を飛び出させても後ろを守る人数が確保されるので、ジェイがトップの位置から降りて受けようとする動きに対して鳥栖はオマリや裕治がついていきます。



札幌のセットアップは3-4-2-1のような形ですが、攻撃時にはセンターバック2名が幅を取ってビルドアップの出口を作り、ボランチ2名がラインを下げてボール保持のヘルプを行います。機を見た福森のオーバーラップ(進藤も時折来ていましたね)という、3列目から飛び出してくる選手をなかなか捕まえきれずに苦労していました。
鳥栖はとにかく守備の基準点探しに苦労していました。チームオーダーは前からのプレッシングで高い位置からのショートカウンターだったかと思われますが、札幌のポジションチェンジが頻繁で、人を捕まえるのに苦労していました。
札幌3-4ビルドアップに対して、鳥栖は2-3で捕まえに行こうとしますが、根本的に数が足りていないので簡単に間のスペースをつかれて抜け口を作られてしまっていました。プレスのスイッチングをどこにおいていたのかもいまいち不明瞭で、トップが行くポイントが前であったり中央であったり。タイミングが計れないので、せっかく前から行っても中盤から後ろが遅れて捕まえにいってしまい、札幌に簡単にスペースと空いている人間を使われるケースが多く見られました。
マンマークではないので、ビルドアップ成功後に札幌センターバックがオーバーラップしても、フォワードが下がるわけではありません。前から行っても人数不足、攻め込まれても人数不足。どこに行っても札幌の選手ばかりな上に簡単にスペースを使われる。サッカーは選手のネームバリューではなく、やはり監督の戦術と選手たちの実行能力が大事だという事がよく分かる試合展開でした。


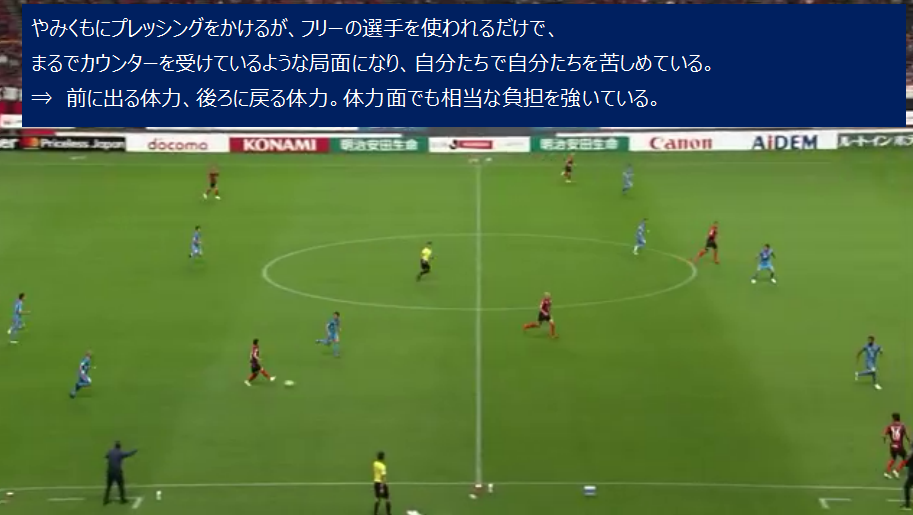
前線からのプレッシングにもっと人数をかける必要があると判断した鳥栖は、安在と吉田に管と早川をマンマーク気味に捕まえさせ、数的同数でプレスをかけようとします。そうなると、札幌は簡単にジェイに向かって蹴っ飛ばします。前からプレスをかけてビルドアップを無効化したと思っても、蹴っとばされた先に待ち構えるのはジェイ。鳥栖にとっては地獄のような展開です(笑)
前から行ったときに蹴られると、中央のスペースが大きく空いて札幌セカンドトップがセカンドボールを取得できる確率が高くなります。ジェイに向かって蹴られるボールでオフサイドを取れる程大胆なラインコントロールもできておらず、この試合ではやりかった守備は実現できなかったかと思われます。
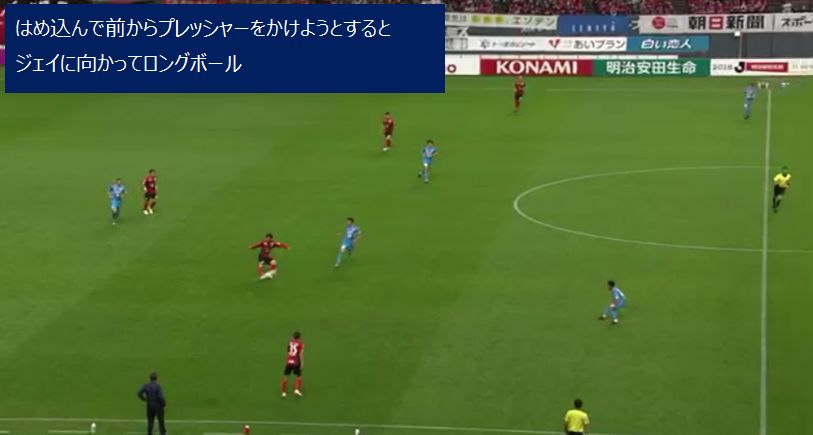
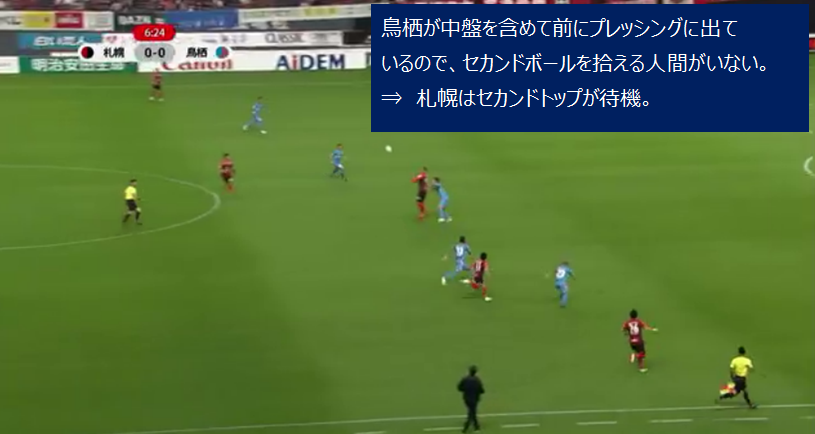
こうして、前から行ってもはがされる、気が付けばロングボールが飛んでくる、駒井も三好も福森も菅も裏に抜けようと迫ってくる、前線、中盤、最終ラインが守備でどこにポイントをおいたらよいのかよくわからない、そうこうするうちに体力がばかりが削られていく。これらのコンボによって、鳥栖はライン間が空いてしまって札幌が攻撃するには十分なスペースを与えてしまっていました。

前線からのプレッシングが機能しなかった事に輪をかけて、攻撃と守備との可変システムそして選手起用も選手たちの混乱を生むのに十分でした。札幌は最終ライン3人ビルドアップのため、同数にあわせようとするとツートップに対してあと1人鳥栖の選手が必要となります。そこで小野がプレッシングにでるのですが、そこをかわされた後に鳥栖が後ろ5枚にしてしまうので、小野が出ていき、安在が下がりという形で中盤がスカスカの状態となります。ジェイにとっては格好のエサでありまして、そのスペースで自由奔放にボールを受ける事ができていました。また、攻撃に特化した選手である小野の起用も守備面で影響があり、スペースを埋めるとか、対人マークに強いとか、守備に特化した選手ではないので、危機察知能力は正直言って低いです。守備時にセントラルハーフの役割を与えるメンバーとして果たして小野のアサインメントが適切だったのか。マッシモの選手起用の神髄がどこにあったのかが知りたい所です。




鳥栖の可変システムは、トランジション時の過渡期対応でも苦労していました。ポジティブトランジションで安在が上がろうとするときに(5-3-2から4-4-2に変えようとするときに)ボールを奪われると、ポジショニングの混乱によって生じるスペースを札幌に与えてしまいます。特に、藤田と安在の関係が複雑(藤田:守備時ストッパー、攻撃時サイドバック、安在:守備時ウイングバック、攻撃時サイドハーフ)だったので、役割を変更しようとした矢先に札幌に奪いかえされると、自分たちではどうしようもないスペースを札幌に与えてしまっていました。これは選手個人の責任ではなく、チーム戦術によって与えてしまったスペースです。


鳥栖が、勝手に自滅してくれたおかげで、札幌はワントップ+セカンドトップが鳥栖のスペースができることを予知できるようになり、ジェイ、駒井、三好が中央のスペースで大いに躍動しておりました。また、彼らが動けるスペースを作るのに貢献したのが、センターバックのオーバーラップです。福森、進藤が飛び出していくことによって鳥栖のセントラルハーフを引き連れていく動きを見せていました。引き連れていって空いたスペースを札幌が上手につかっていました。



もちろん、時折札幌のミスは発生していました。ただし、それは鳥栖の守備によって予見できたミスではなく、偶発的に起きるミスによって得られたボールでしたのでなかなか攻撃につなげることができませんでした。ボールを奪うと同時に安在が高い位置をとりに前進し、小野が幅を取るためにサイドに広がりますが、確実に、ポジションを取るためのタイムラグが発生します。カウンターで安在がフォローに入れる位置に行くまで、いつものように金崎や小野の単騎突破に頼ることになります。


鳥栖はここ数試合を見ても、小野と金崎が交通渋滞を起こしているのがわかります。サイドで起点を作ろうとして、2人ともサイドに来てしまって、クロスを上げる時にゴール前にいないという状況が試合を重ねても何回も発生しています。
選手間のコンビネーションプレーが少なく、つぶされるケースが今回も目立ちました。トーレスはファーに逃げる動きもありますが、ボール保持している選手に近寄ってボールを受けてくれる動きを見せてくれます。しかしながら、近寄った時に使おうとするパスがほぼありません。ワンツーで抜けようとする発想もありません。トーレスに預けると、同点ゴールのきっかけとなったようなパスを送ってくれる選手です。藤田へのパスが同点ゴールを決めたと言っても過言ではありません。辛辣な言葉を書きますが、世界で有数の一流プレイヤーのトーレスがチームメイトを上手に使う効果的なパスを送るのに、世界に行っても活躍できなかった金崎や小野の単騎突破にかける攻撃が果たして本当に効果的なのでしょうか。監督の意向はそれでよいのでしょうか。攻撃に関する約束事は果たしてこのチームに存在するのだろうかと不安に思います。
札幌戦は、小野・金崎がサイドに出てきて相手の選手を引き連れてくるよりは、ウイングバックの安在、吉田が相手と1VS1の機会を作って交わしてクロスを上げるという形がチャンスになっていました。金崎、小野が動きすぎてサイドに出てくるよりは、中央で相手選手をピン止めしてくれたが、サイドの交通渋滞がなくなり、安在と吉田が1VS1で相手ウイングに挑める機会も作れます。その状況を生み出したならば安在も吉田も十分にひとりかわしてクロスを送れる選手です。この形をしつこく続ければ良かったのですが、前線が自由すぎて、形を作ることができません。チームとしてどこにポジションを取って相手をどう誘導するかという形を作らない限りは、セットプレイなどに限定された得点チャンスしか生まれないでしょう。



戦術的要素で完全に後塵を拝していたので、鳥栖は前からのプレッシングを捨てるという手を打つのも一つの選択として必要だったかもしれません。ノープレッシャーでボールを保持できるようになると、福森や進藤があがってきますので、ボールを奪って電光石火のカウンターを放つためのスペースを作ることができます。ツートップの一角は田川。起点は1人で良いので、トーレスもしくは金崎。パスセンスを考えるとトーレスの方が良いと思います。トーレスから田川へのパスがあっても、田川からトーレスへのリターンがかえってくるかはわかりませんが(笑)
先制点は、これまでの鳥栖の対応の不味さをついにつかれてしまった形でした。前線へのプレスが整理されていないので、プレッシングの相手が固まらないまま小野が中途半端に出てしまい、そしてビルドアップで抜けられても小野が中央に戻らずにスペースを空けてしまいます。ジェイがそのスペースをうまく使い、駒井と三好の効果的な飛び出しでついに失点してしまいました。権田がPKセーブしてくれましたが、フィールドプレイヤーは何度も同じ形で崩されてしまっており、権田の頑張りに報いる事ができませんでした。





勝ち越しのシーンも同様です。リスクを負って前にでていったかもしれませんが攻撃にアイデアがないので、やみくもにボールを蹴ってボールロストしてしまいます。選手たちが戻って来れない中、札幌は鳥栖が与えるスペースを効果的に利用して、体力的に万全の都倉と疲労困憊の祐治の1VS1のシーンを作られてしまいました。選手交替の使い方も、ミシャとマッシモとの格の違いを見せつけられたかのようでした。


札幌の攻撃は、将棋でいう所の数手先までは簡単に読んでいました。人を動かせば鳥栖の守備がこうなるという事を理解したかのようにスペースにダイレクトにボールが入っていきます。鳥栖はまったく相手の動きが読めていませんでした。チーム完成度の差、順位の差、まざまざと見せつけられました。
鳥栖の攻撃には、柏の瀬川、札幌の駒井、三好のように気の利いた、チームの為に「戦術的に」「有効な」プレイをする選手が見当たりません。選手個々は頑張っているのですが、その頑張りがチグハグで報われないのが気の毒でしょうがありません。選手個々の質は高いので、なんとか残り試合で少しでも改善することを願います。残留の為には、下位チーム同士の試合で質の勝負に持ち込むしかないですね。
最後に。この試合は、終始札幌の戦術的戦いに押されっぱなしで、同点になった時点でどういったクロージングをするべきかを考えると、同点での勝ち点1でもOKという考えを持つべきではなかったかと考えます。それは確率の問題であって、試合の展開的に、鳥栖が勝ち越しゴールを奪うよりは、札幌が勝ち越しゴールを奪う確率が高かったからです。そのリスクを冒してでも冒険する価値があったかどうかは単なる結果論と言ってしまえばそれまでなのですが、失った勝ち点1が重くのしかからない事を願うのみです。
<画像引用元:DAZN>
鳥栖のセットアップは攻撃時に4-4-2、守備時に5-3-2をベースとした戦い。ミドルサードでは、前にプレスをかけられるタイミングで安在が出ていきます。プレッシングがはがされてディフェンシブサードに入られると安在を藤田の外側にリトリートさせて5-3-2ブロックという形です。
最終ラインを5名でセットアップしているので、1人を飛び出させても後ろを守る人数が確保されるので、ジェイがトップの位置から降りて受けようとする動きに対して鳥栖はオマリや裕治がついていきます。



札幌のセットアップは3-4-2-1のような形ですが、攻撃時にはセンターバック2名が幅を取ってビルドアップの出口を作り、ボランチ2名がラインを下げてボール保持のヘルプを行います。機を見た福森のオーバーラップ(進藤も時折来ていましたね)という、3列目から飛び出してくる選手をなかなか捕まえきれずに苦労していました。
鳥栖はとにかく守備の基準点探しに苦労していました。チームオーダーは前からのプレッシングで高い位置からのショートカウンターだったかと思われますが、札幌のポジションチェンジが頻繁で、人を捕まえるのに苦労していました。
札幌3-4ビルドアップに対して、鳥栖は2-3で捕まえに行こうとしますが、根本的に数が足りていないので簡単に間のスペースをつかれて抜け口を作られてしまっていました。プレスのスイッチングをどこにおいていたのかもいまいち不明瞭で、トップが行くポイントが前であったり中央であったり。タイミングが計れないので、せっかく前から行っても中盤から後ろが遅れて捕まえにいってしまい、札幌に簡単にスペースと空いている人間を使われるケースが多く見られました。
マンマークではないので、ビルドアップ成功後に札幌センターバックがオーバーラップしても、フォワードが下がるわけではありません。前から行っても人数不足、攻め込まれても人数不足。どこに行っても札幌の選手ばかりな上に簡単にスペースを使われる。サッカーは選手のネームバリューではなく、やはり監督の戦術と選手たちの実行能力が大事だという事がよく分かる試合展開でした。


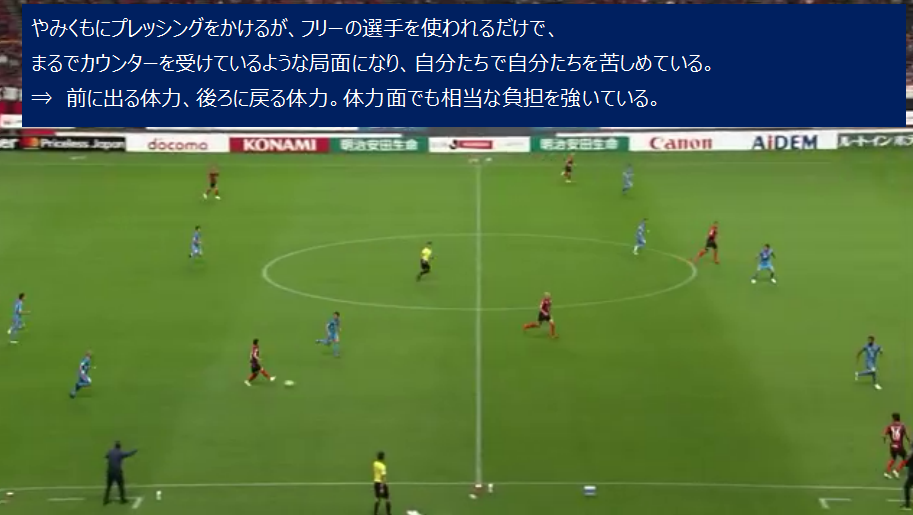
前線からのプレッシングにもっと人数をかける必要があると判断した鳥栖は、安在と吉田に管と早川をマンマーク気味に捕まえさせ、数的同数でプレスをかけようとします。そうなると、札幌は簡単にジェイに向かって蹴っ飛ばします。前からプレスをかけてビルドアップを無効化したと思っても、蹴っとばされた先に待ち構えるのはジェイ。鳥栖にとっては地獄のような展開です(笑)
前から行ったときに蹴られると、中央のスペースが大きく空いて札幌セカンドトップがセカンドボールを取得できる確率が高くなります。ジェイに向かって蹴られるボールでオフサイドを取れる程大胆なラインコントロールもできておらず、この試合ではやりかった守備は実現できなかったかと思われます。
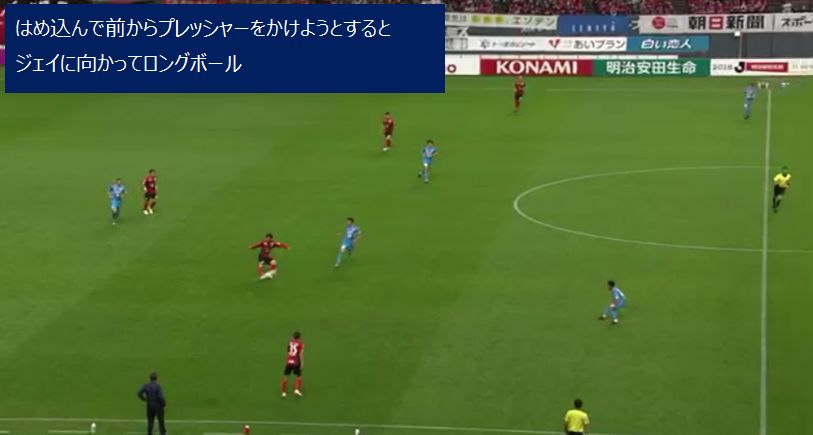
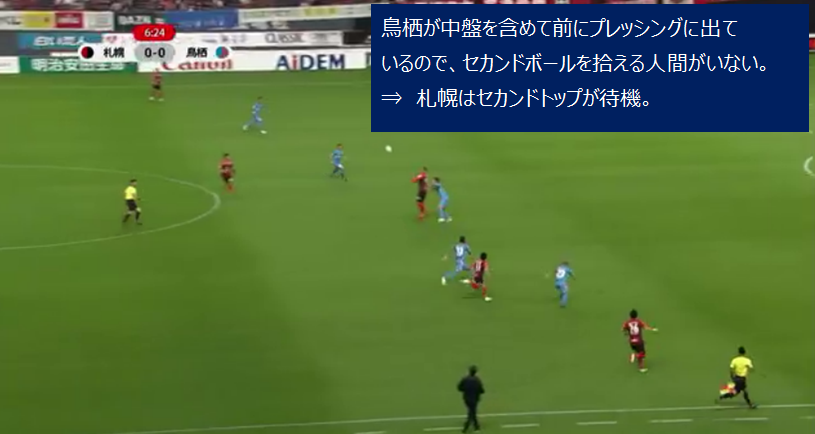
こうして、前から行ってもはがされる、気が付けばロングボールが飛んでくる、駒井も三好も福森も菅も裏に抜けようと迫ってくる、前線、中盤、最終ラインが守備でどこにポイントをおいたらよいのかよくわからない、そうこうするうちに体力がばかりが削られていく。これらのコンボによって、鳥栖はライン間が空いてしまって札幌が攻撃するには十分なスペースを与えてしまっていました。

前線からのプレッシングが機能しなかった事に輪をかけて、攻撃と守備との可変システムそして選手起用も選手たちの混乱を生むのに十分でした。札幌は最終ライン3人ビルドアップのため、同数にあわせようとするとツートップに対してあと1人鳥栖の選手が必要となります。そこで小野がプレッシングにでるのですが、そこをかわされた後に鳥栖が後ろ5枚にしてしまうので、小野が出ていき、安在が下がりという形で中盤がスカスカの状態となります。ジェイにとっては格好のエサでありまして、そのスペースで自由奔放にボールを受ける事ができていました。また、攻撃に特化した選手である小野の起用も守備面で影響があり、スペースを埋めるとか、対人マークに強いとか、守備に特化した選手ではないので、危機察知能力は正直言って低いです。守備時にセントラルハーフの役割を与えるメンバーとして果たして小野のアサインメントが適切だったのか。マッシモの選手起用の神髄がどこにあったのかが知りたい所です。




鳥栖の可変システムは、トランジション時の過渡期対応でも苦労していました。ポジティブトランジションで安在が上がろうとするときに(5-3-2から4-4-2に変えようとするときに)ボールを奪われると、ポジショニングの混乱によって生じるスペースを札幌に与えてしまいます。特に、藤田と安在の関係が複雑(藤田:守備時ストッパー、攻撃時サイドバック、安在:守備時ウイングバック、攻撃時サイドハーフ)だったので、役割を変更しようとした矢先に札幌に奪いかえされると、自分たちではどうしようもないスペースを札幌に与えてしまっていました。これは選手個人の責任ではなく、チーム戦術によって与えてしまったスペースです。


鳥栖が、勝手に自滅してくれたおかげで、札幌はワントップ+セカンドトップが鳥栖のスペースができることを予知できるようになり、ジェイ、駒井、三好が中央のスペースで大いに躍動しておりました。また、彼らが動けるスペースを作るのに貢献したのが、センターバックのオーバーラップです。福森、進藤が飛び出していくことによって鳥栖のセントラルハーフを引き連れていく動きを見せていました。引き連れていって空いたスペースを札幌が上手につかっていました。



もちろん、時折札幌のミスは発生していました。ただし、それは鳥栖の守備によって予見できたミスではなく、偶発的に起きるミスによって得られたボールでしたのでなかなか攻撃につなげることができませんでした。ボールを奪うと同時に安在が高い位置をとりに前進し、小野が幅を取るためにサイドに広がりますが、確実に、ポジションを取るためのタイムラグが発生します。カウンターで安在がフォローに入れる位置に行くまで、いつものように金崎や小野の単騎突破に頼ることになります。


鳥栖はここ数試合を見ても、小野と金崎が交通渋滞を起こしているのがわかります。サイドで起点を作ろうとして、2人ともサイドに来てしまって、クロスを上げる時にゴール前にいないという状況が試合を重ねても何回も発生しています。
選手間のコンビネーションプレーが少なく、つぶされるケースが今回も目立ちました。トーレスはファーに逃げる動きもありますが、ボール保持している選手に近寄ってボールを受けてくれる動きを見せてくれます。しかしながら、近寄った時に使おうとするパスがほぼありません。ワンツーで抜けようとする発想もありません。トーレスに預けると、同点ゴールのきっかけとなったようなパスを送ってくれる選手です。藤田へのパスが同点ゴールを決めたと言っても過言ではありません。辛辣な言葉を書きますが、世界で有数の一流プレイヤーのトーレスがチームメイトを上手に使う効果的なパスを送るのに、世界に行っても活躍できなかった金崎や小野の単騎突破にかける攻撃が果たして本当に効果的なのでしょうか。監督の意向はそれでよいのでしょうか。攻撃に関する約束事は果たしてこのチームに存在するのだろうかと不安に思います。
札幌戦は、小野・金崎がサイドに出てきて相手の選手を引き連れてくるよりは、ウイングバックの安在、吉田が相手と1VS1の機会を作って交わしてクロスを上げるという形がチャンスになっていました。金崎、小野が動きすぎてサイドに出てくるよりは、中央で相手選手をピン止めしてくれたが、サイドの交通渋滞がなくなり、安在と吉田が1VS1で相手ウイングに挑める機会も作れます。その状況を生み出したならば安在も吉田も十分にひとりかわしてクロスを送れる選手です。この形をしつこく続ければ良かったのですが、前線が自由すぎて、形を作ることができません。チームとしてどこにポジションを取って相手をどう誘導するかという形を作らない限りは、セットプレイなどに限定された得点チャンスしか生まれないでしょう。



戦術的要素で完全に後塵を拝していたので、鳥栖は前からのプレッシングを捨てるという手を打つのも一つの選択として必要だったかもしれません。ノープレッシャーでボールを保持できるようになると、福森や進藤があがってきますので、ボールを奪って電光石火のカウンターを放つためのスペースを作ることができます。ツートップの一角は田川。起点は1人で良いので、トーレスもしくは金崎。パスセンスを考えるとトーレスの方が良いと思います。トーレスから田川へのパスがあっても、田川からトーレスへのリターンがかえってくるかはわかりませんが(笑)
先制点は、これまでの鳥栖の対応の不味さをついにつかれてしまった形でした。前線へのプレスが整理されていないので、プレッシングの相手が固まらないまま小野が中途半端に出てしまい、そしてビルドアップで抜けられても小野が中央に戻らずにスペースを空けてしまいます。ジェイがそのスペースをうまく使い、駒井と三好の効果的な飛び出しでついに失点してしまいました。権田がPKセーブしてくれましたが、フィールドプレイヤーは何度も同じ形で崩されてしまっており、権田の頑張りに報いる事ができませんでした。





勝ち越しのシーンも同様です。リスクを負って前にでていったかもしれませんが攻撃にアイデアがないので、やみくもにボールを蹴ってボールロストしてしまいます。選手たちが戻って来れない中、札幌は鳥栖が与えるスペースを効果的に利用して、体力的に万全の都倉と疲労困憊の祐治の1VS1のシーンを作られてしまいました。選手交替の使い方も、ミシャとマッシモとの格の違いを見せつけられたかのようでした。


札幌の攻撃は、将棋でいう所の数手先までは簡単に読んでいました。人を動かせば鳥栖の守備がこうなるという事を理解したかのようにスペースにダイレクトにボールが入っていきます。鳥栖はまったく相手の動きが読めていませんでした。チーム完成度の差、順位の差、まざまざと見せつけられました。
鳥栖の攻撃には、柏の瀬川、札幌の駒井、三好のように気の利いた、チームの為に「戦術的に」「有効な」プレイをする選手が見当たりません。選手個々は頑張っているのですが、その頑張りがチグハグで報われないのが気の毒でしょうがありません。選手個々の質は高いので、なんとか残り試合で少しでも改善することを願います。残留の為には、下位チーム同士の試合で質の勝負に持ち込むしかないですね。
最後に。この試合は、終始札幌の戦術的戦いに押されっぱなしで、同点になった時点でどういったクロージングをするべきかを考えると、同点での勝ち点1でもOKという考えを持つべきではなかったかと考えます。それは確率の問題であって、試合の展開的に、鳥栖が勝ち越しゴールを奪うよりは、札幌が勝ち越しゴールを奪う確率が高かったからです。そのリスクを冒してでも冒険する価値があったかどうかは単なる結果論と言ってしまえばそれまでなのですが、失った勝ち点1が重くのしかからない事を願うのみです。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
18:39
│Match Impression (2018)
2018年09月28日
2018 第27節 : 柏レイソル VS サガン鳥栖
2018年第27節、柏レイソル戦のレビューです。
鳥栖のセットアップは4-3-1-2。今節のスタメンは原川に変わって小野が入り、トップ下での起用となりました。柏のセットアップは4-4-2。攻撃時には、瀬川と大谷、小泉がポジションを上下させて4-5-1や3-6-1のような形を作り、鳥栖の守備陣を巧に揺さぶっていました。
鳥栖は序盤から積極的にプレッシャーをかけて前線からボールを奪おうという動きを見せます。プレッシャーをかけるトリガーとなったのは小野の動き。ビルドアップ時にセンターバックのフォローで列を下げる大谷(もしくは小泉)について行きます。しかしながら、トーレス・金崎と連携がいまひとつ合わず。奪うポイントとタイミングがずれるケースが多くてプレッシングが機能しない場面が目立ちました。柏の2センター+ボランチの3人でのビルドアップに対し、鳥栖がツートップ+トップ下の3人での同数プレスを試みますが、柏はゴールキーパーを使って迂回したり、セントラルハーフの押し上げが足らずに簡単に縦に通されたり、全体の連動性にかけてプレッシングが機能するシーンを多く作ることができませんでした。
柏サイドバックの高木、小池があまり高い位置を取っていなかったというところも鳥栖が選択しなければならない状況を生みました。中盤の位置で構えるサイドバックに対して、インサイドハーフの義希と福田が気にしなければならず、アンカーの秀人との距離感が広くなりがちでした。柏はそのスペースに対して瀬川が2列目まで下がってボールを引き出していました。鳥栖の守備組織は、柏にゴールキーパーを使われたり、フォワードの選手が下がって使われたりと、局面、局面で数的不利に陥るケースが多かったです。柏はビルドアップの出口をしっかりと確立することによって鳥栖の2列目までの突破は困難ではなく、比較的簡単にボール保持することができていました。





柏はビルドアップのみならず、カウンター攻撃の際も瀬川が中盤のスペースを有効活用していました。ボールを奪うと瀬川が基点となるべく秀人の脇のスペースにボールを受けるように顔を出していました。柏のカウンターは役割分担が簡単に整理されていました。
・ 瀬川は引いて受ける
・ オルンガは中央に張る
⇒ センターバックをピン止めする
・ 伊東とクリスティアーノはサイドから前線に飛び出す
単純にこの動きを繰り出すカウンターだったのですが、鳥栖に脅威を与えるには十分迫力があり、チャンスビルディングとしては可能性のあるものばかりでした。最終ラインの踏ん張りによって何とか自由にシュートを打たれるところまでは至っていませんでしたが、引いてボールを受け、そして前線に飛び出す瀬川の活発な動き…スペースがあるところをしっかりと使うという基本的な動きで、鳥栖の守備陣を大いに攪乱していました。




守備が機能していなかった鳥栖は、ほどなくしてシステムを4-4-2に変え、中央のスペースに入ってくる瀬川に対しては義希が面倒を見るという形でやや中盤が落ち着きます。ただ、4-4-2に変えるという事はプレッシング対象が変わるという事になるのですが、その切り替えがなかなかスムーズに行きません。中盤から後ろは引いているにも関わらず、ツートップの二人が前から行ってしまうという事態が発生し、結局は4-3-1-2の時と同じく第1列目は簡単に突破されてしまうというところの改善には至っていませんでした。4-3-1-2と4-4-2の違いは、第1列目が突破されたときに後ろが4-3ブロックか4-4ブロックかという違いだけであり、試合を通じて、柏のいなしに対して前線からのプレッシングが機能していないというなかなか厳しい戦いでした。特に、柏は、キーパーを利用したビルドアップで上手に迂回路を作っていました。事前に調べた所ではキーパーをあまり利用しないと聞いていたのですが…スカウティングミスです(笑)


4-4-2にしたタイミングであったかは定かではないのですが、サイドバックのポジショニングにいつもと変化がありまして、サイドからの攻撃の際に、逆サイドのサイドバックがやや中央にポジションを移し、恐らく瀬川へのパスコース(スペース)を消すという動きを見せていました。三丸、藤田、両サイドバックともそのような動きを見せていたので、おそらくマッシモの指示なのでしょう。特に藤田は、中央にいるケースが多くなっていました。画面越しで映ったタイミングでしか見れないのでもう少しサイドバックのポジションの取り方を見てみたい所でした。こういう動きは、現地で見るからこそよく分かるもので、やっぱりサッカーはスタジアム観戦で面白さが何倍にもなります。


さて、4-3-1-2システムでのプレッシングがうまく機能していなかった鳥栖ですが、裏返しとしては3人が前線に残るのでカウンターにかける人数が多くなるという利点もあります。この試合では、金崎を基点とすることで統一されていた模様で、鳥栖の攻撃は金崎が受けて彼が受け手となるケースが多くみられました。しかしながら、金崎がボールを受けてから先のデザインが統一されていなかったのか、もしくは具現化出来ていなかったのか、どちらにしても、金崎の単騎突破にかけるという個人の質に頼った攻撃(それでも十分怖いのですが)に終始していました。金崎はその期待に応えて、サイドでボールを受けて前を向いて突破を図ってファールを受けるというチャンスビルディングは出来ておりまして、特に前半は、サイドでフリーキックによるチャンスを得る機会が多くありました。




ただし、単騎突破での攻撃は、パスのこぼれ球という可能性がないため、なかなかセカンドボールを拾った二次攻撃に繋がりません。また、鳥栖の中盤より後ろの選手たちのカウンターで上がるタイミングが各々のセンスに任されているような感じで、なかなか判断の良いパスというのを引き出すことができませんでした。金崎が右サイドをドリブルで駆け上がって、中央に福田がいるのに!と思ってもパスが来ないでドリブルを継続してしまったのは、「インサイドハーフがフォローに来るはず」という概念がないからでしょうか。金崎にボールを預けたタイミングで多くはトーレスがファーサイドに離れていくのですが、かといって最後にトーレスを使おうということで統一されているわけでもなさそうですし。カウンター攻撃の際に、小野、トーレスに何を求めるのか、更に2列目、3列目に何を求めるのかというところが柏の統一感に比べると鳥栖は少し見えづらく、カウンターが「フレキシブルな対応」になっており、相手の状況によって成否が決まるのではなく、自分たちの質で成否が決まるという形でした。
鳥栖としては大谷が非常に厄介な存在でありまして、金崎やトーレス経由という攻撃が多かったので、ややマンマーク気味に守備布陣を引いていた柏にとっては入ってくるボールが読みやすかったのかもしれません。ことごとく大谷のインターセプトにあっていました。大谷の素晴らしいところは、奪ったボールを素早く展開するという判断に優れておりまして、幾度となくボールカットから素早いカウンターの起点となるボールをオルンガや瀬川に配球していました。これも、オルンガ、瀬川がここにいるという事が統一されているので、ボールを素早く送ることができます。



さて、上記を踏まえて、鳥栖と柏の非常に好対照で印象的だったシーンを紹介します。
柏センターバックの鈴木がボールを保持しているところに対して鳥栖は前線の3人がプレッシャーをかけますが、柏はゴールキーパーを経由した迂回路を利用してパクまでボールを渡します。そしてパクがそのまま中盤までボールを運びます。パクがボールを運ぶという行為は、カウンターのスペースづくりのために意図的にパクをゴール前から引っ張り出しているならば戦術的要素があるのですが、トーレスの慌てた追い方を見るとそうではないでしょう。パクはクリスティアーノにつないで戻ってきたボールをハーフスペースに降りてくる選手を利用して前進しようとするのですが、そのパスが精度を欠いて鳥栖がボールを奪いました。鳥栖のポジティブトランジション(柏のネガティブトランジション)です。
ここで重要な要素は紛れもなく「センターバックのパクが飛び出している」という状況で、そのスペースはカウンター攻撃として、確実に利用できるスペースです。鳥栖にとっては、吉田やミンヒョクの飛び出しによって散々相手に利用されてきた苦々しいスペースでもあります(笑)鳥栖は、このスペースを活用するべく藤田が飛び出していきます。しかしながら、義希からボールを受けた秀人が選択したパスは中央で構える金崎へのパスでした。金崎に対しては柏の選手がついているので、簡単に囲まれてボールを奪われてしまいます。せっかくパクが空けてくれたスペースに藤田が飛び出していったのですが、そのスペースを利用するまでにも至らず、鳥栖のカウンターのチャンスは早々に消失してしまいました。


今度は柏のポジティブトランジション(鳥栖のネガティブトランジション)です。柏はデザインされたカウンターの通りに、ボランチとインサイドハーフの間のスペースで瀬川が受け、オルンガ、クリスティアーノが鳥栖の最終ラインを引っ張るうごきで瀬川のドリブルコースを作ってシュートまで持って行かれてしまいました。


この場面は、いろいろと考えさせられる場面なのですが、柏のカウンターは、瀬川を経由するという戦術と鳥栖のスペースの空き具合がハマっていたので、カウンター戦術(カウンターデザイン)が機能していたということになります。鳥栖のカウンターは、金崎を基点にするというデザインだったとすると、秀人のパスはマッシモの戦術通りのパスですが、相手の守備ブロックの中に飛び込んでいく形になっているので戦術として機能していません。
センターバックのパクが飛び出しているという状況は、鳥栖としては有効に使えるスペースであり、センターバックが飛び出してきているという事をチームとして理解できていれば、藤田の飛び出しを簡単に使っていたのではないかとも思います。ただ、もしかしたら藤田の飛び出しはチームとして与えられていない行動(藤田の判断による飛び出し)なので、チームにとっては想定外の出来事であり、判断が遅れて彼を活用できなかったのかもしれません。分析の対象としては非常におもしろいです。答えが分からないことだけが難点ですが(笑)
カウンターはビルドアップによる攻撃よりも判断のスピードが要求される攻撃なので、どのように展開するか、誰をつかって行くのかというところにおいてチームとしての共通意識がより必要です。この場面も、このスペースに飛び出すという事が、どれだけ想定で来ていたか、そのプレイモデルが彼らの頭の中に入っていたかというところです。鳥栖のカウンターでは、よほどのことがない限りインサイドハーフが飛び出していくというプレイを見ないので、カウンターは3人(トーレス、金崎、小野)で完結させなさいというオーダーが出ているのではないかとは感じていますがどうなのでしょうか。
鳥栖は、トーレスが下がることもあれば、ロングボールに待機することもある(上下の動き)、金崎は左にいる事もあれば右にいる事もある(左右の動き)、ボールキープするツートップの動きの質としては素晴らしいのですが、中盤の選手としては、パスの配球の際に彼らを探すというワンクッションが入ってしまいます。これは正直言って天秤ですよね。今回の柏みたいに、前線の動きと相手が空けるスペースがハマってしまった場合は、カウンター攻撃が機能します。鳥栖のようにアンカー脇やサイドバックの裏にスペースを空けないチームに対して柏が同じ攻撃をしても、もしかしたら機能しないかもしれません。そこは監督の腕の見せ所ですよね。
今回の鳥栖で機能しなかった事があと一つありまして、それは「困った時のロングボール」で常に相手よりも優位に立っていたトーレスがロングボールでも劣勢に立たされてしまったことです。パクと鈴木に競り負けるケースが多く、なかなか優位に進める事ができませんでした。トーレスが今節は早めに豊田へと交替したのも、ロングボールを支配できていなかったという点もあるでしょう。ただ、ロングボールに競り勝てなかったのはトーレスだけの問題ではなく、いつもピンポイントでボールを配球していた権田のコントロールがいまひとつ調子が悪く、鳥栖の選手がいないところの蹴ってしまうことも多々ありました。失点シーンのきっかけも権田の配球がトーレスよりもはるか手前に落ちてしまって弾き返されたところから始まります。
セカンドボールが柏に落ち着き、オルンガにボールが入ったところで前を向かせないためにオマリがマークに入ります。そのタイミングで、小池がインナーラップをかけて前線に飛びだす動きを見せていました。オマリが上がって来たスペースを積極的に利用しようとする動きです。ここでオマリがボールをひっかけるのですが、鳥栖にとって不運だったのは、ひっかけたボールが大谷の前に転がってしまいました。ここで大谷の判断が素晴らしく、スペースめがけて入ってくる小池に対してダイレクトでパスを送り込みます。先ほど、藤田の上りを利用できなかった鳥栖ですが、柏は小池の上りを即座に利用しました。鳥栖にとっては、オマリがあけたスペースのケアが準備できていないままに電光石火でボールを送られた感覚でしょう。大谷、小池、そしてゴール前に飛び込んできた瀬川。今回の柏の良い所が一気に終結した形でのゴールでした。


最後に、今節も安在が途中出場で非常に良い動きを見せてくれましたね。彼が入ってからシステムが前節と同じく3-5-2となったのですが、安在の右サイドウイングとしての動きは、カットインしてから左足でゴールに向かうアーリークロスを蹴れます。これがファーサイドに逃げるトーレスに対して左足でのキックならではの巻いてゴールに向かうクロスとなって好機も演出しました。当然、カットインしてからのシュートもありますし、ドリブル突破してからの右足のクロスも出来るので、ウイングタイプで利用できる貴重な選手です。安在はハードワークも出来ますし、質的に優位に立つことも出来るので、もっと活用してほしいですね。タイプ的にはキムミヌと同じような気がします。
さて、聞けば、オルンガは初先発、大谷は久しぶりの先発で、鈴木は戻ってきてやっとフィットしてきたという、なぜ鳥栖にターゲットを絞ったのかと恨み節を言わざるを得ない程の試合でございました(笑) そこまで多くの約束事は与えられていなかったでしょうが、守備では「人を捕まえる」攻撃では「スペースを利用する」という最低限果たすべき意思疎通はチーム全体に浸透していたと思います。何度もシステムとポジション変更を繰り返す鳥栖とは対照的でしたね。
ただ、このように状況的には芳しくない中で得られたこの勝ち点1は非常に大きいです。結果的に順位が入れ替わることもなかったですし。権田のセービングに感謝しなければならない試合でした。
<画像引用元:DAZN>
鳥栖のセットアップは4-3-1-2。今節のスタメンは原川に変わって小野が入り、トップ下での起用となりました。柏のセットアップは4-4-2。攻撃時には、瀬川と大谷、小泉がポジションを上下させて4-5-1や3-6-1のような形を作り、鳥栖の守備陣を巧に揺さぶっていました。
鳥栖は序盤から積極的にプレッシャーをかけて前線からボールを奪おうという動きを見せます。プレッシャーをかけるトリガーとなったのは小野の動き。ビルドアップ時にセンターバックのフォローで列を下げる大谷(もしくは小泉)について行きます。しかしながら、トーレス・金崎と連携がいまひとつ合わず。奪うポイントとタイミングがずれるケースが多くてプレッシングが機能しない場面が目立ちました。柏の2センター+ボランチの3人でのビルドアップに対し、鳥栖がツートップ+トップ下の3人での同数プレスを試みますが、柏はゴールキーパーを使って迂回したり、セントラルハーフの押し上げが足らずに簡単に縦に通されたり、全体の連動性にかけてプレッシングが機能するシーンを多く作ることができませんでした。
柏サイドバックの高木、小池があまり高い位置を取っていなかったというところも鳥栖が選択しなければならない状況を生みました。中盤の位置で構えるサイドバックに対して、インサイドハーフの義希と福田が気にしなければならず、アンカーの秀人との距離感が広くなりがちでした。柏はそのスペースに対して瀬川が2列目まで下がってボールを引き出していました。鳥栖の守備組織は、柏にゴールキーパーを使われたり、フォワードの選手が下がって使われたりと、局面、局面で数的不利に陥るケースが多かったです。柏はビルドアップの出口をしっかりと確立することによって鳥栖の2列目までの突破は困難ではなく、比較的簡単にボール保持することができていました。





柏はビルドアップのみならず、カウンター攻撃の際も瀬川が中盤のスペースを有効活用していました。ボールを奪うと瀬川が基点となるべく秀人の脇のスペースにボールを受けるように顔を出していました。柏のカウンターは役割分担が簡単に整理されていました。
・ 瀬川は引いて受ける
・ オルンガは中央に張る
⇒ センターバックをピン止めする
・ 伊東とクリスティアーノはサイドから前線に飛び出す
単純にこの動きを繰り出すカウンターだったのですが、鳥栖に脅威を与えるには十分迫力があり、チャンスビルディングとしては可能性のあるものばかりでした。最終ラインの踏ん張りによって何とか自由にシュートを打たれるところまでは至っていませんでしたが、引いてボールを受け、そして前線に飛び出す瀬川の活発な動き…スペースがあるところをしっかりと使うという基本的な動きで、鳥栖の守備陣を大いに攪乱していました。




守備が機能していなかった鳥栖は、ほどなくしてシステムを4-4-2に変え、中央のスペースに入ってくる瀬川に対しては義希が面倒を見るという形でやや中盤が落ち着きます。ただ、4-4-2に変えるという事はプレッシング対象が変わるという事になるのですが、その切り替えがなかなかスムーズに行きません。中盤から後ろは引いているにも関わらず、ツートップの二人が前から行ってしまうという事態が発生し、結局は4-3-1-2の時と同じく第1列目は簡単に突破されてしまうというところの改善には至っていませんでした。4-3-1-2と4-4-2の違いは、第1列目が突破されたときに後ろが4-3ブロックか4-4ブロックかという違いだけであり、試合を通じて、柏のいなしに対して前線からのプレッシングが機能していないというなかなか厳しい戦いでした。特に、柏は、キーパーを利用したビルドアップで上手に迂回路を作っていました。事前に調べた所ではキーパーをあまり利用しないと聞いていたのですが…スカウティングミスです(笑)


4-4-2にしたタイミングであったかは定かではないのですが、サイドバックのポジショニングにいつもと変化がありまして、サイドからの攻撃の際に、逆サイドのサイドバックがやや中央にポジションを移し、恐らく瀬川へのパスコース(スペース)を消すという動きを見せていました。三丸、藤田、両サイドバックともそのような動きを見せていたので、おそらくマッシモの指示なのでしょう。特に藤田は、中央にいるケースが多くなっていました。画面越しで映ったタイミングでしか見れないのでもう少しサイドバックのポジションの取り方を見てみたい所でした。こういう動きは、現地で見るからこそよく分かるもので、やっぱりサッカーはスタジアム観戦で面白さが何倍にもなります。


さて、4-3-1-2システムでのプレッシングがうまく機能していなかった鳥栖ですが、裏返しとしては3人が前線に残るのでカウンターにかける人数が多くなるという利点もあります。この試合では、金崎を基点とすることで統一されていた模様で、鳥栖の攻撃は金崎が受けて彼が受け手となるケースが多くみられました。しかしながら、金崎がボールを受けてから先のデザインが統一されていなかったのか、もしくは具現化出来ていなかったのか、どちらにしても、金崎の単騎突破にかけるという個人の質に頼った攻撃(それでも十分怖いのですが)に終始していました。金崎はその期待に応えて、サイドでボールを受けて前を向いて突破を図ってファールを受けるというチャンスビルディングは出来ておりまして、特に前半は、サイドでフリーキックによるチャンスを得る機会が多くありました。




ただし、単騎突破での攻撃は、パスのこぼれ球という可能性がないため、なかなかセカンドボールを拾った二次攻撃に繋がりません。また、鳥栖の中盤より後ろの選手たちのカウンターで上がるタイミングが各々のセンスに任されているような感じで、なかなか判断の良いパスというのを引き出すことができませんでした。金崎が右サイドをドリブルで駆け上がって、中央に福田がいるのに!と思ってもパスが来ないでドリブルを継続してしまったのは、「インサイドハーフがフォローに来るはず」という概念がないからでしょうか。金崎にボールを預けたタイミングで多くはトーレスがファーサイドに離れていくのですが、かといって最後にトーレスを使おうということで統一されているわけでもなさそうですし。カウンター攻撃の際に、小野、トーレスに何を求めるのか、更に2列目、3列目に何を求めるのかというところが柏の統一感に比べると鳥栖は少し見えづらく、カウンターが「フレキシブルな対応」になっており、相手の状況によって成否が決まるのではなく、自分たちの質で成否が決まるという形でした。
鳥栖としては大谷が非常に厄介な存在でありまして、金崎やトーレス経由という攻撃が多かったので、ややマンマーク気味に守備布陣を引いていた柏にとっては入ってくるボールが読みやすかったのかもしれません。ことごとく大谷のインターセプトにあっていました。大谷の素晴らしいところは、奪ったボールを素早く展開するという判断に優れておりまして、幾度となくボールカットから素早いカウンターの起点となるボールをオルンガや瀬川に配球していました。これも、オルンガ、瀬川がここにいるという事が統一されているので、ボールを素早く送ることができます。



さて、上記を踏まえて、鳥栖と柏の非常に好対照で印象的だったシーンを紹介します。
柏センターバックの鈴木がボールを保持しているところに対して鳥栖は前線の3人がプレッシャーをかけますが、柏はゴールキーパーを経由した迂回路を利用してパクまでボールを渡します。そしてパクがそのまま中盤までボールを運びます。パクがボールを運ぶという行為は、カウンターのスペースづくりのために意図的にパクをゴール前から引っ張り出しているならば戦術的要素があるのですが、トーレスの慌てた追い方を見るとそうではないでしょう。パクはクリスティアーノにつないで戻ってきたボールをハーフスペースに降りてくる選手を利用して前進しようとするのですが、そのパスが精度を欠いて鳥栖がボールを奪いました。鳥栖のポジティブトランジション(柏のネガティブトランジション)です。
ここで重要な要素は紛れもなく「センターバックのパクが飛び出している」という状況で、そのスペースはカウンター攻撃として、確実に利用できるスペースです。鳥栖にとっては、吉田やミンヒョクの飛び出しによって散々相手に利用されてきた苦々しいスペースでもあります(笑)鳥栖は、このスペースを活用するべく藤田が飛び出していきます。しかしながら、義希からボールを受けた秀人が選択したパスは中央で構える金崎へのパスでした。金崎に対しては柏の選手がついているので、簡単に囲まれてボールを奪われてしまいます。せっかくパクが空けてくれたスペースに藤田が飛び出していったのですが、そのスペースを利用するまでにも至らず、鳥栖のカウンターのチャンスは早々に消失してしまいました。


今度は柏のポジティブトランジション(鳥栖のネガティブトランジション)です。柏はデザインされたカウンターの通りに、ボランチとインサイドハーフの間のスペースで瀬川が受け、オルンガ、クリスティアーノが鳥栖の最終ラインを引っ張るうごきで瀬川のドリブルコースを作ってシュートまで持って行かれてしまいました。


この場面は、いろいろと考えさせられる場面なのですが、柏のカウンターは、瀬川を経由するという戦術と鳥栖のスペースの空き具合がハマっていたので、カウンター戦術(カウンターデザイン)が機能していたということになります。鳥栖のカウンターは、金崎を基点にするというデザインだったとすると、秀人のパスはマッシモの戦術通りのパスですが、相手の守備ブロックの中に飛び込んでいく形になっているので戦術として機能していません。
センターバックのパクが飛び出しているという状況は、鳥栖としては有効に使えるスペースであり、センターバックが飛び出してきているという事をチームとして理解できていれば、藤田の飛び出しを簡単に使っていたのではないかとも思います。ただ、もしかしたら藤田の飛び出しはチームとして与えられていない行動(藤田の判断による飛び出し)なので、チームにとっては想定外の出来事であり、判断が遅れて彼を活用できなかったのかもしれません。分析の対象としては非常におもしろいです。答えが分からないことだけが難点ですが(笑)
カウンターはビルドアップによる攻撃よりも判断のスピードが要求される攻撃なので、どのように展開するか、誰をつかって行くのかというところにおいてチームとしての共通意識がより必要です。この場面も、このスペースに飛び出すという事が、どれだけ想定で来ていたか、そのプレイモデルが彼らの頭の中に入っていたかというところです。鳥栖のカウンターでは、よほどのことがない限りインサイドハーフが飛び出していくというプレイを見ないので、カウンターは3人(トーレス、金崎、小野)で完結させなさいというオーダーが出ているのではないかとは感じていますがどうなのでしょうか。
鳥栖は、トーレスが下がることもあれば、ロングボールに待機することもある(上下の動き)、金崎は左にいる事もあれば右にいる事もある(左右の動き)、ボールキープするツートップの動きの質としては素晴らしいのですが、中盤の選手としては、パスの配球の際に彼らを探すというワンクッションが入ってしまいます。これは正直言って天秤ですよね。今回の柏みたいに、前線の動きと相手が空けるスペースがハマってしまった場合は、カウンター攻撃が機能します。鳥栖のようにアンカー脇やサイドバックの裏にスペースを空けないチームに対して柏が同じ攻撃をしても、もしかしたら機能しないかもしれません。そこは監督の腕の見せ所ですよね。
今回の鳥栖で機能しなかった事があと一つありまして、それは「困った時のロングボール」で常に相手よりも優位に立っていたトーレスがロングボールでも劣勢に立たされてしまったことです。パクと鈴木に競り負けるケースが多く、なかなか優位に進める事ができませんでした。トーレスが今節は早めに豊田へと交替したのも、ロングボールを支配できていなかったという点もあるでしょう。ただ、ロングボールに競り勝てなかったのはトーレスだけの問題ではなく、いつもピンポイントでボールを配球していた権田のコントロールがいまひとつ調子が悪く、鳥栖の選手がいないところの蹴ってしまうことも多々ありました。失点シーンのきっかけも権田の配球がトーレスよりもはるか手前に落ちてしまって弾き返されたところから始まります。
セカンドボールが柏に落ち着き、オルンガにボールが入ったところで前を向かせないためにオマリがマークに入ります。そのタイミングで、小池がインナーラップをかけて前線に飛びだす動きを見せていました。オマリが上がって来たスペースを積極的に利用しようとする動きです。ここでオマリがボールをひっかけるのですが、鳥栖にとって不運だったのは、ひっかけたボールが大谷の前に転がってしまいました。ここで大谷の判断が素晴らしく、スペースめがけて入ってくる小池に対してダイレクトでパスを送り込みます。先ほど、藤田の上りを利用できなかった鳥栖ですが、柏は小池の上りを即座に利用しました。鳥栖にとっては、オマリがあけたスペースのケアが準備できていないままに電光石火でボールを送られた感覚でしょう。大谷、小池、そしてゴール前に飛び込んできた瀬川。今回の柏の良い所が一気に終結した形でのゴールでした。


最後に、今節も安在が途中出場で非常に良い動きを見せてくれましたね。彼が入ってからシステムが前節と同じく3-5-2となったのですが、安在の右サイドウイングとしての動きは、カットインしてから左足でゴールに向かうアーリークロスを蹴れます。これがファーサイドに逃げるトーレスに対して左足でのキックならではの巻いてゴールに向かうクロスとなって好機も演出しました。当然、カットインしてからのシュートもありますし、ドリブル突破してからの右足のクロスも出来るので、ウイングタイプで利用できる貴重な選手です。安在はハードワークも出来ますし、質的に優位に立つことも出来るので、もっと活用してほしいですね。タイプ的にはキムミヌと同じような気がします。
さて、聞けば、オルンガは初先発、大谷は久しぶりの先発で、鈴木は戻ってきてやっとフィットしてきたという、なぜ鳥栖にターゲットを絞ったのかと恨み節を言わざるを得ない程の試合でございました(笑) そこまで多くの約束事は与えられていなかったでしょうが、守備では「人を捕まえる」攻撃では「スペースを利用する」という最低限果たすべき意思疎通はチーム全体に浸透していたと思います。何度もシステムとポジション変更を繰り返す鳥栖とは対照的でしたね。
ただ、このように状況的には芳しくない中で得られたこの勝ち点1は非常に大きいです。結果的に順位が入れ替わることもなかったですし。権田のセービングに感謝しなければならない試合でした。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
08:53
│Match Impression (2018)
2018年09月19日
2018 第26節 : サガン鳥栖 VS サンフレッチェ広島
2018年第26節、サンフレッチェ広島戦のレビューです。
鳥栖のスタメンは、前節から小野に代わって原川が復帰。ツートップと最終ラインのメンバーは変わりません。セットアップはポジショニングが流動的だったのでなかなか表しづらいのですが、あえて表現するならば、攻撃時には4-3-1-2 がベースですが、ビルドアップによるボール保持のためにボランチが1列下がって3-4-1-2へと変化し、義希が高い位置を取って深さを取るような動きを見せると3-4-3のような形にもなっていました。守備時には中盤フラットの4-4-2をベースとして、押し込まれると最終ラインに人をかけて5-3-2という形でしょうか。広島のセットアップも鳥栖と同様に4-4-2で中盤はボックスに近い形。ミスマッチするポイントなく互いにプレスはかけやすかったかと思います。

序盤の展開ですが、広島はパトリックという高さで強力なストロングを発揮できる選手がいるので、長いボールを当ててからのボールキープを狙いますが、このロングボールによる攻撃は端的に言うと機能不全に陥っていました。不全の要因は、間違いなくパトリックを抑え込んだオマリ、秀人、祐治の3人の活躍によるものですよね。広島の攻撃は、ボールを奪うとすぐにパトリックにボールを送り込んで基点を作るか、もしくは遅効となっても低い位置からパトリックの状況を見てボールを送り込むスタイルをベースとしていました。鳥栖のパトリックへの対応としては、オマリが中心となってマークを担当していました。ロングボールに対しても、カウンターの起点となる早いパスの送りこみに対しても、オマリが高い確率でデュエルを制しており、広島は前線でのキープのきっかけができずに全体を押し上げて攻撃にかかる状況を作り出せていませんでした。


ロングボールに最終ラインが勝ってくれるというのは、チーム全体が前からプレッシャーをかけるための大きな勇気となります。例えばプレッシャーを仕掛けて相手が苦し紛れに蹴ったボールであっても、それを繋がれて攻撃を仕掛けられてしまうとなると、プレッシャーにいく事自体が無駄になりかねません。最終ラインが勝ってくれることによって相手に蹴らせても問題なしということになります。オマリのパトリックとのデュエルの勝利は、鳥栖全体の守備のポイント(守備の基準点)を大きく変えるものとなり、鳥栖が徐々に前線から圧力をかけ始めるきっかけともなりました。
鳥栖の前線からのプレッシャーは、アジリティの高い福田と義希のいる左サイドの方がより活発でした。広島がサイドバックを経由してビルドアップしようとするのですが、サイドハーフに対しては三丸が高い位置を取ってプレッシャーをかけ、福田と義希もスペースを圧縮してそれに追随して金崎とトーレスもサイドに寄せるため、広島は非常に狭いスペースでのボール回しを要求されました。そうなってくると、個人の質というところが大事になるのですが、サイドバックからのボールの受け手が稲垣であった際に、コントロールミスが発生して鳥栖がボールを奪うケースが多かったです。実際、義希がボールを奪ってゴールラインぎりぎりまでドリブルしてからの折り返しというシーンがありましたが僅かにトーレスには合わず。高い位置からのプレッシャーで前から奪うというケースが幾度かあったにも関わらず、得点に繋げることができなかったというのは今後の課題ですね。



鳥栖が前からプレッシャーをかけてくるので、広島は長いボールを蹴る位置が段々と低くなります。(キーパーからのロングボールが多くなってきます)また、オマリとのデュエルの分が悪くて思うように基点とならない状況もありまして、長いボールの目標となるポイントが鳥栖の最終ラインよりも1列前へと変わってきました。そうなってくると、デュエルで勝っていたオマリをその位置まで上げて勝負させるか、セントラルハーフにその役目を任せるかという選択が生まれるのですが、鳥栖が取った選択はボランチの秀人によるマーキングでした。そして秀人もパトリックに自由に仕事をさせないという役割をしっかりと演じてくれました。最終ラインにボールが来るとオマリが見て、その前のエリアだと秀人が見るという仕組みづくりが確立され、鳥栖のロングボール対策は盤石の物となっていきました。

鳥栖の攻撃は、序盤こそはトーレスをめがけたロングボールを蹴っていましたが、広島の前線からのプレッシャーが思いのほか強くないということもありまして徐々にボールを保持する戦い方へと変化します。基本的なスタイルとしては、両サイドに幅を取る選手を配置し、4人で固める広島の中盤を分散させて選手間のスペースを作りだして間のスペースでボールを受ける形。サイドでボールを保持する選手と、サイドに幅を取る選手、そして深い位置でボールを引き出す選手という位置関係になるようにポジションが設定され、ボールを保持しながらサイドチェンジを繰り返して空いたスペースを利用するという攻撃を徹底的に再現していました。

広島としてはサイドに幅を取る選手に対しては、ボールが入ってくるまでは必要以上に関知しないという守備体系を取っていたので、大外の藤田、三丸がフリーでボールを受ける準備が常にできていました。今回の鳥栖が良かったのは、フリーで使える選手を使い倒す外一辺倒という攻撃ではなく、いかにして外を捨て駒としてその内側を利用しようかという動きを見せたところです。その思想の中でスペースを作るための動きとして目立ったのは福田と義希でした。福田は上下動の動きで柴崎、稲垣を連れていく動きを良く見せており、トーレスや金崎が利用できるスペースをしっかりと作っていました。また、義希も特徴的な動きを見せていまして、広島の最終ラインと2列目の間でボールを受けるために引いてくるフォワードのスペースを作るために、義希は深さを取る動きを見せ、フォワードと入れ替わりでトップの位置に張りつき、裏へのボールを引きだす動きを見せていました。
また、鳥栖がボール保持できたのは、広島ツートップのプレッシャーを回避するために、秀人を最終ラインに落としてビルドアップで活用するという解決策を準備できていたからです。これにより、センターバック2人の脇のスペースに降りてボールを受ける事によって、広島の同数プレッシングを回避することに成功しました。最終ラインに3人落としたことによって、広島がサイドハーフをあげるかあげないかという選択が必要だったのですが、広島の選択としてはブロックを崩さずに自陣で待ち受けるというスタイルでした。


ボール保持してサイドチェンジを繰り返すと、広島のツートップは二度追い、三度追いをするような執拗さまでは見せないため、鳥栖はボール保持しながら様子を見る事によって、センターバックがボールを運べるスペースを作り出すことに成功します。特にオマリはツートップの脇のスペースに対してボールを持ちだすことができ、彼の持ち上がりが鳥栖の攻撃のスイッチとなっていました。オマリの持ち出しによって広島のサイドハーフを引きだす事ができ、福田、義希、金崎が活用してボールを引き出す動きを見せました。オマリが直接フォワードにくさびを入れるというパスもありましたし、今節はボール保持からの攻撃がよく機能していました。



義希も前後に大きく動き回り、相手ボランチをひきつけたり、裏に飛び出して最終ラインを引き寄せたと今回も素晴らしい動きを見せてくれました。ただし、動きまわりすぎる事の功罪とでもいいましょうか、スペースを作るというタスクでは抜群の動きを見せるものの、空いたスペースを利用する側としてゴールに直結するような仕事が出来たかと言われるとなかなかその役割としては力を発揮できませんでした。チーム全体としてなのですが、福田と義希が大きく動きまわってスペースを作るものの、ではそのスペースは誰が使うのというような場面がありました。また、ポジションチェンジで義希がフォワードの位置に入ったときにくさびのパスが入ってくるのですが、そこは、義希のストロングポイントではないのでつぶされてしまっていました。そういう意味では、小野の方が前線でボールを受けてからのアイデア・テクニックがストロングポイントなので、今回義希が良かったから彼がスタメンということではなく、そこは相手チームとの力関係や試合状況を見てからの起用法になるのかなと思います。


鳥栖としてはボール保持からの攻撃は機能していたものの、カウンターのような早い攻撃を仕掛けたいところや、攻撃のスイッチを入れたいところでスペースをもう少し使って欲しかった場面があり、サイドの裏へのスペースにセントラルハーフがどの程度入っていくのかという所に起因していました。三丸や藤田、義希に関しては、幅を取る要員(深さを取る要員)として、スペースを見つけて思い切ったオーバーラップを仕掛けていったのですが、福田、秀人、原川といった中盤での繋ぎ要員が、大きく前にでていけるタイミングで自重するケースが多く見られました。特にカウンターのシーンで裏のスペースをうまく使う事ができればもっとチャンスを作れていたかもしれません。それはマッシモの指示なのか彼らの判断なのかは我々の知る由はありませんが、気になるところではあります。


序盤は完璧に抑えていた鳥栖ですが、後半になって体力の低下と共に少し様相が変わってきます。前半の体力のあるうちは、ボールロストしても高い位置から早いプレッシャーをかけるために、広島に自由にボールをコントロールさせる隙を与えなかったのですが、体力の低下と共に広島の最終ラインへのプレス強度も徐々に弱まっていきました。プレス強度が弱くなるということは、広島がボールを保持してからパスを出すまでの時間の余裕があり、パスの精度も徐々に上がっていくということになります。鳥栖は前半と同じく高い位置からのプレッシャーをかける準備として、広島の高い位置を取るサイドの選手に対してサイドバック(藤田、三丸)を高い位置に置いていましたが、これによってサイドバックの裏にスペースを作ることになり、広島のツートップがそのスペースを狙いだします。
前半はツートップ(主にパトリック)をめがけてボールを蹴り込んでいた広島ですが、ツートップがスペースに走り込む機会が多くなってくると、パスの送り先もスペースに対するものへと徐々に変化していきます。鳥栖の最終ラインも、前半のステイした状態での高さ勝負から、勝負の舞台がスペースへ走り込むスピード対決となると、やや分が悪い状況へと変化していきました。特にオマリは前半からの空中戦の連続による疲労蓄積が少なからず影響があったかもしれません。三丸の裏のスペースに入ったボールの処理でカバーリングに入ったオマリにミスが発生し、パトリックに2度ほどビッグチャンスを与えてしまいました。この決定的なピンチを権田を中心にその他のメンバーで何とか防ぎきることができたのは大きかったですね。



ビッグチャンスを作った広島は徐々に鳥栖の守備陣を押し込み出します。広島の両サイドが高い位置を取ることによって鳥栖の両サイドバックを押し込み、鳥栖の陣地内でサイドチェンジしながらボールを保持してスライドの遅れによる守備のほころびを狙います。その集大成とでも言いましょうか、右サイドにボールを展開して三丸とオマリとの間にできるスペースを逆サイドから入ってきた柏が受けてクロスを配球し、足の止まった原川を尻目にパトリックが先にボールにさわって佐々木のシュートを生み出しました。マッシモとしてはこのシーンが決定的となったのでしょう。押し込まれる一方になりかけそうな展開を打破するために、フレッシュな安在を投入しました。
安在を投入した鳥栖はシステムを3-5-2へと変更します。サイドのスペースを突かれるケースが多くなったため、センターバック1人がカバーリングに出ていっても中央に2人残せるように最終ラインの人数を3人へ変更しました。また、押し込まれつつあった両サイドで再びイニシアチブを取り戻すために三丸と安在を高い位置に配置しました。前線をかき乱していた福田と義希はインサイドハーフに据えて中央を割られないように秀人と3人でブロックを組みます。


この安在の投入とシステム変更は非常に効果的でありまして、安在と三丸のアグレッシブなランニングによって広島のボール保持をかき乱し、再び前半のように広島のパス精度を低下させるに十分にプレッシャーをかける事ができました。ポジティブトランジション時の前への推進力もありまして、サイドの高い位置にポジショニングしてスペースへ飛び出すことによって、広島のサイドバックを押し込むことにも繋がりました。権田からのロングキックをトーレスが競って、そのこぼれ球を高い位置を拾った三丸のクロスから安在のヘディングシュートというのは、広島の守備ブロックの外からチャンスを作って逆サイドの外でフィニッシュを放つという前半には見られなかった攻撃でした。


ボールを保持した瞬間にアグレッシブにスペースに走るという安在の存在はトーレス、金崎を生き返らせるのに十分でありました。彼らがボールを保持しながら前進するタイミングで安在が素早くフォローに入るため、スペースに入り込む安在に渡してリターンを受けるという攻撃の形が出来ました。先制点のきっかけとなるセットプレイも、オマリからでたサイドのスペースに対して安在が走りこんでボールを受けてから得たファールからでした。セットプレイを安在自らがキッカーとなってアシストを呼び込むという出来すぎと言ってもいいくらいのプレイでしたね。


今節は、マッシモの采配はかなり良かったと思います。パトリック対策によるロングボール封じ、秀人を利用したハーフスペースビルドアップによるボール保持、そして安在の投入に伴うシステム変更。首位広島のお株を奪う程の素晴らしい戦術的な戦いを見せてくれました。安在の投入と期待に応えるかのような彼のアグレッシブな動きは押し込まれていた鳥栖に強烈な追い風を吹き込みましたね。
アウェーの地での広島戦も、互いに我慢比べと言うような戦いだったのですが、今節では逆に終盤に1点をもぎ取ってウノゼロでの勝利を収める事ができました。試合展開としては同じような感じだったのですが、前回の対戦とは前線での質が格段に違います。いまの前線の二人は、ある程度雑なボールを蹴ったとしても競り勝ってくれるし、個人の力でボールをキープして突破もしてくれます。広島がプレスを強めた際に大きく蹴らざるを得ない状況となっても、トーレスがほとんどの場合で空中戦に勝ってくれ、金崎も長いボールを胸トラップでボール保持してくれました。

ボールキープして時間を作ってくれることは、攻撃に対する貢献のみならず、最終ラインが一息つくための時間(ラインを整えるための時間)を作ってくれます。前線の二人は、なかなか得点を取れていない状況ですが、チームの勝利(ここ数試合の無失点)という事を第一に考えると非常に貢献度が高いです。得点が取れない状況を打破するために、トーレス、金崎を試合途中で交代するという手もあるかもしれませんが、そうすると豊田、田川がどこまでボールキープできるのか、どこまで味方の時間を作ってくれるのかという問題が浮上します。攻勢のまま得点が奪えればよいのですが、相手の攻撃を受けてからのトランジションでボールキープができないと押し込まれる要因ともなるので難しい戦いへと変化します。
最後に、今節のオマリの気迫は相当なものでした。後半から少し体力が落ち、ミスが発生してピンチを招きましたが、彼の対応と気迫はサガン鳥栖の選手たちに大きな勇気を与えてくれました。後半途中にマッシモがミンヒョクを準備してベンチからオマリに問いかけたのですが、オマリは両こぶしを握り締めて「俺は大丈夫だ」と言わんばかりのジェスチャーと視線をベンチに送りました。マッシモはオマリを信頼してサムアップを見せ、一旦ミンヒョクの交替を取り下げました。戦う気持ちを前面に押し出してくれるオマリを信頼してこれからもサポートしていきたいですね。
ただし、最後の中東の選手っぽい時間稼ぎのような怪しい動きはちょっと…(苦笑)。権田が少し怒っていたような?
さて、降格圏を脱出したサガン鳥栖。次節はふたたび訪れたシックスポイントマッチである柏戦です。前回のアウェーでのシックスポイントマッチは名古屋に手痛い惨敗を喫してしまいましたが、このような戦いは繰り返したくないもの。はたして今回はどのような結末になるのか。勝てば残留に対して希望が開き、負ければ再び降格圏に落ちてしまうという本当に大事な大事な試合です。是非とも最低でも勝ち点1を持ち帰ってきて欲しいですね。
<画像引用元:DAZN>
鳥栖のスタメンは、前節から小野に代わって原川が復帰。ツートップと最終ラインのメンバーは変わりません。セットアップはポジショニングが流動的だったのでなかなか表しづらいのですが、あえて表現するならば、攻撃時には4-3-1-2 がベースですが、ビルドアップによるボール保持のためにボランチが1列下がって3-4-1-2へと変化し、義希が高い位置を取って深さを取るような動きを見せると3-4-3のような形にもなっていました。守備時には中盤フラットの4-4-2をベースとして、押し込まれると最終ラインに人をかけて5-3-2という形でしょうか。広島のセットアップも鳥栖と同様に4-4-2で中盤はボックスに近い形。ミスマッチするポイントなく互いにプレスはかけやすかったかと思います。

序盤の展開ですが、広島はパトリックという高さで強力なストロングを発揮できる選手がいるので、長いボールを当ててからのボールキープを狙いますが、このロングボールによる攻撃は端的に言うと機能不全に陥っていました。不全の要因は、間違いなくパトリックを抑え込んだオマリ、秀人、祐治の3人の活躍によるものですよね。広島の攻撃は、ボールを奪うとすぐにパトリックにボールを送り込んで基点を作るか、もしくは遅効となっても低い位置からパトリックの状況を見てボールを送り込むスタイルをベースとしていました。鳥栖のパトリックへの対応としては、オマリが中心となってマークを担当していました。ロングボールに対しても、カウンターの起点となる早いパスの送りこみに対しても、オマリが高い確率でデュエルを制しており、広島は前線でのキープのきっかけができずに全体を押し上げて攻撃にかかる状況を作り出せていませんでした。


ロングボールに最終ラインが勝ってくれるというのは、チーム全体が前からプレッシャーをかけるための大きな勇気となります。例えばプレッシャーを仕掛けて相手が苦し紛れに蹴ったボールであっても、それを繋がれて攻撃を仕掛けられてしまうとなると、プレッシャーにいく事自体が無駄になりかねません。最終ラインが勝ってくれることによって相手に蹴らせても問題なしということになります。オマリのパトリックとのデュエルの勝利は、鳥栖全体の守備のポイント(守備の基準点)を大きく変えるものとなり、鳥栖が徐々に前線から圧力をかけ始めるきっかけともなりました。
鳥栖の前線からのプレッシャーは、アジリティの高い福田と義希のいる左サイドの方がより活発でした。広島がサイドバックを経由してビルドアップしようとするのですが、サイドハーフに対しては三丸が高い位置を取ってプレッシャーをかけ、福田と義希もスペースを圧縮してそれに追随して金崎とトーレスもサイドに寄せるため、広島は非常に狭いスペースでのボール回しを要求されました。そうなってくると、個人の質というところが大事になるのですが、サイドバックからのボールの受け手が稲垣であった際に、コントロールミスが発生して鳥栖がボールを奪うケースが多かったです。実際、義希がボールを奪ってゴールラインぎりぎりまでドリブルしてからの折り返しというシーンがありましたが僅かにトーレスには合わず。高い位置からのプレッシャーで前から奪うというケースが幾度かあったにも関わらず、得点に繋げることができなかったというのは今後の課題ですね。



鳥栖が前からプレッシャーをかけてくるので、広島は長いボールを蹴る位置が段々と低くなります。(キーパーからのロングボールが多くなってきます)また、オマリとのデュエルの分が悪くて思うように基点とならない状況もありまして、長いボールの目標となるポイントが鳥栖の最終ラインよりも1列前へと変わってきました。そうなってくると、デュエルで勝っていたオマリをその位置まで上げて勝負させるか、セントラルハーフにその役目を任せるかという選択が生まれるのですが、鳥栖が取った選択はボランチの秀人によるマーキングでした。そして秀人もパトリックに自由に仕事をさせないという役割をしっかりと演じてくれました。最終ラインにボールが来るとオマリが見て、その前のエリアだと秀人が見るという仕組みづくりが確立され、鳥栖のロングボール対策は盤石の物となっていきました。

鳥栖の攻撃は、序盤こそはトーレスをめがけたロングボールを蹴っていましたが、広島の前線からのプレッシャーが思いのほか強くないということもありまして徐々にボールを保持する戦い方へと変化します。基本的なスタイルとしては、両サイドに幅を取る選手を配置し、4人で固める広島の中盤を分散させて選手間のスペースを作りだして間のスペースでボールを受ける形。サイドでボールを保持する選手と、サイドに幅を取る選手、そして深い位置でボールを引き出す選手という位置関係になるようにポジションが設定され、ボールを保持しながらサイドチェンジを繰り返して空いたスペースを利用するという攻撃を徹底的に再現していました。

広島としてはサイドに幅を取る選手に対しては、ボールが入ってくるまでは必要以上に関知しないという守備体系を取っていたので、大外の藤田、三丸がフリーでボールを受ける準備が常にできていました。今回の鳥栖が良かったのは、フリーで使える選手を使い倒す外一辺倒という攻撃ではなく、いかにして外を捨て駒としてその内側を利用しようかという動きを見せたところです。その思想の中でスペースを作るための動きとして目立ったのは福田と義希でした。福田は上下動の動きで柴崎、稲垣を連れていく動きを良く見せており、トーレスや金崎が利用できるスペースをしっかりと作っていました。また、義希も特徴的な動きを見せていまして、広島の最終ラインと2列目の間でボールを受けるために引いてくるフォワードのスペースを作るために、義希は深さを取る動きを見せ、フォワードと入れ替わりでトップの位置に張りつき、裏へのボールを引きだす動きを見せていました。
また、鳥栖がボール保持できたのは、広島ツートップのプレッシャーを回避するために、秀人を最終ラインに落としてビルドアップで活用するという解決策を準備できていたからです。これにより、センターバック2人の脇のスペースに降りてボールを受ける事によって、広島の同数プレッシングを回避することに成功しました。最終ラインに3人落としたことによって、広島がサイドハーフをあげるかあげないかという選択が必要だったのですが、広島の選択としてはブロックを崩さずに自陣で待ち受けるというスタイルでした。


ボール保持してサイドチェンジを繰り返すと、広島のツートップは二度追い、三度追いをするような執拗さまでは見せないため、鳥栖はボール保持しながら様子を見る事によって、センターバックがボールを運べるスペースを作り出すことに成功します。特にオマリはツートップの脇のスペースに対してボールを持ちだすことができ、彼の持ち上がりが鳥栖の攻撃のスイッチとなっていました。オマリの持ち出しによって広島のサイドハーフを引きだす事ができ、福田、義希、金崎が活用してボールを引き出す動きを見せました。オマリが直接フォワードにくさびを入れるというパスもありましたし、今節はボール保持からの攻撃がよく機能していました。



義希も前後に大きく動き回り、相手ボランチをひきつけたり、裏に飛び出して最終ラインを引き寄せたと今回も素晴らしい動きを見せてくれました。ただし、動きまわりすぎる事の功罪とでもいいましょうか、スペースを作るというタスクでは抜群の動きを見せるものの、空いたスペースを利用する側としてゴールに直結するような仕事が出来たかと言われるとなかなかその役割としては力を発揮できませんでした。チーム全体としてなのですが、福田と義希が大きく動きまわってスペースを作るものの、ではそのスペースは誰が使うのというような場面がありました。また、ポジションチェンジで義希がフォワードの位置に入ったときにくさびのパスが入ってくるのですが、そこは、義希のストロングポイントではないのでつぶされてしまっていました。そういう意味では、小野の方が前線でボールを受けてからのアイデア・テクニックがストロングポイントなので、今回義希が良かったから彼がスタメンということではなく、そこは相手チームとの力関係や試合状況を見てからの起用法になるのかなと思います。


鳥栖としてはボール保持からの攻撃は機能していたものの、カウンターのような早い攻撃を仕掛けたいところや、攻撃のスイッチを入れたいところでスペースをもう少し使って欲しかった場面があり、サイドの裏へのスペースにセントラルハーフがどの程度入っていくのかという所に起因していました。三丸や藤田、義希に関しては、幅を取る要員(深さを取る要員)として、スペースを見つけて思い切ったオーバーラップを仕掛けていったのですが、福田、秀人、原川といった中盤での繋ぎ要員が、大きく前にでていけるタイミングで自重するケースが多く見られました。特にカウンターのシーンで裏のスペースをうまく使う事ができればもっとチャンスを作れていたかもしれません。それはマッシモの指示なのか彼らの判断なのかは我々の知る由はありませんが、気になるところではあります。


序盤は完璧に抑えていた鳥栖ですが、後半になって体力の低下と共に少し様相が変わってきます。前半の体力のあるうちは、ボールロストしても高い位置から早いプレッシャーをかけるために、広島に自由にボールをコントロールさせる隙を与えなかったのですが、体力の低下と共に広島の最終ラインへのプレス強度も徐々に弱まっていきました。プレス強度が弱くなるということは、広島がボールを保持してからパスを出すまでの時間の余裕があり、パスの精度も徐々に上がっていくということになります。鳥栖は前半と同じく高い位置からのプレッシャーをかける準備として、広島の高い位置を取るサイドの選手に対してサイドバック(藤田、三丸)を高い位置に置いていましたが、これによってサイドバックの裏にスペースを作ることになり、広島のツートップがそのスペースを狙いだします。
前半はツートップ(主にパトリック)をめがけてボールを蹴り込んでいた広島ですが、ツートップがスペースに走り込む機会が多くなってくると、パスの送り先もスペースに対するものへと徐々に変化していきます。鳥栖の最終ラインも、前半のステイした状態での高さ勝負から、勝負の舞台がスペースへ走り込むスピード対決となると、やや分が悪い状況へと変化していきました。特にオマリは前半からの空中戦の連続による疲労蓄積が少なからず影響があったかもしれません。三丸の裏のスペースに入ったボールの処理でカバーリングに入ったオマリにミスが発生し、パトリックに2度ほどビッグチャンスを与えてしまいました。この決定的なピンチを権田を中心にその他のメンバーで何とか防ぎきることができたのは大きかったですね。



ビッグチャンスを作った広島は徐々に鳥栖の守備陣を押し込み出します。広島の両サイドが高い位置を取ることによって鳥栖の両サイドバックを押し込み、鳥栖の陣地内でサイドチェンジしながらボールを保持してスライドの遅れによる守備のほころびを狙います。その集大成とでも言いましょうか、右サイドにボールを展開して三丸とオマリとの間にできるスペースを逆サイドから入ってきた柏が受けてクロスを配球し、足の止まった原川を尻目にパトリックが先にボールにさわって佐々木のシュートを生み出しました。マッシモとしてはこのシーンが決定的となったのでしょう。押し込まれる一方になりかけそうな展開を打破するために、フレッシュな安在を投入しました。
安在を投入した鳥栖はシステムを3-5-2へと変更します。サイドのスペースを突かれるケースが多くなったため、センターバック1人がカバーリングに出ていっても中央に2人残せるように最終ラインの人数を3人へ変更しました。また、押し込まれつつあった両サイドで再びイニシアチブを取り戻すために三丸と安在を高い位置に配置しました。前線をかき乱していた福田と義希はインサイドハーフに据えて中央を割られないように秀人と3人でブロックを組みます。


この安在の投入とシステム変更は非常に効果的でありまして、安在と三丸のアグレッシブなランニングによって広島のボール保持をかき乱し、再び前半のように広島のパス精度を低下させるに十分にプレッシャーをかける事ができました。ポジティブトランジション時の前への推進力もありまして、サイドの高い位置にポジショニングしてスペースへ飛び出すことによって、広島のサイドバックを押し込むことにも繋がりました。権田からのロングキックをトーレスが競って、そのこぼれ球を高い位置を拾った三丸のクロスから安在のヘディングシュートというのは、広島の守備ブロックの外からチャンスを作って逆サイドの外でフィニッシュを放つという前半には見られなかった攻撃でした。


ボールを保持した瞬間にアグレッシブにスペースに走るという安在の存在はトーレス、金崎を生き返らせるのに十分でありました。彼らがボールを保持しながら前進するタイミングで安在が素早くフォローに入るため、スペースに入り込む安在に渡してリターンを受けるという攻撃の形が出来ました。先制点のきっかけとなるセットプレイも、オマリからでたサイドのスペースに対して安在が走りこんでボールを受けてから得たファールからでした。セットプレイを安在自らがキッカーとなってアシストを呼び込むという出来すぎと言ってもいいくらいのプレイでしたね。


今節は、マッシモの采配はかなり良かったと思います。パトリック対策によるロングボール封じ、秀人を利用したハーフスペースビルドアップによるボール保持、そして安在の投入に伴うシステム変更。首位広島のお株を奪う程の素晴らしい戦術的な戦いを見せてくれました。安在の投入と期待に応えるかのような彼のアグレッシブな動きは押し込まれていた鳥栖に強烈な追い風を吹き込みましたね。
アウェーの地での広島戦も、互いに我慢比べと言うような戦いだったのですが、今節では逆に終盤に1点をもぎ取ってウノゼロでの勝利を収める事ができました。試合展開としては同じような感じだったのですが、前回の対戦とは前線での質が格段に違います。いまの前線の二人は、ある程度雑なボールを蹴ったとしても競り勝ってくれるし、個人の力でボールをキープして突破もしてくれます。広島がプレスを強めた際に大きく蹴らざるを得ない状況となっても、トーレスがほとんどの場合で空中戦に勝ってくれ、金崎も長いボールを胸トラップでボール保持してくれました。

ボールキープして時間を作ってくれることは、攻撃に対する貢献のみならず、最終ラインが一息つくための時間(ラインを整えるための時間)を作ってくれます。前線の二人は、なかなか得点を取れていない状況ですが、チームの勝利(ここ数試合の無失点)という事を第一に考えると非常に貢献度が高いです。得点が取れない状況を打破するために、トーレス、金崎を試合途中で交代するという手もあるかもしれませんが、そうすると豊田、田川がどこまでボールキープできるのか、どこまで味方の時間を作ってくれるのかという問題が浮上します。攻勢のまま得点が奪えればよいのですが、相手の攻撃を受けてからのトランジションでボールキープができないと押し込まれる要因ともなるので難しい戦いへと変化します。
最後に、今節のオマリの気迫は相当なものでした。後半から少し体力が落ち、ミスが発生してピンチを招きましたが、彼の対応と気迫はサガン鳥栖の選手たちに大きな勇気を与えてくれました。後半途中にマッシモがミンヒョクを準備してベンチからオマリに問いかけたのですが、オマリは両こぶしを握り締めて「俺は大丈夫だ」と言わんばかりのジェスチャーと視線をベンチに送りました。マッシモはオマリを信頼してサムアップを見せ、一旦ミンヒョクの交替を取り下げました。戦う気持ちを前面に押し出してくれるオマリを信頼してこれからもサポートしていきたいですね。
ただし、最後の中東の選手っぽい時間稼ぎのような怪しい動きはちょっと…(苦笑)。権田が少し怒っていたような?
さて、降格圏を脱出したサガン鳥栖。次節はふたたび訪れたシックスポイントマッチである柏戦です。前回のアウェーでのシックスポイントマッチは名古屋に手痛い惨敗を喫してしまいましたが、このような戦いは繰り返したくないもの。はたして今回はどのような結末になるのか。勝てば残留に対して希望が開き、負ければ再び降格圏に落ちてしまうという本当に大事な大事な試合です。是非とも最低でも勝ち点1を持ち帰ってきて欲しいですね。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
19:45
│Match Impression (2018)
2018年09月05日
2018 第25節 : FC東京 VS サガン鳥栖
2018年第25節、FC東京戦のレビューです。
鳥栖のスタメンは、前節熱中症で途中交代した小林に代わり藤田、原川に代わって義希が入りました。無失点という結果を出したオマリ、三丸も継続してスタメンです。マッシモの信頼が厚い原川はベンチにも入らず。疲労なのか怪我なのか戦術の影響なのかはわかりません。FC東京も永井、チャンヒョンス、そして怪我明けの橋本が前節と変わってスタメンに入ります。
鳥栖のセットアップは、攻撃時は4-3-3。小野、金崎が流動的にポジションを変えるので4-3-2-1のクリスマスツリー型の時もありましたが、4-3-3の3ラインで表現した方が適切でしょう。守備時は4-3-3から流動的にトーレスが下がったり小野が下がったりして中盤をカバーする形で臨みましたが、試合途中から小野が下がり、4-4-2でのブロックへと変化しました。

途中から4-4-2に変えるくらいならば、なぜ最初から4-4-2にしないのかという疑問が湧きあがるかもしれませんが、恐らくマッシモは試合開始当初は前線からハメていく形を作って押し込んでいきたいのでしょう。相手が立ち上がりでどのように鳥栖のプレッシャーをかわしてビルドアップしていくかという制度設計が完全でない状態であるので、前からプレッシャーをかけてボールを奪えればすぐにビッグチャンスが訪れます。また、試合開始当初は鳥栖としてはビルドアップにこだわらずに、最終ラインからトーレス目がけてロングボールを放り込んでおり、前線に人数を置いているため、奪われても早くプレッシャーをかける事ができます。名古屋戦がそうだったのですが、立ち上がりの状態でプレッシングによって相手のミスを生じさせて早めに得点チャンスを迎えて、そして奪い切れれば万々歳という試合の入り方でした。
ただし、相手がその鳥栖の戦術に慣れ、ビルドアップで鳥栖の前線からのプレッシャーをしのぐ仕組みを確立した頃が鳥栖のシステム変更のタイミングです。おそらく、その頃には相手が鳥栖の4-3-3プレッシングで空いた中盤のスペースを攻略する戦いを仕掛けている状況でしょうから、そのときは4-4-2で中盤のスペースを消す戦いにシフトします。試合の中で、まずは攻撃的な手を打ち、試合を進めながら守備で対応しづらい状況が発生してきたら、少しずつ変化を加えていくという作戦なのでしょう。試合途中での福田のサイドチェンジも同様です。4-4-2で押し込まれると福田がポジションを下げて5-3-2ブロックに変化しますが、相手がそのブロックになれて福田のスペースをうまく利用できるようにすると、福田を逆サイドに持ってきてまた相手の設計を狂わせる形を取ります。守備的なメンバーを付けたいという要素もあるでしょうが、福田を最終ラインに下げるというやり方はどちらのサイドでも変わらないので、よりハマる方を模索しながら対応しているように見えました。
■ 福田を下げる形を攻略されると…


■ 福田を逆サイドに移して対応方法を変える

この試合でも同様に4-3-3でスタートしたのですが、4-3-3プレッシングによる成果はあまり上げる事ができませんでした。正確に言うと4-3-3プレッシングによって相手のミスを生んだシーンもありましたが、それ以上に4-3-3によって生じる中盤のスペースを利用されるケースが多かったという形です。鳥栖にとってネガティブな要素だったのが、FC東京が速いカウンターを仕掛けてきた場合、中盤のプレイヤーという役割を意識している3センターの戻りは早いけれども、攻撃のタスクを与えられているフォワード陣の戻りが甘く、FC東京に3センターの脇のスペースを使われてしまう状況を生んでいました。遅い攻撃の場合はほとんど小野、時折トーレスや金崎が中盤のスペースを埋める役割を担いますが、ボールを奪った時の起点が明確でないという状況も生まれます。結局、4-3-3による守備組織を諦め、30分頃からはっきりと小野が中盤のスペースを埋めてサイドハーフに入るようになりました。


前半30分頃から小野を下げて4-4-2で中盤のスペースを埋めるシステムに変更しましたが、FC東京の洗練された、そして統率された攻撃が鳥栖のディフェンス陣を苦しめます。鳥栖の4-4ブロックを破壊するための基礎的な動きとして、ディエゴ・オリベイラは引いて最終ラインやボランチからボールを受ける動きを見せ、そして永井は裏に飛び出してボールを引き出そうとするダブルアクションを見せます。鳥栖としては、ディエゴについて行ったら最終ラインの裏を狙われるし、永井のケアをしたらディエゴ・オリベイラに簡単にキープされるという状況を生みます。更に厄介な事に東と大森が縦横無尽にその周りを駆けずり回られるという、鳥栖のセントラルハーフと最終ラインは常に対応を考えさせられており、体力と共に精神的疲労も大きかったかと思います。


ディエゴ・オリベイラのライン間で受ける動きは非常に効果的でした。FC東京が室屋と太田を高い位置に上げて幅を取る動きを見せ、最終ラインに寄るサイドチェンジも素早く行われるので、鳥栖が片方のサイドを捨てきれないで徐々に中盤の4人のライン間が広がります。ディエゴ・オリベイラは、セントラルハーフ4人のメンバー間のスペースが空くことを見越してポジションを下げ、ボランチからのボールの配球を引き出します。そこからは個人の質という要素もありますが、ボールを受けてからひとり剥がすのは造作もないとばかりにターンして前を向きます。このタイミングで、両サイドバックや永井が最終ラインの裏に抜けようとするので、その対応で鳥栖のオリベイラに対するプレッシャーも完全ではなくなり、いくつかのミドルシュートを狙われました。
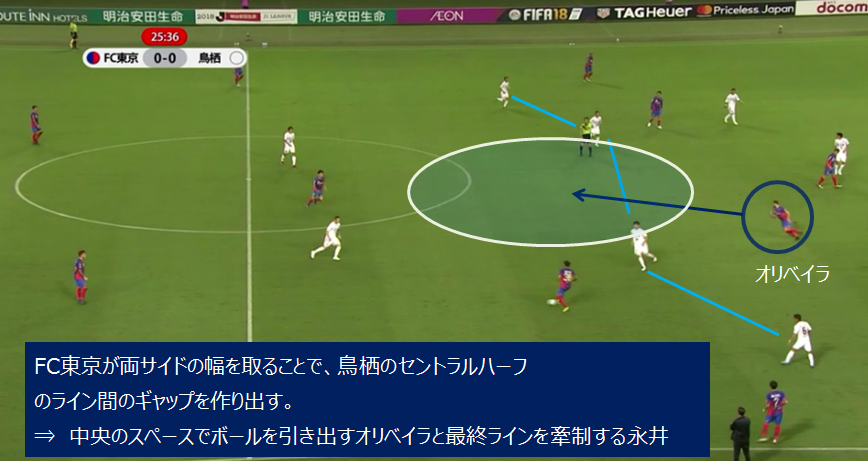

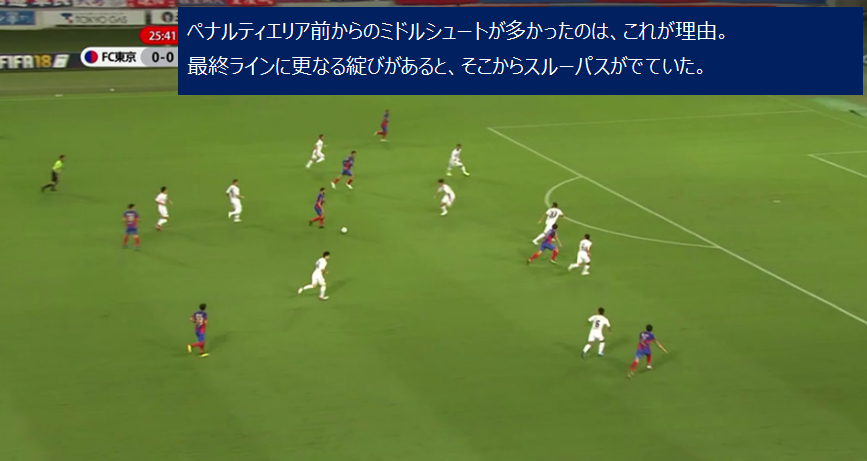
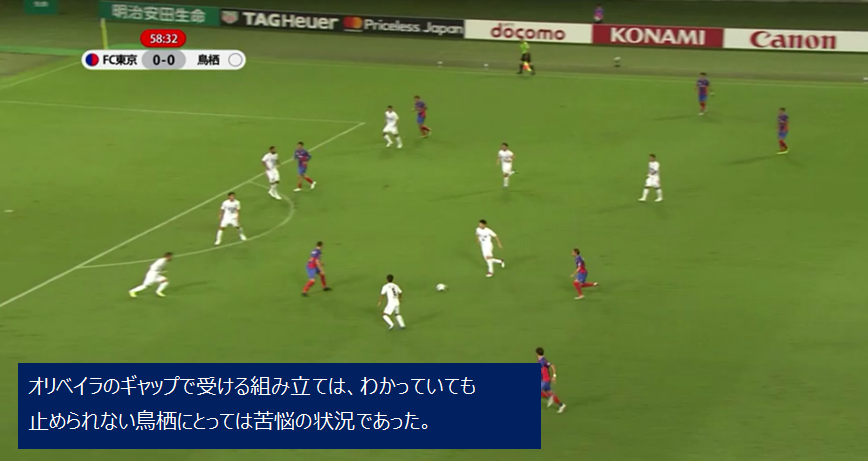
FC東京の戦術の浸透が浸透していたのは、下の図の動きにも現れており、このシーンでは役割分担を変えて、最終ラインを押し下げる役割をオリベイラが果たし、中盤に引いてボールを引き出す役割を永井が果たしています。結果的には、永井がスピードを利用して自分で空けた最終ラインの裏のスペースに走り込んでシュートを放ちますが、ツートップの動きは統率がとれていました。


実況では、ディエゴ・オリベイラの単独ショウという言葉もありましたが、実際にはディエゴ・オリベイラがボールを受けるタイミングやスペースを作るためにFC東京全体が動いていたという感じです。両サイドの幅を取る太田と室屋は、チャンスに直結する仕事が出来なかったとしても、高いポジションを取るだけで鳥栖にとっては対応の手を準備しなければならず、かなりの脅威でありました。
鳥栖の最終ライン…特にオマリと三丸ですが、この試合でも相手を無失点に抑える良い守備対応を見せていました。この結果を手放しで褒め称えても良いのですが、更なる強靭な守備組織の構築という事で、あえて今後の課題を投げかけます。
FC東京がサイドバックとサイドハーフを高い位置に押し上げてきたときに、鳥栖はサイドハーフと三丸がプレッシャーをかけるためにややマンマーク気味につくことになります。これによってオマリの特徴である中央にプライオリティを置くという守備思想とのギャップが生まれ、サイドバックとの間のスペースを空けることになります。このスペースに対してはオリベイラや永井がしっかりとそのエリアを狙ってボールを引き出す動きを見せました。最終的には中央を固める事によってなんとか失点を喫することはなかったのですが、ボックス内にボールを運ばれる仕組みをFC東京に作られてしまいました。ちなみに、ここは神戸戦やG大阪戦でも使えるスペースだったのですが、利用するためのプレーは見られず。攻撃が洗練されているFC東京ならではというところでしょう。




また、三丸も吉田に比べると前からのプレッシャーというよりは、最終ラインのスペースをしっかりと埋めるタイプです。必要以上に前に圧縮をかけないというプレイ性質が、取りに行くところで取れないという状況を生み出しました。下図に示しますが、サイドに追い込んでボールを奪い取れればと言うところだったのですが、ボールを中央に寄せられたところで三丸は更なるプレッシャーをかけるのではなく、撤退守備という選択をしました。これによって、FC東京は中央で前を向いてボールを持つことができ、三丸の裏のスペースへボールを送り込むことに成功しました。マッシモのリアクションを見たらわかりますが、恐らく、彼の意図としてはあのシチュエーションになったら、更なるプレッシャーをかけて欲しかったのでしょう。ボールが取れないとわかるとそっぽを向いてしまいました。(笑) 吉田ならば前へのプレッシャーをかけていたでしょうから、この場面では、吉田のプレイ性質の方がマッシモの守備戦術に合っていたということです。



オマリの件も、三丸の件も、どこか(誰か)に対して集中すると、かならず空いてしまうスペース(誰か)は出来てしまいます。チームとしてそれをどうやって埋めるのか(逆にどこを捨てるのか)を意思統一することが守備的戦術としては重要な要素になります。オマリも三丸も、狙えるときは前から行きますが、どちらかというと後ろをしっかりというタイプなのでお互いの守備性質はマッチしているのかなという感じです。これが、片方が前からどんどん行くタイプで、片方が後ろをしっかりというタイプであれば、ラインを乱してしまうことになります。守備戦術でコントロールすることが必要なのですが、最終的には個人の「クセ」というのは出てしまうものですので、そのあたりのコーディネイトも監督としては重要な仕事となります。
また、小野のサイドハーフはFC東京のようにしっかりと幅を取ってくるチームに対して果たして正解の対応だったかという疑問は残ります。鳥栖がボールサイドに寄せた時に逆サイドの小野がスライドしなかった事によって中央にスペースを空け、そのスペースを狙われてシュートまで持って行かれたケースがありました。守備の教科書だと全体のスライドに合わせて小野もスライドしなければなりません。ただ、攻撃を考えるとカウンターの起点としてサイドにポジションを残しておくという事は考えられますのでマッシモが彼の配置をどう考えていたかですね。単に守備だけを考えると、安在を先発で起用した4-4-2の方が守備の安定感はでるでしょうね。
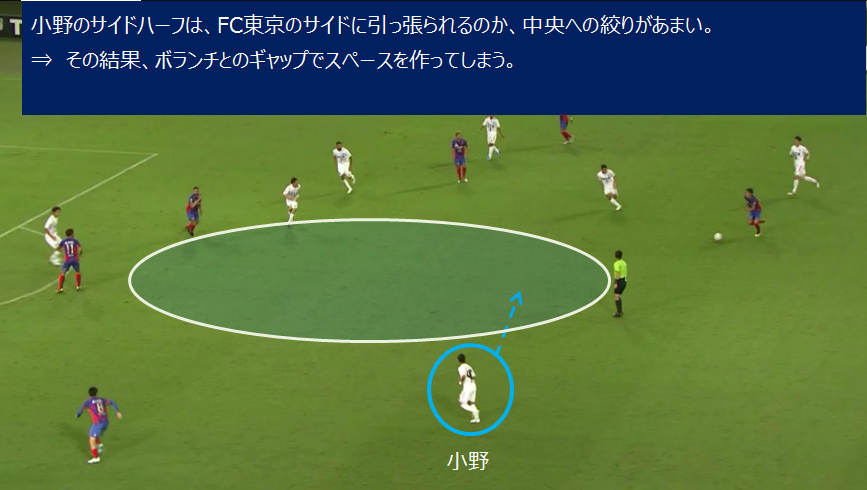

最終的には、ビルドアップで崩されても両サイドハーフが最終ラインにリトリートしてゴール前を圧縮する事によって人海戦術でゴールを防ぎましたが、FC東京の鳥栖のディフェンスを動かすための連動したプレイ、そして空いたスペースをしっかりと狙ってくる攻撃は非常に脅威でした。ここ数試合勝てていないチームという情報だったので、どれだけ調子が悪いのかと思っていたのですが、そんなことはまったくなく、ふたを開けてみればチーム戦術も整っていて今シーズン上位にポジションしているのが納得できる非常に強いチームでした。
さて、鳥栖の攻撃ですが、試合開始序盤のロングボールの応酬もひと段落した頃に、少し落ち着いてビルドアップによる攻撃を試みることになります。鳥栖の攻撃はサイドバックを高く上げて幅を取らせて、最終ラインからインサイドハーフを経由してサイドから攻撃を仕掛ける形です。

鳥栖のビルドアップに対して、FC東京はツートップが隙あらば相手もろともと言わんばかりの勢いでボールをさらいに来ます。FC東京のツートップのプレスは、チーム全体で奪うというよりは、彼ら2人で完結するならば行ってしまおうという形でした。前からのプレスに関しては、永井が一度祐治からかっさらうことに成功しましたね。オマリのカバーリングで何とか事なきを得ましたが危ないシーンでした。
FC東京の4-4(5-3)ブロックは、後述しますが鳥栖の三丸対策としてFC東京はボランチを最終ラインに下げるケースが多く、サイドバックやサイドハーフが不用意に前に出てしまうと後ろにスペースを生んでしまう事になるので、永井とオリベイラに連動するよりは、彼らがプレスしたことに抜け出てくるだろうボールの行先を抑えるというクレバーな立ち回りでした。鳥栖がツートップをかわした先のブロックの間を縫うところを探し切れず、こまねいている間にいつの間にか永井もディエゴ・オリベイラもリトリート守備に切り替えられ、打開するには大きなサイドチェンジか長いボールをトーレスめがけて蹴っ飛ばすという形になっていました。
G大阪戦で機能していた三丸の動けるスペースづくりはFC東京にしっかりと対策されておりまして、G大阪はハーフスペースに入り込む小野へのマーキングをサイドバックが担ってた為に大外のスペースが空いてしまったのですが、FC東京はハーフスペースにポジションを取る小野に対してはボランチが1列下がってマーキングにつくか、もしくはセンターバックが埋める事になりました。これにより、室屋が外をしかける三丸とマッチアップを生み、三丸が裏に抜けてクロスというシーンは結局1回も訪れませんでした。FC東京が対策を打ってきたのか、それともドイスボランチの通常の動きの中でのこの対応だったのかはわかりませんが、非常に堅固な守備組織で、鳥栖としては固められてから崩すのは難しかった感じでした。
前節ではうまくいった三丸への攻撃パターンが封じられてしまったので、単純にクロスチャンスの減少につながりました。G大阪戦のような再現性のある攻撃は影を潜め、攻撃の活路はカウンターによる速い攻めとロングボールに対するセカンドボールの奪取時に限られました。


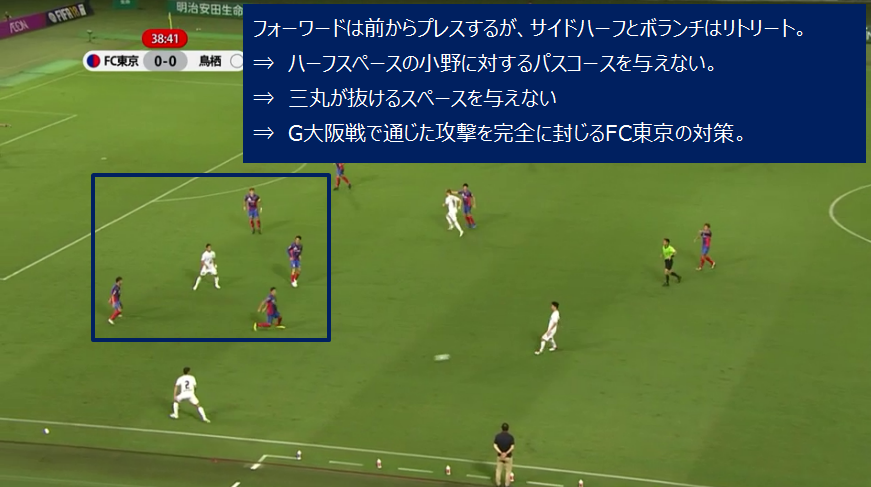

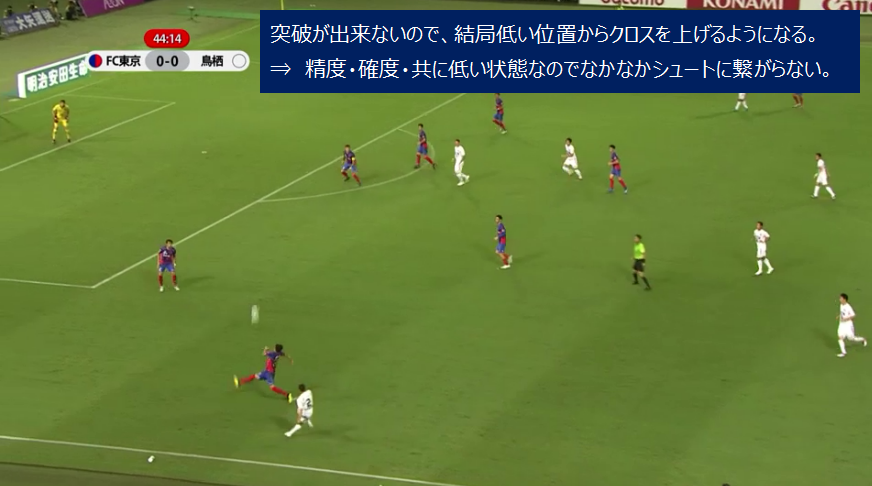



ただ、ビルドアップからの崩しはなかなか果たせなかったのですが、FC東京もミスがなかったわけではなく、鳥栖のプレッシャーによって相手にパスミスを誘発したり、カウンターによる速い攻撃はある程度の成果を見せました。しかしながら、基本的には、攻撃のタクトを天性の才能を持つ前線の3人のアイデアに任されている状態ですので、例えばFC東京のように「永井は裏を狙う」「オリベイラは引いて受ける」のような基礎構造といいますか、明確な役割分担が存在しないために、かみ合わない攻撃も見られました。

後半も終盤に入るとオープンな展開になり、特に小野が流れる右サイドからはクロスを上げるチャンスも増えてきました。FC東京も疲れていてプレスもリトリートも甘くなってきたので、前半にビルドアップで体制を崩すことができなくて苦労した攻撃だったのがウソのようにボールを簡単に前線に運べるようになりました。しかしながら、ラストパスの質が上がらず、なかなかシュートチャンスにつながりません。特に金崎に対するパス、そして右サイドからのクロスにもう少し質があれば…と悔やまれるシーンは多く作れました。
■金崎へのパス


■クロスの質



秩序と混沌。サガン鳥栖の現状として、守備は秩序を保たれていますが、攻撃はまだ混沌としています。確かに、攻撃は秩序ばかりでは機能しません。相手が秩序を持って守っているところに意図的に混沌を生み出す事によって構築している守備体系に風穴を空ける事ができます。しかしながら、秩序のないままでの混沌では、それは自分たちの攻撃の形が作れていないという事であり、自分たちのリズムに乗った攻撃ではありません。ボールを奪って前に送っても選手がバッティングしてボールロストしたり、前線に起点を作ってもサイドに人がかぶってしまってクロスを上げたら選手がいないという状況を生み出すのは、ロールが定まっていない証拠です。
ボールを受けるロール、ラストパスを送るロール、そしてシュートを決めるロール。事前に役割分担を決めても相手あってのことですから、用意してきたものが通用しない場合もあります。しかしながら、ロールをしっかりと決めていれば相手の守備が整備されない状況を生み出した時、サイドに出る人、ゴール前に構える人、ポジションの迷うことなく効率的に攻撃を再構築することが可能となります。現在のサガン鳥栖は基本とするロールがない事が、カウンターチャンスでも、ビルドアップの出口を見つけても、それがシュートチャンスまで至らない状況を生んでいる気がしてなりません。
サガン鳥栖の攻撃の正解とは何か。サガン鳥栖の攻撃における適正な状態とは何か。トーレスが引いて藤田に浮き球を送るプレイは果たして求めているプレイなのか。金崎がサイドのスペースに入ってクロスを上げるのは果たして求めているプレイなのか。この試合でのシュート数は6本だったのですが、ラスト10分で投入された安在がそのうちの多くを稼いだ印象です。そういう状況が果たして正解なのかという所ですよね。一瞬のチャンスを作っても、それが選手の個々のアイデアによって生み出されたものであるならば、同じ攻撃を再現することはできません。そのあたりを良く整理して、チームとして求める形を多く作り上げてほしいですね。
FC東京のロールは完全に整理されていました。ディエゴ・オリベイラのスペースを見つけて引いて受ける立ち回りは攻撃の基軸として明確に機能していましたし、リンスが入ると今度はリンスがそのロールを演じることになりスペースを見つけてボールを受けていました。そしてディエゴ・オリベイラはストライカーと立ち回りを変えていました。
チーム全体がやるべき事を理解し、そしてそのやるべき事を実践する。FC東京がここ最近勝てていない理由がわからなくなる試合でした(笑)
<画像引用元:DAZN>
鳥栖のスタメンは、前節熱中症で途中交代した小林に代わり藤田、原川に代わって義希が入りました。無失点という結果を出したオマリ、三丸も継続してスタメンです。マッシモの信頼が厚い原川はベンチにも入らず。疲労なのか怪我なのか戦術の影響なのかはわかりません。FC東京も永井、チャンヒョンス、そして怪我明けの橋本が前節と変わってスタメンに入ります。
鳥栖のセットアップは、攻撃時は4-3-3。小野、金崎が流動的にポジションを変えるので4-3-2-1のクリスマスツリー型の時もありましたが、4-3-3の3ラインで表現した方が適切でしょう。守備時は4-3-3から流動的にトーレスが下がったり小野が下がったりして中盤をカバーする形で臨みましたが、試合途中から小野が下がり、4-4-2でのブロックへと変化しました。

途中から4-4-2に変えるくらいならば、なぜ最初から4-4-2にしないのかという疑問が湧きあがるかもしれませんが、恐らくマッシモは試合開始当初は前線からハメていく形を作って押し込んでいきたいのでしょう。相手が立ち上がりでどのように鳥栖のプレッシャーをかわしてビルドアップしていくかという制度設計が完全でない状態であるので、前からプレッシャーをかけてボールを奪えればすぐにビッグチャンスが訪れます。また、試合開始当初は鳥栖としてはビルドアップにこだわらずに、最終ラインからトーレス目がけてロングボールを放り込んでおり、前線に人数を置いているため、奪われても早くプレッシャーをかける事ができます。名古屋戦がそうだったのですが、立ち上がりの状態でプレッシングによって相手のミスを生じさせて早めに得点チャンスを迎えて、そして奪い切れれば万々歳という試合の入り方でした。
ただし、相手がその鳥栖の戦術に慣れ、ビルドアップで鳥栖の前線からのプレッシャーをしのぐ仕組みを確立した頃が鳥栖のシステム変更のタイミングです。おそらく、その頃には相手が鳥栖の4-3-3プレッシングで空いた中盤のスペースを攻略する戦いを仕掛けている状況でしょうから、そのときは4-4-2で中盤のスペースを消す戦いにシフトします。試合の中で、まずは攻撃的な手を打ち、試合を進めながら守備で対応しづらい状況が発生してきたら、少しずつ変化を加えていくという作戦なのでしょう。試合途中での福田のサイドチェンジも同様です。4-4-2で押し込まれると福田がポジションを下げて5-3-2ブロックに変化しますが、相手がそのブロックになれて福田のスペースをうまく利用できるようにすると、福田を逆サイドに持ってきてまた相手の設計を狂わせる形を取ります。守備的なメンバーを付けたいという要素もあるでしょうが、福田を最終ラインに下げるというやり方はどちらのサイドでも変わらないので、よりハマる方を模索しながら対応しているように見えました。
■ 福田を下げる形を攻略されると…


■ 福田を逆サイドに移して対応方法を変える

この試合でも同様に4-3-3でスタートしたのですが、4-3-3プレッシングによる成果はあまり上げる事ができませんでした。正確に言うと4-3-3プレッシングによって相手のミスを生んだシーンもありましたが、それ以上に4-3-3によって生じる中盤のスペースを利用されるケースが多かったという形です。鳥栖にとってネガティブな要素だったのが、FC東京が速いカウンターを仕掛けてきた場合、中盤のプレイヤーという役割を意識している3センターの戻りは早いけれども、攻撃のタスクを与えられているフォワード陣の戻りが甘く、FC東京に3センターの脇のスペースを使われてしまう状況を生んでいました。遅い攻撃の場合はほとんど小野、時折トーレスや金崎が中盤のスペースを埋める役割を担いますが、ボールを奪った時の起点が明確でないという状況も生まれます。結局、4-3-3による守備組織を諦め、30分頃からはっきりと小野が中盤のスペースを埋めてサイドハーフに入るようになりました。


前半30分頃から小野を下げて4-4-2で中盤のスペースを埋めるシステムに変更しましたが、FC東京の洗練された、そして統率された攻撃が鳥栖のディフェンス陣を苦しめます。鳥栖の4-4ブロックを破壊するための基礎的な動きとして、ディエゴ・オリベイラは引いて最終ラインやボランチからボールを受ける動きを見せ、そして永井は裏に飛び出してボールを引き出そうとするダブルアクションを見せます。鳥栖としては、ディエゴについて行ったら最終ラインの裏を狙われるし、永井のケアをしたらディエゴ・オリベイラに簡単にキープされるという状況を生みます。更に厄介な事に東と大森が縦横無尽にその周りを駆けずり回られるという、鳥栖のセントラルハーフと最終ラインは常に対応を考えさせられており、体力と共に精神的疲労も大きかったかと思います。


ディエゴ・オリベイラのライン間で受ける動きは非常に効果的でした。FC東京が室屋と太田を高い位置に上げて幅を取る動きを見せ、最終ラインに寄るサイドチェンジも素早く行われるので、鳥栖が片方のサイドを捨てきれないで徐々に中盤の4人のライン間が広がります。ディエゴ・オリベイラは、セントラルハーフ4人のメンバー間のスペースが空くことを見越してポジションを下げ、ボランチからのボールの配球を引き出します。そこからは個人の質という要素もありますが、ボールを受けてからひとり剥がすのは造作もないとばかりにターンして前を向きます。このタイミングで、両サイドバックや永井が最終ラインの裏に抜けようとするので、その対応で鳥栖のオリベイラに対するプレッシャーも完全ではなくなり、いくつかのミドルシュートを狙われました。
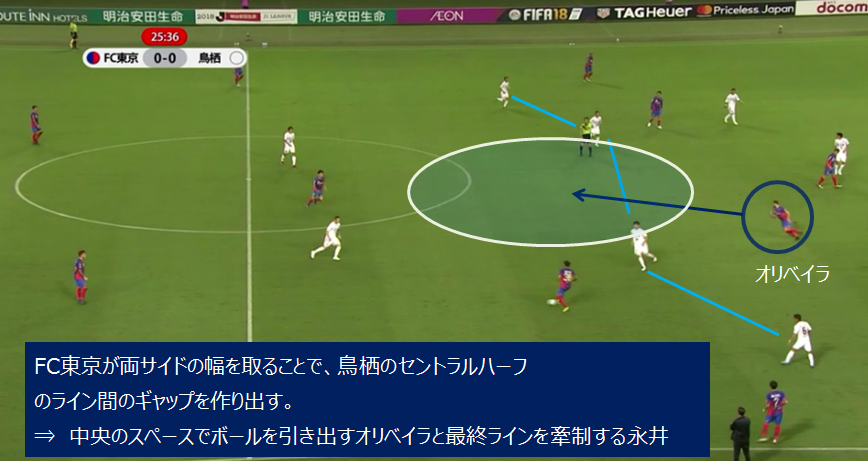

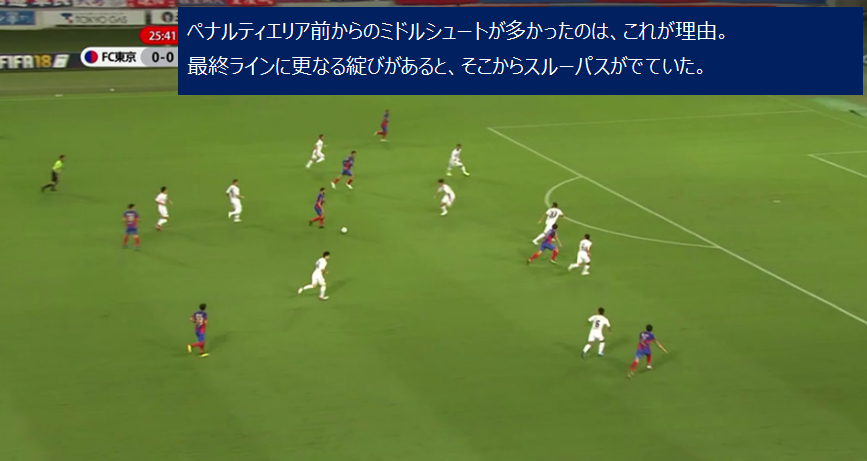
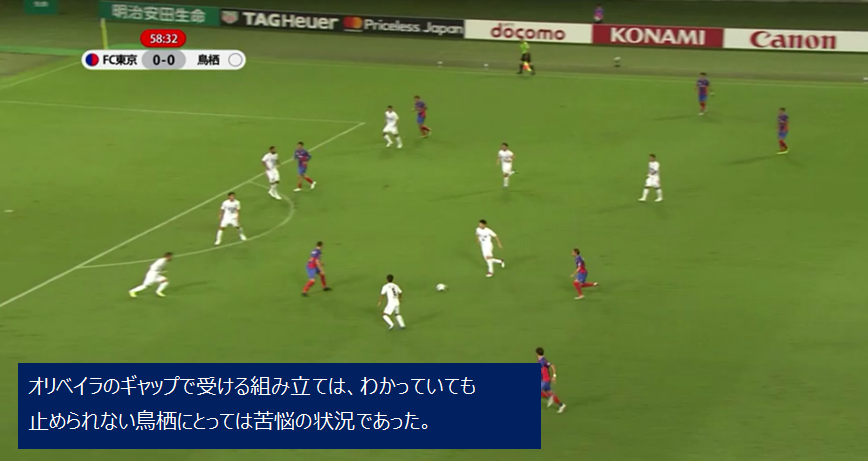
FC東京の戦術の浸透が浸透していたのは、下の図の動きにも現れており、このシーンでは役割分担を変えて、最終ラインを押し下げる役割をオリベイラが果たし、中盤に引いてボールを引き出す役割を永井が果たしています。結果的には、永井がスピードを利用して自分で空けた最終ラインの裏のスペースに走り込んでシュートを放ちますが、ツートップの動きは統率がとれていました。


実況では、ディエゴ・オリベイラの単独ショウという言葉もありましたが、実際にはディエゴ・オリベイラがボールを受けるタイミングやスペースを作るためにFC東京全体が動いていたという感じです。両サイドの幅を取る太田と室屋は、チャンスに直結する仕事が出来なかったとしても、高いポジションを取るだけで鳥栖にとっては対応の手を準備しなければならず、かなりの脅威でありました。
鳥栖の最終ライン…特にオマリと三丸ですが、この試合でも相手を無失点に抑える良い守備対応を見せていました。この結果を手放しで褒め称えても良いのですが、更なる強靭な守備組織の構築という事で、あえて今後の課題を投げかけます。
FC東京がサイドバックとサイドハーフを高い位置に押し上げてきたときに、鳥栖はサイドハーフと三丸がプレッシャーをかけるためにややマンマーク気味につくことになります。これによってオマリの特徴である中央にプライオリティを置くという守備思想とのギャップが生まれ、サイドバックとの間のスペースを空けることになります。このスペースに対してはオリベイラや永井がしっかりとそのエリアを狙ってボールを引き出す動きを見せました。最終的には中央を固める事によってなんとか失点を喫することはなかったのですが、ボックス内にボールを運ばれる仕組みをFC東京に作られてしまいました。ちなみに、ここは神戸戦やG大阪戦でも使えるスペースだったのですが、利用するためのプレーは見られず。攻撃が洗練されているFC東京ならではというところでしょう。




また、三丸も吉田に比べると前からのプレッシャーというよりは、最終ラインのスペースをしっかりと埋めるタイプです。必要以上に前に圧縮をかけないというプレイ性質が、取りに行くところで取れないという状況を生み出しました。下図に示しますが、サイドに追い込んでボールを奪い取れればと言うところだったのですが、ボールを中央に寄せられたところで三丸は更なるプレッシャーをかけるのではなく、撤退守備という選択をしました。これによって、FC東京は中央で前を向いてボールを持つことができ、三丸の裏のスペースへボールを送り込むことに成功しました。マッシモのリアクションを見たらわかりますが、恐らく、彼の意図としてはあのシチュエーションになったら、更なるプレッシャーをかけて欲しかったのでしょう。ボールが取れないとわかるとそっぽを向いてしまいました。(笑) 吉田ならば前へのプレッシャーをかけていたでしょうから、この場面では、吉田のプレイ性質の方がマッシモの守備戦術に合っていたということです。



オマリの件も、三丸の件も、どこか(誰か)に対して集中すると、かならず空いてしまうスペース(誰か)は出来てしまいます。チームとしてそれをどうやって埋めるのか(逆にどこを捨てるのか)を意思統一することが守備的戦術としては重要な要素になります。オマリも三丸も、狙えるときは前から行きますが、どちらかというと後ろをしっかりというタイプなのでお互いの守備性質はマッチしているのかなという感じです。これが、片方が前からどんどん行くタイプで、片方が後ろをしっかりというタイプであれば、ラインを乱してしまうことになります。守備戦術でコントロールすることが必要なのですが、最終的には個人の「クセ」というのは出てしまうものですので、そのあたりのコーディネイトも監督としては重要な仕事となります。
また、小野のサイドハーフはFC東京のようにしっかりと幅を取ってくるチームに対して果たして正解の対応だったかという疑問は残ります。鳥栖がボールサイドに寄せた時に逆サイドの小野がスライドしなかった事によって中央にスペースを空け、そのスペースを狙われてシュートまで持って行かれたケースがありました。守備の教科書だと全体のスライドに合わせて小野もスライドしなければなりません。ただ、攻撃を考えるとカウンターの起点としてサイドにポジションを残しておくという事は考えられますのでマッシモが彼の配置をどう考えていたかですね。単に守備だけを考えると、安在を先発で起用した4-4-2の方が守備の安定感はでるでしょうね。
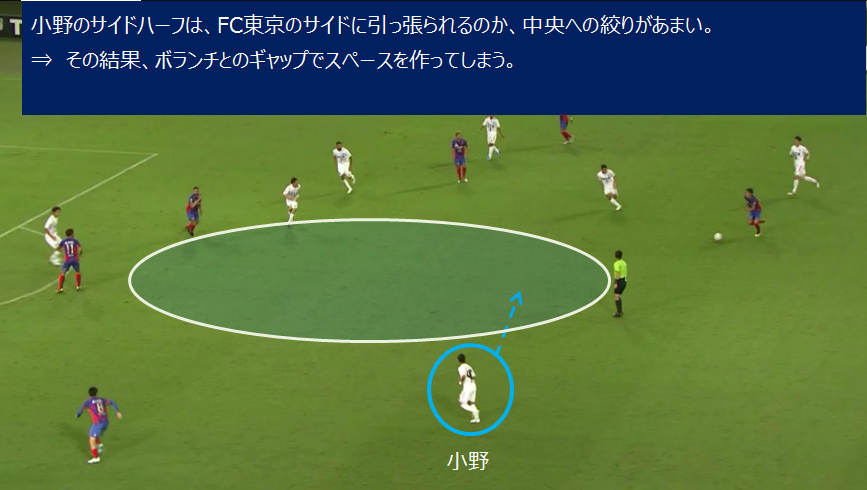

最終的には、ビルドアップで崩されても両サイドハーフが最終ラインにリトリートしてゴール前を圧縮する事によって人海戦術でゴールを防ぎましたが、FC東京の鳥栖のディフェンスを動かすための連動したプレイ、そして空いたスペースをしっかりと狙ってくる攻撃は非常に脅威でした。ここ数試合勝てていないチームという情報だったので、どれだけ調子が悪いのかと思っていたのですが、そんなことはまったくなく、ふたを開けてみればチーム戦術も整っていて今シーズン上位にポジションしているのが納得できる非常に強いチームでした。
さて、鳥栖の攻撃ですが、試合開始序盤のロングボールの応酬もひと段落した頃に、少し落ち着いてビルドアップによる攻撃を試みることになります。鳥栖の攻撃はサイドバックを高く上げて幅を取らせて、最終ラインからインサイドハーフを経由してサイドから攻撃を仕掛ける形です。

鳥栖のビルドアップに対して、FC東京はツートップが隙あらば相手もろともと言わんばかりの勢いでボールをさらいに来ます。FC東京のツートップのプレスは、チーム全体で奪うというよりは、彼ら2人で完結するならば行ってしまおうという形でした。前からのプレスに関しては、永井が一度祐治からかっさらうことに成功しましたね。オマリのカバーリングで何とか事なきを得ましたが危ないシーンでした。
FC東京の4-4(5-3)ブロックは、後述しますが鳥栖の三丸対策としてFC東京はボランチを最終ラインに下げるケースが多く、サイドバックやサイドハーフが不用意に前に出てしまうと後ろにスペースを生んでしまう事になるので、永井とオリベイラに連動するよりは、彼らがプレスしたことに抜け出てくるだろうボールの行先を抑えるというクレバーな立ち回りでした。鳥栖がツートップをかわした先のブロックの間を縫うところを探し切れず、こまねいている間にいつの間にか永井もディエゴ・オリベイラもリトリート守備に切り替えられ、打開するには大きなサイドチェンジか長いボールをトーレスめがけて蹴っ飛ばすという形になっていました。
G大阪戦で機能していた三丸の動けるスペースづくりはFC東京にしっかりと対策されておりまして、G大阪はハーフスペースに入り込む小野へのマーキングをサイドバックが担ってた為に大外のスペースが空いてしまったのですが、FC東京はハーフスペースにポジションを取る小野に対してはボランチが1列下がってマーキングにつくか、もしくはセンターバックが埋める事になりました。これにより、室屋が外をしかける三丸とマッチアップを生み、三丸が裏に抜けてクロスというシーンは結局1回も訪れませんでした。FC東京が対策を打ってきたのか、それともドイスボランチの通常の動きの中でのこの対応だったのかはわかりませんが、非常に堅固な守備組織で、鳥栖としては固められてから崩すのは難しかった感じでした。
前節ではうまくいった三丸への攻撃パターンが封じられてしまったので、単純にクロスチャンスの減少につながりました。G大阪戦のような再現性のある攻撃は影を潜め、攻撃の活路はカウンターによる速い攻めとロングボールに対するセカンドボールの奪取時に限られました。


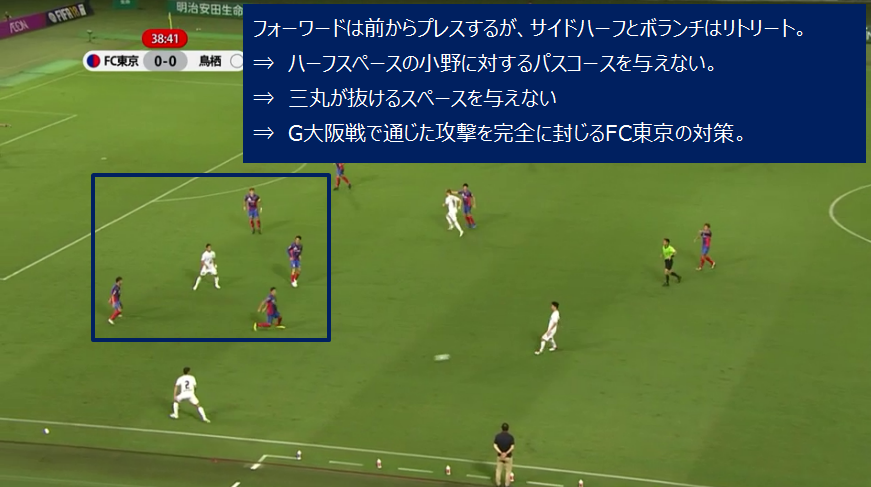

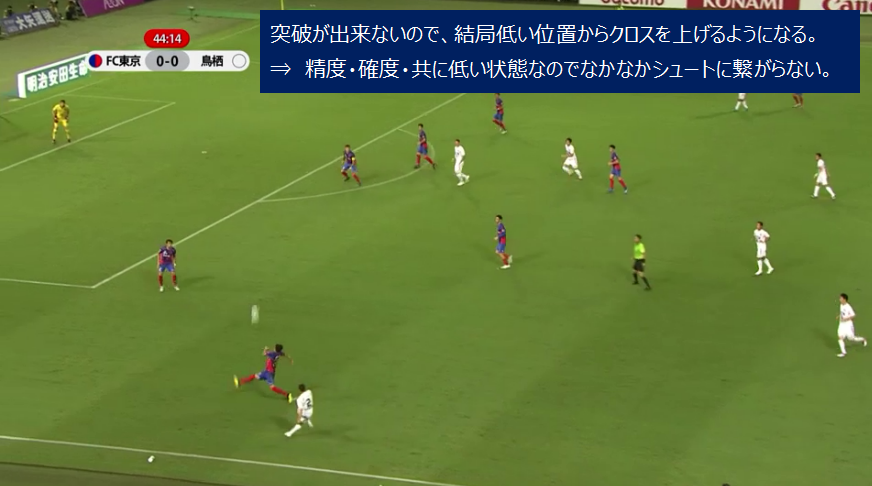



ただ、ビルドアップからの崩しはなかなか果たせなかったのですが、FC東京もミスがなかったわけではなく、鳥栖のプレッシャーによって相手にパスミスを誘発したり、カウンターによる速い攻撃はある程度の成果を見せました。しかしながら、基本的には、攻撃のタクトを天性の才能を持つ前線の3人のアイデアに任されている状態ですので、例えばFC東京のように「永井は裏を狙う」「オリベイラは引いて受ける」のような基礎構造といいますか、明確な役割分担が存在しないために、かみ合わない攻撃も見られました。

後半も終盤に入るとオープンな展開になり、特に小野が流れる右サイドからはクロスを上げるチャンスも増えてきました。FC東京も疲れていてプレスもリトリートも甘くなってきたので、前半にビルドアップで体制を崩すことができなくて苦労した攻撃だったのがウソのようにボールを簡単に前線に運べるようになりました。しかしながら、ラストパスの質が上がらず、なかなかシュートチャンスにつながりません。特に金崎に対するパス、そして右サイドからのクロスにもう少し質があれば…と悔やまれるシーンは多く作れました。
■金崎へのパス


■クロスの質



秩序と混沌。サガン鳥栖の現状として、守備は秩序を保たれていますが、攻撃はまだ混沌としています。確かに、攻撃は秩序ばかりでは機能しません。相手が秩序を持って守っているところに意図的に混沌を生み出す事によって構築している守備体系に風穴を空ける事ができます。しかしながら、秩序のないままでの混沌では、それは自分たちの攻撃の形が作れていないという事であり、自分たちのリズムに乗った攻撃ではありません。ボールを奪って前に送っても選手がバッティングしてボールロストしたり、前線に起点を作ってもサイドに人がかぶってしまってクロスを上げたら選手がいないという状況を生み出すのは、ロールが定まっていない証拠です。
ボールを受けるロール、ラストパスを送るロール、そしてシュートを決めるロール。事前に役割分担を決めても相手あってのことですから、用意してきたものが通用しない場合もあります。しかしながら、ロールをしっかりと決めていれば相手の守備が整備されない状況を生み出した時、サイドに出る人、ゴール前に構える人、ポジションの迷うことなく効率的に攻撃を再構築することが可能となります。現在のサガン鳥栖は基本とするロールがない事が、カウンターチャンスでも、ビルドアップの出口を見つけても、それがシュートチャンスまで至らない状況を生んでいる気がしてなりません。
サガン鳥栖の攻撃の正解とは何か。サガン鳥栖の攻撃における適正な状態とは何か。トーレスが引いて藤田に浮き球を送るプレイは果たして求めているプレイなのか。金崎がサイドのスペースに入ってクロスを上げるのは果たして求めているプレイなのか。この試合でのシュート数は6本だったのですが、ラスト10分で投入された安在がそのうちの多くを稼いだ印象です。そういう状況が果たして正解なのかという所ですよね。一瞬のチャンスを作っても、それが選手の個々のアイデアによって生み出されたものであるならば、同じ攻撃を再現することはできません。そのあたりを良く整理して、チームとして求める形を多く作り上げてほしいですね。
FC東京のロールは完全に整理されていました。ディエゴ・オリベイラのスペースを見つけて引いて受ける立ち回りは攻撃の基軸として明確に機能していましたし、リンスが入ると今度はリンスがそのロールを演じることになりスペースを見つけてボールを受けていました。そしてディエゴ・オリベイラはストライカーと立ち回りを変えていました。
チーム全体がやるべき事を理解し、そしてそのやるべき事を実践する。FC東京がここ最近勝てていない理由がわからなくなる試合でした(笑)
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
17:59
│Match Impression (2018)
2018年08月30日
2018 第24節 : サガン鳥栖 VS ガンバ大阪
2018年第24節、ガンバ大阪戦のレビューです。
スタメンですが、鳥栖は天皇杯で神戸に快勝したメンバーから、最終ラインのオマリ、三丸がスタメン抜擢となりました。両名共にミンヒョクや吉田に比べて派手なデュエルで見せるタイプではありませんが、クレバーな守備対応でポドルスキ、イニエスタ、ウェリントンなどの屈強なフォワードを相手にしてもゴールの鍵をしっかり締めきったのが認められた格好です。ガンバも最終ラインに少し変化をかけてきまして、勝ち点3を奪うためにはより攻撃的な選手の投入を…という考えだったのか、ファビオ、オジェソクが控えに回り、米倉、藤春の出場となりました。
鳥栖のシステムは、攻撃時は4-3-3でトーレスへのロングボールを軸として、金崎と小野が時にはセカンドトップのように、時にはウイングのように流動的にポジションを変えてしかける形。守備時は4-4-2で中盤をフラットにして中盤のスペースを圧縮した形でした。スタメン発表を見る限りでは、守備時は名古屋戦のように3枚のフォワードが前から圧力をかける形かと思っていましたが、ふたを開けてみれば4-4-2フラットによる守備陣形で、そのシステム可変の対応は、小野が左のサイドハーフに下がるという仕組みでした。
ガンバの攻撃は、ボール保持ファーストとでも言いましょうか。鳥栖が4-4-2を引いて最終ラインへのプレッシャーはミドルサード付近からではあったのですが、ドイスボランチ(遠藤、高)の双方を下げてでもボールを保持し、繰り返しパスを回すことによって、鳥栖のディフェンスのほころびを狙うという形でした。このガンバの攻撃が機能したのは、サイドチェンジによる逆サイドのサイドバックへの大外ルートと、鳥栖がボールを奪いに来たときに奪えなかった事によって発生したスペース、この2パターンでした。

サイド攻撃をピックアップしますが、最終ラインでボール保持しながら、そして繰り返しサイドを変えながら、ビルドアップの出口を探ります。「意外と守備はするよ」というトーレスと金崎ではありますが、豊田程に二度追い、三度追いするようなことはありません。ガンバの攻撃のスイッチが入るのは、そんな二度追い、三度追いがなくなる(フォワードのプレスが間に合わなくなる)時でした。
逆サイドへの展開でトーレスや金崎が間に合わなくなった時、最終ラインで回していたセンターバック(もしくはボランチ)がボールを運べるスペースを利用して前進します。ボールを運ばれると鳥栖のサイドハーフも出てこざるを得ず、鳥栖のサイドバックはガンバのサイドハーフを見ないといけないので、ガンバサイドバックへのマークが薄れます。その流れを利用して、ガンバはサイドバックまでボールを運ぶのは比較的苦労していなかった印象です。
大切なのはビルドアップの出口のみならず、ではそこからどうやってシュートまで繋げるのかという所なのですが、ガンバは人数をかけてサイドから縦もしくは中央に入っていくやり方を試みていました。ボランチをビルドアップ要員で利用しているので、サイドバックをフォローするのには少し距離が遠すぎます。そうなると、サイドハーフもしくはフォワードがサイドの数的優位要員とならなければなりません。そこに制約はなかった模様で、倉田、藤本、アデミウソンがその時々に応じてサイドにポジションを広げていました。カズマはサイドに加担することは少なかったのですが、サイドバックが上がったスペースに入っていくシーンもあったので、「お前はゴール前にいろ」という制約はなかったかに思えます。基本的には中央にいる事が多かったのですけどね。
藤本は中央でのプレイを好むのか、右サイドハーフの位置から中央や時折逆サイドに顔を見せていました。藤本のポジションチェンジによってガンバの攻撃が機能したシーンを紹介しますが、右サイドでボール保持して鳥栖のフォワード(トーレス)を引き寄せます。そこから逆サイドに展開してフォワードのスライドが追い付く前に前方への侵入を図ります。この時は倉田がボール保持要員としてポジションを下げており、左サイドはセンターバック、ボランチ、サイドハーフでビルドアップを試みるという、まさにこのゲームのガンバのボール保持戦術が現れています。
ここで、倉田のポジションに逆サイドの藤本が入ってきて数的・位置的優位を作り、鳥栖のライン間で藤本がボールを受ける事によって藤春のオーバーラップを活用しました。クロスの場面までは完璧だったのですが、この形だと別の課題が発生しておりまして、藤本がサイドの崩しに参画したため、クロスを上げてもファーサイドのフィニッシャーがいないという現象が発生しました。よいクロスでしたがシュートまでには至らなかったという状況です。
藤本を動かして崩した時に、ゴール前にボランチが飛び込むのか、逆サイドバックが飛び込むのか、このあたりのデザインをどう考えていたのかというのがポイントですね。サイドバックを飛び込ませるとカウンターのリスクが発生するので、自重してフォワード2人のみに託したのかもしれません。無論、前半、後半(残り時間)、点差などで攻撃デザインは異なりますが、もし、あのシーンで逆サイドのサイドバックが飛び込むというチームとしての約束があったのならば、藤春のクロスがミスなのではなく、米倉のポジショニングがミスという事になります。パスミスは、出し手のミスのように見える物でも、実はチームの約束としては受け手の方の問題であることもあります。


鳥栖の攻撃は、ボールを保持されていたもののガンバのクロスミスやパスミスに乗じて適度にカウンター攻撃を仕掛けられていました。ガンバと異なるのは、鳥栖は長いボールを基調としていたことでありまして、特にこの試合で分かり易いのはゴールキックをセンターバックにつなぐのではなく、ほぼすべてがトーレスに当てるボールとなっていました。ストロングポイントを生かすべくロングボールを送り込み、セカンドボールの回収から全体を押し上げようという戦術です。
鳥栖の攻撃のシステム可変対応は非常に機能しておりまして、ボール保持した時に左サイドで小野が高い位置を取ります。これによって、ガンバとしてはハーフスペースにポジションを取る小野を誰が見るのかという選択をしなければならなくなりました。
ガンバの回答としては、トーレスとセンターバックが1VS1となることを回避したのか、小野のサイドにスライドさせて逆サイドのスペースを空けるのを嫌ったのか、その理由は様々あるでしょうが、右サイドバックの米倉が小野につくことになり、大外のスペースとしてはガンバとして捨てざるを得ないエリアとなってしまいました。大外のスペースという、三丸にとっては格好のエサが出来ましたので、インサイドハーフがガンバのサイドハーフとボランチの間のスペースを縫って縦位置にいる小野に当て、そこからワンタッチで大外のスペースに流すという、一連の攻撃パターンが確立できました。これにより、何度も三丸のクロスというチャンスを得る事ができました。




三丸が良かったのは、大外レーンに待機するものの前過ぎず、後ろ過ぎずというポジションの取り方。ガンバのサイドハーフにとっては、ボールが三丸に直接出た時に備えた対応も考えなければならず、非常に間合いの取り方が難しかったかと思います。三丸のスピードが速くて、ハーフスペースに待機する小野にパスが出た後にダッシュを始めても間に合うので、このようなポジショニングが可能となりました。ガンバとしては複数の選択肢のなかでどれを重要視するのかという選択を迫られていて難しい対応だったかなと。
さて、そんなこんなで前半終わってからの感想のツイートはこういう事でした。
前半のボール保持するガンバとそれを4-4-2ブロックで待ち受ける鳥栖という堅い構図では、試合が動くようなイベントはありませんでした。ガンバとしては予定通りボールは保持できていてサイドを使って攻撃はできている、あとはフィニッシュ次第。鳥栖としては予定通りブロックを組んでガンバに決定的なチャンスは作られず、適度にカウンター攻撃は仕掛けられている、あとはフィニッシュ次第。前半終了時点では、どちらもある程度思いのままに試合を進められていて、ネガティブな印象はなかったかと思います。
後半から、(正確には、小林の熱中症症状による交替くらいから)膠着状態を打開するべく、鳥栖がポジションを変えてきます。ガンバがビルドアップでボランチをさげるために、2トップのプレスがサイドチェンジによって完全に無効化してしまっているので、少し前方からプレッシングをかけるような形に変えました。具体的には左サイドハーフに下がっていた小野を1列上げました。ボール保持のために下がるガンバのボランチに対するプレッシャー要員という役割変更です。
これによって、最終ラインによるパス交換で簡単にサイドにパスが出せていたガンバに窮屈さが生まれる事になりました。ガンバのフォワードにはサイドに流れるタスクはあっても中央で引いて受けるというタスクは与えられていなかった模様で、ガンバとしてはビルドアップの出口はこれまで通り高い位置を取るサイドバックしかなく、これまで通りの攻撃パターンであるものの、最終ラインに対するプレッシャーが前半よりは強度が強くなったという状況です。鳥栖としては、これが功を奏してガンバのパスミスが発生し、鳥栖のカウンター機会の増加となりました。
■ 後半の守備体系


鳥栖の先制点は、この試合の攻撃の基軸となっていたトーレスへのロングボールから生まれたものでした。試合開始当初から献身的にチームの為にロングボールを競っていたトーレスが、このシーンでも相手に競り勝ってマイボールにします。中盤のパス交換にミスがあってガンバに奪われるものの、いち早くトーレスがプレスをかけ再度ボールを奪い返します。トーレスのロングボール対応と、ネガティブトランジション対応(ボールを奪われても直後にトーレスが中盤でプレスをかけてボールを奪いかえすシーン)はこの試合でチームを大きく助けるものとなっていました。


ここからが大事なポイントなのですが、トーレスが奪い返したボールを受けた藤田が間髪入れずに左足で逆サイドの三丸に鋭いボールで大きく展開します。左足で蹴ったという所が大事なのでありまして、これを右足で持ち替えたりしていると、逆サイドへの展開と言うのが読まれるので、ガンバの右サイドハーフや右サイドバックがサイドチェンジの準備で三丸に対するプレッシャーをかけることができます。しかしながら、藤田の間髪いれない左足のキックによって、三丸が余裕を持ってトラップをすることができました。ここが一つの成功要因です。

さて、ボールを受けた三丸ですが、前半は早いタイミングで(時にはダイレクトで)クロスを中央に入れていました。あわやオウンゴールというシーンもあったのですが、繰り返し入ってくるクロスはガンバの最終ラインを緊張させるのには十分のインパクトを与えていました。あのクロスのイメージがあるので、ガンバは三丸がボールを持つと当時に、ボランチも最終ラインにさげてゴール前を固める動きにでます。三丸はクロスを入れるという選択と、中央に繋ぐという選択があったのですが、三丸の選択は中央への繋ぎ。この繋ぎがもう一つのポイントでありまして、クロスに備えてゴール前を固めるガンバは、バイタルエリアのスペースを空けてしまう状況が生まれていました。

ここからは、スペースを見つけるのが得意なトーレスが引き、原川がトーレスにあてて、トーレスは小野に落として小野がシュートを放つという、最終ラインを押し下げた上でミドルシュートを放つという攻撃の教科書に載っているようなパス交換を演じてくれました。
前半に三丸が度重なる早いクロスをあげ、得点にはつながらなかったものの、クロスによって与えた脅威から、小野のミドルシュートによるゴールが生まれました。(相手に当たったのは運が良かったですけどね。大事なのはフリーでのシュートの機会を作るという事です。)


特に後半は、鳥栖のカウンター攻撃によるチャンスメイクが活発に行われておりまして、際立ったのがオマリのボールコントロールです。相手の攻撃をクリアするときに、これまでは攻撃回避のためにロングボールを相手の裏に送り込むことが多かったのですが、オマリはそれをクリアボールで攻撃をかわすだけのキックとせずに、しっかりと味方にあててカウンター攻撃に繋げる縦パスとするケースを多く作っていました。守備でも周りをしっかりとコーチングしておりますが、その時から周りのポジショニングが見えているからこそ、クリアではなくパスとしてマイボールにすることができています。
■ カウンターの起点となるオマリのパス




そのオマリですが、守備対応も神戸戦と同様に安定しておりまして、基本はゴールマウスの前を固めてしっかりとスペースを締める思想ですが、ボールの状況、味方の状況、そして相手の状況を見計らって縦パスをつぶしにかかる対応も見せておりました。その辺りのリトリートするケースと前に出てプレッシャーをかけるケースの判断力や相手との駆け引き面で選択ミスの少ない非常にインテリジェンスな対応をとっていました。
もちろん、守備頭脳だけでなく、裏を取られようとした時の反転の速さなど、個人としての守備能力の高さも見せてくれました。オマリが我らの天敵である渡邊千真を完璧に抑え込むことによって、この試合を無失点で終える原動力となりました。人間としてのコミュニケーション能力も高そうで、トーレスとともにこの夏の素晴らしい補強選手ですね。
■ カズマ対応


■ ゴール前のポジショニング


同点に追い付くために攻勢をしかけるガンバでしたが、鳥栖も要所要所でカウンター攻撃をしかけ、原川のシュートがポストに当たったシーンやトーレスのスルーパスから金崎がゴール前に抜けたシーンなど、いくつかの得点チャンスを作ります。そして追加点の時が訪れるのですが、追加点も起点はトーレスへの長いボールの落としによるものでした。
トーレスのヘディングを上手く拾った金崎が、右サイドをあがるトーレスにボールを渡します。トーレスはドリブルで前進しながら、タイミングを見計らって金崎に好パスを送り込みました。実はこのシーンは伏線がありまして、この2得点目の約5分前のシーンで、同じくトーレスが右サイドでボールを持って縦への突破を図るシーンがあります。このように縦への突破を一度見せられていますので、ディフェンスとしては縦の突破も意識しなければなりません。この場面で縦を切るか横を切るかと言うのは後ろの選手との連係が必要なのですが、前を向いてしっかりと相対するトーレスの動きを抑えるのは難しかったでしょう。パスを受けてディフェンス(ボランチ)が戻りきる前にバイタルスペースを狙い打ちしてトラップ、そしてシュートを放った金崎も見事でした。先制点も追加点も、前半から築き上げてきた攻撃パターンによって相手の対応の難しさを生み、ゴールとして仕留めた感じですね。
■2点目



トーレスはロングボールのデュエル勝率とネガトラプレスによるボール奪取による活躍もありましたが、当然のことながら、ストライカーとしての嗅覚を存分に発揮して、ゴールチャンスを幾度も演出しておりました。いくつか紹介します。
一つ目が原川のシュートがポストに当たったシーンです。原川がシュートを放った時点では、ガンバの最終ラインよりも手前にポジショニングを取っています。(オフサイドにならないように)そして、原川がシュートを放ったタイミングで、しっかりと相手最終ラインよりも前に出て、ゴールキーパーのセービングや、ポストの跳ね返りなど、セカンドボールが発生した際に備えてしっかりとポジションを取っています。これぞ、スペイン代表のストライカーというポジショニングです。
■ストライカーとしての嗅覚1


2つ目ですが、安在がドリブル突破で右サイドに侵入した時には、トーレスはファーサイドに逃げる動きを見せます。しかしながら、安在の突破への備えでガンバのセンターバックがニアのスペースを埋めるためにポジションを変えた瞬間、そのスペースを狙ってダイアゴナルに入ってきました。その動きを見てバスを送り込んだ安在も見事でしたね。1点もののシーンでしたが、東口もポジショニングをしっかり取って好セーブでした。
■ストライカーとしての嗅覚2



そして、歓喜のシーンが訪れます。ゴールキーパーのクリアボールを拾った福田が右サイドに侵入してきた時には、トーレスはニアサイドを走っていました。そして福田が縦に入るのを見て、ファーサイドに逃げるようにポジションを動かします。それに合わせて、金崎がニアサイドに入り込んできたのも、ガンバセンターバックを動かす形で良い連係でした。ファーサイドのスペースを見つけたトーレス、福田の息があってあのダイビングヘッドのシーンを作ることが出来ました。
■ストライカーとしての嗅覚3(3点目)




ガンバとしては疲れもあったのかもしれませんが、サイドバックの絞りが遅れたことが致命的でしたね。ゴール前の守備は人数が足りている、足りていないよりも、スペースを守る選手がいるのか、いないのかが重要になります。ガンバの方が選手の人数は多かったのですが、肝心なエリアを守れる選手がいなかったですね。
鳥栖のサイドバックはその辺りはしっかりと守備意識がありまして、ゴール前で小林、藤田、吉田がクリアするというシーンをよく見るかと思います。逆サイドのサイドバックは、センターバックとしての役割も求められます。
さて、大事な大事なシックスポイントマッチを、金崎のサガン鳥栖初ゴール、トーレスのリーグ初ゴールというおまけ付きで快勝したサガン鳥栖。それでもまだ降格圏内ですので、次節もしっかりと勝利(最低でも勝ち点1)を取ることが求められます。苦しい戦いが続きますが、少しずつ連係を上げて、良い試合を行いたいですね。
<画像引用元:DAZN>
スタメンですが、鳥栖は天皇杯で神戸に快勝したメンバーから、最終ラインのオマリ、三丸がスタメン抜擢となりました。両名共にミンヒョクや吉田に比べて派手なデュエルで見せるタイプではありませんが、クレバーな守備対応でポドルスキ、イニエスタ、ウェリントンなどの屈強なフォワードを相手にしてもゴールの鍵をしっかり締めきったのが認められた格好です。ガンバも最終ラインに少し変化をかけてきまして、勝ち点3を奪うためにはより攻撃的な選手の投入を…という考えだったのか、ファビオ、オジェソクが控えに回り、米倉、藤春の出場となりました。
鳥栖のシステムは、攻撃時は4-3-3でトーレスへのロングボールを軸として、金崎と小野が時にはセカンドトップのように、時にはウイングのように流動的にポジションを変えてしかける形。守備時は4-4-2で中盤をフラットにして中盤のスペースを圧縮した形でした。スタメン発表を見る限りでは、守備時は名古屋戦のように3枚のフォワードが前から圧力をかける形かと思っていましたが、ふたを開けてみれば4-4-2フラットによる守備陣形で、そのシステム可変の対応は、小野が左のサイドハーフに下がるという仕組みでした。
ガンバの攻撃は、ボール保持ファーストとでも言いましょうか。鳥栖が4-4-2を引いて最終ラインへのプレッシャーはミドルサード付近からではあったのですが、ドイスボランチ(遠藤、高)の双方を下げてでもボールを保持し、繰り返しパスを回すことによって、鳥栖のディフェンスのほころびを狙うという形でした。このガンバの攻撃が機能したのは、サイドチェンジによる逆サイドのサイドバックへの大外ルートと、鳥栖がボールを奪いに来たときに奪えなかった事によって発生したスペース、この2パターンでした。

サイド攻撃をピックアップしますが、最終ラインでボール保持しながら、そして繰り返しサイドを変えながら、ビルドアップの出口を探ります。「意外と守備はするよ」というトーレスと金崎ではありますが、豊田程に二度追い、三度追いするようなことはありません。ガンバの攻撃のスイッチが入るのは、そんな二度追い、三度追いがなくなる(フォワードのプレスが間に合わなくなる)時でした。
逆サイドへの展開でトーレスや金崎が間に合わなくなった時、最終ラインで回していたセンターバック(もしくはボランチ)がボールを運べるスペースを利用して前進します。ボールを運ばれると鳥栖のサイドハーフも出てこざるを得ず、鳥栖のサイドバックはガンバのサイドハーフを見ないといけないので、ガンバサイドバックへのマークが薄れます。その流れを利用して、ガンバはサイドバックまでボールを運ぶのは比較的苦労していなかった印象です。
大切なのはビルドアップの出口のみならず、ではそこからどうやってシュートまで繋げるのかという所なのですが、ガンバは人数をかけてサイドから縦もしくは中央に入っていくやり方を試みていました。ボランチをビルドアップ要員で利用しているので、サイドバックをフォローするのには少し距離が遠すぎます。そうなると、サイドハーフもしくはフォワードがサイドの数的優位要員とならなければなりません。そこに制約はなかった模様で、倉田、藤本、アデミウソンがその時々に応じてサイドにポジションを広げていました。カズマはサイドに加担することは少なかったのですが、サイドバックが上がったスペースに入っていくシーンもあったので、「お前はゴール前にいろ」という制約はなかったかに思えます。基本的には中央にいる事が多かったのですけどね。
藤本は中央でのプレイを好むのか、右サイドハーフの位置から中央や時折逆サイドに顔を見せていました。藤本のポジションチェンジによってガンバの攻撃が機能したシーンを紹介しますが、右サイドでボール保持して鳥栖のフォワード(トーレス)を引き寄せます。そこから逆サイドに展開してフォワードのスライドが追い付く前に前方への侵入を図ります。この時は倉田がボール保持要員としてポジションを下げており、左サイドはセンターバック、ボランチ、サイドハーフでビルドアップを試みるという、まさにこのゲームのガンバのボール保持戦術が現れています。
ここで、倉田のポジションに逆サイドの藤本が入ってきて数的・位置的優位を作り、鳥栖のライン間で藤本がボールを受ける事によって藤春のオーバーラップを活用しました。クロスの場面までは完璧だったのですが、この形だと別の課題が発生しておりまして、藤本がサイドの崩しに参画したため、クロスを上げてもファーサイドのフィニッシャーがいないという現象が発生しました。よいクロスでしたがシュートまでには至らなかったという状況です。
藤本を動かして崩した時に、ゴール前にボランチが飛び込むのか、逆サイドバックが飛び込むのか、このあたりのデザインをどう考えていたのかというのがポイントですね。サイドバックを飛び込ませるとカウンターのリスクが発生するので、自重してフォワード2人のみに託したのかもしれません。無論、前半、後半(残り時間)、点差などで攻撃デザインは異なりますが、もし、あのシーンで逆サイドのサイドバックが飛び込むというチームとしての約束があったのならば、藤春のクロスがミスなのではなく、米倉のポジショニングがミスという事になります。パスミスは、出し手のミスのように見える物でも、実はチームの約束としては受け手の方の問題であることもあります。


鳥栖の攻撃は、ボールを保持されていたもののガンバのクロスミスやパスミスに乗じて適度にカウンター攻撃を仕掛けられていました。ガンバと異なるのは、鳥栖は長いボールを基調としていたことでありまして、特にこの試合で分かり易いのはゴールキックをセンターバックにつなぐのではなく、ほぼすべてがトーレスに当てるボールとなっていました。ストロングポイントを生かすべくロングボールを送り込み、セカンドボールの回収から全体を押し上げようという戦術です。
鳥栖の攻撃のシステム可変対応は非常に機能しておりまして、ボール保持した時に左サイドで小野が高い位置を取ります。これによって、ガンバとしてはハーフスペースにポジションを取る小野を誰が見るのかという選択をしなければならなくなりました。
ガンバの回答としては、トーレスとセンターバックが1VS1となることを回避したのか、小野のサイドにスライドさせて逆サイドのスペースを空けるのを嫌ったのか、その理由は様々あるでしょうが、右サイドバックの米倉が小野につくことになり、大外のスペースとしてはガンバとして捨てざるを得ないエリアとなってしまいました。大外のスペースという、三丸にとっては格好のエサが出来ましたので、インサイドハーフがガンバのサイドハーフとボランチの間のスペースを縫って縦位置にいる小野に当て、そこからワンタッチで大外のスペースに流すという、一連の攻撃パターンが確立できました。これにより、何度も三丸のクロスというチャンスを得る事ができました。




三丸が良かったのは、大外レーンに待機するものの前過ぎず、後ろ過ぎずというポジションの取り方。ガンバのサイドハーフにとっては、ボールが三丸に直接出た時に備えた対応も考えなければならず、非常に間合いの取り方が難しかったかと思います。三丸のスピードが速くて、ハーフスペースに待機する小野にパスが出た後にダッシュを始めても間に合うので、このようなポジショニングが可能となりました。ガンバとしては複数の選択肢のなかでどれを重要視するのかという選択を迫られていて難しい対応だったかなと。
さて、そんなこんなで前半終わってからの感想のツイートはこういう事でした。
小野、原川がハーフスペースで相手をピン止めして左サイドを空け、大外から入ってきた三丸がクロスを上げる機会を作れてるので、なんとか一本良いのが入れば。
— オオタニ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2018年8月26日
あと5本はクロスチャンスあるでしょうから、なんとか一本ピンポイントクロスを!
前半のボール保持するガンバとそれを4-4-2ブロックで待ち受ける鳥栖という堅い構図では、試合が動くようなイベントはありませんでした。ガンバとしては予定通りボールは保持できていてサイドを使って攻撃はできている、あとはフィニッシュ次第。鳥栖としては予定通りブロックを組んでガンバに決定的なチャンスは作られず、適度にカウンター攻撃は仕掛けられている、あとはフィニッシュ次第。前半終了時点では、どちらもある程度思いのままに試合を進められていて、ネガティブな印象はなかったかと思います。
後半から、(正確には、小林の熱中症症状による交替くらいから)膠着状態を打開するべく、鳥栖がポジションを変えてきます。ガンバがビルドアップでボランチをさげるために、2トップのプレスがサイドチェンジによって完全に無効化してしまっているので、少し前方からプレッシングをかけるような形に変えました。具体的には左サイドハーフに下がっていた小野を1列上げました。ボール保持のために下がるガンバのボランチに対するプレッシャー要員という役割変更です。
これによって、最終ラインによるパス交換で簡単にサイドにパスが出せていたガンバに窮屈さが生まれる事になりました。ガンバのフォワードにはサイドに流れるタスクはあっても中央で引いて受けるというタスクは与えられていなかった模様で、ガンバとしてはビルドアップの出口はこれまで通り高い位置を取るサイドバックしかなく、これまで通りの攻撃パターンであるものの、最終ラインに対するプレッシャーが前半よりは強度が強くなったという状況です。鳥栖としては、これが功を奏してガンバのパスミスが発生し、鳥栖のカウンター機会の増加となりました。
■ 後半の守備体系


鳥栖の先制点は、この試合の攻撃の基軸となっていたトーレスへのロングボールから生まれたものでした。試合開始当初から献身的にチームの為にロングボールを競っていたトーレスが、このシーンでも相手に競り勝ってマイボールにします。中盤のパス交換にミスがあってガンバに奪われるものの、いち早くトーレスがプレスをかけ再度ボールを奪い返します。トーレスのロングボール対応と、ネガティブトランジション対応(ボールを奪われても直後にトーレスが中盤でプレスをかけてボールを奪いかえすシーン)はこの試合でチームを大きく助けるものとなっていました。


ここからが大事なポイントなのですが、トーレスが奪い返したボールを受けた藤田が間髪入れずに左足で逆サイドの三丸に鋭いボールで大きく展開します。左足で蹴ったという所が大事なのでありまして、これを右足で持ち替えたりしていると、逆サイドへの展開と言うのが読まれるので、ガンバの右サイドハーフや右サイドバックがサイドチェンジの準備で三丸に対するプレッシャーをかけることができます。しかしながら、藤田の間髪いれない左足のキックによって、三丸が余裕を持ってトラップをすることができました。ここが一つの成功要因です。

さて、ボールを受けた三丸ですが、前半は早いタイミングで(時にはダイレクトで)クロスを中央に入れていました。あわやオウンゴールというシーンもあったのですが、繰り返し入ってくるクロスはガンバの最終ラインを緊張させるのには十分のインパクトを与えていました。あのクロスのイメージがあるので、ガンバは三丸がボールを持つと当時に、ボランチも最終ラインにさげてゴール前を固める動きにでます。三丸はクロスを入れるという選択と、中央に繋ぐという選択があったのですが、三丸の選択は中央への繋ぎ。この繋ぎがもう一つのポイントでありまして、クロスに備えてゴール前を固めるガンバは、バイタルエリアのスペースを空けてしまう状況が生まれていました。

ここからは、スペースを見つけるのが得意なトーレスが引き、原川がトーレスにあてて、トーレスは小野に落として小野がシュートを放つという、最終ラインを押し下げた上でミドルシュートを放つという攻撃の教科書に載っているようなパス交換を演じてくれました。
前半に三丸が度重なる早いクロスをあげ、得点にはつながらなかったものの、クロスによって与えた脅威から、小野のミドルシュートによるゴールが生まれました。(相手に当たったのは運が良かったですけどね。大事なのはフリーでのシュートの機会を作るという事です。)


特に後半は、鳥栖のカウンター攻撃によるチャンスメイクが活発に行われておりまして、際立ったのがオマリのボールコントロールです。相手の攻撃をクリアするときに、これまでは攻撃回避のためにロングボールを相手の裏に送り込むことが多かったのですが、オマリはそれをクリアボールで攻撃をかわすだけのキックとせずに、しっかりと味方にあててカウンター攻撃に繋げる縦パスとするケースを多く作っていました。守備でも周りをしっかりとコーチングしておりますが、その時から周りのポジショニングが見えているからこそ、クリアではなくパスとしてマイボールにすることができています。
■ カウンターの起点となるオマリのパス




そのオマリですが、守備対応も神戸戦と同様に安定しておりまして、基本はゴールマウスの前を固めてしっかりとスペースを締める思想ですが、ボールの状況、味方の状況、そして相手の状況を見計らって縦パスをつぶしにかかる対応も見せておりました。その辺りのリトリートするケースと前に出てプレッシャーをかけるケースの判断力や相手との駆け引き面で選択ミスの少ない非常にインテリジェンスな対応をとっていました。
もちろん、守備頭脳だけでなく、裏を取られようとした時の反転の速さなど、個人としての守備能力の高さも見せてくれました。オマリが我らの天敵である渡邊千真を完璧に抑え込むことによって、この試合を無失点で終える原動力となりました。人間としてのコミュニケーション能力も高そうで、トーレスとともにこの夏の素晴らしい補強選手ですね。
■ カズマ対応


■ ゴール前のポジショニング


同点に追い付くために攻勢をしかけるガンバでしたが、鳥栖も要所要所でカウンター攻撃をしかけ、原川のシュートがポストに当たったシーンやトーレスのスルーパスから金崎がゴール前に抜けたシーンなど、いくつかの得点チャンスを作ります。そして追加点の時が訪れるのですが、追加点も起点はトーレスへの長いボールの落としによるものでした。
トーレスのヘディングを上手く拾った金崎が、右サイドをあがるトーレスにボールを渡します。トーレスはドリブルで前進しながら、タイミングを見計らって金崎に好パスを送り込みました。実はこのシーンは伏線がありまして、この2得点目の約5分前のシーンで、同じくトーレスが右サイドでボールを持って縦への突破を図るシーンがあります。このように縦への突破を一度見せられていますので、ディフェンスとしては縦の突破も意識しなければなりません。この場面で縦を切るか横を切るかと言うのは後ろの選手との連係が必要なのですが、前を向いてしっかりと相対するトーレスの動きを抑えるのは難しかったでしょう。パスを受けてディフェンス(ボランチ)が戻りきる前にバイタルスペースを狙い打ちしてトラップ、そしてシュートを放った金崎も見事でした。先制点も追加点も、前半から築き上げてきた攻撃パターンによって相手の対応の難しさを生み、ゴールとして仕留めた感じですね。
■2点目



トーレスはロングボールのデュエル勝率とネガトラプレスによるボール奪取による活躍もありましたが、当然のことながら、ストライカーとしての嗅覚を存分に発揮して、ゴールチャンスを幾度も演出しておりました。いくつか紹介します。
一つ目が原川のシュートがポストに当たったシーンです。原川がシュートを放った時点では、ガンバの最終ラインよりも手前にポジショニングを取っています。(オフサイドにならないように)そして、原川がシュートを放ったタイミングで、しっかりと相手最終ラインよりも前に出て、ゴールキーパーのセービングや、ポストの跳ね返りなど、セカンドボールが発生した際に備えてしっかりとポジションを取っています。これぞ、スペイン代表のストライカーというポジショニングです。
■ストライカーとしての嗅覚1


2つ目ですが、安在がドリブル突破で右サイドに侵入した時には、トーレスはファーサイドに逃げる動きを見せます。しかしながら、安在の突破への備えでガンバのセンターバックがニアのスペースを埋めるためにポジションを変えた瞬間、そのスペースを狙ってダイアゴナルに入ってきました。その動きを見てバスを送り込んだ安在も見事でしたね。1点もののシーンでしたが、東口もポジショニングをしっかり取って好セーブでした。
■ストライカーとしての嗅覚2



そして、歓喜のシーンが訪れます。ゴールキーパーのクリアボールを拾った福田が右サイドに侵入してきた時には、トーレスはニアサイドを走っていました。そして福田が縦に入るのを見て、ファーサイドに逃げるようにポジションを動かします。それに合わせて、金崎がニアサイドに入り込んできたのも、ガンバセンターバックを動かす形で良い連係でした。ファーサイドのスペースを見つけたトーレス、福田の息があってあのダイビングヘッドのシーンを作ることが出来ました。
■ストライカーとしての嗅覚3(3点目)




ガンバとしては疲れもあったのかもしれませんが、サイドバックの絞りが遅れたことが致命的でしたね。ゴール前の守備は人数が足りている、足りていないよりも、スペースを守る選手がいるのか、いないのかが重要になります。ガンバの方が選手の人数は多かったのですが、肝心なエリアを守れる選手がいなかったですね。
鳥栖のサイドバックはその辺りはしっかりと守備意識がありまして、ゴール前で小林、藤田、吉田がクリアするというシーンをよく見るかと思います。逆サイドのサイドバックは、センターバックとしての役割も求められます。
さて、大事な大事なシックスポイントマッチを、金崎のサガン鳥栖初ゴール、トーレスのリーグ初ゴールというおまけ付きで快勝したサガン鳥栖。それでもまだ降格圏内ですので、次節もしっかりと勝利(最低でも勝ち点1)を取ることが求められます。苦しい戦いが続きますが、少しずつ連係を上げて、良い試合を行いたいですね。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
17:59
│Match Impression (2018)
2018年08月23日
2018 天皇杯4回戦 サガン鳥栖 VS ヴィッセル神戸
2018年度 天皇杯4回戦 ヴィッセル神戸戦のレビューです。録画を忘れたので画像なしの記憶に頼った簡易版です。
鳥栖のセットアップは4-4-2。リーグ戦の合間のウィークデー開催という事でメンバーも大幅に入れ替えました。フォワードの豊田、田川のツートップは久しぶりのスタメン、中盤には小野、原川に代わって義希、安在が入り、最終ラインは三丸、そして初見参のオマリが入りました。一方、神戸は多少の入れ替わりはあったもののベストメンバーに近い顔ぶれ。鳥栖の選手としては、ここで結果をだせばリーグ戦でのスタメン選出が期待できるモチベーションの上がる試合となりました。
鳥栖は4-4-2で中盤はセントラルハーフを4人並べるフラットな形でこの試合に臨みました。神戸はポドルスキがフォワード登録であったのですが、序盤はボランチの位置まで下がってゲームメイクに加担します。これによって、システム的には互いに4-4-2のような形になり、鳥栖としてはマークが捕まえやすい形になりました。ポドルスキ、藤田のどちらかが下がって二人で縦の関係を築いた時でも、義希、秀人がバランスよくプレッシングに入ることによって縦へのチャレンジを防ぎ、サイドにボールを散らす程度に抑え込んでいました。豊田、田川が前線から地道に二度追い、三度追いを繰り返すプレッシングも神戸の自由を阻害するには十分すぎる働きでした。
前線が積極的にプレスに入る状況でありながらも、この日の鳥栖は前線から最終ラインまでの守備バランスが良く、全体の統率がとれていました。特に最終ラインから前線までの距離感が良くて、神戸が縦にボールを入れてもすぐにつぶせる距離を保ち、また、誰かが持場を離れてチャレンジにいってもいつでもカバーできる状態であったため、綻びが綻びを生むという負の連鎖がありませんでした。急造のコンビではありましたが、サイドバックとサイドハーフの関係性が良く、サイドバックの三丸と藤田がプレッシングに行っても、そのカバーリングに安在と福田がしっかり入るという、サイドハーフの守備力の高さがサイドの堅牢性を保つ要因となっていました。
逆にいうと、神戸としては鳥栖のディフェンスを動かせた時にそのスペースを活用しようという意識が少なかったかもしれません。藤田やオマリもパスカットを狙って引いたフォワードにアプローチを仕掛けていましたが、そこで空けたスペースに誰かが入るという形を作れずに、攻撃の流動性という点では特に怖さを生み出すことが出来ませんでした。裏抜けして最終ラインの背後を狙う選手も少なかったですし、攻撃のバリエーションと言う意味では鳥栖の脅威とはなりえていませんでした。
その中でも、神戸のチームとしての連動が見えたのは、サイドバック(高橋・ティーラトン)が高い位置を取ってからの攻撃で、彼らが高い位置を取ることによって鳥栖のサイドハーフを押し下げる事ができます。そのエリアを狙って神戸のサイドハーフ(三田・郷家)がボールを運んで侵入するケースを作れていました。そこはビルドアップとしては再現性があり、神戸がボールを握る時間帯を作れていました。
神戸も侵入はするものの、鳥栖のバランスの良い守備によって、なかなかシュートまで持ち込むことができていませんでした。個人的にはウェリントンを早めに使った方が良かったのかなと思いました。なんとかオマリが抑えていましたが、やはり空中戦は無頼の強さを誇っていますし、ペナルティエリア外から放ったウェリントンのシュートがバーを叩いたシーンは少し肝を冷やしましたし。そのウェリントンはイニエスタとの交代でお役御免となりましたが、個人的にはウェリントンこそイニエスタがいると力が発揮できたのではないかなという印象です。ポジショニングも体の使い方もうまいので、イニエスタからのパスも上手に引き出せたのではないかなと思いました。ポドルスキを前線に上げたかったのでしょうが、ストライカーを下げる代わりにゲームメーカーを入れたという風に眼に映ってしまいました。
鳥栖もビルドアップとしては神戸の守備を崩せていたというわけではありませんでしたが、豊田への長いボールに対するセカンドボールの反応は神戸よりも鋭く感じました。綺麗な形でなくてもボールを保持できているというのは、神戸に対して位置的に優位に立っているという状況です。ポドルスキが、ボランチの位置にいたり、前線に顔を出したりと神出鬼没であることも影響したかもしれません。守備の際に、「そこにいるはずの選手がいない」という状況を生み、中央にぽっかりスペースが空いているケースがありました。
鳥栖の先制点は秀人のサイドチェンジからでした。神戸がプレッシングで大きく鳥栖の右サイドに寄っていたところなので、このサイドチェンジが通ったことで一瞬にして数的優位を生みました。三丸が外から回ってオーバーラップするのを福田が感じ取ってパスを送り、三丸がしっかりと可能性のあるクロスを上げたことがオウンゴールを生み出しました。ゴール前に豊田、田川、安在と入っていたことも神戸の焦りを生みました。
2点目は、2列目の選手が裏に抜けるという動きですよね。それを義希が上手く感じ取ってパスを送り込めました。神戸も配置の変更があってうまくプレッシングがハマっていなかったタイミングなので、上手にその隙を突きましたね。
3点目は、福田のターンで決まりですね。トーレスも絶妙な位置にボールをコントロールしていて、それでかつ、キーパーが届かないようなスピードでシュートを放っていました。流石ストライカーですね。待望のゴールを挙げる事ができたので、これからリーグ戦でも調子に乗ってきて欲しいですね。
鳥栖としては、先制点を挙げ、更に後半の早い時間帯で追加点を挙げたことによって、プレッシングも自分たちのペースでコントロールできるようになりました。また、ターンオーバーで体力的にもフレッシュな選手が多かったため、全体がコンパクトなまま後半終了間際まで戦えました。とにかく、この試合は前線からの献身的な守備、そしてラインコントロールによるコンパクトネスの確保、これがすべてだと思います。
さて、この試合ではこれまで秘密のベールに包まれていたオマリですが、初見の印象はこんな感じでした。
タイプとしては、人にも強く、ゾーンを意識する守備も問題なくこなす印象です。縦にボールが入るタイミングやクロスが入るタイミングをしっかりと計っていて、その場で奪えなくても相手に自由を与えないという知的な守備をしていました。ポジショニングは中央を意識する守備を行うようです。サイドを破られても、サイドチェンジをされても、安易にボール保持者に飛び出していくのではなく、まずはゴール前のスペースを意識します。ゴール前を出てプレッシングに行く場合も、味方も戻りやボールの状況を見ながら動いています。プレッシングの役目を終えた時にはしっかりとゴール前に戻ります。ゴール前の意識が高いのは素晴らしいです。
余談ですが、今日の最終ラインの4人は、全員が離れてもよいタイミングを見計らいながら動けるメンバーでした。無理したチャレンジやスペースを開けてのプレッシングというのが少なかったので、ゴール前への侵入というのを最小限に抑え込む事ができましたね。
オマリのパスカットで前に出ていくよりは、ゴール前のスペースを優先して守るという意識の高さにより、クロスのヘッドでのクリア、イニエスタのシュートブロックなど、中央にしっかりと腰を据えているからこそ対応出来たプレイも見えました。三丸や福田が大きく外れようとした時やサイドチェンジでのスライドが遅れた時には、しっかりとコーチングして守備組織を整えていましたし、ラインコントロールにも遅れることなく祐治と調整しながら全体をコンパクトに収めてしました。
スピードは遅くはないのですが、アジリティのある選手と競争になるとちょっと怖いかなというのは感じました。前半の最後の方と、後半の最後の方は少し疲れていましたね。鳥栖では初めての試合ですし、コンディションが上がってきたらそこまで心配はなくなるかもしれません。
攻撃時にも守備時にも周りがしっかり見えているので、効果的なパスを送ることができますし、ボールを保持してペースを落とすこともできます。田川に縦にパスを付けるシーンや、相手を少しひきつけてサイドに送り込むパスがありました。攻撃のテンポを上げるパス能力があるので、慣れてくるとビルドアップの中心になれる可能性を秘めています。
大きなサイドチェンジや、前線へのダイレクトのスルーパスなど、リスクをかけたパスをチャレンジすることが少ないので思いもしないようなボールロストは少ないと思います。フォワードの裏に放り込むパスはトーレスを狙った1回だけだったかな。前半に左サイドで良い形でボールを受けましたが、前方の味方の連動が少なかったため無理せずにキーパーに戻すというプレイがありました。あのシーンは2度ほど前に出すパスを躊躇したので、無理せずにキーパーに戻して正解だったと思います。とにかくパスは堅実なイメージです。
抜群の高さや速さはないので、目を見張るようなパスカットや空中戦で全戦全勝みたいな派手なプレイは少ないと思いますが、ポジショニングとタイミングの良さで堅実に守ることができ、予想もしないような失点をするようなこともなく、確実な守備が出来るタイプだと思いました。
昨日のプレイだけで判断すると、正直、好きなタイプです(笑)
久しぶりの快勝でリーグ戦にも弾みを付けたいですね。絶対に負けられないガンバ大阪との戦い。楽しみですね!
鳥栖のセットアップは4-4-2。リーグ戦の合間のウィークデー開催という事でメンバーも大幅に入れ替えました。フォワードの豊田、田川のツートップは久しぶりのスタメン、中盤には小野、原川に代わって義希、安在が入り、最終ラインは三丸、そして初見参のオマリが入りました。一方、神戸は多少の入れ替わりはあったもののベストメンバーに近い顔ぶれ。鳥栖の選手としては、ここで結果をだせばリーグ戦でのスタメン選出が期待できるモチベーションの上がる試合となりました。
鳥栖は4-4-2で中盤はセントラルハーフを4人並べるフラットな形でこの試合に臨みました。神戸はポドルスキがフォワード登録であったのですが、序盤はボランチの位置まで下がってゲームメイクに加担します。これによって、システム的には互いに4-4-2のような形になり、鳥栖としてはマークが捕まえやすい形になりました。ポドルスキ、藤田のどちらかが下がって二人で縦の関係を築いた時でも、義希、秀人がバランスよくプレッシングに入ることによって縦へのチャレンジを防ぎ、サイドにボールを散らす程度に抑え込んでいました。豊田、田川が前線から地道に二度追い、三度追いを繰り返すプレッシングも神戸の自由を阻害するには十分すぎる働きでした。
前線が積極的にプレスに入る状況でありながらも、この日の鳥栖は前線から最終ラインまでの守備バランスが良く、全体の統率がとれていました。特に最終ラインから前線までの距離感が良くて、神戸が縦にボールを入れてもすぐにつぶせる距離を保ち、また、誰かが持場を離れてチャレンジにいってもいつでもカバーできる状態であったため、綻びが綻びを生むという負の連鎖がありませんでした。急造のコンビではありましたが、サイドバックとサイドハーフの関係性が良く、サイドバックの三丸と藤田がプレッシングに行っても、そのカバーリングに安在と福田がしっかり入るという、サイドハーフの守備力の高さがサイドの堅牢性を保つ要因となっていました。
逆にいうと、神戸としては鳥栖のディフェンスを動かせた時にそのスペースを活用しようという意識が少なかったかもしれません。藤田やオマリもパスカットを狙って引いたフォワードにアプローチを仕掛けていましたが、そこで空けたスペースに誰かが入るという形を作れずに、攻撃の流動性という点では特に怖さを生み出すことが出来ませんでした。裏抜けして最終ラインの背後を狙う選手も少なかったですし、攻撃のバリエーションと言う意味では鳥栖の脅威とはなりえていませんでした。
その中でも、神戸のチームとしての連動が見えたのは、サイドバック(高橋・ティーラトン)が高い位置を取ってからの攻撃で、彼らが高い位置を取ることによって鳥栖のサイドハーフを押し下げる事ができます。そのエリアを狙って神戸のサイドハーフ(三田・郷家)がボールを運んで侵入するケースを作れていました。そこはビルドアップとしては再現性があり、神戸がボールを握る時間帯を作れていました。
神戸も侵入はするものの、鳥栖のバランスの良い守備によって、なかなかシュートまで持ち込むことができていませんでした。個人的にはウェリントンを早めに使った方が良かったのかなと思いました。なんとかオマリが抑えていましたが、やはり空中戦は無頼の強さを誇っていますし、ペナルティエリア外から放ったウェリントンのシュートがバーを叩いたシーンは少し肝を冷やしましたし。そのウェリントンはイニエスタとの交代でお役御免となりましたが、個人的にはウェリントンこそイニエスタがいると力が発揮できたのではないかなという印象です。ポジショニングも体の使い方もうまいので、イニエスタからのパスも上手に引き出せたのではないかなと思いました。ポドルスキを前線に上げたかったのでしょうが、ストライカーを下げる代わりにゲームメーカーを入れたという風に眼に映ってしまいました。
鳥栖もビルドアップとしては神戸の守備を崩せていたというわけではありませんでしたが、豊田への長いボールに対するセカンドボールの反応は神戸よりも鋭く感じました。綺麗な形でなくてもボールを保持できているというのは、神戸に対して位置的に優位に立っているという状況です。ポドルスキが、ボランチの位置にいたり、前線に顔を出したりと神出鬼没であることも影響したかもしれません。守備の際に、「そこにいるはずの選手がいない」という状況を生み、中央にぽっかりスペースが空いているケースがありました。
鳥栖の先制点は秀人のサイドチェンジからでした。神戸がプレッシングで大きく鳥栖の右サイドに寄っていたところなので、このサイドチェンジが通ったことで一瞬にして数的優位を生みました。三丸が外から回ってオーバーラップするのを福田が感じ取ってパスを送り、三丸がしっかりと可能性のあるクロスを上げたことがオウンゴールを生み出しました。ゴール前に豊田、田川、安在と入っていたことも神戸の焦りを生みました。
2点目は、2列目の選手が裏に抜けるという動きですよね。それを義希が上手く感じ取ってパスを送り込めました。神戸も配置の変更があってうまくプレッシングがハマっていなかったタイミングなので、上手にその隙を突きましたね。
3点目は、福田のターンで決まりですね。トーレスも絶妙な位置にボールをコントロールしていて、それでかつ、キーパーが届かないようなスピードでシュートを放っていました。流石ストライカーですね。待望のゴールを挙げる事ができたので、これからリーグ戦でも調子に乗ってきて欲しいですね。
鳥栖としては、先制点を挙げ、更に後半の早い時間帯で追加点を挙げたことによって、プレッシングも自分たちのペースでコントロールできるようになりました。また、ターンオーバーで体力的にもフレッシュな選手が多かったため、全体がコンパクトなまま後半終了間際まで戦えました。とにかく、この試合は前線からの献身的な守備、そしてラインコントロールによるコンパクトネスの確保、これがすべてだと思います。
さて、この試合ではこれまで秘密のベールに包まれていたオマリですが、初見の印象はこんな感じでした。
オマリ良いですね。
— オオタニ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2018年8月22日
幅取り要員に食いつこうとした福田と三丸を大きな声で呼び寄せて中央を閉めるコーチング。
機を見て縦に入れる好パス。
良い選手の雰囲気醸し出してます。
タイプとしては、人にも強く、ゾーンを意識する守備も問題なくこなす印象です。縦にボールが入るタイミングやクロスが入るタイミングをしっかりと計っていて、その場で奪えなくても相手に自由を与えないという知的な守備をしていました。ポジショニングは中央を意識する守備を行うようです。サイドを破られても、サイドチェンジをされても、安易にボール保持者に飛び出していくのではなく、まずはゴール前のスペースを意識します。ゴール前を出てプレッシングに行く場合も、味方も戻りやボールの状況を見ながら動いています。プレッシングの役目を終えた時にはしっかりとゴール前に戻ります。ゴール前の意識が高いのは素晴らしいです。
余談ですが、今日の最終ラインの4人は、全員が離れてもよいタイミングを見計らいながら動けるメンバーでした。無理したチャレンジやスペースを開けてのプレッシングというのが少なかったので、ゴール前への侵入というのを最小限に抑え込む事ができましたね。
オマリのパスカットで前に出ていくよりは、ゴール前のスペースを優先して守るという意識の高さにより、クロスのヘッドでのクリア、イニエスタのシュートブロックなど、中央にしっかりと腰を据えているからこそ対応出来たプレイも見えました。三丸や福田が大きく外れようとした時やサイドチェンジでのスライドが遅れた時には、しっかりとコーチングして守備組織を整えていましたし、ラインコントロールにも遅れることなく祐治と調整しながら全体をコンパクトに収めてしました。
スピードは遅くはないのですが、アジリティのある選手と競争になるとちょっと怖いかなというのは感じました。前半の最後の方と、後半の最後の方は少し疲れていましたね。鳥栖では初めての試合ですし、コンディションが上がってきたらそこまで心配はなくなるかもしれません。
攻撃時にも守備時にも周りがしっかり見えているので、効果的なパスを送ることができますし、ボールを保持してペースを落とすこともできます。田川に縦にパスを付けるシーンや、相手を少しひきつけてサイドに送り込むパスがありました。攻撃のテンポを上げるパス能力があるので、慣れてくるとビルドアップの中心になれる可能性を秘めています。
大きなサイドチェンジや、前線へのダイレクトのスルーパスなど、リスクをかけたパスをチャレンジすることが少ないので思いもしないようなボールロストは少ないと思います。フォワードの裏に放り込むパスはトーレスを狙った1回だけだったかな。前半に左サイドで良い形でボールを受けましたが、前方の味方の連動が少なかったため無理せずにキーパーに戻すというプレイがありました。あのシーンは2度ほど前に出すパスを躊躇したので、無理せずにキーパーに戻して正解だったと思います。とにかくパスは堅実なイメージです。
抜群の高さや速さはないので、目を見張るようなパスカットや空中戦で全戦全勝みたいな派手なプレイは少ないと思いますが、ポジショニングとタイミングの良さで堅実に守ることができ、予想もしないような失点をするようなこともなく、確実な守備が出来るタイプだと思いました。
昨日のプレイだけで判断すると、正直、好きなタイプです(笑)
久しぶりの快勝でリーグ戦にも弾みを付けたいですね。絶対に負けられないガンバ大阪との戦い。楽しみですね!
Posted by オオタニ at
19:36
│Match Impression (2018)
2018年08月23日
2018 第23節 : 名古屋グランパス VS サガン鳥栖
2018年第23節、名古屋グランパス戦のレビューです。
■ 補強とコンセプト
システムの前にスタメンに関して触れたいのですが、名古屋とのホームでの戦いは3月でした。その時の対戦から比べると、怪我や出場停止の影響があるとはいえ、名古屋が7名、鳥栖は4名メンバーが異なります。互いに下位脱出に向けて夏の移籍ウインドウオープンの期間に積極的な補強を仕掛け、そして、獲得した選手たちが続々とスタメンに名を連ねました。
ただし、補強の内容を比べると「監督のサッカーを具現化できる選手」という明確な補強コンセプトで取った名古屋に対し、「個人の質の高さで違いを見せることの出来る選手」という形で取った鳥栖という違いがあり、そのコンセプトの違いが、現在の選手たちの戦術理解度、パフォーマンスの発揮具合の違いとして出ているのではないかと感じます。
名古屋のコンセプトは「止める」「蹴る」そして「目をそろえる」という言葉がよく話題に出てきます。これはショートパスを繋ぎ、ボールを保持しながら攻撃を仕掛けるポゼションサッカーと思われがちなのですが、実態はもう少し概念的なものというか、名古屋でサッカーをする上での理念に近いものだと解釈しています。
特に、「目をそろえる」の部分は、チーム全体が共通のポジション、共通のスペース、そして共通の攻撃イメージが出来ていれば、それが短いパスであろうと、長いパスであろうと、攻撃の手段としては有意であるという意味ではないかと。風間さんが伝えている言葉は戦術ではなく、戦術を発揮するための前提条件のようなものでしょうね。目がそろった段階で、もしかしたらもう一段レベルをあげた戦術が出てくるのかもしれません。それに、この「目をそろえる」は、特にサッカーに限ったことではありませんよね。一般のお仕事でも、上司、同僚、部下、みんなの目がそろってないと、効率的で質の高い仕事は出来ません。一般業界にも通用する言葉だと思います。
この試合を終えて、サッカーという組織で戦術を意思統一し、そして更にプレイとして具現化する必要があるスポーツの前では、過去の実績やネームバリューというものは一切アドバンテージにはならないという現実を突きつけられました。コミュニケーションとコンビネーションの構築には時間かかる事は理解できますが、マッシモの攻撃構築に当たって、いまだに彼が求める選手像が見えません。彼の攻撃の理想形とはいかなるものなのでしょうか。風間監督の言葉を借りますが、それが我々サポーターにも見えてきて監督、選手、サポーターの「目がそろう」ようになってくるようになると、サガン鳥栖が本当に強いチームになれるのかなと思っています。
■ 試合
鳥栖のセットアップは4-3-3でした。小野はトップ下というよりは、今節はトップに近い形での振る舞いであったと見ています。それは、試合開始からの鳥栖の積極的なボールへのアプローチに現れていました。名古屋は4-4-2でのセットアップでしたが、攻撃時はビルドアップを丁寧に行うためにボランチが1枚下りる形になります。序盤は、風間チルドレンとまでは言いすぎなのかもしれませんが、川崎から移籍してきたネットがその役目を担っていました。そして、鳥栖はそのネットを狙い撃ちするかのように前線から圧力をかけていきます。
その、鳥栖の全力で追い回すわけではないけれども、静かに前進していく圧力は意外と効果がありました。ボールを保持したい名古屋が出しどころを探す間に、トーレス、金崎、小野、そして福田がじわりじわりと追い詰めていきます。前へと繋ぎたいもののその先がない名古屋は、それでも頑張って狭い所を繋ぐか、中盤のプレスをかいくぐるために直接フォワードまで蹴っ飛ばすかという選択を迫られました。
まず、味方に繋ぐという選択は、端的に言うと、思いのほか鳥栖の網にかかっていました。それが単なるボールロスト程度で済めば良かったのですが、鳥栖の決定的チャンス(金崎とランゲラックとの1VS1)まで生むケースもありました。ネットはやや狙い撃ちされていた感があり、パスミスが続いたことによって味方から指摘があって少しチームに不穏な空気が流れましたね。後で仲直りしていましたが(笑)それくらい、序盤の名古屋のビルドアップは少し手をこまねいていました。後半は、ネットを少し前に押し出して、ビルドアップを小林が担当するようになり、安定感と迫力が増した感じです。ある意味修正力ですね。


鳥栖は、この序盤に上手くいっている時にゴールと言う形で仕留めなければなりませんでした。名古屋はワールドカップブレイク明けで大きく調子を上げてきたチームです。風間監督のイメージにある完成形とは程遠いでしょうが、シーズン前半のJ1に対してうまく適用できていなかった状況と異なり、少しずつ、戦術的実りが生まれつつある状況で、いまはそれがまさに連勝と言う結果に現れています。そういった名古屋の最近の状況を見ると、試合が進むにつれて鳥栖の弱点を見抜き、そしてチーム全体が「目をそろえて」攻撃の勘所(狙いのポイント)をチーム共通の意識として作り上げていくのは明らかでした。だからこそ、まだ鳥栖の前からのプレスに慣れていない頃に訪れるであろう決定的チャンスに得点を取ることが必要でした。ということで、下のツイートをしたわけであります。
先制点をあげるというのは非常に大事なわけでありまして、得点を取ることによって確実に守備リスクのかけ方が変わります。得点を取るためには何らかのリスクをかけなければなりませんが、得点を取るというアドバンテージでそのリスクをかける必要が少なくなるのです。C大阪戦、浦和戦の勝利はまさにその典型的な例です。後述しますが失点シーンはまさに前から奪い取ろうという積極的な守備が生んだリスクによる失点でありまして、金崎の決定的チャンスが決まっていれば、この試合はもしかしたら逆に3-0で勝てていた試合なのかもしれません。そのくらい微妙なバランスの上で成り立っていた試合だったと思います。
さて、先ほど書いたもう一つの選択肢である蹴っ飛ばすの方は、実はこれがサガン鳥栖の守備陣にじわりじわりとダメージを与えます。もちろん、鳥栖のプレッシャーに負けて単純に蹴っ飛ばすというだけであれば、直接権田の守備範疇となりボールロストとなってしまうだけなのですが、しっかりと前を向きつつ、ディフェンスラインの裏に意図を持って送りこむボールは、前田と最終ラインとの競争というものを生み出します。ジョーがいなければ前田をうまく使えばいいじゃない…と風間監督が言ったかいわないかは分からない…というか言わないでしょうが、前田の使い方は移籍して1ヶ月強であるにも関わらず、名古屋の選手たちの中で統一されていた感があります。
風間さんがこの試合に対して望んだものかはわかりませんが、前田のスピードを生かそうとするパスは鳥栖の最終ラインにじわりじわりとダメージを与えていました。スピードを発揮して抜け出されることを阻止するためには、センターバックは相手よりも早く始動しなければなりませんし、相手よりもより自陣に近い位置にスタート地点をおけばおいて行かれることを少しでも防ぐことができます。裏に抜けるというのは一発で決まらなくても、繰り返すことによって少しずつ最終ラインを動かすジャブのようなものです。そうして、徐々に、徐々に、鳥栖の最終ラインが前にでるという勇気を失って、ポジションを前田よりも数m手前に取るようになってきました。

金崎のランゲラックとの1VS1という決定的チャンスを決めきれなかった鳥栖は、序盤には出てこなかった綻びを少しずつ名古屋に突かれてくるようになりました。それはどのような綻びであったかというと、福田の運動量の豊富さに起因するものでした。運動量の豊富さが綻びになるというのはイメージがつかないかもしれませんが、福田は運動量があるから頑張ります。頑張って前にプレスをかけ、はがされたら全力でリトリートします。ただし、その運動量の豊富さに周りが着いてこないとどいいうことになるでしょうか。
それは、彼が持場を動いたことによって自分がいるべきスペースを相手に分け与えてしまうことに繋がるのです。彼が運動量を最大限生かして前からボールを奪えるというメリットもあれば、その動きに対して周りが連動しなければ、(彼の動きに対して共通の意識を持ち合わせてなければ)相手に隙を与えるという諸刃の剣になりやすいものなのです。

ここで少し前からのプレスに関しておさらいします。まず、コンパクトな状態とはどのような状態かというと、最終ラインの選手と相手に一番近い選手との距離が30m~35m程度の範囲であることが理想と言われています。最終ラインと中盤の距離が15m、中盤とトップの選手が15m程度ですね。もちろん、戦術や選手たちの状況によってチームごとに異なりますが、ひとまずはそれを基準として考えて良いでしょう。
そして、フィールドの縦の長さを約100mとすると、リトリートして守備ブロックを固めた場合は、自陣だけのスペースを守れば良いので、自陣からゴール30m~50mの間に選手を配置してスペースをケアすることになります。しかしながら、前からプレスをかける場合は、ボールの位置から自陣ゴールまで50m~80m分の広さのスペースに対して、ラインと範囲を定め、味方の位置を決めなければなりません。当然、その範囲が広くなればなるほどにひとりひとりがカバーしなければならないエリアが広くなります。よって、オフサイドというルールを活用して、最終ラインを押し上げて相手が使えない(待ち伏せできない)デッドスペースを作り出す事によって、自分たちの守備のゾーンを少しでも狭めて相手にプレッシャーをかける(相手を迎え打つ)のです。
相手の攻撃における自由を奪うためには、前からプレスした時にフォワードの選手に連動して、ハーフの選手も、最終ラインの選手も、全体が味方の位置を意識して動き、相手に与えるスペースを極小化しなければなりません。それが出来ないと前線と中盤、中盤と最終ラインの間に相手が利用しやすいスペースを与えてしまう事になります。間延びというのは、相手との駆け引きや疲れなどによって、最終ラインや中盤のラインを押し上げられず(最前線が素早いリトリートをできず)相手が使いやすいスペースを生み出すという事です。試合の終盤になると、よく、中盤に誰もいない状況でカウンターの応酬になったりすることがありますよね。それは、攻撃したい前線と守りたい最終ラインの間があいて、60m~70mの間に人を配置しなければならず、仕方なく間のスペースを捨てている(捨てざるを得ない)という状況という事です。



では、この試合ではどうだったのかというと、鳥栖は前から圧力をかけて丁寧なビルドアップを行う名古屋のパスの出所を抑えようという戦術でこの戦いに挑みました。前からの圧力というのは、どの位置で、どのメンバーが、そしてどのタイミングでしかけるのかと言うディテールが明確になっていないと相手に隙を見せることになります。
最初は少しぐらいのプレスのずれがあっても相手が対応できないのですが、徐々に相手が慣れてきたときに、ほころびをつかれてしまうことになります。それが、先ほど記載した福田の動きの部分です。前半から、福田が前に圧力をかけるのですが、彼が動いたことによって空けたスペースを誰がケアするのかと言うところが意思疎通取れておらず、アンカーがサイドによるのか、サイドバックが1列あげるのか、そこの対応に苦慮していました。
また、前田の裏抜けのスピードというのも最終ラインに徐々に刷り込まれて行ってまして、鳥栖の最終ラインが少しずつ、後ろのスペースに対する意識が増してきました。それにより、先ほどの50m守っているところが52m、54mと、じわじわとライン間が空いてくることに繋がりました。
試合開始当初は、当然のことながら相手のやり方や出方を見定めている状態だったので、鳥栖のプレスに名古屋もハマってしまったのですが、徐々に、「福田の裏のエリア」にスペースがあることを名古屋の選手たちは理解してきます。そして、選手たちの共通理解の下に、名古屋の逆襲が始まりました。
シャビエルのシュートが外れたのはその前兆でした。名古屋の選手たちに、福田が空けたスペースは使えるという共通理解が生まれます。その理解が生まれたことにより、ボランチの小林がすっとそのスペースに入っていきます。全員の「目が揃った」段階で、左サイドからの崩しによる先制点が生まれたという事です。
■ シャビエルのシュートシーン



■ 先制点のシーン




ここで気を付けて頂きたいのは、決して、福田の前からのプレスが悪いというのではありません。福田のプレスに連動しなかった味方が悪かったかもしれませんし、もしかしたら、「前からのプレス」という戦術を与えていたけどそのディテールの部分を伝えきれていなかった監督が悪かったのかもしれません。
ここで言いたいのは「福田がプレスによって空けたスペース」を使われて幾度もピンチを招いたという現象であり、その現象を改善するための解決策を監督も選手も出せずに、結局試合終了近くまで同じような形で幾度ものピンチを招いたという事です。58分にピンチを迎えたシーンを下に示しますが、原理としては同じです。チームとして連動した守備ができていなかったことによって、福田が前に行ったスペースをうまく使われてしまいました。
■ 後半のピンチのシーン


個人的には、75分くらいまでは前からのプレスを一旦ゆるめて、リトリートしてブロックを組む戦術変更でもよかったのかなと思いました。名古屋の守備ブロックも盤石ではありませんでしたし、ボールさえ持つことが出来れば、鳥栖のビルドアップで崩せる予兆はあったからです。
鳥栖のビルドアップは実はそこまで苦労していなかったのではないかと思っていまして、名古屋のドイスボランチが比較的最終ラインの前で構えているケースが多く、前につっついてくるような守備はあまりありませんでした。鳥栖はサイド攻撃を良く使うので、名古屋はサイドハーフがどう動くかという所は大事な要素になるのですが、児玉と玉田が、鳥栖のサイドバックにつくのか、ドイスボランチにつくのか、少し迷っているのではないかという節がありました。結局、サイドハーフはサイドバックを見る形が多くなるのですが、それにより、センターバックから鳥栖のドイスボランチへのパスコースが良く通るようになっていました。基本的に、鳥栖のボランチは最終ラインに下がってサイドバックを押し上げるという攻撃がよく見られるのですが、この試合では、センターバックから縦の位置でボールをもらえるケースが多く作り出せていました。もしかしたら、事前に名古屋を分析してマッシモが出した指示だったのかもしれません。

しかしながら、そこから先が問題でして、サイドに大きく展開するパスや、フォワードの裏抜けに対するパスの精度が悪く、せっかくビルドアップの抜け道として前を向くことができても、そこから先の効果的な攻撃になかなか繋がりませんでした。
パスの精度が悪いのは当然「止める」「蹴る」の技術不足ということもあるのですが、チームとして、組織として作り上げられた攻撃であれば迷いなく蹴ることができ、これが、パスの精度としては大事な要素でもあります。逆に言うと、今の鳥栖には欠けている事でありまして、前に抜けるのか、後ろで受けるのか、サイドで受けるのか、その時その時の選手の判断によって変わります。トーレスが裏に抜けたり、手前に引いてボールを受けたり、金崎がサイドに逃げたり、ハーフスペースで待って受けたり、小野も様々なところに顔を出しています。このあたりの役割分担がしっかりされていないことが、パスの精度に大きく影響しておりまして、裏に抜けると思ってパスしたら相手は手前に引いてきたという事が発生したりしていました。いかにもとんでもない所にパスを出したかのように見えてしまいますが、実は好パスだったにも関わらず、受け手がその意図を理解できなかったという事なのかもしれないのです。
そのチームとしての意図の統一の必要性はカウンターにも現れておりまして、カウンター攻撃の際に誰があがっていくのか、誰がどのようにフォローするのか、誰がフィニッシュするのか、そのあたりが不明瞭でしたね。(監督が決めていなかったのか、決めていることを選手が実現できなかったのか、それはわかりません。誰かマッシモに聞いてくれませんかね(笑))
もうひとつ、選手の力量を把握するという事も大事な要素です。金崎やトーレスに対するパスにしても、彼らがある状況で「ここでボールを受けれたらシュートまで持ち込める状況」と思っても、回りが「彼はマークにつかれてパスを出しても苦しい状況」と判断すれば、それは確実にチャンスロストとなってしまいます。言葉は悪いですが、鳥栖のきぞんの選手がトラップできないボールでも、トーレスや金崎はトラップできます。既存の選手たちが判断している以上のプレーが出来るにも関わらず、その機会を彼らに与えきれてないのかも知れません。風間さんの言葉を借りると、その辺りを少しでも早く選手たちが高いレベルで「目をそろえる」必要がありますよね。


もうひとつ、この試合で目立ったプレイがありまして、それはボールを奪われた直後の名古屋の守備でした。鳥栖が最終ラインでボールを奪って持ち上がろうとした直後、シャビエルや前田がしっかりとプレスに入ります。そのプレスで奪わなくても、鳥栖をちょっと遅らせて、遅攻フェーズに入らせることによって、名古屋としては失点の確率がガクンと下がるのを分かっているかのようでした。2失点目はその献身的なプレイが実を結んで、ゴール前でボールを奪い返して得点に繋げました。
その2失点目のクロスも先制点のヒールパスと同様なくらいにネットの非常に素晴らしいテクニカルなパスだったのですが、そこに選手がいる事が分かって迷いなく蹴ったことが精度の高さに繋がっています。精度を上げるためには迷いを持たないということが大事なのです。今の鳥栖は、ボールを持ちながら味方を探して探りながらパスを出すシーンが多いので、少しでも早く、個人を理解し、戦術を理解することが重要ですよね。
3対0という点差でしたが、金崎の序盤での1VS1、トーレスのコーナーやクロスからのシュート、そしてアディショナルタイムの金崎の決定的チャンス。得点の機会は作っています。ガンバ大阪戦で、これらのチャンスをしっかりと仕留められるように期待しましょう。
<画像引用元:DAZN>
■ 補強とコンセプト
システムの前にスタメンに関して触れたいのですが、名古屋とのホームでの戦いは3月でした。その時の対戦から比べると、怪我や出場停止の影響があるとはいえ、名古屋が7名、鳥栖は4名メンバーが異なります。互いに下位脱出に向けて夏の移籍ウインドウオープンの期間に積極的な補強を仕掛け、そして、獲得した選手たちが続々とスタメンに名を連ねました。
ただし、補強の内容を比べると「監督のサッカーを具現化できる選手」という明確な補強コンセプトで取った名古屋に対し、「個人の質の高さで違いを見せることの出来る選手」という形で取った鳥栖という違いがあり、そのコンセプトの違いが、現在の選手たちの戦術理解度、パフォーマンスの発揮具合の違いとして出ているのではないかと感じます。
名古屋のコンセプトは「止める」「蹴る」そして「目をそろえる」という言葉がよく話題に出てきます。これはショートパスを繋ぎ、ボールを保持しながら攻撃を仕掛けるポゼションサッカーと思われがちなのですが、実態はもう少し概念的なものというか、名古屋でサッカーをする上での理念に近いものだと解釈しています。
特に、「目をそろえる」の部分は、チーム全体が共通のポジション、共通のスペース、そして共通の攻撃イメージが出来ていれば、それが短いパスであろうと、長いパスであろうと、攻撃の手段としては有意であるという意味ではないかと。風間さんが伝えている言葉は戦術ではなく、戦術を発揮するための前提条件のようなものでしょうね。目がそろった段階で、もしかしたらもう一段レベルをあげた戦術が出てくるのかもしれません。それに、この「目をそろえる」は、特にサッカーに限ったことではありませんよね。一般のお仕事でも、上司、同僚、部下、みんなの目がそろってないと、効率的で質の高い仕事は出来ません。一般業界にも通用する言葉だと思います。
この試合を終えて、サッカーという組織で戦術を意思統一し、そして更にプレイとして具現化する必要があるスポーツの前では、過去の実績やネームバリューというものは一切アドバンテージにはならないという現実を突きつけられました。コミュニケーションとコンビネーションの構築には時間かかる事は理解できますが、マッシモの攻撃構築に当たって、いまだに彼が求める選手像が見えません。彼の攻撃の理想形とはいかなるものなのでしょうか。風間監督の言葉を借りますが、それが我々サポーターにも見えてきて監督、選手、サポーターの「目がそろう」ようになってくるようになると、サガン鳥栖が本当に強いチームになれるのかなと思っています。
■ 試合
鳥栖のセットアップは4-3-3でした。小野はトップ下というよりは、今節はトップに近い形での振る舞いであったと見ています。それは、試合開始からの鳥栖の積極的なボールへのアプローチに現れていました。名古屋は4-4-2でのセットアップでしたが、攻撃時はビルドアップを丁寧に行うためにボランチが1枚下りる形になります。序盤は、風間チルドレンとまでは言いすぎなのかもしれませんが、川崎から移籍してきたネットがその役目を担っていました。そして、鳥栖はそのネットを狙い撃ちするかのように前線から圧力をかけていきます。
その、鳥栖の全力で追い回すわけではないけれども、静かに前進していく圧力は意外と効果がありました。ボールを保持したい名古屋が出しどころを探す間に、トーレス、金崎、小野、そして福田がじわりじわりと追い詰めていきます。前へと繋ぎたいもののその先がない名古屋は、それでも頑張って狭い所を繋ぐか、中盤のプレスをかいくぐるために直接フォワードまで蹴っ飛ばすかという選択を迫られました。
まず、味方に繋ぐという選択は、端的に言うと、思いのほか鳥栖の網にかかっていました。それが単なるボールロスト程度で済めば良かったのですが、鳥栖の決定的チャンス(金崎とランゲラックとの1VS1)まで生むケースもありました。ネットはやや狙い撃ちされていた感があり、パスミスが続いたことによって味方から指摘があって少しチームに不穏な空気が流れましたね。後で仲直りしていましたが(笑)それくらい、序盤の名古屋のビルドアップは少し手をこまねいていました。後半は、ネットを少し前に押し出して、ビルドアップを小林が担当するようになり、安定感と迫力が増した感じです。ある意味修正力ですね。


鳥栖は、この序盤に上手くいっている時にゴールと言う形で仕留めなければなりませんでした。名古屋はワールドカップブレイク明けで大きく調子を上げてきたチームです。風間監督のイメージにある完成形とは程遠いでしょうが、シーズン前半のJ1に対してうまく適用できていなかった状況と異なり、少しずつ、戦術的実りが生まれつつある状況で、いまはそれがまさに連勝と言う結果に現れています。そういった名古屋の最近の状況を見ると、試合が進むにつれて鳥栖の弱点を見抜き、そしてチーム全体が「目をそろえて」攻撃の勘所(狙いのポイント)をチーム共通の意識として作り上げていくのは明らかでした。だからこそ、まだ鳥栖の前からのプレスに慣れていない頃に訪れるであろう決定的チャンスに得点を取ることが必要でした。ということで、下のツイートをしたわけであります。
今日の名古屋ならば、3点分位は決定的チャンス出来そうですが、その時に決めきれるかどうかですね。
— オオタニ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2018年8月19日
決めきれなければ名古屋の1発に沈む試合になりそう。
先制点をあげるというのは非常に大事なわけでありまして、得点を取ることによって確実に守備リスクのかけ方が変わります。得点を取るためには何らかのリスクをかけなければなりませんが、得点を取るというアドバンテージでそのリスクをかける必要が少なくなるのです。C大阪戦、浦和戦の勝利はまさにその典型的な例です。後述しますが失点シーンはまさに前から奪い取ろうという積極的な守備が生んだリスクによる失点でありまして、金崎の決定的チャンスが決まっていれば、この試合はもしかしたら逆に3-0で勝てていた試合なのかもしれません。そのくらい微妙なバランスの上で成り立っていた試合だったと思います。
さて、先ほど書いたもう一つの選択肢である蹴っ飛ばすの方は、実はこれがサガン鳥栖の守備陣にじわりじわりとダメージを与えます。もちろん、鳥栖のプレッシャーに負けて単純に蹴っ飛ばすというだけであれば、直接権田の守備範疇となりボールロストとなってしまうだけなのですが、しっかりと前を向きつつ、ディフェンスラインの裏に意図を持って送りこむボールは、前田と最終ラインとの競争というものを生み出します。ジョーがいなければ前田をうまく使えばいいじゃない…と風間監督が言ったかいわないかは分からない…というか言わないでしょうが、前田の使い方は移籍して1ヶ月強であるにも関わらず、名古屋の選手たちの中で統一されていた感があります。
風間さんがこの試合に対して望んだものかはわかりませんが、前田のスピードを生かそうとするパスは鳥栖の最終ラインにじわりじわりとダメージを与えていました。スピードを発揮して抜け出されることを阻止するためには、センターバックは相手よりも早く始動しなければなりませんし、相手よりもより自陣に近い位置にスタート地点をおけばおいて行かれることを少しでも防ぐことができます。裏に抜けるというのは一発で決まらなくても、繰り返すことによって少しずつ最終ラインを動かすジャブのようなものです。そうして、徐々に、徐々に、鳥栖の最終ラインが前にでるという勇気を失って、ポジションを前田よりも数m手前に取るようになってきました。

金崎のランゲラックとの1VS1という決定的チャンスを決めきれなかった鳥栖は、序盤には出てこなかった綻びを少しずつ名古屋に突かれてくるようになりました。それはどのような綻びであったかというと、福田の運動量の豊富さに起因するものでした。運動量の豊富さが綻びになるというのはイメージがつかないかもしれませんが、福田は運動量があるから頑張ります。頑張って前にプレスをかけ、はがされたら全力でリトリートします。ただし、その運動量の豊富さに周りが着いてこないとどいいうことになるでしょうか。
それは、彼が持場を動いたことによって自分がいるべきスペースを相手に分け与えてしまうことに繋がるのです。彼が運動量を最大限生かして前からボールを奪えるというメリットもあれば、その動きに対して周りが連動しなければ、(彼の動きに対して共通の意識を持ち合わせてなければ)相手に隙を与えるという諸刃の剣になりやすいものなのです。

ここで少し前からのプレスに関しておさらいします。まず、コンパクトな状態とはどのような状態かというと、最終ラインの選手と相手に一番近い選手との距離が30m~35m程度の範囲であることが理想と言われています。最終ラインと中盤の距離が15m、中盤とトップの選手が15m程度ですね。もちろん、戦術や選手たちの状況によってチームごとに異なりますが、ひとまずはそれを基準として考えて良いでしょう。
そして、フィールドの縦の長さを約100mとすると、リトリートして守備ブロックを固めた場合は、自陣だけのスペースを守れば良いので、自陣からゴール30m~50mの間に選手を配置してスペースをケアすることになります。しかしながら、前からプレスをかける場合は、ボールの位置から自陣ゴールまで50m~80m分の広さのスペースに対して、ラインと範囲を定め、味方の位置を決めなければなりません。当然、その範囲が広くなればなるほどにひとりひとりがカバーしなければならないエリアが広くなります。よって、オフサイドというルールを活用して、最終ラインを押し上げて相手が使えない(待ち伏せできない)デッドスペースを作り出す事によって、自分たちの守備のゾーンを少しでも狭めて相手にプレッシャーをかける(相手を迎え打つ)のです。
相手の攻撃における自由を奪うためには、前からプレスした時にフォワードの選手に連動して、ハーフの選手も、最終ラインの選手も、全体が味方の位置を意識して動き、相手に与えるスペースを極小化しなければなりません。それが出来ないと前線と中盤、中盤と最終ラインの間に相手が利用しやすいスペースを与えてしまう事になります。間延びというのは、相手との駆け引きや疲れなどによって、最終ラインや中盤のラインを押し上げられず(最前線が素早いリトリートをできず)相手が使いやすいスペースを生み出すという事です。試合の終盤になると、よく、中盤に誰もいない状況でカウンターの応酬になったりすることがありますよね。それは、攻撃したい前線と守りたい最終ラインの間があいて、60m~70mの間に人を配置しなければならず、仕方なく間のスペースを捨てている(捨てざるを得ない)という状況という事です。



では、この試合ではどうだったのかというと、鳥栖は前から圧力をかけて丁寧なビルドアップを行う名古屋のパスの出所を抑えようという戦術でこの戦いに挑みました。前からの圧力というのは、どの位置で、どのメンバーが、そしてどのタイミングでしかけるのかと言うディテールが明確になっていないと相手に隙を見せることになります。
最初は少しぐらいのプレスのずれがあっても相手が対応できないのですが、徐々に相手が慣れてきたときに、ほころびをつかれてしまうことになります。それが、先ほど記載した福田の動きの部分です。前半から、福田が前に圧力をかけるのですが、彼が動いたことによって空けたスペースを誰がケアするのかと言うところが意思疎通取れておらず、アンカーがサイドによるのか、サイドバックが1列あげるのか、そこの対応に苦慮していました。
また、前田の裏抜けのスピードというのも最終ラインに徐々に刷り込まれて行ってまして、鳥栖の最終ラインが少しずつ、後ろのスペースに対する意識が増してきました。それにより、先ほどの50m守っているところが52m、54mと、じわじわとライン間が空いてくることに繋がりました。
試合開始当初は、当然のことながら相手のやり方や出方を見定めている状態だったので、鳥栖のプレスに名古屋もハマってしまったのですが、徐々に、「福田の裏のエリア」にスペースがあることを名古屋の選手たちは理解してきます。そして、選手たちの共通理解の下に、名古屋の逆襲が始まりました。
シャビエルのシュートが外れたのはその前兆でした。名古屋の選手たちに、福田が空けたスペースは使えるという共通理解が生まれます。その理解が生まれたことにより、ボランチの小林がすっとそのスペースに入っていきます。全員の「目が揃った」段階で、左サイドからの崩しによる先制点が生まれたという事です。
■ シャビエルのシュートシーン



■ 先制点のシーン




ここで気を付けて頂きたいのは、決して、福田の前からのプレスが悪いというのではありません。福田のプレスに連動しなかった味方が悪かったかもしれませんし、もしかしたら、「前からのプレス」という戦術を与えていたけどそのディテールの部分を伝えきれていなかった監督が悪かったのかもしれません。
ここで言いたいのは「福田がプレスによって空けたスペース」を使われて幾度もピンチを招いたという現象であり、その現象を改善するための解決策を監督も選手も出せずに、結局試合終了近くまで同じような形で幾度ものピンチを招いたという事です。58分にピンチを迎えたシーンを下に示しますが、原理としては同じです。チームとして連動した守備ができていなかったことによって、福田が前に行ったスペースをうまく使われてしまいました。
■ 後半のピンチのシーン


個人的には、75分くらいまでは前からのプレスを一旦ゆるめて、リトリートしてブロックを組む戦術変更でもよかったのかなと思いました。名古屋の守備ブロックも盤石ではありませんでしたし、ボールさえ持つことが出来れば、鳥栖のビルドアップで崩せる予兆はあったからです。
鳥栖のビルドアップは実はそこまで苦労していなかったのではないかと思っていまして、名古屋のドイスボランチが比較的最終ラインの前で構えているケースが多く、前につっついてくるような守備はあまりありませんでした。鳥栖はサイド攻撃を良く使うので、名古屋はサイドハーフがどう動くかという所は大事な要素になるのですが、児玉と玉田が、鳥栖のサイドバックにつくのか、ドイスボランチにつくのか、少し迷っているのではないかという節がありました。結局、サイドハーフはサイドバックを見る形が多くなるのですが、それにより、センターバックから鳥栖のドイスボランチへのパスコースが良く通るようになっていました。基本的に、鳥栖のボランチは最終ラインに下がってサイドバックを押し上げるという攻撃がよく見られるのですが、この試合では、センターバックから縦の位置でボールをもらえるケースが多く作り出せていました。もしかしたら、事前に名古屋を分析してマッシモが出した指示だったのかもしれません。

しかしながら、そこから先が問題でして、サイドに大きく展開するパスや、フォワードの裏抜けに対するパスの精度が悪く、せっかくビルドアップの抜け道として前を向くことができても、そこから先の効果的な攻撃になかなか繋がりませんでした。
パスの精度が悪いのは当然「止める」「蹴る」の技術不足ということもあるのですが、チームとして、組織として作り上げられた攻撃であれば迷いなく蹴ることができ、これが、パスの精度としては大事な要素でもあります。逆に言うと、今の鳥栖には欠けている事でありまして、前に抜けるのか、後ろで受けるのか、サイドで受けるのか、その時その時の選手の判断によって変わります。トーレスが裏に抜けたり、手前に引いてボールを受けたり、金崎がサイドに逃げたり、ハーフスペースで待って受けたり、小野も様々なところに顔を出しています。このあたりの役割分担がしっかりされていないことが、パスの精度に大きく影響しておりまして、裏に抜けると思ってパスしたら相手は手前に引いてきたという事が発生したりしていました。いかにもとんでもない所にパスを出したかのように見えてしまいますが、実は好パスだったにも関わらず、受け手がその意図を理解できなかったという事なのかもしれないのです。
そのチームとしての意図の統一の必要性はカウンターにも現れておりまして、カウンター攻撃の際に誰があがっていくのか、誰がどのようにフォローするのか、誰がフィニッシュするのか、そのあたりが不明瞭でしたね。(監督が決めていなかったのか、決めていることを選手が実現できなかったのか、それはわかりません。誰かマッシモに聞いてくれませんかね(笑))
もうひとつ、選手の力量を把握するという事も大事な要素です。金崎やトーレスに対するパスにしても、彼らがある状況で「ここでボールを受けれたらシュートまで持ち込める状況」と思っても、回りが「彼はマークにつかれてパスを出しても苦しい状況」と判断すれば、それは確実にチャンスロストとなってしまいます。言葉は悪いですが、鳥栖のきぞんの選手がトラップできないボールでも、トーレスや金崎はトラップできます。既存の選手たちが判断している以上のプレーが出来るにも関わらず、その機会を彼らに与えきれてないのかも知れません。風間さんの言葉を借りると、その辺りを少しでも早く選手たちが高いレベルで「目をそろえる」必要がありますよね。


もうひとつ、この試合で目立ったプレイがありまして、それはボールを奪われた直後の名古屋の守備でした。鳥栖が最終ラインでボールを奪って持ち上がろうとした直後、シャビエルや前田がしっかりとプレスに入ります。そのプレスで奪わなくても、鳥栖をちょっと遅らせて、遅攻フェーズに入らせることによって、名古屋としては失点の確率がガクンと下がるのを分かっているかのようでした。2失点目はその献身的なプレイが実を結んで、ゴール前でボールを奪い返して得点に繋げました。
その2失点目のクロスも先制点のヒールパスと同様なくらいにネットの非常に素晴らしいテクニカルなパスだったのですが、そこに選手がいる事が分かって迷いなく蹴ったことが精度の高さに繋がっています。精度を上げるためには迷いを持たないということが大事なのです。今の鳥栖は、ボールを持ちながら味方を探して探りながらパスを出すシーンが多いので、少しでも早く、個人を理解し、戦術を理解することが重要ですよね。
3対0という点差でしたが、金崎の序盤での1VS1、トーレスのコーナーやクロスからのシュート、そしてアディショナルタイムの金崎の決定的チャンス。得点の機会は作っています。ガンバ大阪戦で、これらのチャンスをしっかりと仕留められるように期待しましょう。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
12:53
│Match Impression (2018)
2018年08月17日
2018 第22節 : 川崎フロンターレ VS サガン鳥栖
2018年第22節、川崎フロンターレ戦のレビューです。
鳥栖のセットアップは、今節はフラットな4-4-2をベースとしたシステムでした。中盤は右から小野、原川、秀人、福田の並びで、最終ラインは左サイドバックに前節負傷の吉田に替わって藤田が入ります。
川崎のセットアップは4-5-1をベースとするような形でしょうか。攻撃時には大島が最終ラインに落ちて、エウシーニョと登里を前に押し出し、3-6-1のような形でのビルドアップを試みていました。
鳥栖は今節も守備のバランスはサイドハーフのポジショニングによってコントロールしていました。川崎も両サイドに幅を取るウイングタイプの選手がいますので、サイドバックで補いきれないスペースにはサイドハーフを1列落とすことによってカバーリングしていました。浦和戦と異なったのは、サイドハーフが落ちた時のフォワードの動きでありまして、トーレス、金崎が明確に中盤のカバーリングでポジションを落とし、流動的に5-3-2、6-2-2とブロックを変遷していました。
押されたときにトーレスと金崎が引いて中央に構えているのは先日のセレッソ戦と同じだったのですが、セレッソ戦と異なりなかなかカウンターへとつなぐことができませんでした。川崎が中央を起点とした攻撃をしかけて選手が密集している事により、セカンドボールを拾う確率が下がった事、ツートップにボールを繋ごうとしてもパスコースがなかった事が要因と考えられます。また、トーレスや金崎がボールを受ける事ができてもすぐにつぶされて逆にショートカウンターを受けるという状況も発生していたため、一旦サイドに逃げてボールを繋いだり、2トップが裏のスペースに走らざるを得ない(そこに蹴らざるを得ない)という状況も発生していました。鳥栖のカウンター効率としてはあまり高いものではありませんでした。
さて、今節は、川崎と鳥栖との攻撃に関する哲学の違いとでも言いましょうか。川崎は鳥栖よりもはるかに高い位置にいるなというのを痛感させられました。まとまりのない文章となりましたが、その違いを記します。
■ カウンター
今節は、カウンター攻撃のスピードに川崎と鳥栖の違いがよく現れていました。川崎のカウンターは、一旦小林悠に預けて彼がボールさえキープしていれば必ずフォローがやってきます。サイドであれ、中央であれ、小林悠がミンヒョクを引き連れるケースが多かったのですが、ミンヒョクを背負ってボールキープするだけで周りが自然とボールを受けに来てくれ、受けに来た選手に預けるだけで他のメンバーがスペースを使ってくれます。選手間の距離が近いのでパスのミスも少なく、小気味良いダイレクトパスによる展開で攻撃をしかけていました。
具体例で言うならば、11分20秒頃のシーンでしょうか。川崎はボールを奪って小林悠にボールを当てます。ミンヒョクから厳しいプレスを受けますが、彼のタスクはキープすることであり、なんとかキープして大島にボールを受け渡します。大島はミンヒョクの空けたスペースに流れ込む守田にパスを送ります。このパスは惜しくもミスとなってしまいましたが、スピードもあり、通ったらゴールの可能性を感じる事のできるカウンターでした。何よりも、小林悠をフォローしてボールをさばくのもボランチ、小林悠が空けたスペースへ飛び出していくのもボランチというのが、川崎のカウンター攻撃の役割が整理されている印象を受けます。
一方、サガン鳥栖のカウンターは、まず、トーレスもしくは金崎がボールキープし、マーカーをかわして独力で前を向かなければ成立しませんでした。彼らをフォローするメンバーは、彼らを追い越して前線に飛び出していき、ボールを引き出そうという動きはとりますが、金崎とトーレスが独力で前を向くことに成功しないとパスは出てきませんでしたし、彼らが独力で前を向いたものの、フェイントなどで時間がかかって気が付いた時には川崎の選手も戻っていたというシーンも多くありました。(トーレスがボールを奪われないのは本当に見事なのですが、川崎としてはボールをそこで奪えなくても時間稼ぎができたので、ベストではなくともベターの守備が出来ていました。)
また、前述の通り、金崎、トーレスが相手をはがすプレイがすべて成功するわけではないので、逆に、預けた位置でボールを奪われてショートカウンターを受けてしまう事もあり、そうなってくると中盤の選手も飛び出していくタイミングを見計らうという、カウンターのスピードが落ちる事にも繋がってしまいました。更に、福田と小野が最終ラインに引く守備をとるので、彼らが前に出るまでの距離(時間)が長くなり、フォローも遅くなるので、預けどころがなくて金崎が一人でかわしてドリブルで前に上がろうとするシーンも少しずつ増えていました。そうして、徐々にカウンターとしては成立しがたい個人の質頼みの攻撃となってしまいました。
具体例であげるならば、69分30秒頃のシーンでしょうか。ゴール前でカットして小野にボールを渡します。小野から金崎へパスを入れるのですが、距離も長く相手もマークについており、その上アウトサイドキックと言う非常に難しいパスを試みなければならないので相手に弾かれます。それでも、なんとかトーレスがこぼれ球を拾って金崎に繋ぐのですが、金崎の周りにフォローはなく、味方は追い越してゴール前に走り込もうとしているので、彼の選択肢は相手をかわすという行為に挑むしかありません。ここで残念ながらかわしきれずにボールを奪われてカウンターは終わってしまいました。小林悠はボールをキープするだけで良いのですが、金崎は相手をかわさなければカウンターが成立しないという状況の違いは、カウンターの成否に大きく影響を与えていました。
繰り返しますが、川崎のカウンターは個人の技術を持った選手たちが連動し、組織として推進力を上げてカウンター攻撃をしかけるのに対し、鳥栖のカウンターは個人としての技術を持った選手の単発の動きに依存し、組織としてのフォローが薄い攻撃となってしまっていました。このカウンターデザインの違いによる成果の差は、両チームのシュート数の違いを見れば明らかですよね。
■ ビルドアップ
ビルドアップやサイドの使い方も両チームでのスタイルの違いを感じました。川崎は、基本的には突破するのは中央です。中央を縦で繋いでゴールへの最短の道を進みます。川崎はパサーを中央に配置してそこからボールを配球することを目指します。
そのためには鳥栖の2トップのプレスが邪魔となります。よって、大島は2トップからの逃げ道を作るために下がります。センターバック2名から直接縦に良いパスを出せれば良いのですが、それが出来ない時はセンターバックが囮の役割を演じていました。最終ラインでフォワードにプレスをかけさせて、フォワードのプレスが入らないように大島がボールを握ります。そして斜めの位置もしくは縦の位置に守田、中村が入ります。ボランチ同士が縦の関係でパス交換をするという形は鳥栖にはありませんが、川崎はむしろボランチ同士が縦位置でパス交換してプレスをかわします。ゴールに向かう最短の道を作り上げたいからです。
10分20秒くらいのシーンはまさに中央突破でした。ビルドアップのために引いた大島から守田、中村とつないで小林悠にラストパスを送り込むシーンは、見ていて清々しい程にサガン鳥栖守備陣の背骨……骨格を貫かれました。



川崎の選手は、鳥栖の2トップと2ボランチが作るスクエアの中に自ら飛び込みます。その位置でボールを受けて前を向く技術があるので、相手の守備を破壊するために意図してその場所に飛び込むのです。スクエアに飛びこんでボールを受ける事によって相手が集中してプレスをかけてきますが、その時こそ、チャンスの芽が発生します。鳥栖の選手が特定のエリアに集中するという事は、その他のエリアにいる選手たちのプレスが緩んだり、視線がそれたりします。自ら厳しいエリアに飛び込むことによって他の選手たちのマークを軽減しつつ、チームとしてのチャンスを作り出します。そして、ボールを受けてはたいたらパスアンドゴーで前にでます。受けた選手は出し手が前進することが分かっているので同じくワンタッチではたきます。そうやって、ワンタッチの連続であっという間にチャンスを作り上げます。
無論、鳥栖の選手たちも黙ってはおらず、網にかけてボールを奪おうとします。川崎も中央突破のフィロソフィーは持っていますが、その網が上手くくぐれない時はサイドに大きく展開します。ボールを一旦中央から逃がして鳥栖の選手たちが寄せるのを待ちます。サイドでボールをキープして、鳥栖の選手たちのプレスの目線がサイドに行った時に再びボールを中央に戻します。そして、再び中央で縦にボールを入れる事の出来る場所を探します。
サイドでボールを受けた選手が前に走り出しますが、安直には出しません。なぜならばサイドへのパスの優先順位は、中央へのパスの優先順位より低いからです。サイドの選手が一人相手のサイドハーフを引き連れるだけでスペースを空けるのに十分な役割を果たしてくれます。その頃には、中央に家長や中村が入り込んでいます。一旦サイドにボールを振って目の位置を変え、本筋で狙う中央へのパスコースを巧みに作っているのです。
…と、長くなりましたが、そういう川崎のフィロソフィーの下に崩されたのが25分からのシーンです。最終ラインで組み立てながらパスコースを探すのですが、最初は鳥栖のスクエアの中に中村が入り込みます。そこでボールを受ける準備を作りますが、まだ鳥栖の陣形が崩れていないのでパスを送り込まず、右サイドで回しながら阿部へ縦パスを入れたりしながら鳥栖のほころびを待ちます。
そこで弾き返されたので今度は左サイドへボールを回します。左サイドからボールが中央の大島に戻ってきたときにスクエアの中に守田が入ります。川崎のボランチが縦の関係を築いたので鳥栖の守備(2トップと2ボランチのスクエア)が守田に集中しかけた時、一旦視界から消えていた中村が最終ラインの前のスペースに動いてポジションを取ります。ここで待ってましたとばかりに、大島は2トップ、2ボランチの網をくぐって直接最終ラインの前の中村にパスを送ります。登里も守田も囮として使ったのです。中村はトラップして華麗に前を向いて、右サイドでフリーになっている阿部に送り込みました。もう、敵ながらあっぱれの、見ていてほれぼれする連動した攻撃です(笑)
一方、鳥栖のビルドアップはサイドを使います。縦にボールが入るのは、サイドバックからサイドハーフに入れるのが中心となります。そこでボールキープできてボランチが横の関係を作ることができればチャンスになります。ビルドアップの出口をうまく作れなくても、ボールキープさえすれば、川崎の選手をサイドによせることで逆サイドにフリーの選手を作ることもできます。ただし、選手間の距離が広く、パスの距離がなくなるのでパスの精度は落ちるケースが多く、ここで!というところでのパスがミスになってチャンスロストしてしまっていました。

川崎のミスと鳥栖のミスはミスの度合が異なりました。川崎のパスは選手間の距離が近いのでパスの精度自体高いのですが、ミスになってもすぐにボールを拾いかえすことができたり、ミスパスなのにはねかえりが良い形で繋がるケースですらあります。しかしながら、鳥栖の攻撃のスイッチはディフェンスラインの裏へのボールであったり、逆サイドへの大きな展開であったりするので、高い精度のパスが要求され、残念ながら要求に応えきれずにパスミスが発生しやすくなります。先ほどミスの度合いと書きましたが、鳥栖の方はミスがただのミスでなく、まったくノーチャンスのミス(選手を大きく飛び越えてゴールラインやサイドラインを割る。相手がトラップ出来るような位置に行ってしまう等)となっているケースが多かったです。
象徴的だったのは、スタジアムが沸いたトーレスのダイナミックなサイドチェンジで得たチャンスは、小野のクロスがフィールドを大きく飛び出してしまう可能性のない形で終わりました。ボールがフィールドを出てしまうので、セカンドボールを奪取してからの二次攻撃にすら繋がりません。川崎は10点満点中、ミスが発生しても2点、3点のパスなのですが、鳥栖の場合は、0点パスが多く、この差が、試合全体の流れに影響していました。


■ 縦に入れる勇気
この試合でちょっと腑に落ちなかったシーンを書きたいと思います。それは78分30秒頃のシーンです。
川崎に押し込まれていながらもやっとボールを保持し、左サイドから右サイドに展開したシーンです。小野が右サイドでボールをなんとかキープして秀人に預けます。小野はパスアンドゴーで裏にうまく抜けましたし、また、ゴール前に入る小林と入れ替わるように金崎が秀人から縦位置にパスコースを作ります。
ところが、秀人は前への選択をせずに後ろにパスを送りました。せっかく全体を前に押し上げ、金崎も小野もサイドを崩すパスコースを作りあげたのに、後ろに戻す行為で川崎がラインを押し上げる手助けをしたかのようでした。確かに川崎の選手の絞りもうまかったのですが、浮き球で渡すなど勇気をもって縦へのチャレンジをしてほしかったところです。
この後、川崎の最終ラインが揃っている中で、義希からトーレスに送り込むパスがミスとなりました。ボールを下げたことで、距離も長く、精度の高いパスが要求され、イチかバチかのパスをチャレンジしなければならなくなりました。川崎が跳ね返したボールを最終ラインが拾うものの小林悠のプレッシャーを受けて権田に下げる羽目になり、権田のキックは車屋のトラップで納められてしまいました。この時点で完全にボールロストです。
それだけではありません。そこからリトリートが遅れてコンパクトさを保てない鳥栖を嘲笑うようにスムーズに縦パスがつながり、あっという間に小林悠の決定的なシュートまで繋げられてしまいました。権田の奇跡的なセーブがあったから助けられたものの、本当に危ないシーンで、秀人の勇気を失ったパスが、リスクを回避した「つもり」の消極的なパスが、川崎の決定的チャンスに繋がってしまうという実に皮肉なシーンでした。
リスクをかけて攻撃を仕掛けられないならばサイドバックの小林がゴール前に上がるポジショニングは自重するべきですし、川崎のラインを上げさせて裏を狙う擬似カウンターをしたかったのならば、川崎が出てくる前に出した義希のパスは拙速でした。いずれにしても、チームとして何がしたかったのか選手間の相互理解が出来ていないように見えました。
このシーンで秀人が金崎や小野にパスを入れる勇気を持つためにはどのようにしたら良かったのでしょうか。秀人の個人の技量の向上なのか、マッシモのマネジメントなのか。川崎が縦にパスを入れる攻撃のバックボーンは個人の技術力にあることはわかるのですが、それ以上にチーム全体の意思の力なのかなと思いました。チームとして統一された意志があの鳥栖の背骨を貫く縦へのパスを産み出すと思うのです。マッシモは攻撃に関してどの程度の勇気を選手に与えているのでしょうか。
「虎穴に入らずんば虎子を得ず」
ふと思い出してしまいました。

話を守備に戻しますが、浦和戦よりも向上していたことがありまして、ブロックを作る動きの連動はとれていたと思います。4-4-2 ⇒ 5-3-2 ⇒ 6-2-2 と移り変わるポジションは、よどみなく動けていたように思います。だだし、ブロックを組んでいますが、ボールを奪いにいくスイッチが連動していませんでした。時折、相手が背後を向くようなパスが入った時にトーレスが積極果敢に狙っていきましたが、周りが連動してプレスに入らないのでなかなかボールを奪えませんでした。(それでもトーレス一人だけのプレスでボールを奪うという素晴らしい守備もありました)ブロックを組み、組織として連動してスペースを消すために「動く」のですが、組織として連動して「奪う」スイッチの共有が出来ていなかったので、各々のタイミングでプレッシャーに入るものの、連動がほんの少し遅れ、また、川崎のスイッチが入ったあとにチャレンジする形になってしまい、プレスに行くもののワンタッチでかわされ、繋がれて気がつけばシュートされていたというケースが多くありました。
試合展開はこのような状況だったのですが、結果としてはスコアレスのドロー。勝ち点は両チームで1ずつを分け合いました。これは非常に喜ばしい事ですし、サッカーは不思議なスポーツだなとも思いました。チームとしての完成度の差がそのまま試合の中で如実に出ていたのですが、最後は最終ラインの踏ん張りや相手のミス、そして何よりも権田の奮闘によって失点0で抑える事ができました。どれだけ支配されていても、どれだけシュートを受けても、サッカーには判定勝ちはありません。この勝ち点1は非常に大きいと思います。
コンビネーションに関しては、少しずつ向上させていくしかありませんし、個人技術もトレーニングで向上していくしかありません。そして、選手が勇気をもってチャレンジする気持ち(チャレンジできる環境づくり)というのは監督が与えるより他はないので、チームマネジメントをしっかりしてほしいと思います。
ある意味完膚なきまでに叩き潰されたといっても過言ではない試合でしたが、何とか次に繋がる試合とすることが出来ました。まだまだ背水の陣は続きます。名古屋戦、いよいよ6ポイントマッチがやってきました。面白い試合になりそうですね。
<画像引用元:DAZN>
鳥栖のセットアップは、今節はフラットな4-4-2をベースとしたシステムでした。中盤は右から小野、原川、秀人、福田の並びで、最終ラインは左サイドバックに前節負傷の吉田に替わって藤田が入ります。
川崎のセットアップは4-5-1をベースとするような形でしょうか。攻撃時には大島が最終ラインに落ちて、エウシーニョと登里を前に押し出し、3-6-1のような形でのビルドアップを試みていました。
鳥栖は今節も守備のバランスはサイドハーフのポジショニングによってコントロールしていました。川崎も両サイドに幅を取るウイングタイプの選手がいますので、サイドバックで補いきれないスペースにはサイドハーフを1列落とすことによってカバーリングしていました。浦和戦と異なったのは、サイドハーフが落ちた時のフォワードの動きでありまして、トーレス、金崎が明確に中盤のカバーリングでポジションを落とし、流動的に5-3-2、6-2-2とブロックを変遷していました。
押されたときにトーレスと金崎が引いて中央に構えているのは先日のセレッソ戦と同じだったのですが、セレッソ戦と異なりなかなかカウンターへとつなぐことができませんでした。川崎が中央を起点とした攻撃をしかけて選手が密集している事により、セカンドボールを拾う確率が下がった事、ツートップにボールを繋ごうとしてもパスコースがなかった事が要因と考えられます。また、トーレスや金崎がボールを受ける事ができてもすぐにつぶされて逆にショートカウンターを受けるという状況も発生していたため、一旦サイドに逃げてボールを繋いだり、2トップが裏のスペースに走らざるを得ない(そこに蹴らざるを得ない)という状況も発生していました。鳥栖のカウンター効率としてはあまり高いものではありませんでした。
さて、今節は、川崎と鳥栖との攻撃に関する哲学の違いとでも言いましょうか。川崎は鳥栖よりもはるかに高い位置にいるなというのを痛感させられました。まとまりのない文章となりましたが、その違いを記します。
■ カウンター
今節は、カウンター攻撃のスピードに川崎と鳥栖の違いがよく現れていました。川崎のカウンターは、一旦小林悠に預けて彼がボールさえキープしていれば必ずフォローがやってきます。サイドであれ、中央であれ、小林悠がミンヒョクを引き連れるケースが多かったのですが、ミンヒョクを背負ってボールキープするだけで周りが自然とボールを受けに来てくれ、受けに来た選手に預けるだけで他のメンバーがスペースを使ってくれます。選手間の距離が近いのでパスのミスも少なく、小気味良いダイレクトパスによる展開で攻撃をしかけていました。
具体例で言うならば、11分20秒頃のシーンでしょうか。川崎はボールを奪って小林悠にボールを当てます。ミンヒョクから厳しいプレスを受けますが、彼のタスクはキープすることであり、なんとかキープして大島にボールを受け渡します。大島はミンヒョクの空けたスペースに流れ込む守田にパスを送ります。このパスは惜しくもミスとなってしまいましたが、スピードもあり、通ったらゴールの可能性を感じる事のできるカウンターでした。何よりも、小林悠をフォローしてボールをさばくのもボランチ、小林悠が空けたスペースへ飛び出していくのもボランチというのが、川崎のカウンター攻撃の役割が整理されている印象を受けます。
一方、サガン鳥栖のカウンターは、まず、トーレスもしくは金崎がボールキープし、マーカーをかわして独力で前を向かなければ成立しませんでした。彼らをフォローするメンバーは、彼らを追い越して前線に飛び出していき、ボールを引き出そうという動きはとりますが、金崎とトーレスが独力で前を向くことに成功しないとパスは出てきませんでしたし、彼らが独力で前を向いたものの、フェイントなどで時間がかかって気が付いた時には川崎の選手も戻っていたというシーンも多くありました。(トーレスがボールを奪われないのは本当に見事なのですが、川崎としてはボールをそこで奪えなくても時間稼ぎができたので、ベストではなくともベターの守備が出来ていました。)
また、前述の通り、金崎、トーレスが相手をはがすプレイがすべて成功するわけではないので、逆に、預けた位置でボールを奪われてショートカウンターを受けてしまう事もあり、そうなってくると中盤の選手も飛び出していくタイミングを見計らうという、カウンターのスピードが落ちる事にも繋がってしまいました。更に、福田と小野が最終ラインに引く守備をとるので、彼らが前に出るまでの距離(時間)が長くなり、フォローも遅くなるので、預けどころがなくて金崎が一人でかわしてドリブルで前に上がろうとするシーンも少しずつ増えていました。そうして、徐々にカウンターとしては成立しがたい個人の質頼みの攻撃となってしまいました。
具体例であげるならば、69分30秒頃のシーンでしょうか。ゴール前でカットして小野にボールを渡します。小野から金崎へパスを入れるのですが、距離も長く相手もマークについており、その上アウトサイドキックと言う非常に難しいパスを試みなければならないので相手に弾かれます。それでも、なんとかトーレスがこぼれ球を拾って金崎に繋ぐのですが、金崎の周りにフォローはなく、味方は追い越してゴール前に走り込もうとしているので、彼の選択肢は相手をかわすという行為に挑むしかありません。ここで残念ながらかわしきれずにボールを奪われてカウンターは終わってしまいました。小林悠はボールをキープするだけで良いのですが、金崎は相手をかわさなければカウンターが成立しないという状況の違いは、カウンターの成否に大きく影響を与えていました。
繰り返しますが、川崎のカウンターは個人の技術を持った選手たちが連動し、組織として推進力を上げてカウンター攻撃をしかけるのに対し、鳥栖のカウンターは個人としての技術を持った選手の単発の動きに依存し、組織としてのフォローが薄い攻撃となってしまっていました。このカウンターデザインの違いによる成果の差は、両チームのシュート数の違いを見れば明らかですよね。
■ ビルドアップ
ビルドアップやサイドの使い方も両チームでのスタイルの違いを感じました。川崎は、基本的には突破するのは中央です。中央を縦で繋いでゴールへの最短の道を進みます。川崎はパサーを中央に配置してそこからボールを配球することを目指します。
そのためには鳥栖の2トップのプレスが邪魔となります。よって、大島は2トップからの逃げ道を作るために下がります。センターバック2名から直接縦に良いパスを出せれば良いのですが、それが出来ない時はセンターバックが囮の役割を演じていました。最終ラインでフォワードにプレスをかけさせて、フォワードのプレスが入らないように大島がボールを握ります。そして斜めの位置もしくは縦の位置に守田、中村が入ります。ボランチ同士が縦の関係でパス交換をするという形は鳥栖にはありませんが、川崎はむしろボランチ同士が縦位置でパス交換してプレスをかわします。ゴールに向かう最短の道を作り上げたいからです。
10分20秒くらいのシーンはまさに中央突破でした。ビルドアップのために引いた大島から守田、中村とつないで小林悠にラストパスを送り込むシーンは、見ていて清々しい程にサガン鳥栖守備陣の背骨……骨格を貫かれました。



川崎の選手は、鳥栖の2トップと2ボランチが作るスクエアの中に自ら飛び込みます。その位置でボールを受けて前を向く技術があるので、相手の守備を破壊するために意図してその場所に飛び込むのです。スクエアに飛びこんでボールを受ける事によって相手が集中してプレスをかけてきますが、その時こそ、チャンスの芽が発生します。鳥栖の選手が特定のエリアに集中するという事は、その他のエリアにいる選手たちのプレスが緩んだり、視線がそれたりします。自ら厳しいエリアに飛び込むことによって他の選手たちのマークを軽減しつつ、チームとしてのチャンスを作り出します。そして、ボールを受けてはたいたらパスアンドゴーで前にでます。受けた選手は出し手が前進することが分かっているので同じくワンタッチではたきます。そうやって、ワンタッチの連続であっという間にチャンスを作り上げます。
無論、鳥栖の選手たちも黙ってはおらず、網にかけてボールを奪おうとします。川崎も中央突破のフィロソフィーは持っていますが、その網が上手くくぐれない時はサイドに大きく展開します。ボールを一旦中央から逃がして鳥栖の選手たちが寄せるのを待ちます。サイドでボールをキープして、鳥栖の選手たちのプレスの目線がサイドに行った時に再びボールを中央に戻します。そして、再び中央で縦にボールを入れる事の出来る場所を探します。
サイドでボールを受けた選手が前に走り出しますが、安直には出しません。なぜならばサイドへのパスの優先順位は、中央へのパスの優先順位より低いからです。サイドの選手が一人相手のサイドハーフを引き連れるだけでスペースを空けるのに十分な役割を果たしてくれます。その頃には、中央に家長や中村が入り込んでいます。一旦サイドにボールを振って目の位置を変え、本筋で狙う中央へのパスコースを巧みに作っているのです。
…と、長くなりましたが、そういう川崎のフィロソフィーの下に崩されたのが25分からのシーンです。最終ラインで組み立てながらパスコースを探すのですが、最初は鳥栖のスクエアの中に中村が入り込みます。そこでボールを受ける準備を作りますが、まだ鳥栖の陣形が崩れていないのでパスを送り込まず、右サイドで回しながら阿部へ縦パスを入れたりしながら鳥栖のほころびを待ちます。
そこで弾き返されたので今度は左サイドへボールを回します。左サイドからボールが中央の大島に戻ってきたときにスクエアの中に守田が入ります。川崎のボランチが縦の関係を築いたので鳥栖の守備(2トップと2ボランチのスクエア)が守田に集中しかけた時、一旦視界から消えていた中村が最終ラインの前のスペースに動いてポジションを取ります。ここで待ってましたとばかりに、大島は2トップ、2ボランチの網をくぐって直接最終ラインの前の中村にパスを送ります。登里も守田も囮として使ったのです。中村はトラップして華麗に前を向いて、右サイドでフリーになっている阿部に送り込みました。もう、敵ながらあっぱれの、見ていてほれぼれする連動した攻撃です(笑)
一方、鳥栖のビルドアップはサイドを使います。縦にボールが入るのは、サイドバックからサイドハーフに入れるのが中心となります。そこでボールキープできてボランチが横の関係を作ることができればチャンスになります。ビルドアップの出口をうまく作れなくても、ボールキープさえすれば、川崎の選手をサイドによせることで逆サイドにフリーの選手を作ることもできます。ただし、選手間の距離が広く、パスの距離がなくなるのでパスの精度は落ちるケースが多く、ここで!というところでのパスがミスになってチャンスロストしてしまっていました。

川崎のミスと鳥栖のミスはミスの度合が異なりました。川崎のパスは選手間の距離が近いのでパスの精度自体高いのですが、ミスになってもすぐにボールを拾いかえすことができたり、ミスパスなのにはねかえりが良い形で繋がるケースですらあります。しかしながら、鳥栖の攻撃のスイッチはディフェンスラインの裏へのボールであったり、逆サイドへの大きな展開であったりするので、高い精度のパスが要求され、残念ながら要求に応えきれずにパスミスが発生しやすくなります。先ほどミスの度合いと書きましたが、鳥栖の方はミスがただのミスでなく、まったくノーチャンスのミス(選手を大きく飛び越えてゴールラインやサイドラインを割る。相手がトラップ出来るような位置に行ってしまう等)となっているケースが多かったです。
象徴的だったのは、スタジアムが沸いたトーレスのダイナミックなサイドチェンジで得たチャンスは、小野のクロスがフィールドを大きく飛び出してしまう可能性のない形で終わりました。ボールがフィールドを出てしまうので、セカンドボールを奪取してからの二次攻撃にすら繋がりません。川崎は10点満点中、ミスが発生しても2点、3点のパスなのですが、鳥栖の場合は、0点パスが多く、この差が、試合全体の流れに影響していました。


■ 縦に入れる勇気
この試合でちょっと腑に落ちなかったシーンを書きたいと思います。それは78分30秒頃のシーンです。
川崎に押し込まれていながらもやっとボールを保持し、左サイドから右サイドに展開したシーンです。小野が右サイドでボールをなんとかキープして秀人に預けます。小野はパスアンドゴーで裏にうまく抜けましたし、また、ゴール前に入る小林と入れ替わるように金崎が秀人から縦位置にパスコースを作ります。
ところが、秀人は前への選択をせずに後ろにパスを送りました。せっかく全体を前に押し上げ、金崎も小野もサイドを崩すパスコースを作りあげたのに、後ろに戻す行為で川崎がラインを押し上げる手助けをしたかのようでした。確かに川崎の選手の絞りもうまかったのですが、浮き球で渡すなど勇気をもって縦へのチャレンジをしてほしかったところです。
この後、川崎の最終ラインが揃っている中で、義希からトーレスに送り込むパスがミスとなりました。ボールを下げたことで、距離も長く、精度の高いパスが要求され、イチかバチかのパスをチャレンジしなければならなくなりました。川崎が跳ね返したボールを最終ラインが拾うものの小林悠のプレッシャーを受けて権田に下げる羽目になり、権田のキックは車屋のトラップで納められてしまいました。この時点で完全にボールロストです。
それだけではありません。そこからリトリートが遅れてコンパクトさを保てない鳥栖を嘲笑うようにスムーズに縦パスがつながり、あっという間に小林悠の決定的なシュートまで繋げられてしまいました。権田の奇跡的なセーブがあったから助けられたものの、本当に危ないシーンで、秀人の勇気を失ったパスが、リスクを回避した「つもり」の消極的なパスが、川崎の決定的チャンスに繋がってしまうという実に皮肉なシーンでした。
リスクをかけて攻撃を仕掛けられないならばサイドバックの小林がゴール前に上がるポジショニングは自重するべきですし、川崎のラインを上げさせて裏を狙う擬似カウンターをしたかったのならば、川崎が出てくる前に出した義希のパスは拙速でした。いずれにしても、チームとして何がしたかったのか選手間の相互理解が出来ていないように見えました。
このシーンで秀人が金崎や小野にパスを入れる勇気を持つためにはどのようにしたら良かったのでしょうか。秀人の個人の技量の向上なのか、マッシモのマネジメントなのか。川崎が縦にパスを入れる攻撃のバックボーンは個人の技術力にあることはわかるのですが、それ以上にチーム全体の意思の力なのかなと思いました。チームとして統一された意志があの鳥栖の背骨を貫く縦へのパスを産み出すと思うのです。マッシモは攻撃に関してどの程度の勇気を選手に与えているのでしょうか。
「虎穴に入らずんば虎子を得ず」
ふと思い出してしまいました。

話を守備に戻しますが、浦和戦よりも向上していたことがありまして、ブロックを作る動きの連動はとれていたと思います。4-4-2 ⇒ 5-3-2 ⇒ 6-2-2 と移り変わるポジションは、よどみなく動けていたように思います。だだし、ブロックを組んでいますが、ボールを奪いにいくスイッチが連動していませんでした。時折、相手が背後を向くようなパスが入った時にトーレスが積極果敢に狙っていきましたが、周りが連動してプレスに入らないのでなかなかボールを奪えませんでした。(それでもトーレス一人だけのプレスでボールを奪うという素晴らしい守備もありました)ブロックを組み、組織として連動してスペースを消すために「動く」のですが、組織として連動して「奪う」スイッチの共有が出来ていなかったので、各々のタイミングでプレッシャーに入るものの、連動がほんの少し遅れ、また、川崎のスイッチが入ったあとにチャレンジする形になってしまい、プレスに行くもののワンタッチでかわされ、繋がれて気がつけばシュートされていたというケースが多くありました。
試合展開はこのような状況だったのですが、結果としてはスコアレスのドロー。勝ち点は両チームで1ずつを分け合いました。これは非常に喜ばしい事ですし、サッカーは不思議なスポーツだなとも思いました。チームとしての完成度の差がそのまま試合の中で如実に出ていたのですが、最後は最終ラインの踏ん張りや相手のミス、そして何よりも権田の奮闘によって失点0で抑える事ができました。どれだけ支配されていても、どれだけシュートを受けても、サッカーには判定勝ちはありません。この勝ち点1は非常に大きいと思います。
コンビネーションに関しては、少しずつ向上させていくしかありませんし、個人技術もトレーニングで向上していくしかありません。そして、選手が勇気をもってチャレンジする気持ち(チャレンジできる環境づくり)というのは監督が与えるより他はないので、チームマネジメントをしっかりしてほしいと思います。
ある意味完膚なきまでに叩き潰されたといっても過言ではない試合でしたが、何とか次に繋がる試合とすることが出来ました。まだまだ背水の陣は続きます。名古屋戦、いよいよ6ポイントマッチがやってきました。面白い試合になりそうですね。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
10:42
│Match Impression (2018)
2018年08月15日
2018 第21節 : サガン鳥栖 VS 浦和レッズ
2018年第21節、浦和レッズ戦のレビューです。
鳥栖のセットアップは、攻撃時には4-3-3(4-3-1-2)、守備時には5-2-3(5-3-2)という形で始まり、途中から攻撃時には4-4-2、守備時には5-3-2(5-4-1)という形に変わっていきました。ただし、今節に関してはセットアップポジションを示しても、あまり意義のあるものではないのかもしれません。
特に、守備時においてはそれが顕著で、浦和が積極的に攻撃に人数をかけ、また、ポジションの移動を激しく繰り返していたので、鳥栖として「ここならばボールを奪える」というポイントがなかなか作れず、ブロックを組んでもボールの出し引きをされて選手を動かされるので確固たる組織守備とならず、システムも選手の配置も様々替わって局面に応じてフレキシブルな対応を課せられてしまいました。
突き付けられた課題は、ゾーンで守りたいけど質的にも数的にも位置的にもすべてにおいて不利な状況が発生しており、どのような対応策を取るかというなかなか過酷なものでありましたが、最終的に、解決策としては「最終ラインでの人海戦術」という形にならざるを得ず、その着地点に向けて局所局所で選手たちを動かしていきながら、形を模索しながらという試合進行でした。
今回ばかりは、最後は人について離さないという恐らくインテリジェンスな組織とはなかなか言い難い守り方…でもサガン鳥栖らしい泥臭い執念を感じる守り方になりましたが、先制点という追い風もあり、選手やベンチのみならず、スタジアムにいるサガン鳥栖サポーターも含めた全員で虎の子の1点を守りきることが出来ました。
守備を詳しく見ていきましょう。浦和がボールを保持してビルドアップを始めた段階でインサイドハーフの福田が1列下がって5人で最終ラインを組むケースが多く、これは鳥栖が5バックで臨むときの定型で、宇賀神の動きに連動して福田がポジションを決めたというよりは、いつも通りセットアップとしてこの形を選択したのだと考えます。逆に、左サイドの原川は無条件に最終ラインに組み込むのではなく、中盤のスペースケアと攻撃の基点となる事を見据え、状況を見ながらそのポジショニングを決める形でした。
福田を1列下げますので、中央は原川、秀人、小野によってスペースをケアしつつ、ウイングバック対策としては、サイドの局面でスピードに対抗できるように「宇賀神VS福田」「橋岡VS吉田」というマッチアップを作ることによって、質的に劣ることなくサイド攻撃を防ぎたいという意図を感じました。
しかしながら、この目論見は浦和の巧みなポジショニングとビルドアップによって見事に破壊されることになります。
(1)鳥栖の左サイドにおける武藤、橋岡による崩し
試合開始序盤に左サイドを崩されて何回かクロスを上げられ、興梠のヘディングなどのピンチを迎える事になりましたが、その原動力となったのは、武藤の動きによるものでした。
吉田はどちらかというと人に食いつくタイプで、ポジションを動かす選手に対してもボールが出る事を見越してインターセプト狙いで食いついていきます。武藤はトップの興梠のフォローというよりは、左サイドの吉田の周りを狙ってポジショニングを取っていました。そこから、武藤がポジションを移す事によって吉田がついていくので、時折、吉田が武藤に引っ張られて、原川よりも前のポジションで武藤をマークするという状況が生まれていました。こうなると、どうしても原川は中盤のケアよりも吉田のカバーの方が優先となり、最終ラインに引いてスペースを埋めたり、ウイングの橋岡にでたボールに対するマークをとらなければならない状況が生まれました。

これは、鳥栖にとってはあまり迎えたくなかった形でありまして、吉田に対して武藤をぶつけられたことによって橋岡に対してアジリティに劣る原川が対応しなければならないという、質的に不利なマッチアップとなってしまいました。この形を作られた事によって、鳥栖の左サイドで縦に突破されてクロスを上げられたり、裏のスペースに走り込まれて長いサイドチェンジを受けたり、ゴール前へのラストパスを送り込まれる形を作られてしまっていました。原川を引かせるということは、当然金崎や小野も引かなければならなくなってしまうわけでありまして、スコアレスの状態でそこまで徹底して守備に入ることができるかと言う所が悩ましいところであり、それが下記の(2)に繋がってしまいます。
試合中に下のようなツイートをしたのはこういう状況だったということです。
■ 浦和の崩し





(2)中盤に大きく空いたスペース
(1)のように、ポジションを大きく前に取るウイングへの対応によって、福田と原川が最終ラインに引きこまれてしまうという現象が発生しました。システム的には6バックのような形です。これによって何が起きるかというと、インサイドハーフのうちの2名が不在となり、では、中盤のスペースをケアするのは誰?という問題が発生します。

実は試合開始序盤からサガン鳥栖はこの問題を抱えていましたが、なかなか解決できずに、トーレス、金崎、小野にどこまで守備のタスクを与えるかと言うところをベンチは試案していた模様でした。
完全に守備に踏み切れない背景には、実は浦和は守備に回った時にはそこまで積極的にボールを奪いに来るわけではなく、しっかりと5-3-2(5-4-1)ブロックを組んで前線に残す人数を最小限にしていため、浦和のカウンターに対する脅威をさほど感じられないというメンタル面も影響していたかと思います。浦和が前から来るわけではないので、鳥栖もビルドアップやトーレスの高さを利用した前進はそれなりに図れており、心理的に圧迫感や閉塞感を感じる状況でもなく、(スタジアムの熱気もありまして)一進一退だという雰囲気を感じます。こういう状況になると、セカンドボールを拾って二次攻撃、前から奪いに行ってショートカウンターという、試合展開として押し込みたいという気持ちが出てきます。
こういう背景から、序盤から小野と金崎を引かせて完全撤退という形になかなか踏み切れず、中途半端に浦和のビルドアップに仕掛けていってしまう前線と、ウイングのポジショニングの恐怖にさらされて出来る限り裏のスペースを空けられたくない最終ラインという構図になり、浦和のビルドアップへの対抗策に対する意思統一が図れないまま試合が進んでいってしまいました。
浦和のビルドアップもよく考えられておりまして、槇野と岩波がボール保持時に両サイドに大きく張りだしてポジションを取ります。鳥栖は機を見てトーレス、金崎の二人が前からプレスをしかけたのですが、両センターバック間が空いてしまったエリアを柏木がうまくポジションを出しいれして最終ラインからの経由地として機能していました。この柏木の巧みな動きによって鳥栖が前線でプレスをかけるには数的不利であることは明確でして、追っては交わされ、追っては交わされという、不毛なプレスを強いられていました。


特に、困っであろうのが小野のポジショニングでありまして、ある程度前から行くのか、それとも完全に引いてしまうのか選択を迫られました。5-3-2として割り切るならばポジションを引かなければなりませんが、トーレスと金崎が完全にリトリートするような構え(ミドルサード付近での迎撃)でもなく、相手ペナルティエリア付近まで行ってしまうので、連動して前に行かなければならず、かといって後ろの原川と福田は思い切って前に出て来れないという状況になり、本来は自分が見なければならない柏木、青木もうまく捕まえることが出来ず、小野のポジションの取り方は非常に難しいものでした。

それにも増して、秀人にかかる負担は相当なものでして、見過ごしていたらそのまま押し込まれるだけの状況となり、かといって前から行っても数的不利で交わされて広大なスペースを与えてしまい、サイドハーフは引いてしまっているので中盤のスペースをカバーしなければならず、しかしながら押し込まれたときには最終ラインに入ってクロスも跳ね返さなければならないという、小野以上に厳しい状況にさらされ、そして様々な対応を迫られていました。
秀人がひとりでスペースをケアする中盤のキープレイヤーとなってしまったおかげで、皮肉にも秀人が動いて空けた場所が浦和が使えるスペースになるという状況を生んでいました。フォワードたちの前進に呼応して秀人が動くとそのスペースを使われ、サイドを崩されたことによって最終ラインのカバーに入るとバイタル前のエリアからミドルシュートを打たれ、こういう状況下ではありましたが、前線と最終ラインを繋ぐ唯一のブリッジとして、まさに孤軍奮闘の活躍であり、コーナーキックからのゴールはまるで八面六臂の活躍に対するご褒美であるかのようでした。ヒーローインタビューは本当に胸を打たれる熱い言葉でしたね。


これらの(1)、(2)の状況は、橋岡がボールを受けるエリア、武藤がボールを受けるエリア、両センターバックがボールを持ちあがれるエリア、ハーフウェーライン近くで柏木がボールを配球するエリアが浦和の狙いどころになっていたことが、浦和のヒートマップにも現れています。

(3)対応策
上記のように、序盤は(1)(2)による状況によって、非常に難しいサッカーを強いられていましたが、まずもって、ウイングへの対応によって最大6人が引いてしまっているので、中盤のスペースをコンパクトにしてボールを奪い取る事はかなり難しい状況です。この状況で大事なのは
「どこのスペースを捨てるのか」
「どこのエリア(サイド)を集中して守るのか」
「ポジションはどのように動かすのか(セットアップポジションから誰を引かせて、誰を残すのか)」
「プレスのラインはどこにおくのか」
といった約束事をはっきりすることでした。
そういう意味では、中盤のスペースをどうするのかというところが序盤からの最大の課題だったかと思われます。前に出ようとする前線と、後ろをしっかりと守ろうとする最終ラインとの間にギャップが生まれ、そこをついて岩波、槇野が上手にボールを持ちあげたり、柏木や青木が大きな展開でボールを前に進められるというのは、ビルドアップという行為に苦労せずともに鳥栖の陣地深くまで押し上げる事が出来ていたからです。
ただし、序盤から明確になっていることはありまして、一旦浦和に奥深く入られてしまったときには、完全にリトリートするというスイッチが入りまして、金崎も小野もトーレスも、しっかりとリトリートして守備をこなしていました。最後はゴール前で跳ね返せばいいじゃん!という割り切りです。
特に小野は最終ラインまで下がってのディフェンスもこなしており、難しい状況ながらもしっかりとその役目を果たしたと思います。本来は小野に前線でのキープと推進力を求められていたのでしょうが、このように守備に追われる時間が長くなってしまったため、試合展開からなかなかその場面を作ることはできませんでした。
鳥栖もベンチから様々な指示がでていたのですが、前半の途中から少しずつやり方を変え出してきておりまして、まず、守備フェーズに切り替わった時に割り切って原川を最終ラインに組み込んで原川が武藤を見る形を作り上げ、橋岡に吉田を当てる形を作りました。これによって橋岡にスピードで振り切られるのを阻止する形を作り上げました。


また、給水タイムに指示があったと思われるのですが、小野が明確にポジションを下げて左サイドのインサイドハーフにポジションを移しました。これに合わせて原川を中央、秀人を右サイドにポジションを変更し、槇野、岩波が上がってくるスペースを秀人、小野で対応するという形をとりました。

それでも、橋岡に対しては小野が振り切られてクロスを上げられるなど、守備強度に対する不安がありましたので、後半になって福田を左サイドに移して橋岡の突破を防ぐという形をとりました。福田を左サイドで最終ラインに落とす形になったので、守備時に明確に5-3-2のブロックを組みました。中盤は秀人を中央に戻して原川と小野がインサイドハーフの役割となりました。




そして、選手たちに勇気を与えたのは何よりも秀人の先制ゴールでした。このゴールによって、チーム全体に1点を守りきるという明確な目標がうまれ、明確に「守備」を優先したポジショニングへと意識が変わり、チーム全体の動きが連動しだして、ミドルゾーンからの守備と言う形で統一されました。
前半開始したのままの戦い方では、確実に鳥栖は浦和の攻撃に屈していたことでしょう。しかしながら、システムを変え、ポジションを変え、選手の配置を変え、構え方を変え、チーム全体でいろいろと試行錯誤することによって、無失点と言う最適な結果を作り上げました。改めて、試合は生き物であるということを知ることができました。
■ サガン鳥栖の攻撃
攻めに関しては、特別にこれまでと変わった様子はなく、トーレスにボールに集めて彼に入るボールに対するセカンドボールを拾いながら、陣地を押し上げるという形と、良い形でボールを奪えた場合は金崎や小野の推進力を利用してカウンターで一気に前にでるというものでした。
しかしながら、槇野の素晴らしい対応によって、トーレスが制空権を完全に握ることができず、また、今回の守備組織ではボールの奪いどころが低い位置にならざるを得なかったので、効果的なカウンターという状況もそこまで多くは作れず、シュートまでの形作りとしてはツートップの質に頼らざるを得ない状況が続きました。
また、浦和が守勢に回ったときが、5-3-2(5-4-1)によるブロックであったため、4-4-2でビルドアップするという選択をとった鳥栖は、サイドのスペースを有効活用してボールの前進を図れたシーンもあったのですが、最後のクロスのところでどうしてもひっかかってしまうというシュートに繋がらない状況が発生しました。
その中でも、福田のクロスがひっかかってしまうのは毎試合気になるところでありまして、福田の類まれなる運動量と献身的な動きによって、彼がサイドのスペースに上手く入り込んでトーレス、金崎、小野からのパスを上手に引き出してくれますが、最後の大事な場面でクロスがどうしても相手にひっかかってしまいます。そこでしっかりとクロスを中央に送り込む事(もしくはカットインしてシュートなりラストパスなり)を送り込むことができれば、もっともっと福田が相手にとって脅威の存在となりますよね。
※ 福田のクロスがひっかかって得られたコーナーキックでゴールを奪ったんですけど伏せておきます(笑)
そこで、今回はそこに着目して、福田のプレーを分解してみました。ちなみに、予め言っておきますが、私は大好きな福田君の今後の活躍に期待しているからこそ、ピックアップしたということですので、この件に関しては、一切苦情は受け付けません(笑)
では、なぜ、彼のクロスがひっかかってしまうのか、彼がカットインできないのかというところなのですが、簡単に言うと、
「ノッキングしながら進んでしまう」
「横を向いてしまう」
という2点に尽きます。
例えば、今節の橋岡であれば、縦に突破と決めたら、縦にしか進みません。そこでスピードに乗ったところでクロスを上げるので、アジリティに劣る相手であれば簡単に振り切ってクロスを送り込むことができます。しかしながら、福田はフェイントを入れながら、前に進もうとしながら止まりながら、徐々に徐々に自分自身でサイドやエンドラインに追いこんでいきます。これによって少しずつプレーできるエリアが狭くなり、そして縦に抜けてもクロスを上げる瞬間に減速してしまい、スピードに乗ってクロスを上げられなくなります。だから、相手が追い付いてクロスがひっかかってしまうという事になります。
しかしながら、これでは理由としては30%程です。もうひとつの大きな理由は、ボールキープの為に、相手に対して横を向いてしまう事なのです。横を向いてしまう事によって、これも先ほどの理由と同様に、自分のプレーできるエリアが制限されてしまいます。エリアが制限されるということは、相手にとって守るべきエリアが限られます。
福田がボールを受けた時には、相手にとって
「カットインされそう」
「スピードで振り切られそう」
「クロス上げられそう」
という状況で対峙するので非常に難しいマッチアップなのですが、じわりじわりと自らの動きで状況を悪化させてしまって、最後は相手の対応が
「クロスだけ気を付けよう」
となり、クロスがひっかかってしまう確率が高くなってしまうのです。浦和戦の2分過ぎからのシーンがよく福田の状況を表しているので見てみてください。
余談ですが、自分が小学校の時のサッカークラブで右サイドハーフをやっていて、ドリブルを仕掛ける時に、先生から「逃げるな」と言われていました。これは、相手に立ち向かって自分でプレーエリアを作りなさいという意味だったのだと思います。しかしながら、言語化されていなかったために「逃げるな」という非常に抽象的な指示と言うか怒号が飛んできていて、小学生のオオタニ少年は頭にはてなが浮かんで大成しなかったのだなと(笑)





上記の動きを解決するためには、もうトレーニングと成功体験しかないです。彼がサイドプレイヤーとして攻撃を担って効果的な仕掛けをするためには、個人としての技術を上げていく事が必要となります。そして、実は、鳥栖には非常に素晴らしいお手本となるプレイヤーがいます。(いました。)それは、小野と鎌田です。
小野や鎌田は、サイドでボールを受けた時に、横を向いて受ける形になっても、ボールをキープしながら自分の動けるエリアを確保していき、そしてバックステップを使って徐々に相手と向き合える状態を作ります。この試合でも、小野が最初にボールを受けた状況では、動ける範囲は縦へのスペースしかないのですが、ボールを持ちながら体の向きを変える事によって、右足でも左足でも蹴られる状況を作り出しました。この動きによって、彼の次のプレーに対する選択肢が大きく広がるのです。


鎌田もそのプレイが非常に上手だったわけでありまして、彼はどのような状態でボールを受けても、体を上手に使って相手と向き合って自ら選択肢を増やす動きで相手と正対します。だからこそ、どのような状況でボールを受けても、気が付けばカットインしてシュートも打ちますし、全体を見渡してスルーパスも出しますし、縦に突破してクロスを上げることも出来るということです。
相手と向き合うとボールを取られるのではないかというリスクを感じて、どうしても、相手から遠い足の方にボールを置きたくなりますが、逆にそのことによって自らのプレーエリアを制限してしまっているというのが、いまの福田の状況です。
まず、縦に抜けるなら抜ける!その思い切りとスピードだけで振り切れる相手はいるのですから、勇気をもって縦に突破してほしいですね。もしくは、トーレスや金崎に早めにボールを当てる事です。彼が保持している間にどんどん相手はブロックを築き上げてゴール前を固めてしまうので、パスコースがあるうちにストライカーに早めにパスを送ると、自らの個人技で突破しなければならない状況を生まなくてすみます。彼に今後はどのようなプレイヤーとして成長してほしいのかという所は監督・コーチのビジョン次第でしょうが。


最後にひとつだけ。仙台戦のデビュー戦から述べていますが、もっともっとチームとしてトーレスを見てほしいなという気がします。最終ラインがリトリートするのを見計らって、すっとポジションを引いてフリーになるのがすごく上手です。そういったところを見て、厳しい状況ではなくフリーでいる状況でトーレスにボールを預けたいですね。



さて、本日は川崎フロンターレ戦です。2連勝している勢いをそのままに、思い切って勇気をもってぶつかってほしいと思います。
※これまで高橋3人を「義希」「高橋秀」「高橋祐」と表現しておりましたが、今節から、「義希」「秀人」「祐治」へと変更しました。
<画像引用元:DAZN>
<画像引用元:Football LAB>
鳥栖のセットアップは、攻撃時には4-3-3(4-3-1-2)、守備時には5-2-3(5-3-2)という形で始まり、途中から攻撃時には4-4-2、守備時には5-3-2(5-4-1)という形に変わっていきました。ただし、今節に関してはセットアップポジションを示しても、あまり意義のあるものではないのかもしれません。
特に、守備時においてはそれが顕著で、浦和が積極的に攻撃に人数をかけ、また、ポジションの移動を激しく繰り返していたので、鳥栖として「ここならばボールを奪える」というポイントがなかなか作れず、ブロックを組んでもボールの出し引きをされて選手を動かされるので確固たる組織守備とならず、システムも選手の配置も様々替わって局面に応じてフレキシブルな対応を課せられてしまいました。
突き付けられた課題は、ゾーンで守りたいけど質的にも数的にも位置的にもすべてにおいて不利な状況が発生しており、どのような対応策を取るかというなかなか過酷なものでありましたが、最終的に、解決策としては「最終ラインでの人海戦術」という形にならざるを得ず、その着地点に向けて局所局所で選手たちを動かしていきながら、形を模索しながらという試合進行でした。
今回ばかりは、最後は人について離さないという恐らくインテリジェンスな組織とはなかなか言い難い守り方…でもサガン鳥栖らしい泥臭い執念を感じる守り方になりましたが、先制点という追い風もあり、選手やベンチのみならず、スタジアムにいるサガン鳥栖サポーターも含めた全員で虎の子の1点を守りきることが出来ました。
守備を詳しく見ていきましょう。浦和がボールを保持してビルドアップを始めた段階でインサイドハーフの福田が1列下がって5人で最終ラインを組むケースが多く、これは鳥栖が5バックで臨むときの定型で、宇賀神の動きに連動して福田がポジションを決めたというよりは、いつも通りセットアップとしてこの形を選択したのだと考えます。逆に、左サイドの原川は無条件に最終ラインに組み込むのではなく、中盤のスペースケアと攻撃の基点となる事を見据え、状況を見ながらそのポジショニングを決める形でした。
福田を1列下げますので、中央は原川、秀人、小野によってスペースをケアしつつ、ウイングバック対策としては、サイドの局面でスピードに対抗できるように「宇賀神VS福田」「橋岡VS吉田」というマッチアップを作ることによって、質的に劣ることなくサイド攻撃を防ぎたいという意図を感じました。
しかしながら、この目論見は浦和の巧みなポジショニングとビルドアップによって見事に破壊されることになります。
(1)鳥栖の左サイドにおける武藤、橋岡による崩し
試合開始序盤に左サイドを崩されて何回かクロスを上げられ、興梠のヘディングなどのピンチを迎える事になりましたが、その原動力となったのは、武藤の動きによるものでした。
吉田はどちらかというと人に食いつくタイプで、ポジションを動かす選手に対してもボールが出る事を見越してインターセプト狙いで食いついていきます。武藤はトップの興梠のフォローというよりは、左サイドの吉田の周りを狙ってポジショニングを取っていました。そこから、武藤がポジションを移す事によって吉田がついていくので、時折、吉田が武藤に引っ張られて、原川よりも前のポジションで武藤をマークするという状況が生まれていました。こうなると、どうしても原川は中盤のケアよりも吉田のカバーの方が優先となり、最終ラインに引いてスペースを埋めたり、ウイングの橋岡にでたボールに対するマークをとらなければならない状況が生まれました。

これは、鳥栖にとってはあまり迎えたくなかった形でありまして、吉田に対して武藤をぶつけられたことによって橋岡に対してアジリティに劣る原川が対応しなければならないという、質的に不利なマッチアップとなってしまいました。この形を作られた事によって、鳥栖の左サイドで縦に突破されてクロスを上げられたり、裏のスペースに走り込まれて長いサイドチェンジを受けたり、ゴール前へのラストパスを送り込まれる形を作られてしまっていました。原川を引かせるということは、当然金崎や小野も引かなければならなくなってしまうわけでありまして、スコアレスの状態でそこまで徹底して守備に入ることができるかと言う所が悩ましいところであり、それが下記の(2)に繋がってしまいます。
試合中に下のようなツイートをしたのはこういう状況だったということです。
さて、武藤が右サイドで吉田を引き連れて、サイドでは橋岡と原川のマッチアップとなり、攻守ともに分が悪いという状況が発生してますが、どうしますかね。
— オオタニ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2018年8月11日
■ 浦和の崩し





(2)中盤に大きく空いたスペース
(1)のように、ポジションを大きく前に取るウイングへの対応によって、福田と原川が最終ラインに引きこまれてしまうという現象が発生しました。システム的には6バックのような形です。これによって何が起きるかというと、インサイドハーフのうちの2名が不在となり、では、中盤のスペースをケアするのは誰?という問題が発生します。

実は試合開始序盤からサガン鳥栖はこの問題を抱えていましたが、なかなか解決できずに、トーレス、金崎、小野にどこまで守備のタスクを与えるかと言うところをベンチは試案していた模様でした。
完全に守備に踏み切れない背景には、実は浦和は守備に回った時にはそこまで積極的にボールを奪いに来るわけではなく、しっかりと5-3-2(5-4-1)ブロックを組んで前線に残す人数を最小限にしていため、浦和のカウンターに対する脅威をさほど感じられないというメンタル面も影響していたかと思います。浦和が前から来るわけではないので、鳥栖もビルドアップやトーレスの高さを利用した前進はそれなりに図れており、心理的に圧迫感や閉塞感を感じる状況でもなく、(スタジアムの熱気もありまして)一進一退だという雰囲気を感じます。こういう状況になると、セカンドボールを拾って二次攻撃、前から奪いに行ってショートカウンターという、試合展開として押し込みたいという気持ちが出てきます。
こういう背景から、序盤から小野と金崎を引かせて完全撤退という形になかなか踏み切れず、中途半端に浦和のビルドアップに仕掛けていってしまう前線と、ウイングのポジショニングの恐怖にさらされて出来る限り裏のスペースを空けられたくない最終ラインという構図になり、浦和のビルドアップへの対抗策に対する意思統一が図れないまま試合が進んでいってしまいました。
浦和のビルドアップもよく考えられておりまして、槇野と岩波がボール保持時に両サイドに大きく張りだしてポジションを取ります。鳥栖は機を見てトーレス、金崎の二人が前からプレスをしかけたのですが、両センターバック間が空いてしまったエリアを柏木がうまくポジションを出しいれして最終ラインからの経由地として機能していました。この柏木の巧みな動きによって鳥栖が前線でプレスをかけるには数的不利であることは明確でして、追っては交わされ、追っては交わされという、不毛なプレスを強いられていました。


特に、困っであろうのが小野のポジショニングでありまして、ある程度前から行くのか、それとも完全に引いてしまうのか選択を迫られました。5-3-2として割り切るならばポジションを引かなければなりませんが、トーレスと金崎が完全にリトリートするような構え(ミドルサード付近での迎撃)でもなく、相手ペナルティエリア付近まで行ってしまうので、連動して前に行かなければならず、かといって後ろの原川と福田は思い切って前に出て来れないという状況になり、本来は自分が見なければならない柏木、青木もうまく捕まえることが出来ず、小野のポジションの取り方は非常に難しいものでした。

それにも増して、秀人にかかる負担は相当なものでして、見過ごしていたらそのまま押し込まれるだけの状況となり、かといって前から行っても数的不利で交わされて広大なスペースを与えてしまい、サイドハーフは引いてしまっているので中盤のスペースをカバーしなければならず、しかしながら押し込まれたときには最終ラインに入ってクロスも跳ね返さなければならないという、小野以上に厳しい状況にさらされ、そして様々な対応を迫られていました。
秀人がひとりでスペースをケアする中盤のキープレイヤーとなってしまったおかげで、皮肉にも秀人が動いて空けた場所が浦和が使えるスペースになるという状況を生んでいました。フォワードたちの前進に呼応して秀人が動くとそのスペースを使われ、サイドを崩されたことによって最終ラインのカバーに入るとバイタル前のエリアからミドルシュートを打たれ、こういう状況下ではありましたが、前線と最終ラインを繋ぐ唯一のブリッジとして、まさに孤軍奮闘の活躍であり、コーナーキックからのゴールはまるで八面六臂の活躍に対するご褒美であるかのようでした。ヒーローインタビューは本当に胸を打たれる熱い言葉でしたね。


これらの(1)、(2)の状況は、橋岡がボールを受けるエリア、武藤がボールを受けるエリア、両センターバックがボールを持ちあがれるエリア、ハーフウェーライン近くで柏木がボールを配球するエリアが浦和の狙いどころになっていたことが、浦和のヒートマップにも現れています。

(3)対応策
上記のように、序盤は(1)(2)による状況によって、非常に難しいサッカーを強いられていましたが、まずもって、ウイングへの対応によって最大6人が引いてしまっているので、中盤のスペースをコンパクトにしてボールを奪い取る事はかなり難しい状況です。この状況で大事なのは
「どこのスペースを捨てるのか」
「どこのエリア(サイド)を集中して守るのか」
「ポジションはどのように動かすのか(セットアップポジションから誰を引かせて、誰を残すのか)」
「プレスのラインはどこにおくのか」
といった約束事をはっきりすることでした。
そういう意味では、中盤のスペースをどうするのかというところが序盤からの最大の課題だったかと思われます。前に出ようとする前線と、後ろをしっかりと守ろうとする最終ラインとの間にギャップが生まれ、そこをついて岩波、槇野が上手にボールを持ちあげたり、柏木や青木が大きな展開でボールを前に進められるというのは、ビルドアップという行為に苦労せずともに鳥栖の陣地深くまで押し上げる事が出来ていたからです。
ただし、序盤から明確になっていることはありまして、一旦浦和に奥深く入られてしまったときには、完全にリトリートするというスイッチが入りまして、金崎も小野もトーレスも、しっかりとリトリートして守備をこなしていました。最後はゴール前で跳ね返せばいいじゃん!という割り切りです。
特に小野は最終ラインまで下がってのディフェンスもこなしており、難しい状況ながらもしっかりとその役目を果たしたと思います。本来は小野に前線でのキープと推進力を求められていたのでしょうが、このように守備に追われる時間が長くなってしまったため、試合展開からなかなかその場面を作ることはできませんでした。
鳥栖もベンチから様々な指示がでていたのですが、前半の途中から少しずつやり方を変え出してきておりまして、まず、守備フェーズに切り替わった時に割り切って原川を最終ラインに組み込んで原川が武藤を見る形を作り上げ、橋岡に吉田を当てる形を作りました。これによって橋岡にスピードで振り切られるのを阻止する形を作り上げました。


また、給水タイムに指示があったと思われるのですが、小野が明確にポジションを下げて左サイドのインサイドハーフにポジションを移しました。これに合わせて原川を中央、秀人を右サイドにポジションを変更し、槇野、岩波が上がってくるスペースを秀人、小野で対応するという形をとりました。

それでも、橋岡に対しては小野が振り切られてクロスを上げられるなど、守備強度に対する不安がありましたので、後半になって福田を左サイドに移して橋岡の突破を防ぐという形をとりました。福田を左サイドで最終ラインに落とす形になったので、守備時に明確に5-3-2のブロックを組みました。中盤は秀人を中央に戻して原川と小野がインサイドハーフの役割となりました。




そして、選手たちに勇気を与えたのは何よりも秀人の先制ゴールでした。このゴールによって、チーム全体に1点を守りきるという明確な目標がうまれ、明確に「守備」を優先したポジショニングへと意識が変わり、チーム全体の動きが連動しだして、ミドルゾーンからの守備と言う形で統一されました。
前半開始したのままの戦い方では、確実に鳥栖は浦和の攻撃に屈していたことでしょう。しかしながら、システムを変え、ポジションを変え、選手の配置を変え、構え方を変え、チーム全体でいろいろと試行錯誤することによって、無失点と言う最適な結果を作り上げました。改めて、試合は生き物であるということを知ることができました。
■ サガン鳥栖の攻撃
攻めに関しては、特別にこれまでと変わった様子はなく、トーレスにボールに集めて彼に入るボールに対するセカンドボールを拾いながら、陣地を押し上げるという形と、良い形でボールを奪えた場合は金崎や小野の推進力を利用してカウンターで一気に前にでるというものでした。
しかしながら、槇野の素晴らしい対応によって、トーレスが制空権を完全に握ることができず、また、今回の守備組織ではボールの奪いどころが低い位置にならざるを得なかったので、効果的なカウンターという状況もそこまで多くは作れず、シュートまでの形作りとしてはツートップの質に頼らざるを得ない状況が続きました。
また、浦和が守勢に回ったときが、5-3-2(5-4-1)によるブロックであったため、4-4-2でビルドアップするという選択をとった鳥栖は、サイドのスペースを有効活用してボールの前進を図れたシーンもあったのですが、最後のクロスのところでどうしてもひっかかってしまうというシュートに繋がらない状況が発生しました。
その中でも、福田のクロスがひっかかってしまうのは毎試合気になるところでありまして、福田の類まれなる運動量と献身的な動きによって、彼がサイドのスペースに上手く入り込んでトーレス、金崎、小野からのパスを上手に引き出してくれますが、最後の大事な場面でクロスがどうしても相手にひっかかってしまいます。そこでしっかりとクロスを中央に送り込む事(もしくはカットインしてシュートなりラストパスなり)を送り込むことができれば、もっともっと福田が相手にとって脅威の存在となりますよね。
※ 福田のクロスがひっかかって得られたコーナーキックでゴールを奪ったんですけど伏せておきます(笑)
そこで、今回はそこに着目して、福田のプレーを分解してみました。ちなみに、予め言っておきますが、私は大好きな福田君の今後の活躍に期待しているからこそ、ピックアップしたということですので、この件に関しては、一切苦情は受け付けません(笑)
では、なぜ、彼のクロスがひっかかってしまうのか、彼がカットインできないのかというところなのですが、簡単に言うと、
「ノッキングしながら進んでしまう」
「横を向いてしまう」
という2点に尽きます。
例えば、今節の橋岡であれば、縦に突破と決めたら、縦にしか進みません。そこでスピードに乗ったところでクロスを上げるので、アジリティに劣る相手であれば簡単に振り切ってクロスを送り込むことができます。しかしながら、福田はフェイントを入れながら、前に進もうとしながら止まりながら、徐々に徐々に自分自身でサイドやエンドラインに追いこんでいきます。これによって少しずつプレーできるエリアが狭くなり、そして縦に抜けてもクロスを上げる瞬間に減速してしまい、スピードに乗ってクロスを上げられなくなります。だから、相手が追い付いてクロスがひっかかってしまうという事になります。
しかしながら、これでは理由としては30%程です。もうひとつの大きな理由は、ボールキープの為に、相手に対して横を向いてしまう事なのです。横を向いてしまう事によって、これも先ほどの理由と同様に、自分のプレーできるエリアが制限されてしまいます。エリアが制限されるということは、相手にとって守るべきエリアが限られます。
福田がボールを受けた時には、相手にとって
「カットインされそう」
「スピードで振り切られそう」
「クロス上げられそう」
という状況で対峙するので非常に難しいマッチアップなのですが、じわりじわりと自らの動きで状況を悪化させてしまって、最後は相手の対応が
「クロスだけ気を付けよう」
となり、クロスがひっかかってしまう確率が高くなってしまうのです。浦和戦の2分過ぎからのシーンがよく福田の状況を表しているので見てみてください。
余談ですが、自分が小学校の時のサッカークラブで右サイドハーフをやっていて、ドリブルを仕掛ける時に、先生から「逃げるな」と言われていました。これは、相手に立ち向かって自分でプレーエリアを作りなさいという意味だったのだと思います。しかしながら、言語化されていなかったために「逃げるな」という非常に抽象的な指示と言うか怒号が飛んできていて、小学生のオオタニ少年は頭にはてなが浮かんで大成しなかったのだなと(笑)





上記の動きを解決するためには、もうトレーニングと成功体験しかないです。彼がサイドプレイヤーとして攻撃を担って効果的な仕掛けをするためには、個人としての技術を上げていく事が必要となります。そして、実は、鳥栖には非常に素晴らしいお手本となるプレイヤーがいます。(いました。)それは、小野と鎌田です。
小野や鎌田は、サイドでボールを受けた時に、横を向いて受ける形になっても、ボールをキープしながら自分の動けるエリアを確保していき、そしてバックステップを使って徐々に相手と向き合える状態を作ります。この試合でも、小野が最初にボールを受けた状況では、動ける範囲は縦へのスペースしかないのですが、ボールを持ちながら体の向きを変える事によって、右足でも左足でも蹴られる状況を作り出しました。この動きによって、彼の次のプレーに対する選択肢が大きく広がるのです。


鎌田もそのプレイが非常に上手だったわけでありまして、彼はどのような状態でボールを受けても、体を上手に使って相手と向き合って自ら選択肢を増やす動きで相手と正対します。だからこそ、どのような状況でボールを受けても、気が付けばカットインしてシュートも打ちますし、全体を見渡してスルーパスも出しますし、縦に突破してクロスを上げることも出来るということです。
相手と向き合うとボールを取られるのではないかというリスクを感じて、どうしても、相手から遠い足の方にボールを置きたくなりますが、逆にそのことによって自らのプレーエリアを制限してしまっているというのが、いまの福田の状況です。
まず、縦に抜けるなら抜ける!その思い切りとスピードだけで振り切れる相手はいるのですから、勇気をもって縦に突破してほしいですね。もしくは、トーレスや金崎に早めにボールを当てる事です。彼が保持している間にどんどん相手はブロックを築き上げてゴール前を固めてしまうので、パスコースがあるうちにストライカーに早めにパスを送ると、自らの個人技で突破しなければならない状況を生まなくてすみます。彼に今後はどのようなプレイヤーとして成長してほしいのかという所は監督・コーチのビジョン次第でしょうが。


最後にひとつだけ。仙台戦のデビュー戦から述べていますが、もっともっとチームとしてトーレスを見てほしいなという気がします。最終ラインがリトリートするのを見計らって、すっとポジションを引いてフリーになるのがすごく上手です。そういったところを見て、厳しい状況ではなくフリーでいる状況でトーレスにボールを預けたいですね。



さて、本日は川崎フロンターレ戦です。2連勝している勢いをそのままに、思い切って勇気をもってぶつかってほしいと思います。
※これまで高橋3人を「義希」「高橋秀」「高橋祐」と表現しておりましたが、今節から、「義希」「秀人」「祐治」へと変更しました。
<画像引用元:DAZN>
<画像引用元:Football LAB>
Posted by オオタニ at
12:26
│Match Impression (2018)
2018年08月09日
2018 第20節 : サガン鳥栖 VS セレッソ大阪 (番外編)
2018年第20節、C大阪戦のレビューの番外編です。
今回は、本編であまり触れなかった「機能しなかったシーン」を中心に振り返ります。
1.トーレスと福田の合わない連係
この試合でおもしろかったのは、トーレスと福田の息が合わないシーンが結構ありまして。そのたびにトーレスが少しずつストレスをためていったのですが、とうとういつかスペイン代表で見た彼のように福田に対して不満を表すようになりました。これは逆に、トーレスがお客さまではなくてチームメイトになってきたということで喜ばしいですよね。チームビルディングの上では、メンバーがお互いに要求を言い合う事が大事です。コミュニケーションは双方向のものなので、今後は福田も言い返せるようになってください(笑)
では、トーレスのストレスがMAXたまるまでの軌跡が10分間に濃縮されていたので、これらをダイジェストでお送りします(笑)
① ラストパスが来ない



② スルーパスが来ない



③ パスが合わない



④ クロスが来ない



こうして見ると、やはり、トーレスのポジショニングは秀逸ですよね。うまく相手を外してボールを受けられるスペースに入り込んでいます。難しい選択をせずに、もっと簡単にトーレスを信頼してボールを預けても良いと思いますけどね。ひとまず、福田くん、頑張ってください(笑)
2.トーレスと金崎がポジションを取れないケース
本編では、守備時にトーレスと金崎がペナルティエリア付近でポジショニングを取っているため、カウンター攻撃の起点としてボールを預ける事が出来るという戦術を書きました。しかしながら、当然、戦術通りの動きがとれずに、彼らがポジショニングを取れないという事も発生します。では、そうなった時にチームとしてどのような現象が発生していたか、ひとつのシーンを紹介したいと思います。
場面は、ゴールキーパーからのロングフィードをセレッソが拾ってからの攻撃です。フォワード二人はゴールキーパーの持ち上がりがありましたので、それぞれゴールキーパーとセンターバックに対してプレスに入りました。そこへ、トーレスと金崎の頭上を越えるロングボールを蹴られて、セレッソがペナルティエリア近くでボールを納めます(この時、鳥栖が最終ラインを上げる事ができなかったので、オフサイドも取れずに最終ラインの前のスペースでボールキープされてしまいます)この一連の流れでトーレスと金崎がリトリートしてポジションを取れないという状況が発生してしまいました。なんとか攻撃を防いでボールを奪いますが……その続きが以下の図です。




トーレス、金崎が、約束された位置にいないだけで、カウンターにつながらないばかりか、ボールロストでピンチまで迎えてしまうという事象が起きてしまいました。今回のマッシモのとった戦術(カウンターのデザイン)の機能性が分かるシーンでもありますし、前線と中盤、最終ラインが連係してラインコントロールすることの大切さがわかりますね。
さて、浦和戦ではどのような戦術で、どのような戦いかたを見せてくれるのか、楽しみですね。満員のスタジアムで素晴らしい勝利を見せて欲しいです。
<画像引用元:DAZN>
今回は、本編であまり触れなかった「機能しなかったシーン」を中心に振り返ります。
1.トーレスと福田の合わない連係
この試合でおもしろかったのは、トーレスと福田の息が合わないシーンが結構ありまして。そのたびにトーレスが少しずつストレスをためていったのですが、とうとういつかスペイン代表で見た彼のように福田に対して不満を表すようになりました。これは逆に、トーレスがお客さまではなくてチームメイトになってきたということで喜ばしいですよね。チームビルディングの上では、メンバーがお互いに要求を言い合う事が大事です。コミュニケーションは双方向のものなので、今後は福田も言い返せるようになってください(笑)
では、トーレスのストレスがMAXたまるまでの軌跡が10分間に濃縮されていたので、これらをダイジェストでお送りします(笑)
① ラストパスが来ない



② スルーパスが来ない



③ パスが合わない



④ クロスが来ない



こうして見ると、やはり、トーレスのポジショニングは秀逸ですよね。うまく相手を外してボールを受けられるスペースに入り込んでいます。難しい選択をせずに、もっと簡単にトーレスを信頼してボールを預けても良いと思いますけどね。ひとまず、福田くん、頑張ってください(笑)
2.トーレスと金崎がポジションを取れないケース
本編では、守備時にトーレスと金崎がペナルティエリア付近でポジショニングを取っているため、カウンター攻撃の起点としてボールを預ける事が出来るという戦術を書きました。しかしながら、当然、戦術通りの動きがとれずに、彼らがポジショニングを取れないという事も発生します。では、そうなった時にチームとしてどのような現象が発生していたか、ひとつのシーンを紹介したいと思います。
場面は、ゴールキーパーからのロングフィードをセレッソが拾ってからの攻撃です。フォワード二人はゴールキーパーの持ち上がりがありましたので、それぞれゴールキーパーとセンターバックに対してプレスに入りました。そこへ、トーレスと金崎の頭上を越えるロングボールを蹴られて、セレッソがペナルティエリア近くでボールを納めます(この時、鳥栖が最終ラインを上げる事ができなかったので、オフサイドも取れずに最終ラインの前のスペースでボールキープされてしまいます)この一連の流れでトーレスと金崎がリトリートしてポジションを取れないという状況が発生してしまいました。なんとか攻撃を防いでボールを奪いますが……その続きが以下の図です。




トーレス、金崎が、約束された位置にいないだけで、カウンターにつながらないばかりか、ボールロストでピンチまで迎えてしまうという事象が起きてしまいました。今回のマッシモのとった戦術(カウンターのデザイン)の機能性が分かるシーンでもありますし、前線と中盤、最終ラインが連係してラインコントロールすることの大切さがわかりますね。
さて、浦和戦ではどのような戦術で、どのような戦いかたを見せてくれるのか、楽しみですね。満員のスタジアムで素晴らしい勝利を見せて欲しいです。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
20:25
│Match Impression (2018)
2018年08月08日
2018 第20節 : サガン鳥栖 VS セレッソ大阪
2018年第20節、C大阪戦のレビューです。
鳥栖のセットアップは、攻撃時と守備時とで可変のシステムとなっていました。攻撃時は4-3-1-2で、中盤の底に高橋秀を置き、原川と福田をインサイドハーフに据え、トップ下に義希を起用というシステムでした。ボールを奪うと早めに前線にボールを送り込むスタイルへと変革(原点回帰?)させ、義希にはツートップのフォローによるセカンドボールの奪取と裏に抜ける動きというタスクが与えられていました。
守備時はその義希を中央から高橋秀の位置まで下ろしてフラット気味に4-4-2の形を作ります。フォワードは積極的にボールを奪う形ではなく、ミドルサード(センターサークル付近)で中央を締める動きを取り、ドイスボランチとの連動でセレッソのボールをサイドへと追いやるタスクを果たしていました。セレッソには、ソウザ、山口というゲームメイクと展開が持ち味であるプレイヤーがボランチにいるため中央をしっかりしめつつ、清水戦のように簡単にサイドを利用されないように中盤を4人でスライドしてスペースを素早く埋めるという形です。セレッソがサイドにボールを回した時には、サイドバックにサイドハーフを付けてそこでボールを奪えたらベスト。ボールを奪えずとも追い返えすだけでもOKという守備でした。
これにより、攻撃時は4-3-1-2にして早いボールを送り込んでセレッソのボランチのプレスを無効化し、守備時には4-4-2にしてセレッソとミラーゲームのような形を取って、ビルドアップによる崩しを防ぐという戦術を取ることができました。
■ 4-4-2対応によるミラーゲームへの持ち込み

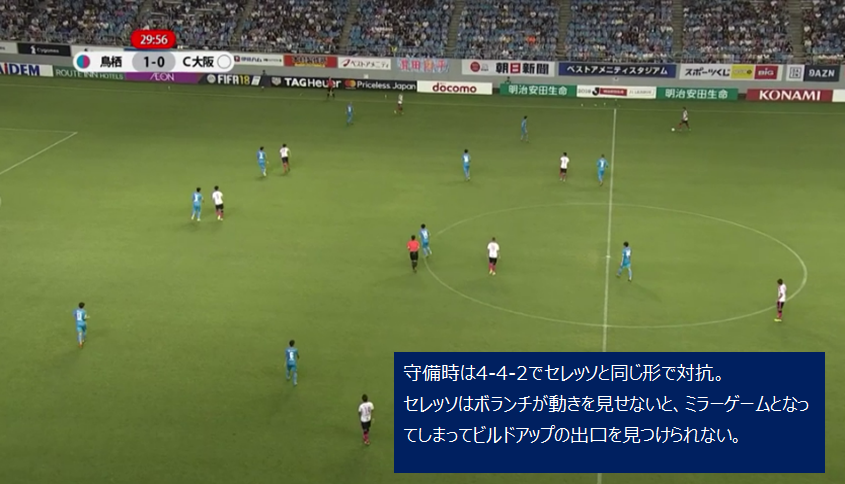
この試合で鳥栖に変化が見られたのは、ツートップのポジショニング及びツートップへのボールの配球でした。ひとまず、トーレスと金崎に与えられていた(と想定される)オーダーを列挙します。
(1)ポジショニングの幅は中央エリアをメインとし、横の関係を維持する。
(2)センターバックのボールキープに対して過度にプレッシャーをかけずミドルサードで待ち受け、中央にいるボランチへのボールの配球を防ぐ。
(3)自陣に押し込まれたときは、2人とも平行にポジションをとったままペナルティエリア付近までリトリートする。
(4)最終ラインは外からのクロスを中央に跳ね返すのでツートップはセカンドボールをキープする
(5)味方がボールを奪った時は、カウンターの起点とするため金崎、トーレスのどちらかがボールを早めに引き受ける
これらのポイントを盛り込んで、今節の鳥栖の戦いを振り返ります。
基本的に今回のツートップは横の関係を築いており、ポジショニングを平行にとる形でした。それはミドルサードで構えている時でも、ディフェンシブサードに押し込まれた場合でも同様で、常にトーレスと金崎を近くに配置し、連係できるポジションを取っていました。また、暑さもあって体力が消耗しやすい季節なので、常に前からボールを奪いに行くというプランではなく、基本的にはミドルサードで待ち受けるプランで試合に臨みました。当然、試合の中で前からボールを奪いに行けるタイミングはありますが、深追いせずにタイミングを見計らってという感じです。
セレッソにはソウザ ⇒ 杉本という一発で決定的な仕事を出来るプレイヤーがセンターラインにいるため、鳥栖としてはなるべく中央を使われたくありません。(サイドはサイドで清武、水沼と強力ですが。)よって、ミドルゾーンでのプレスでは、ツートップがセレッソのセンターバック2名からドイスボランチ2名へのパスコースを遮断し、義希、高橋秀と共にボックスの関係を構築してソウザと山口蛍が中央で仕事をできないような対応を取ります。これにより、ソウザが楽にボールを受けられるエリアを求めてサイドにポジションを移したり、山口蛍がボールキープの為に最終ラインにポジションを移したりと、中央でのプレッシャーを嫌がるようになりました。
中央が使えないセレッソは、必然的に鳥栖が人数をかけてこないサイドを利用するようになります。当然鳥栖としてもサイドを無視するわけにはいかないので、その解決策が必要になるのですが、「サイドチェンジはされるもの」と割り切り、中盤にセントラルハーフを4人並べる事によって、サイドチェンジされた後にいかに早くスペースを圧縮するか(いかにスペース圧縮が遅れないか)という形を取りました。
これにより、清水戦と異なり、サイドチェンジ後に鳥栖のサイドバックが孤立することなく、ファーストディフェンスをサイドハーフが対応することが可能となりました。セレッソとしては、サイドに基点を作って攻撃を優位に進めようとしても、福田や原川の頑張りによってプレッシャーが早く、なかなか崩す事が出来なかったため、徐々に選択肢が早めのクロスと言う形に絞られていきました。サイドバックが釣り出されないというのは非常に大きな効果がありまして、単純な事なのですが、サイドチェンジからクロスを上げられる際に、ゴール前にセンターバックの2名だけになるのか、サイドバックも含めて3人になるのかというのは大きな違いありました。人数を多く構える事によって跳ね返すことの出来る確率があがりますよね。
■ セレッソサイドチェンジへの対応(1)


■ セレッソサイドチェンジへの対応(2)


この早めのクロスに対するセカンドボールの対応策も鳥栖は準備されていて、鳥栖が押し込まれて最終ラインがゴール前にリトリートした場合にも、トーレス、金崎がそのまま中央のポジションでペナルティーエリアの少し前の位置にポジションを取っていました。これによるメリットが2点ありまして、一つは山口とソウザがゲームメイクの為に鳥栖のスクエアから逃れようとするポジションを取っていた為、中央に落ちてきたセカンドボールをトーレスと金崎が拾いやすい点。もう一つは、ディフェンシブサードでボールを奪った時のカウンターの起点として、より最終ラインに近い範囲で金崎、トーレスにボールを預けられるという点です。清水戦までは、トーレスも金崎もどちらかというとセンターサークル付近で待機しており、カウンターの際にはインサイドハーフを経由してボールを前に送り込むか、トーレスと金崎を走らせるパスを送り込むかという形でしたが、どちらにしても精度にかけて良い攻撃へと繋がりませんでした。しかしながら、トーレスと金崎をペナルティエリア付近までポジションを落とすことによって、彼らへのボールの配球も早くなりますし、何よりも彼らの技術力でセレッソのネガティブトランジションのプレスをかわすことが可能となります。
■ ディフェンシブサードのポジショニング(1)

■ ディフェンシブサードのポジショニング(2)


このツートップが早めにボールを受けられる態勢を作るというのは非常に効果的でした。本来は中央でのキープというのは相手にボールを奪われるとすぐに攻撃を受けるリスクがあるのですが、彼らはひとり程度だったらプレスをはがすことができるので、そのリスクの発生確率というのは非常に低く、この位置でボールキープすることによって、前方に空いている広大なスペースを狙って、義希と福田のスプリントを生かすという形を作ることができました。磐田戦、清水戦のように、トーレスと金崎を前方に押し上げてインサイドハーフでゲームを作ろうとすると、相手もコンパクトにスペースを埋めようとするので狭いエリアを繋げていくキープ力とパスワークが必要となります。しかしながら、今節のようにトーレスと金崎を引かせることによって、彼らの裏に空いた広大なスペースをサガン鳥栖自慢の「走力」によって利用できるという事です。今回は、福田、義希、原川がそれぞれカウンターでよいスプリントを見せていたので、それぞれのシーンを紹介します。
■ ツートップ+福田のカウンター


■ ツートップ+義希のカウンター


■ ツートップ+原川のカウンター



鳥栖は自分たちがボールキープしてからの攻撃でも、早めにツートップにボールを預けるという形には変わりませんでした。攻撃のパターンとしては2点ありまして、1つ目はゴールキーパーやセンターバックの位置からでもトーレスをめがけて大きく蹴り、金崎と義希を斜めの位置にポジショニングを取らせてセカンドボールを拾わせるという攻撃。2つ目は、一旦サイドバックを経由して、そこから中央のツートップ+義希の3人目がけて斜めのパスを入れるという形です。徹底的に中央の強力なツートップで崩そうとする形にこだわり、その結果、多くのチャンスを作り出すことができました。
余談ですが、この戦い方は、サガン鳥栖がJ1昇格して初年度に躍進した頃のような戦い方ですよね。豊田に向けてボールを集めるあの頃のようなプレーモデル。ユンジョンファンの前でマッシモがそのようなサッカーを見せるというのも少し趣深いものでした。
■ ロングボールのシフト





■ サイドから中央への楔のパス


■ 中央での崩しの例



今節、トーレスと金崎がペナルティエリアまで中央で起点になるのは、ヒートマップに現れていて、清水戦と比較すると一目瞭然です。この試合でマッシモが準備してきた戦い方の違いが伺えるデータとなっています。
■ 清水戦(前半)のプレーエリア

■ C大阪戦(前半)のプレーエリア

※「Football LAB」の解析画像を引用させて頂きました。
ボール保持時の攻撃も、カウンターの攻撃も、今節は選手たちの特性を生かした戦術でいい感じで機能していたのですが、この試合の展開を生んだのはやはり先制点を挙げた事が非常に大きかったです。先に点を取られるとどうしても追い付くために攻撃に出なければならないため、また、相手も無理せずに引いて構えるために、スペースを走力で有効活用するという鳥栖の戦術の威力が半減してしまいます。先に得点を挙げてセレッソにボールを持たせる事によって、鳥栖にとっての攻撃のスペースを生み出すことになり、準備されたカウンターの機会を多く作り出すことができました。キャプテンが挙げた先制点によってまさに自分たちの戦いの土俵に引きづり込むことができたという事です。ただし、吉田のゴールはコーナーキックからのこぼれ球をダイレクトでゴールを決めたものでしたが、同じようなシュートシーンはセレッソにも多くありました。(山口蛍が何回か、吉田と同じような形でシュートを放っていました)一つ間違えれば逆の展開もありえたわけで、今回は展開の利も結果に大きく左右しました。
非常に大きな勝ち点3を得たものの、全てを手放しで喜ぶわけにはいかず、この試合でも少なからずや問題点は発生しておりました。この試合で目についたシーンを少し紹介したいと思います。
1.ボールの持ち方によるリスク回避とチャンスメイク
先日の試合中に以下のようなツイートをしました。
前節までは、選手の配置上、外に持ち出すしか選択肢がなかったケースが多かったのですが、今節は前述のように、中央に選手を配置しており、また、セレッソの選手たちも攻撃の仕組み上サイドに寄っているケースが多かったため、後ろの選手が前を向いたり中央に持ち出したりすることで自分たちのプレイエリアの確保(ボールキープの継続)を果たせる状況下にありました。
しかしながら、選手たちの技術の問題及び戦術的な傾向の問題により、最初のチョイスが外への持ち出しであったり、バックパスであったりするケースがあり、相手に寄せられるきっかけを作ってしまって結局チャンスロスト(ボールロスト)というケースが発生していました。後ろに下げたり、サイドにはたくという事が必ずしもリスク回避という事ではありません。適切にポジションを取っている味方に対して、ボール保持者が適切なパスを送るもしくはボールを運ぶというプレイを選択することで、リスクを回避しつつチャンスメイクに繋げることが出来ます。
上記に上げた、この試合一番盛り上がったカウンターの場面で、原川が後ろを向いてしまいますが、あの場面だからこそ発生したのではなく、相手に詰められた時の「プレイのクセ」というものが単純に露見しただけのシーンです。そのためにも、常日頃からボールを持って前を向く(適切な態勢を取る)という技術を身に付けなければなりません。トーレスや金崎という素晴らしいお手本のような選手も来てくれましたし、これからトレーニングの中でボールの持ち方と扱い方を向上させ、チーム全体として今後のサガン鳥栖のサッカー品質を向上してほしいですね。
■原川の体の向け方によるチャンスロスト


■ミンヒョクの体の向け方によるボールロスト


2.セントラルハーフの連係ミスと守るべきエリアの再確認
今回の鳥栖の守備は、ミドルサードで構えるという約束事があり、また、4-4-2(しかも2トップは中央のみ)と自分の守るべきスペースが比較的分かり易い状態であったため、大きなほころびを生むことはありませんでした。しかしながら、前述の通り、タイミングを見計らってボールを前から奪う形をとりに行くこともあるのですが、そこで自分のエリアを抜け出してでもプレスに行った時の連動について、まだまだ組織として未完成である状況が発生していました。いわゆる、応用編になったときにどのような対応が取れるかという所です。具体的なシーンを紹介します。





実際は60分過ぎという体力的にも非常に厳しい状況なので、体力的には動くのが厳しい状況です。当然フィジカル的な問題もあるのですが、やはり、失点というのはこういうミスから発生してしまいます。ミスと言うのは、パスミス、トラップミス、クリアミス、キャッチミスなどの目に見えて分かり易いミスもあるのですが、そういうミスはこのレベルの選手たちでは早々発生しません。むしろ、ポジショニングミスという、一見してわかりづらいミスの方が得てして簡単にピンチを迎えてしまうのです。
味方の動きに合わせた連動と、優先的に守らなければならないスペースの認知という、めまぐるしく味方とボールの位置が変わるサッカーでは一番難しいプレーですが、強いチームというのは綻びのない守備組織を構築しています。サガン鳥栖も、まだまだ成長の伸び代があるので、堅固な守備組織を目指して、成長して欲しいですね。
ひとまず、長いトンネルを抜け出して勝ち点3を上げる事ができました。攻撃パターンも少しずつ確立してきたので、あとはトーレスや金崎の得点ですね。ホーム浦和戦でトーレスのゴールを見る事ができたら、盛り上がるでしょうね。ぜひ、満員のスタジアムでそのような興奮するシーンを見たいと思います。
<画像引用元:DAZN>
<画像引用元:Football LAB>
鳥栖のセットアップは、攻撃時と守備時とで可変のシステムとなっていました。攻撃時は4-3-1-2で、中盤の底に高橋秀を置き、原川と福田をインサイドハーフに据え、トップ下に義希を起用というシステムでした。ボールを奪うと早めに前線にボールを送り込むスタイルへと変革(原点回帰?)させ、義希にはツートップのフォローによるセカンドボールの奪取と裏に抜ける動きというタスクが与えられていました。
守備時はその義希を中央から高橋秀の位置まで下ろしてフラット気味に4-4-2の形を作ります。フォワードは積極的にボールを奪う形ではなく、ミドルサード(センターサークル付近)で中央を締める動きを取り、ドイスボランチとの連動でセレッソのボールをサイドへと追いやるタスクを果たしていました。セレッソには、ソウザ、山口というゲームメイクと展開が持ち味であるプレイヤーがボランチにいるため中央をしっかりしめつつ、清水戦のように簡単にサイドを利用されないように中盤を4人でスライドしてスペースを素早く埋めるという形です。セレッソがサイドにボールを回した時には、サイドバックにサイドハーフを付けてそこでボールを奪えたらベスト。ボールを奪えずとも追い返えすだけでもOKという守備でした。
これにより、攻撃時は4-3-1-2にして早いボールを送り込んでセレッソのボランチのプレスを無効化し、守備時には4-4-2にしてセレッソとミラーゲームのような形を取って、ビルドアップによる崩しを防ぐという戦術を取ることができました。
■ 4-4-2対応によるミラーゲームへの持ち込み

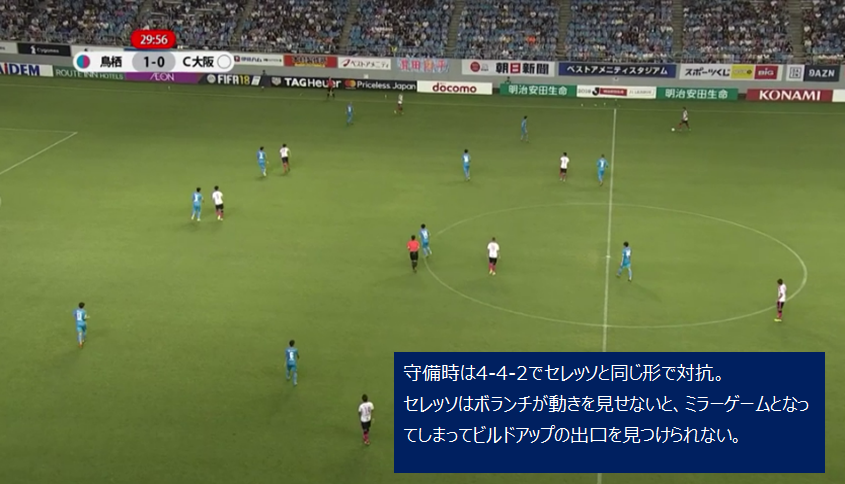
この試合で鳥栖に変化が見られたのは、ツートップのポジショニング及びツートップへのボールの配球でした。ひとまず、トーレスと金崎に与えられていた(と想定される)オーダーを列挙します。
(1)ポジショニングの幅は中央エリアをメインとし、横の関係を維持する。
(2)センターバックのボールキープに対して過度にプレッシャーをかけずミドルサードで待ち受け、中央にいるボランチへのボールの配球を防ぐ。
(3)自陣に押し込まれたときは、2人とも平行にポジションをとったままペナルティエリア付近までリトリートする。
(4)最終ラインは外からのクロスを中央に跳ね返すのでツートップはセカンドボールをキープする
(5)味方がボールを奪った時は、カウンターの起点とするため金崎、トーレスのどちらかがボールを早めに引き受ける
これらのポイントを盛り込んで、今節の鳥栖の戦いを振り返ります。
基本的に今回のツートップは横の関係を築いており、ポジショニングを平行にとる形でした。それはミドルサードで構えている時でも、ディフェンシブサードに押し込まれた場合でも同様で、常にトーレスと金崎を近くに配置し、連係できるポジションを取っていました。また、暑さもあって体力が消耗しやすい季節なので、常に前からボールを奪いに行くというプランではなく、基本的にはミドルサードで待ち受けるプランで試合に臨みました。当然、試合の中で前からボールを奪いに行けるタイミングはありますが、深追いせずにタイミングを見計らってという感じです。
セレッソにはソウザ ⇒ 杉本という一発で決定的な仕事を出来るプレイヤーがセンターラインにいるため、鳥栖としてはなるべく中央を使われたくありません。(サイドはサイドで清武、水沼と強力ですが。)よって、ミドルゾーンでのプレスでは、ツートップがセレッソのセンターバック2名からドイスボランチ2名へのパスコースを遮断し、義希、高橋秀と共にボックスの関係を構築してソウザと山口蛍が中央で仕事をできないような対応を取ります。これにより、ソウザが楽にボールを受けられるエリアを求めてサイドにポジションを移したり、山口蛍がボールキープの為に最終ラインにポジションを移したりと、中央でのプレッシャーを嫌がるようになりました。
中央が使えないセレッソは、必然的に鳥栖が人数をかけてこないサイドを利用するようになります。当然鳥栖としてもサイドを無視するわけにはいかないので、その解決策が必要になるのですが、「サイドチェンジはされるもの」と割り切り、中盤にセントラルハーフを4人並べる事によって、サイドチェンジされた後にいかに早くスペースを圧縮するか(いかにスペース圧縮が遅れないか)という形を取りました。
これにより、清水戦と異なり、サイドチェンジ後に鳥栖のサイドバックが孤立することなく、ファーストディフェンスをサイドハーフが対応することが可能となりました。セレッソとしては、サイドに基点を作って攻撃を優位に進めようとしても、福田や原川の頑張りによってプレッシャーが早く、なかなか崩す事が出来なかったため、徐々に選択肢が早めのクロスと言う形に絞られていきました。サイドバックが釣り出されないというのは非常に大きな効果がありまして、単純な事なのですが、サイドチェンジからクロスを上げられる際に、ゴール前にセンターバックの2名だけになるのか、サイドバックも含めて3人になるのかというのは大きな違いありました。人数を多く構える事によって跳ね返すことの出来る確率があがりますよね。
■ セレッソサイドチェンジへの対応(1)


■ セレッソサイドチェンジへの対応(2)


この早めのクロスに対するセカンドボールの対応策も鳥栖は準備されていて、鳥栖が押し込まれて最終ラインがゴール前にリトリートした場合にも、トーレス、金崎がそのまま中央のポジションでペナルティーエリアの少し前の位置にポジションを取っていました。これによるメリットが2点ありまして、一つは山口とソウザがゲームメイクの為に鳥栖のスクエアから逃れようとするポジションを取っていた為、中央に落ちてきたセカンドボールをトーレスと金崎が拾いやすい点。もう一つは、ディフェンシブサードでボールを奪った時のカウンターの起点として、より最終ラインに近い範囲で金崎、トーレスにボールを預けられるという点です。清水戦までは、トーレスも金崎もどちらかというとセンターサークル付近で待機しており、カウンターの際にはインサイドハーフを経由してボールを前に送り込むか、トーレスと金崎を走らせるパスを送り込むかという形でしたが、どちらにしても精度にかけて良い攻撃へと繋がりませんでした。しかしながら、トーレスと金崎をペナルティエリア付近までポジションを落とすことによって、彼らへのボールの配球も早くなりますし、何よりも彼らの技術力でセレッソのネガティブトランジションのプレスをかわすことが可能となります。
■ ディフェンシブサードのポジショニング(1)

■ ディフェンシブサードのポジショニング(2)


このツートップが早めにボールを受けられる態勢を作るというのは非常に効果的でした。本来は中央でのキープというのは相手にボールを奪われるとすぐに攻撃を受けるリスクがあるのですが、彼らはひとり程度だったらプレスをはがすことができるので、そのリスクの発生確率というのは非常に低く、この位置でボールキープすることによって、前方に空いている広大なスペースを狙って、義希と福田のスプリントを生かすという形を作ることができました。磐田戦、清水戦のように、トーレスと金崎を前方に押し上げてインサイドハーフでゲームを作ろうとすると、相手もコンパクトにスペースを埋めようとするので狭いエリアを繋げていくキープ力とパスワークが必要となります。しかしながら、今節のようにトーレスと金崎を引かせることによって、彼らの裏に空いた広大なスペースをサガン鳥栖自慢の「走力」によって利用できるという事です。今回は、福田、義希、原川がそれぞれカウンターでよいスプリントを見せていたので、それぞれのシーンを紹介します。
■ ツートップ+福田のカウンター


■ ツートップ+義希のカウンター


■ ツートップ+原川のカウンター



鳥栖は自分たちがボールキープしてからの攻撃でも、早めにツートップにボールを預けるという形には変わりませんでした。攻撃のパターンとしては2点ありまして、1つ目はゴールキーパーやセンターバックの位置からでもトーレスをめがけて大きく蹴り、金崎と義希を斜めの位置にポジショニングを取らせてセカンドボールを拾わせるという攻撃。2つ目は、一旦サイドバックを経由して、そこから中央のツートップ+義希の3人目がけて斜めのパスを入れるという形です。徹底的に中央の強力なツートップで崩そうとする形にこだわり、その結果、多くのチャンスを作り出すことができました。
余談ですが、この戦い方は、サガン鳥栖がJ1昇格して初年度に躍進した頃のような戦い方ですよね。豊田に向けてボールを集めるあの頃のようなプレーモデル。ユンジョンファンの前でマッシモがそのようなサッカーを見せるというのも少し趣深いものでした。
■ ロングボールのシフト





■ サイドから中央への楔のパス


■ 中央での崩しの例



今節、トーレスと金崎がペナルティエリアまで中央で起点になるのは、ヒートマップに現れていて、清水戦と比較すると一目瞭然です。この試合でマッシモが準備してきた戦い方の違いが伺えるデータとなっています。
■ 清水戦(前半)のプレーエリア

■ C大阪戦(前半)のプレーエリア

※「Football LAB」の解析画像を引用させて頂きました。
ボール保持時の攻撃も、カウンターの攻撃も、今節は選手たちの特性を生かした戦術でいい感じで機能していたのですが、この試合の展開を生んだのはやはり先制点を挙げた事が非常に大きかったです。先に点を取られるとどうしても追い付くために攻撃に出なければならないため、また、相手も無理せずに引いて構えるために、スペースを走力で有効活用するという鳥栖の戦術の威力が半減してしまいます。先に得点を挙げてセレッソにボールを持たせる事によって、鳥栖にとっての攻撃のスペースを生み出すことになり、準備されたカウンターの機会を多く作り出すことができました。キャプテンが挙げた先制点によってまさに自分たちの戦いの土俵に引きづり込むことができたという事です。ただし、吉田のゴールはコーナーキックからのこぼれ球をダイレクトでゴールを決めたものでしたが、同じようなシュートシーンはセレッソにも多くありました。(山口蛍が何回か、吉田と同じような形でシュートを放っていました)一つ間違えれば逆の展開もありえたわけで、今回は展開の利も結果に大きく左右しました。
非常に大きな勝ち点3を得たものの、全てを手放しで喜ぶわけにはいかず、この試合でも少なからずや問題点は発生しておりました。この試合で目についたシーンを少し紹介したいと思います。
1.ボールの持ち方によるリスク回避とチャンスメイク
先日の試合中に以下のようなツイートをしました。
守備ブロックは442から451
— オオタニ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2018年8月5日
攻撃時には4312
義希が巧みにポジションを動かしコントロールしていて、彼の運動量を活用した可変システムは機能していると思います。
あとはカウンター時のパスの精度と、ボールを取って前を向くこと。
秀人とCBの最初の選択肢が後ろか横になってるので、前を向きたい。
前節までは、選手の配置上、外に持ち出すしか選択肢がなかったケースが多かったのですが、今節は前述のように、中央に選手を配置しており、また、セレッソの選手たちも攻撃の仕組み上サイドに寄っているケースが多かったため、後ろの選手が前を向いたり中央に持ち出したりすることで自分たちのプレイエリアの確保(ボールキープの継続)を果たせる状況下にありました。
しかしながら、選手たちの技術の問題及び戦術的な傾向の問題により、最初のチョイスが外への持ち出しであったり、バックパスであったりするケースがあり、相手に寄せられるきっかけを作ってしまって結局チャンスロスト(ボールロスト)というケースが発生していました。後ろに下げたり、サイドにはたくという事が必ずしもリスク回避という事ではありません。適切にポジションを取っている味方に対して、ボール保持者が適切なパスを送るもしくはボールを運ぶというプレイを選択することで、リスクを回避しつつチャンスメイクに繋げることが出来ます。
上記に上げた、この試合一番盛り上がったカウンターの場面で、原川が後ろを向いてしまいますが、あの場面だからこそ発生したのではなく、相手に詰められた時の「プレイのクセ」というものが単純に露見しただけのシーンです。そのためにも、常日頃からボールを持って前を向く(適切な態勢を取る)という技術を身に付けなければなりません。トーレスや金崎という素晴らしいお手本のような選手も来てくれましたし、これからトレーニングの中でボールの持ち方と扱い方を向上させ、チーム全体として今後のサガン鳥栖のサッカー品質を向上してほしいですね。
■原川の体の向け方によるチャンスロスト


■ミンヒョクの体の向け方によるボールロスト


2.セントラルハーフの連係ミスと守るべきエリアの再確認
今回の鳥栖の守備は、ミドルサードで構えるという約束事があり、また、4-4-2(しかも2トップは中央のみ)と自分の守るべきスペースが比較的分かり易い状態であったため、大きなほころびを生むことはありませんでした。しかしながら、前述の通り、タイミングを見計らってボールを前から奪う形をとりに行くこともあるのですが、そこで自分のエリアを抜け出してでもプレスに行った時の連動について、まだまだ組織として未完成である状況が発生していました。いわゆる、応用編になったときにどのような対応が取れるかという所です。具体的なシーンを紹介します。





実際は60分過ぎという体力的にも非常に厳しい状況なので、体力的には動くのが厳しい状況です。当然フィジカル的な問題もあるのですが、やはり、失点というのはこういうミスから発生してしまいます。ミスと言うのは、パスミス、トラップミス、クリアミス、キャッチミスなどの目に見えて分かり易いミスもあるのですが、そういうミスはこのレベルの選手たちでは早々発生しません。むしろ、ポジショニングミスという、一見してわかりづらいミスの方が得てして簡単にピンチを迎えてしまうのです。
味方の動きに合わせた連動と、優先的に守らなければならないスペースの認知という、めまぐるしく味方とボールの位置が変わるサッカーでは一番難しいプレーですが、強いチームというのは綻びのない守備組織を構築しています。サガン鳥栖も、まだまだ成長の伸び代があるので、堅固な守備組織を目指して、成長して欲しいですね。
ひとまず、長いトンネルを抜け出して勝ち点3を上げる事ができました。攻撃パターンも少しずつ確立してきたので、あとはトーレスや金崎の得点ですね。ホーム浦和戦でトーレスのゴールを見る事ができたら、盛り上がるでしょうね。ぜひ、満員のスタジアムでそのような興奮するシーンを見たいと思います。
<画像引用元:DAZN>
<画像引用元:Football LAB>
Posted by オオタニ at
19:35
│Match Impression (2018)
2018年08月03日
2018 第19節 : 清水エスパルス VS サガン鳥栖
2018年第19節、清水戦のレビューです。今回は、時間がないので前半のシーンのみです。
鳥栖のセットアップは4-3-3。前線はトーレスを中央に配置して、小野と金崎が両翼を担っていました。セントラルハーフは、福田、義希、原川の3人。出場停止のミンヒョクの替わりは高橋秀がセンターバックを務めました。清水のセットアップはオーソドックスな4-4-2スタイル。鳥栖のホームで試合した時に比べると、プレスに行くところ、リトリートするところ、組織としての意思が統一されており、チームとして洗練されてきた印象です。
今回4-3-3で臨んだのは、中3日の鳥栖に対して、台風の影響で順延して休養たっぷりの清水(中9日)という戦いになったので、マッシモが早めに得点を取って後は守備を固めようという作戦だったことが伺えます。多少のリスクを負ってでも先に得点を取ろうというちょっとした賭けに出てきた感じでした。
鳥栖の攻撃は、インサイドハーフ(原川、福田)をセンターバックの脇に落として、最終ラインでのボール保持に対する数的優位を確保しつつ、その間にサイドバックを押し上げて相手のサイドハーフが詰めてきたら空いたスペースをフォワード(小野、金崎)に狙わせて前への展開の道筋を作るというものでした。フォワードに繋いでから更にその先の選択肢が、中央の義希ではなくサイドバックである小林や吉田を使うケースが多く、そのことによって、特に吉田は相手のサイドバックと1VS1というシーンを多く作り上げる事が出来ていました。後は質の勝負と言わんばかりに縦に突破を試みたり、ペナルティエリア角付近からのパスやクロスを狙ったりとしていましたが、残念ながらその精度がもう一歩足りていなかったですね。ただ、この短い期間で金崎を利用したビルドアップを構築してきたのは素晴らしいのではないでしょうか。
■ 鳥栖のビルドアップ1



■ 鳥栖のビルドアップ2


ただ、攻撃の組み立て方としては確立されていますが、最後は精度の問題でなかなかゴールに結びつけることができません。磐田戦も福田がサイドでフリーになる形作りをしましたが、そこからのクロスがなかなか入りませんでした。確かにサイド攻撃における形作りはできているので、それがマッシモの言う「戦い方としてはしっかりとできている。」のようなコメントに現れているのかもしれません。しかしながら、現実としてはその作り上げられた組み立てや、数多く取ることの出来ているセットプレイ中でのゴールが決まっていないという状況であり、結果が伴っていません。トーレスや金崎という成果を出すことのできる強力なフォワードが入ってきたので、攻撃の狙い・ポイントに関しては、少し変えていく必要があるのではないかなと思います。
例えば、下の図のシーンでも、義希がボールを受けてトーレスが引いてボールを受けに来ますが、義希はトーレスにボールを渡さずに縦にドリブルで入ってつぶされてしまいます。また、トーレスがゴール前で受ける準備をしていて、パスコースが空いているにも関わらず、原川の選択はサイドにいる小野へのパスでした。トーレスの技術は抜きんでていますから、彼を信頼してもっともっと使い倒す方が、チャンスの数は増えるはずです。清水戦は、特にこのようなシーンが多く、チーム全体がトーレスを使うような意識を持っても(監督がそのような意識を持たせても)良いのではないかと感じました。



さて、守備面ですが、その得点を取るために組織された4-3-3が逆に相手に対するスペースを与えることになってしまっていました。諸刃の剣という事です。気になったのは、金崎に対する守備タスクが与えられていなかった(カウンターに備えて前線に張るために意図していたかもしれませんが)点と、中盤のプレスの強度が弱く、清水の左サイドから右サイドへの展開を自由に許していた点です。PKで失点する前も、危ないシーンがいくつかありまして、前半から互いにアグレッシブな展開で、鳥栖が得点するか、それとも清水が得点するか、という状況で戦いが進められていました。
■ 清水の展開1



■ 清水の展開2

■ 清水のカウンター


そのような戦いの中で、残念ながら先制点を奪われてしまったのですが、この失点シーン、同じような場面を見た記憶はありませんか?本年度の札幌戦で、吉田が高い位置を取っているにも関わらず、スンヒョンがフリーキックをミスし、ジュリーニョに一発で通されて、スンヒョンと1VS1になり、スライディングするものの交わされて失点してしまったという、あの苦々しい失点と同じような形なのです。
そして、さらに、実は、鳥栖の失点は、インサイドハーフを落として組み立てるやり方が原因となっていたのはお気づきでしょうか。失点シーンを詳しく見てみましょう。今回のコンセプトである、「インサイドハーフを落としてボールキープしてフォワードへのパスコースを作る」による形を作って攻撃をしかけています。このシーンでは高橋祐が直接金崎へ縦パスをいれていますが、それがミスとなってしまい、清水にボールを奪われてしまいました。この段階で、鳥栖にとってはネガティブトランジション(攻撃から守備への転換)が発生しています。
では、清水にボールが渡った時点での陣形はというと、組み立ての為に吉田を高く押し上げており、原川は最終ラインに引いている状態です。この時点で、吉田と原川はポジションチェンジをしており、守備的側面では、原川は「サイドバック」、吉田は「インサイドハーフ」としての役割を果たさなければなりません。ところが、清水のボランチがボールを持った段階で、原川と吉田の二人が同時にポジションを前に移動して(プレスをかけようとして)、二人がインサイドハーフの役割を果たそうとしてしまって「サイドバック不在」の状況を作り出しています。これにより、本来サイドバックが構えているはずの裏のスペースにパスを通されて、ドウグラスと高橋祐の二人の質的勝負という状況を生んでしまいました。ネガティブトランジション時に、吉田と原川にどのような約束事が取り付けられているのかうかがい知ることはできませんが、少なくともポジションの配置から考えると、原川は前への圧力をかけるのではなく、高橋と共に最終ラインを整えるという動きが必要でありました。




当ブログでは、昨年から度々、失点シーンにおける原川の守備の脆さを指摘しています。それは、攻撃に備えたポジショニングという意図的に取ったリスクから発生した脆弱性ではなく、ゾーン守備の原則に基づいて、守らなければならないエリアを守れないという脆弱性に対する指摘です。では、このインサイドハーフを落としてサイドバックを上げるという組み立てを行い、それに伴って発生するリスクに対する備え(守備意識)を備えつけなければならないのは誰かというと、それは当然監督やコーチの仕事であります。私がマッシモに対して憂慮するのは、攻撃面のデザイン力に乏しい事よりも、数年間かけてきたにも関わらず、選手たちに守備面における意識付けと連係が思うように構築(向上)出来ていない事です。
試合の中でミスと言うのはどうしても発生するものです。そのミスが発生した際にいかに失点リスクを下げる事ができるのか、また、失点リスクが発生しないためにはどのような形で攻撃したら良いのかというのは準備しておく必要があります。一発のスーパーなプレイでやられたのであればそれは諦めるしかしょうがないのですが、同じ形での失点を繰り返しているというのは、その戦い方に何らかの欠陥があるということを示しています。欠陥があるということは、改善をしなければなりませんが、その改善がなされない限りは、いつかまた同じ形での失点シーンを見てしまう事になるのでしょう。
また、小野が、画面の中でPKを与えてしまった高橋祐を叱りつけているような場面が映りました。確かに、高橋祐のパスミスが発端となっていますし、裏に抜けられた時であっても、彼がドウグラスに個の力で勝てれば何の問題もなかった場面です。しかしながら、組織として戦わなければならないチームが、個人のミスや個人の力量不足を叱責して強いチームになれるのでしょうか。この場面で、ピッチ全体で何が発生してしまったのか小野が瞬時に把握して、組織として、戦術としての問題点を察知して、原川や吉田に守備に対する修正を促せるようにならないと、本当に勝てるチームになれないのではないでしょうか?
このような状態になったら、小野のパスミス、クロスミス、シュートミスに対して、高橋祐が
「お前だってミスしとるやないか」
と思いたくなりませんか?
こんな気持ちで戦ってもモチベーションが上がらず、最高の状態でプレーできないですよね。
小野は磐田戦で決定的なチャンスを外しました。小野のシュート力が、カミンスキーのセーブ力という個の力で、質的に劣っていたからです。彼の力量不足により得点が出来なかったのです。ただ、それに対して、誰も叱責しなかったはずです。チームの中で互いのプレイに関して確認し、修正を促すことは良いことだと思うのですが、目の前にだけ見える現象だけで判断して、組織としての責任を問うことなく、個人の責任を追及するのはチームビルディングではありません。札幌戦でスンヒョンがミスした時も、小野が厳しい口調でスンヒョンを責めたてていました。彼がチームを去ったのは、そのような背景があったのではないかと考えたりするのは邪推でしょうか?
最後になりますが、この試合、鳥栖の選手たちのパスミスが多くて、ほんのちょっとの事なのですが、それによって相手に押し込まれたり、ボールロストにつながるようなシーンが多かったです。それが体力的なものなのか、組織(戦術)的なものなのか、個人の技量によるものなのか、メンタルによるものなのか、しっかりと分析する必要があります。ハードなスケジュールで次の試合はすぐ目の前に迫ってきています。監督、コーチ、選手自身、それぞれが勝つために何をしなければならないか、しっかりと考えて次の試合に臨んで欲しいと思います。
<画像引用元:DAZN>
鳥栖のセットアップは4-3-3。前線はトーレスを中央に配置して、小野と金崎が両翼を担っていました。セントラルハーフは、福田、義希、原川の3人。出場停止のミンヒョクの替わりは高橋秀がセンターバックを務めました。清水のセットアップはオーソドックスな4-4-2スタイル。鳥栖のホームで試合した時に比べると、プレスに行くところ、リトリートするところ、組織としての意思が統一されており、チームとして洗練されてきた印象です。
今回4-3-3で臨んだのは、中3日の鳥栖に対して、台風の影響で順延して休養たっぷりの清水(中9日)という戦いになったので、マッシモが早めに得点を取って後は守備を固めようという作戦だったことが伺えます。多少のリスクを負ってでも先に得点を取ろうというちょっとした賭けに出てきた感じでした。
鳥栖の攻撃は、インサイドハーフ(原川、福田)をセンターバックの脇に落として、最終ラインでのボール保持に対する数的優位を確保しつつ、その間にサイドバックを押し上げて相手のサイドハーフが詰めてきたら空いたスペースをフォワード(小野、金崎)に狙わせて前への展開の道筋を作るというものでした。フォワードに繋いでから更にその先の選択肢が、中央の義希ではなくサイドバックである小林や吉田を使うケースが多く、そのことによって、特に吉田は相手のサイドバックと1VS1というシーンを多く作り上げる事が出来ていました。後は質の勝負と言わんばかりに縦に突破を試みたり、ペナルティエリア角付近からのパスやクロスを狙ったりとしていましたが、残念ながらその精度がもう一歩足りていなかったですね。ただ、この短い期間で金崎を利用したビルドアップを構築してきたのは素晴らしいのではないでしょうか。
■ 鳥栖のビルドアップ1



■ 鳥栖のビルドアップ2


ただ、攻撃の組み立て方としては確立されていますが、最後は精度の問題でなかなかゴールに結びつけることができません。磐田戦も福田がサイドでフリーになる形作りをしましたが、そこからのクロスがなかなか入りませんでした。確かにサイド攻撃における形作りはできているので、それがマッシモの言う「戦い方としてはしっかりとできている。」のようなコメントに現れているのかもしれません。しかしながら、現実としてはその作り上げられた組み立てや、数多く取ることの出来ているセットプレイ中でのゴールが決まっていないという状況であり、結果が伴っていません。トーレスや金崎という成果を出すことのできる強力なフォワードが入ってきたので、攻撃の狙い・ポイントに関しては、少し変えていく必要があるのではないかなと思います。
例えば、下の図のシーンでも、義希がボールを受けてトーレスが引いてボールを受けに来ますが、義希はトーレスにボールを渡さずに縦にドリブルで入ってつぶされてしまいます。また、トーレスがゴール前で受ける準備をしていて、パスコースが空いているにも関わらず、原川の選択はサイドにいる小野へのパスでした。トーレスの技術は抜きんでていますから、彼を信頼してもっともっと使い倒す方が、チャンスの数は増えるはずです。清水戦は、特にこのようなシーンが多く、チーム全体がトーレスを使うような意識を持っても(監督がそのような意識を持たせても)良いのではないかと感じました。



さて、守備面ですが、その得点を取るために組織された4-3-3が逆に相手に対するスペースを与えることになってしまっていました。諸刃の剣という事です。気になったのは、金崎に対する守備タスクが与えられていなかった(カウンターに備えて前線に張るために意図していたかもしれませんが)点と、中盤のプレスの強度が弱く、清水の左サイドから右サイドへの展開を自由に許していた点です。PKで失点する前も、危ないシーンがいくつかありまして、前半から互いにアグレッシブな展開で、鳥栖が得点するか、それとも清水が得点するか、という状況で戦いが進められていました。
■ 清水の展開1



■ 清水の展開2

■ 清水のカウンター


そのような戦いの中で、残念ながら先制点を奪われてしまったのですが、この失点シーン、同じような場面を見た記憶はありませんか?本年度の札幌戦で、吉田が高い位置を取っているにも関わらず、スンヒョンがフリーキックをミスし、ジュリーニョに一発で通されて、スンヒョンと1VS1になり、スライディングするものの交わされて失点してしまったという、あの苦々しい失点と同じような形なのです。
そして、さらに、実は、鳥栖の失点は、インサイドハーフを落として組み立てるやり方が原因となっていたのはお気づきでしょうか。失点シーンを詳しく見てみましょう。今回のコンセプトである、「インサイドハーフを落としてボールキープしてフォワードへのパスコースを作る」による形を作って攻撃をしかけています。このシーンでは高橋祐が直接金崎へ縦パスをいれていますが、それがミスとなってしまい、清水にボールを奪われてしまいました。この段階で、鳥栖にとってはネガティブトランジション(攻撃から守備への転換)が発生しています。
では、清水にボールが渡った時点での陣形はというと、組み立ての為に吉田を高く押し上げており、原川は最終ラインに引いている状態です。この時点で、吉田と原川はポジションチェンジをしており、守備的側面では、原川は「サイドバック」、吉田は「インサイドハーフ」としての役割を果たさなければなりません。ところが、清水のボランチがボールを持った段階で、原川と吉田の二人が同時にポジションを前に移動して(プレスをかけようとして)、二人がインサイドハーフの役割を果たそうとしてしまって「サイドバック不在」の状況を作り出しています。これにより、本来サイドバックが構えているはずの裏のスペースにパスを通されて、ドウグラスと高橋祐の二人の質的勝負という状況を生んでしまいました。ネガティブトランジション時に、吉田と原川にどのような約束事が取り付けられているのかうかがい知ることはできませんが、少なくともポジションの配置から考えると、原川は前への圧力をかけるのではなく、高橋と共に最終ラインを整えるという動きが必要でありました。




当ブログでは、昨年から度々、失点シーンにおける原川の守備の脆さを指摘しています。それは、攻撃に備えたポジショニングという意図的に取ったリスクから発生した脆弱性ではなく、ゾーン守備の原則に基づいて、守らなければならないエリアを守れないという脆弱性に対する指摘です。では、このインサイドハーフを落としてサイドバックを上げるという組み立てを行い、それに伴って発生するリスクに対する備え(守備意識)を備えつけなければならないのは誰かというと、それは当然監督やコーチの仕事であります。私がマッシモに対して憂慮するのは、攻撃面のデザイン力に乏しい事よりも、数年間かけてきたにも関わらず、選手たちに守備面における意識付けと連係が思うように構築(向上)出来ていない事です。
試合の中でミスと言うのはどうしても発生するものです。そのミスが発生した際にいかに失点リスクを下げる事ができるのか、また、失点リスクが発生しないためにはどのような形で攻撃したら良いのかというのは準備しておく必要があります。一発のスーパーなプレイでやられたのであればそれは諦めるしかしょうがないのですが、同じ形での失点を繰り返しているというのは、その戦い方に何らかの欠陥があるということを示しています。欠陥があるということは、改善をしなければなりませんが、その改善がなされない限りは、いつかまた同じ形での失点シーンを見てしまう事になるのでしょう。
また、小野が、画面の中でPKを与えてしまった高橋祐を叱りつけているような場面が映りました。確かに、高橋祐のパスミスが発端となっていますし、裏に抜けられた時であっても、彼がドウグラスに個の力で勝てれば何の問題もなかった場面です。しかしながら、組織として戦わなければならないチームが、個人のミスや個人の力量不足を叱責して強いチームになれるのでしょうか。この場面で、ピッチ全体で何が発生してしまったのか小野が瞬時に把握して、組織として、戦術としての問題点を察知して、原川や吉田に守備に対する修正を促せるようにならないと、本当に勝てるチームになれないのではないでしょうか?
このような状態になったら、小野のパスミス、クロスミス、シュートミスに対して、高橋祐が
「お前だってミスしとるやないか」
と思いたくなりませんか?
こんな気持ちで戦ってもモチベーションが上がらず、最高の状態でプレーできないですよね。
小野は磐田戦で決定的なチャンスを外しました。小野のシュート力が、カミンスキーのセーブ力という個の力で、質的に劣っていたからです。彼の力量不足により得点が出来なかったのです。ただ、それに対して、誰も叱責しなかったはずです。チームの中で互いのプレイに関して確認し、修正を促すことは良いことだと思うのですが、目の前にだけ見える現象だけで判断して、組織としての責任を問うことなく、個人の責任を追及するのはチームビルディングではありません。札幌戦でスンヒョンがミスした時も、小野が厳しい口調でスンヒョンを責めたてていました。彼がチームを去ったのは、そのような背景があったのではないかと考えたりするのは邪推でしょうか?
最後になりますが、この試合、鳥栖の選手たちのパスミスが多くて、ほんのちょっとの事なのですが、それによって相手に押し込まれたり、ボールロストにつながるようなシーンが多かったです。それが体力的なものなのか、組織(戦術)的なものなのか、個人の技量によるものなのか、メンタルによるものなのか、しっかりと分析する必要があります。ハードなスケジュールで次の試合はすぐ目の前に迫ってきています。監督、コーチ、選手自身、それぞれが勝つために何をしなければならないか、しっかりと考えて次の試合に臨んで欲しいと思います。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
13:09
│Match Impression (2018)
2018年08月01日
2018 第18節 : サガン鳥栖 VS ジュビロ磐田
2018年第18節、磐田戦のレビューです。
鳥栖のセットアップは4-4-2。ツートップは早速新加入組のトーレス、金崎の二人を起用してきました。中盤はフラットな構成で、ウイングバックを利用して幅広く攻めてくる磐田に対応するため4人を中盤で並べてセントラルハーフの役割とプレイエリアをはっきりとさせました。最終ラインは小林が右サイドのスタメンに復帰です。磐田のセットアップは3-4-2-1。セカンドトップの松浦と山田が攻守の起点となり、ドイスボランチの上原、田口が運動量豊富に全体をコントロールしていました。
■ 磐田の守備システム

この試合の互いの攻撃面での印象ですが、ロジカルに鳥栖の守備の隙をついて再現性のある動きで攻撃してくる磐田と、パターンにはまらずにその場のインテュイティブで攻撃を組み立てる鳥栖という、対照的な面白さを感じていました。ポジショナルプレーの観点で言うと、磐田は「位置的優位」を最大限活用し、鳥栖は「数的優位」「質的優位」を最大限活用していたという所でしょうか。磐田の連動性を利用した攻撃も見事でしたし、鳥栖も金崎、トーレスを生かして個の力で襲い掛かるという補強が理にかなっていた攻撃で、シュート数が少ないながらも面白味のあった試合でした。現役時代に天才レフティと言われた才能の固まりである名波さんのチームの方が統率された動きで地道にボディブローのような攻撃をしかけ、戦術と選手配置で知的な采配を揮うマッシモの方がトーレスや金崎の個人技、小野や福田の運動量など、個人のインスピレーションを生かした攻撃をしかけるというのは、人間は表面だけでは分からないという深い部分を教えてくれた気がします(笑)
また、前半から両チームともに守備の意識が高く、相手にスペースを与えまいと運動量豊富に攻守の切り替えを行っていました。スペースのない中でアグレッシブに動きつつ、それでいて互いに相手のミス待ちという様相を呈しており、引き締まった戦いで一瞬の気も抜けませんでしたが、最後まで得点(失点)につながるような大きなミスは発生せず。当然、細かいミスや狭いスペースの間隙を抜くようなスーパーなプレイ、一瞬の隙を突いたカウンターは随所に現れていましたが、フィニッシュの場面(クロスの場面)でわずかに精度が足らなかったり、最後は守備側があきらめないメンタルで最後の一歩で踏ん張ったりと、お互いに最後の牙城を崩す(ゴール)までには至りませんでした。
■ 鳥栖のハードワーク



まずは磐田のビルドアップですが、磐田の3バックに対して鳥栖は2トップであるので、最終ラインでのボール回しは磐田の方が数的優位を生みます。磐田の目論見としては、サイドチェンジを繰り返すことによって、センターバックを余らせる状態を作り、鳥栖のプレスをかわしてセンターバックがボールを持ちだすタイミングを作ることにありました。そうすることによって、鳥栖はサイドハーフがセンターバックに対してケアをしなければならなくなり、サイドハーフが前に出る事で最終ラインと2列目との間にスペースを生み出すことができます。よって、磐田における「効果的な攻撃」は、センターバックと鳥栖のサイドハーフがマッチアップする状況を作ることであり、実際にその場面を作り上げる事が出来ると川又、松浦、山田が入り込んでワンタッチでボールを運ぼうとする攻撃のスイッチが入っていました。そのあたりの意識は共有されていたと思われます。以下に、磐田の崩しのパターンを図解します。
■ 磐田の崩し




鳥栖にとっては、当然のことながらそのような場面を作らないことが大事でありますが、展開の中ではどうしても発生してしまいます。これに対して鳥栖がどのように対応したかというと、非常に原始的でありますが、サイドハーフである小野と福田の頑張り(二度追い、三度追い)とドイスボランチのスライドによって対応しておりました。
無論、フォワードのプレスが間に合えばサイドハーフが釣り出されてスペースを空けることもなく、トーレスと金崎の2人が上手に磐田をサイドに追い込んだ時は、相手のミスを発生させるプレスが出来ていました。磐田も狭いエリアでの細かいパス交換が洗練されているわけでもないので、簡単にパスミスしてボールロストするシーンは少なくはなかったです。解決策が「頑張る」というのも、見方によっては、当たり前の話ではありますが、この当たり前のハードワークが90分間しっかりできるというのも、鳥栖の大きな強みですよね。
■ 鳥栖の対応




この試合におけるサイドハーフ(小野、福田)へ与えられたタスクが非常に多く、上記のようにセンターバックへのファーストディフェンスという役割もあれば、リトリートした場合にはウイングバックに対するマークもこなさなければならず、また、攻撃ではサイドの基点を作るために幅を取る役割もあれば、構造的に相手のウイングバックと1VS1で対峙する機会も多くてアタッカーのような役割も求められ、特には逆サイドから入ってくるボールにゴール前に飛び込んでフィニッシャーの役割も与えられていました。その中でも更に、小野はセンターバックのビルドアップが詰まったときの逃げ道としてロングボールの狙いどころにもなっていましたし、福田は相手のロングボールに対するセカンドボールの回収も求められていましたし、これらのタスクをすべてこなすためには、彼ら2人の運動量がなければ成り立たなかったでしょう。
そのようなかなり運動量を酷使した中ですから、もともとアタッカーではない福田がサイドの局面で1VS1で相手のウイングと対峙した際に、かわしきってクロスを上げたり、カットインしてシュートしたりというプレイはちょっと難しかったかと思います。攻撃にでるか、守備にでるかと言う所で難しい選択ではありましたが、終盤で全体が中央で待ち構えてクロスを待っている状態、そして左サイドから右サイドに展開した後に幅を取っている福田がアタックをしかけるということであれば、ラスト5分でも良いので、選手交代の選択肢としては「田川」というのも面白かったのではないかと思いましたが、マッシモの中では、福田の「守備」の部分に重きをおいたのではないかと考えます。
話しを戻しますが、鳥栖としては、割り切って多少センターバックが持ち上がって来たとしてもそれを見過ごして持たせるという選択肢があったかもしれません。自陣への侵入を許すというリスクはありますが、そうすることによって、カウンターで利用できるスペースを確保できるというメリットはあります。そのあたりは福田が行こうか戻ろうか迷うシーンもありましたが、チームオーダーがどのように出ていたかというところは気になるところです。
■ 鳥栖のビルドアップ
さて、鳥栖のビルドアップに対する磐田の守備ですが、鳥栖もセンターバック2名に対して川又1名と、通常の状態では鳥栖の方が数的優位を生んでいるので、ここで川又は選択を迫られることになるのですが、川又の選択としては「ステイ」でした。例えば鳥栖で言えば池田や豊田のように、相手のセンターバックに対して数的不利であっても執拗に追いかけるプレスもひとつの選択肢ですが、今節の川又の役割としては、鳥栖のボランチへのボール配球の抑止が一番のタスクで、次のタスクがサイドに追いやる動きでした。面白かったのは、前から奪えると判断した時には、川又がセンターバックを捕まえにいくのではなく、セカンドトップの2人が両センターバックにプレスをしかけにいくシーンがありました。川又のタスクは中央を抑えることというのがよく伺えたシーンでした。
そうして、川又が鳥栖のボールをサイドに追いやってからが磐田のプレスの開始の合図でした。磐田のセカンドトップが鳥栖のサイドバックにプレスをかけ、そこからセンターバックに戻すボールを狙って川又が追い込んだ方にプレスをかけます。鳥栖のドイスボランチは磐田のドイスボランチに捕まえさせて、鳥栖のサイドハーフは磐田のウイングバックが見るという構図です。
■ 磐田の守備



基本的に磐田の想定するプレスのパターンとなってしまったら、普通にパスを出しても鳥栖はいわゆる詰みの状態です。追い詰められて長いボールを蹴らされてしまいます。トーレス(豊田)、小野などのハイボールに強い選手がいるので、長いボールからでもチャンスに繋がるシーンもあったのですが、マッシモとしては最初からロングボールを蹴って前進していくという戦いは取りませんでした。あくまでもサイドを利用したビルドアップで崩そうという狙いです。
では、この磐田のプレスをどうやって回避を試みたかというと、鳥栖にとってはどこかでスペースを作り出さなければならないので、上記のような磐田のプレスにはまらない形を作る必要があります。鳥栖がとった工夫としては、
① ウイングバックをサイドから引き出してからの小野、金崎のサイドのスペースへの飛び出し
② トーレスや義希のハーフスペースで受ける事によるボールの引き出し
の2点が多かったでしょうか。そして、更にそこからの繋ぎとしての
③ 小林のインナーラップ(ボールを持っている選手の内側を抜けて前に出ていく動き)
も非常に良く目立ちました。
それらのシーンを図で説明します。
図の中の「インナーラップ」とは、ボール保持者に対して後ろから上がってくる選手が内側を駆け抜けていく事で、「ハーフスペース」とは、ピッチの横幅の中でセンターバックとサイドバック(ウイングバック)のどっちにマークにつくべきか迷ってしまうような、分水嶺的なエリアと思ってください。
■ 鳥栖の崩し








攻撃面で、試合中に気になったのは、トーレスは小林や吉田に対して何度も裏へのボールを要求していました。そのボールこそ、トーレスの長所を生かせるボールだとも思いますし、ミンヒョクから裏へ出した一発のボールでシュートチャンスを生み出しました。一発で裏を狙うのも難しいですが、サイドを崩すよりもゴールに直接向かうボールの方が相手に脅威を生むという事も確かです。チームとしてトーレスの要求にどのように応えるのか、その答えは今週のトレーニングや試合の振り返りを終えて、清水戦で見せてくれるでしょう。
攻撃としては、トーレス、金崎の個人の力もあり、あと一歩というところまでは進めていました。しかしながら、ゴール前というセンシティブなエリアでは、磐田の守備強度も増しますので、ゴール前に近づけば近づくほど、より味方同士で感じ合ったり、約束事によって考える前に体が動くという事が必要です。そういう意味で行くと、今回のラストパスの精度と意思疎通が足りなかったのかなというのは感じました。小野や金崎、義希や福田もクロスを上げていますが、もう一歩の所で味方に合わない状態が続きました。実は、トーレスも、金崎も、ゴール前のポジションとしては、相手の最終ラインよりもマイナスの所でポジショニングをとっているのですが、それにも関わらず、クロスを上げる選手はキーパーと最終ラインの間をめがけて蹴っているケースが多くありました。ここは、約束事が段々と出来てくるでしょうから、試合を重ねるごとに改善していくポイントだと思います。問題は、それが今シーズンの終わりまでに間に合うか。昨年の新潟のように、終盤に驚異的なペースで連勝したけど、僅かに及ばなかったということにならないことを願うのみです。
■ 鳥栖のクロス



■ ハロー効果について
さて、みなさんは、ハロー効果という言葉はご存知でしょうか。目立ちやすい特徴に引きずられて他の特徴についての評価が歪められる現象のことです。今回、選手たちの評価に関して、ハロー効果が生まれやすいシーンが多かったと思います。
例えば、トーレスや金崎に関しては、過去の輝かしい実績がありますので、ポジティブハロー効果が生まれやすい状況にあります。実際、この試合でもボールキープとスルーパスや飛び出しからのシュートなどチャンスメイクに大きく貢献しましたが、その反面、相手を執拗に追うような守備強度で磐田のチャンスの芽をすべてつぶせるようなプレスを行ったわけではありませんし、ドリブルミスやパスミスなどのボールロストがなかったわけでもありません。そういった所に目をつぶって手放しで良い評価を与えてよいのかという公平な視点は持たなければなりません。
逆に、福田はネガティブハロー効果が生まれやすい状況にありまして、ゴール前でのチャンスの逸機やサイドでの1VS1でのクロスのミスなどが目立ってしまいましたが、彼の90分間走り抜ける事のできる運動量を基にした、スペースのカバーリング、セカンドボールの奪取、チャンスに対する顔の出し方は大きくチームに貢献しております。終盤のクロスミスというプレイだけを見てしまって、その試合全体で貢献度が低かったかのような評価をしてしまうと、それもまた適正な評価をしていないことになってしまいます。
サッカーは組織として取り組むものであります。そして、選手個々の評価は過去の実績や大きく目立つ場面だけで決まるわけではありません。もちろん、ゲームを決める事の出来るプレイは大きく評価されるべきではありますが、90分間の中においては様々なプレイがありますので、そのあたりを総合して評価しなければならないと思っています。そして、もし、ある選手がミスをしたとしても、個人だけが責任を負うのではなく、チームとして、組織として考えるべきであるということを認識して頂ければと思います。
なかなか勝ちきれない鳥栖ですが、トーレスが鳥栖に入って3試合目、金崎が鳥栖に入って2試合目、そろそろゴール決まってもいいんじゃない?と思っていますが果たしてどうでしょうか。清水には前節勝っているだけに、是非とも今節も勝って、シーズンダブルという形で8月反攻のスタートと行きたいですね。
<画像引用元:DAZN>
鳥栖のセットアップは4-4-2。ツートップは早速新加入組のトーレス、金崎の二人を起用してきました。中盤はフラットな構成で、ウイングバックを利用して幅広く攻めてくる磐田に対応するため4人を中盤で並べてセントラルハーフの役割とプレイエリアをはっきりとさせました。最終ラインは小林が右サイドのスタメンに復帰です。磐田のセットアップは3-4-2-1。セカンドトップの松浦と山田が攻守の起点となり、ドイスボランチの上原、田口が運動量豊富に全体をコントロールしていました。
■ 磐田の守備システム

この試合の互いの攻撃面での印象ですが、ロジカルに鳥栖の守備の隙をついて再現性のある動きで攻撃してくる磐田と、パターンにはまらずにその場のインテュイティブで攻撃を組み立てる鳥栖という、対照的な面白さを感じていました。ポジショナルプレーの観点で言うと、磐田は「位置的優位」を最大限活用し、鳥栖は「数的優位」「質的優位」を最大限活用していたという所でしょうか。磐田の連動性を利用した攻撃も見事でしたし、鳥栖も金崎、トーレスを生かして個の力で襲い掛かるという補強が理にかなっていた攻撃で、シュート数が少ないながらも面白味のあった試合でした。現役時代に天才レフティと言われた才能の固まりである名波さんのチームの方が統率された動きで地道にボディブローのような攻撃をしかけ、戦術と選手配置で知的な采配を揮うマッシモの方がトーレスや金崎の個人技、小野や福田の運動量など、個人のインスピレーションを生かした攻撃をしかけるというのは、人間は表面だけでは分からないという深い部分を教えてくれた気がします(笑)
また、前半から両チームともに守備の意識が高く、相手にスペースを与えまいと運動量豊富に攻守の切り替えを行っていました。スペースのない中でアグレッシブに動きつつ、それでいて互いに相手のミス待ちという様相を呈しており、引き締まった戦いで一瞬の気も抜けませんでしたが、最後まで得点(失点)につながるような大きなミスは発生せず。当然、細かいミスや狭いスペースの間隙を抜くようなスーパーなプレイ、一瞬の隙を突いたカウンターは随所に現れていましたが、フィニッシュの場面(クロスの場面)でわずかに精度が足らなかったり、最後は守備側があきらめないメンタルで最後の一歩で踏ん張ったりと、お互いに最後の牙城を崩す(ゴール)までには至りませんでした。
■ 鳥栖のハードワーク



まずは磐田のビルドアップですが、磐田の3バックに対して鳥栖は2トップであるので、最終ラインでのボール回しは磐田の方が数的優位を生みます。磐田の目論見としては、サイドチェンジを繰り返すことによって、センターバックを余らせる状態を作り、鳥栖のプレスをかわしてセンターバックがボールを持ちだすタイミングを作ることにありました。そうすることによって、鳥栖はサイドハーフがセンターバックに対してケアをしなければならなくなり、サイドハーフが前に出る事で最終ラインと2列目との間にスペースを生み出すことができます。よって、磐田における「効果的な攻撃」は、センターバックと鳥栖のサイドハーフがマッチアップする状況を作ることであり、実際にその場面を作り上げる事が出来ると川又、松浦、山田が入り込んでワンタッチでボールを運ぼうとする攻撃のスイッチが入っていました。そのあたりの意識は共有されていたと思われます。以下に、磐田の崩しのパターンを図解します。
■ 磐田の崩し




鳥栖にとっては、当然のことながらそのような場面を作らないことが大事でありますが、展開の中ではどうしても発生してしまいます。これに対して鳥栖がどのように対応したかというと、非常に原始的でありますが、サイドハーフである小野と福田の頑張り(二度追い、三度追い)とドイスボランチのスライドによって対応しておりました。
無論、フォワードのプレスが間に合えばサイドハーフが釣り出されてスペースを空けることもなく、トーレスと金崎の2人が上手に磐田をサイドに追い込んだ時は、相手のミスを発生させるプレスが出来ていました。磐田も狭いエリアでの細かいパス交換が洗練されているわけでもないので、簡単にパスミスしてボールロストするシーンは少なくはなかったです。解決策が「頑張る」というのも、見方によっては、当たり前の話ではありますが、この当たり前のハードワークが90分間しっかりできるというのも、鳥栖の大きな強みですよね。
■ 鳥栖の対応




この試合におけるサイドハーフ(小野、福田)へ与えられたタスクが非常に多く、上記のようにセンターバックへのファーストディフェンスという役割もあれば、リトリートした場合にはウイングバックに対するマークもこなさなければならず、また、攻撃ではサイドの基点を作るために幅を取る役割もあれば、構造的に相手のウイングバックと1VS1で対峙する機会も多くてアタッカーのような役割も求められ、特には逆サイドから入ってくるボールにゴール前に飛び込んでフィニッシャーの役割も与えられていました。その中でも更に、小野はセンターバックのビルドアップが詰まったときの逃げ道としてロングボールの狙いどころにもなっていましたし、福田は相手のロングボールに対するセカンドボールの回収も求められていましたし、これらのタスクをすべてこなすためには、彼ら2人の運動量がなければ成り立たなかったでしょう。
そのようなかなり運動量を酷使した中ですから、もともとアタッカーではない福田がサイドの局面で1VS1で相手のウイングと対峙した際に、かわしきってクロスを上げたり、カットインしてシュートしたりというプレイはちょっと難しかったかと思います。攻撃にでるか、守備にでるかと言う所で難しい選択ではありましたが、終盤で全体が中央で待ち構えてクロスを待っている状態、そして左サイドから右サイドに展開した後に幅を取っている福田がアタックをしかけるということであれば、ラスト5分でも良いので、選手交代の選択肢としては「田川」というのも面白かったのではないかと思いましたが、マッシモの中では、福田の「守備」の部分に重きをおいたのではないかと考えます。
話しを戻しますが、鳥栖としては、割り切って多少センターバックが持ち上がって来たとしてもそれを見過ごして持たせるという選択肢があったかもしれません。自陣への侵入を許すというリスクはありますが、そうすることによって、カウンターで利用できるスペースを確保できるというメリットはあります。そのあたりは福田が行こうか戻ろうか迷うシーンもありましたが、チームオーダーがどのように出ていたかというところは気になるところです。
■ 鳥栖のビルドアップ
さて、鳥栖のビルドアップに対する磐田の守備ですが、鳥栖もセンターバック2名に対して川又1名と、通常の状態では鳥栖の方が数的優位を生んでいるので、ここで川又は選択を迫られることになるのですが、川又の選択としては「ステイ」でした。例えば鳥栖で言えば池田や豊田のように、相手のセンターバックに対して数的不利であっても執拗に追いかけるプレスもひとつの選択肢ですが、今節の川又の役割としては、鳥栖のボランチへのボール配球の抑止が一番のタスクで、次のタスクがサイドに追いやる動きでした。面白かったのは、前から奪えると判断した時には、川又がセンターバックを捕まえにいくのではなく、セカンドトップの2人が両センターバックにプレスをしかけにいくシーンがありました。川又のタスクは中央を抑えることというのがよく伺えたシーンでした。
そうして、川又が鳥栖のボールをサイドに追いやってからが磐田のプレスの開始の合図でした。磐田のセカンドトップが鳥栖のサイドバックにプレスをかけ、そこからセンターバックに戻すボールを狙って川又が追い込んだ方にプレスをかけます。鳥栖のドイスボランチは磐田のドイスボランチに捕まえさせて、鳥栖のサイドハーフは磐田のウイングバックが見るという構図です。
■ 磐田の守備



基本的に磐田の想定するプレスのパターンとなってしまったら、普通にパスを出しても鳥栖はいわゆる詰みの状態です。追い詰められて長いボールを蹴らされてしまいます。トーレス(豊田)、小野などのハイボールに強い選手がいるので、長いボールからでもチャンスに繋がるシーンもあったのですが、マッシモとしては最初からロングボールを蹴って前進していくという戦いは取りませんでした。あくまでもサイドを利用したビルドアップで崩そうという狙いです。
では、この磐田のプレスをどうやって回避を試みたかというと、鳥栖にとってはどこかでスペースを作り出さなければならないので、上記のような磐田のプレスにはまらない形を作る必要があります。鳥栖がとった工夫としては、
① ウイングバックをサイドから引き出してからの小野、金崎のサイドのスペースへの飛び出し
② トーレスや義希のハーフスペースで受ける事によるボールの引き出し
の2点が多かったでしょうか。そして、更にそこからの繋ぎとしての
③ 小林のインナーラップ(ボールを持っている選手の内側を抜けて前に出ていく動き)
も非常に良く目立ちました。
それらのシーンを図で説明します。
図の中の「インナーラップ」とは、ボール保持者に対して後ろから上がってくる選手が内側を駆け抜けていく事で、「ハーフスペース」とは、ピッチの横幅の中でセンターバックとサイドバック(ウイングバック)のどっちにマークにつくべきか迷ってしまうような、分水嶺的なエリアと思ってください。
■ 鳥栖の崩し








攻撃面で、試合中に気になったのは、トーレスは小林や吉田に対して何度も裏へのボールを要求していました。そのボールこそ、トーレスの長所を生かせるボールだとも思いますし、ミンヒョクから裏へ出した一発のボールでシュートチャンスを生み出しました。一発で裏を狙うのも難しいですが、サイドを崩すよりもゴールに直接向かうボールの方が相手に脅威を生むという事も確かです。チームとしてトーレスの要求にどのように応えるのか、その答えは今週のトレーニングや試合の振り返りを終えて、清水戦で見せてくれるでしょう。
攻撃としては、トーレス、金崎の個人の力もあり、あと一歩というところまでは進めていました。しかしながら、ゴール前というセンシティブなエリアでは、磐田の守備強度も増しますので、ゴール前に近づけば近づくほど、より味方同士で感じ合ったり、約束事によって考える前に体が動くという事が必要です。そういう意味で行くと、今回のラストパスの精度と意思疎通が足りなかったのかなというのは感じました。小野や金崎、義希や福田もクロスを上げていますが、もう一歩の所で味方に合わない状態が続きました。実は、トーレスも、金崎も、ゴール前のポジションとしては、相手の最終ラインよりもマイナスの所でポジショニングをとっているのですが、それにも関わらず、クロスを上げる選手はキーパーと最終ラインの間をめがけて蹴っているケースが多くありました。ここは、約束事が段々と出来てくるでしょうから、試合を重ねるごとに改善していくポイントだと思います。問題は、それが今シーズンの終わりまでに間に合うか。昨年の新潟のように、終盤に驚異的なペースで連勝したけど、僅かに及ばなかったということにならないことを願うのみです。
■ 鳥栖のクロス



■ ハロー効果について
さて、みなさんは、ハロー効果という言葉はご存知でしょうか。目立ちやすい特徴に引きずられて他の特徴についての評価が歪められる現象のことです。今回、選手たちの評価に関して、ハロー効果が生まれやすいシーンが多かったと思います。
例えば、トーレスや金崎に関しては、過去の輝かしい実績がありますので、ポジティブハロー効果が生まれやすい状況にあります。実際、この試合でもボールキープとスルーパスや飛び出しからのシュートなどチャンスメイクに大きく貢献しましたが、その反面、相手を執拗に追うような守備強度で磐田のチャンスの芽をすべてつぶせるようなプレスを行ったわけではありませんし、ドリブルミスやパスミスなどのボールロストがなかったわけでもありません。そういった所に目をつぶって手放しで良い評価を与えてよいのかという公平な視点は持たなければなりません。
逆に、福田はネガティブハロー効果が生まれやすい状況にありまして、ゴール前でのチャンスの逸機やサイドでの1VS1でのクロスのミスなどが目立ってしまいましたが、彼の90分間走り抜ける事のできる運動量を基にした、スペースのカバーリング、セカンドボールの奪取、チャンスに対する顔の出し方は大きくチームに貢献しております。終盤のクロスミスというプレイだけを見てしまって、その試合全体で貢献度が低かったかのような評価をしてしまうと、それもまた適正な評価をしていないことになってしまいます。
サッカーは組織として取り組むものであります。そして、選手個々の評価は過去の実績や大きく目立つ場面だけで決まるわけではありません。もちろん、ゲームを決める事の出来るプレイは大きく評価されるべきではありますが、90分間の中においては様々なプレイがありますので、そのあたりを総合して評価しなければならないと思っています。そして、もし、ある選手がミスをしたとしても、個人だけが責任を負うのではなく、チームとして、組織として考えるべきであるということを認識して頂ければと思います。
なかなか勝ちきれない鳥栖ですが、トーレスが鳥栖に入って3試合目、金崎が鳥栖に入って2試合目、そろそろゴール決まってもいいんじゃない?と思っていますが果たしてどうでしょうか。清水には前節勝っているだけに、是非とも今節も勝って、シーズンダブルという形で8月反攻のスタートと行きたいですね。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
17:13
│Match Impression (2018)
2018年07月26日
2018 第17節 : サガン鳥栖 VS ベガルタ仙台(後編)
仙台戦のレビューです。今回はシステムが異なるチーム同士の対戦でしたので、局面において有利、不利が生まれやすい状態の試合が想定されたのですが、両チームともに、自分たちのスタイルは崩さないように相手の守備の仕組みを利用した攻撃をしっかりと模索しておりました。いつも通り鳥栖が試合中にシステムを変更したり、メンバーを可変に動かしたりするので、ボールや人の動きによって有利・不利となる局面が互いにめまぐるしく変わっていく状況下ではありましたが、鳥栖がホームでの戦いという点と、システム変更によって鳥栖がビルドアップの出口を確立していたという点において、最終的には鳥栖が攻めて仙台がカウンターを仕掛けるという展開になりました。
鳥栖のセットアップは、攻撃時には4-3-3、守備時には前からプレスをかける時には4-3-3、ミドルサードで構える時には4-4-2、押し込まれてリトリートした時には5-3-2という陣形でした。仙台のセットアップは、攻撃時にはウイングバックが大きく前進し、フォワードに近い位置でプレイしていたので、3-1-4-2のような形でしょうか。守備時には5-1-2-2でミドルサード付近からのプレスを慣行していましたが、ウイングバックがせり出すことによって鳥栖とのミスマッチを解消し、ボールの追い出しに成功しておりました。鳥栖にとっては、ボール回しが窮屈であるうえに、湘南に比べると仙台の方が比較的後ろに重心がありましたので、ウイングバックの裏というスペースも簡単には与えてくれず、攻撃的には小野のドリブルや池田のキープ、ロングボールのセカンドボール狙いという形に依存する格好となってしまいました。


鳥栖の序盤は4-3-3での守備で進めていたのですが、思うようにボールの追い込みが上手くいかずに取りどころを設定できず、ショートカウンターに繋げることが出来ませんでした。4-3-3は攻撃も詰まっていましたが、守備面でもウイークポイントをつかれておりまして、仙台がキーパーやアンカーを利用してフォワードのプレスを外すことに成功すると、鳥栖の中盤が4-3でのブロックにならざるを得ず、センターバックからウイングバックへ早い展開でスライドが追い付かずに、蜂須賀からダイレクトに縦へのパスを出されたり、蜂須賀が吉田を引きずり出すようなドリブルで鳥栖のセンターバックーサイドバック間を空けてそこに仙台のセカンドトップが飛び込むという攻撃を仕掛けられていました。今回はセンターバックーサイドバック間が空いてしまった時には、原川や福田がしっかりとカバーリングできていたため、決定的なピンチとはまでは至らなかったのですが、早い展開でボールをゴールライン近くまで運ばれるのは気持ちよいものではありません。守備を4-4-2にして、仙台最終ライン3人に対してフォワード2人と数的不利を生んだとしても、ウイングバックの攻撃に対する守備アクションを早めるという修正は良かったと思います。



このように、鳥栖にとっては仙台の陣形は
「自分たちの攻撃時にはミラーゲームのようにプレスを受ける」
「守備時にはミスマッチをつかれて3センターの脇をつかれて早い攻撃を受ける」
という決して自分たちの望むような展開とはなっておりませんでした。この状況を察知して、マッシモは前半途中から小野を下げたり、池田に代えて義希を入れたりしつつ、4-4-2システムへとシフトしていきました。結果的にはこの変更が奏功して段々とイニシアチブを握れるようになり、後半の猛攻に繋がったと思います。
前半と後半のシステムの違いによる成果ですが、前半の30分頃から、前からのプレスを少し抑えて、小野を下げてミドルサードから4-4-2で構えるようになり、また、後半に入って池田に代わって義希が入ると4-4-2でビルドアップを試みるようになりました。この変更が良かったのは、サイドハーフ(福田、義希)を高い位置にポジショニングさせてウイングバックをピン止めさせることができた事です。ウイングバックが上がれない仙台はサイドバック(藤田、吉田)にボールが入った時には仙台のセカンドトップがプレスに入る仕組みに変わりました。この鳥栖のシステム変更による仙台のファースト守備の変更によって、最終ラインの前にスペースを作ることができ、そのスペースを利用してフォワードがボールを受けたり、ドイスボランチ(高橋秀、原川)がボールを運べるようになりました。後半の方が鳥栖の攻撃が機能するようになったのは、ビルドアップにおけるパス回しのルートを確保することができたからということです。



実は、前半も4-3-3のまま少し形を変える事によってビルドアップがうまく行く仕組みも構築できていました。それは、ボランチの高橋秀が鳥栖の最終ライン(高橋祐の脇)におちてビルドアップを実施した時です。ミラーゲームのような形になって右サイドで詰まってしまって左サイドに展開したシーンですが、高橋秀が最終ラインに降りることによって、仙台のツートップのプレスに対してひとり余らせることができました。また、センターバックの脇でボールを受けたタイミングで、吉田と原川が高い位置でポジションを取ることにより、仙台のディフェンス陣が高橋秀にプレスをかけるのを躊躇させます。高橋秀はそのスペースを狙ってボールを運び、吉田にボールを預けてサイドの裏のスペースへ走り込みます。この状況を作ることによって、高橋秀が中野を引っ張り、原川は奥埜のポジショニングを引きさげて吉田が前を向いてボールを持つことに成功しました。その後は3人のパス交換で原川がスルーパスを出すチャンスまで演出しています。




この形は仙台のウイングバックのプレスでブレーキがかかっていた右サイドに比べると非常にスムーズにボールを運ぶことができていました。この形を繰り返すと面白いなと思っていたのですが、高橋秀がサイドに出て行ってしまうので、ネガティブトランジション時(攻から守への切り替え時)のリスクを考えると、前半でもありましたし、多用するのを躊躇したのかもしれません。
※ ちなみに、試合中にこのビルドアップの形についてツイートしたのですが、そのツイートが消えてしまっていました。どこに行ったのだろう?(笑) 観客が多くて通信状況が悪かったのかな。
前半から攻守ともに良くもないけど悪くもないという4-3-3ベースの戦いだったのですが、システムを4-4-2に切り替えた結果、試合のイニシアチブを握ることに成功しました。マッシモのこのシステム切り替えの判断としては非常に良かったと思います。(ただし前編で語っていますが、最後の選手交代で藤田を外して安在を投入した上での全体の配置変更は疑問が残るところではあります。)あとは得点を取るだけという状況だったのですが、その1点が本当に遠く、逆に仙台にショートカウンターから決められてしまうという、本当に残念な試合結果に終わりました。なお、失点シーンに関しては、前編に記載しているので本編ではふれません。
さて、今回の目玉は何と言ってもフェルナンド・トーレスですよね。トーレスのプレイの良かったところをまとめました。
1.スペース認知
トーレスのアシスト未遂やゴール未遂に終わったシーンは、上記で述べた、仙台の最終ラインのスペースが空きがちであるという事を察知したトーレスが、上手にそのスペースを使うプレイが絡んでいます。トーレスと言えばスルーパスに対して裏抜けしてゴールというシーンを想像してしまうのですが、裏に使えるスペースがあるかどうかというのは相手の陣形あっての事です。今回の仙台の守備組織では最終ラインの前のスペースを活用した方がより良いという戦術的思想が働いたのだと思います。




2.味方の位置の認知
トーレスが入って最初のボールアクションだったでしょうか。スローインを受けてバックヘッドで小野の下へパスを送ったシーンがありました。ゴール前の場面でも、ハイボールに対して早いタイミングのジャンプで相手を制して、バックヘッドで味方に送り込むというシーンがありました。(義希の飛び込みが僅かに及ばず得点には繋がりませんでしたが、コーナーキックのチャンスを得ました)。トーレスは自分のポジション、そして味方のポジションを常に把握しています。これが、自分も生きる、味方も生きるというプレイの大前提です。味方の認知ができているプレイヤーなので確実にチャンスメイクを遂行することができます。


3.シュートコースの認知
右サイド、左サイド、双方ともに1度ずつ見せてくれたのですが、ペナルティエリア付近でボールを受けた際に、カットインしてシュートというこのスピードが非常に速かったです。どちらもキーパーセーブやディフェンスのスライディングで入りはしなかったものの、確実にシュートというアクションを取れるのは非常に大きな武器です。ゴールのにおいは確実に充満しています。


改めて言う話でもないのですが、トーレスはまだコンディションが上がらない中でも十分にその実力の片鱗を見せてくれました。分かりきったことですが、鳥栖としての課題は、如何に良いクロスをトーレスに上げるかという所ですよね。それがかなえば豊田を囮にしてトーレスが決めたり、トーレスを囮にして豊田が決めたりという事もできるのですが、いかんせん、この試合でもクロスがトーレスまで行かずに手前でカットされるというシーンが多かったです。トーレスのストロングポイントを生かすためのプレイヤーという意味でも、金崎の加入は非常に大きいかもですね。
ここの所めまぐるしく環境が変わっているサガン鳥栖ですが、現実的には降格圏内にあえいでいます。次節ホーム磐田戦は、一戦必勝の構えで必ず勝ち点3を奪って欲しいと思います。
<画像引用元:DAZN>
鳥栖のセットアップは、攻撃時には4-3-3、守備時には前からプレスをかける時には4-3-3、ミドルサードで構える時には4-4-2、押し込まれてリトリートした時には5-3-2という陣形でした。仙台のセットアップは、攻撃時にはウイングバックが大きく前進し、フォワードに近い位置でプレイしていたので、3-1-4-2のような形でしょうか。守備時には5-1-2-2でミドルサード付近からのプレスを慣行していましたが、ウイングバックがせり出すことによって鳥栖とのミスマッチを解消し、ボールの追い出しに成功しておりました。鳥栖にとっては、ボール回しが窮屈であるうえに、湘南に比べると仙台の方が比較的後ろに重心がありましたので、ウイングバックの裏というスペースも簡単には与えてくれず、攻撃的には小野のドリブルや池田のキープ、ロングボールのセカンドボール狙いという形に依存する格好となってしまいました。


鳥栖の序盤は4-3-3での守備で進めていたのですが、思うようにボールの追い込みが上手くいかずに取りどころを設定できず、ショートカウンターに繋げることが出来ませんでした。4-3-3は攻撃も詰まっていましたが、守備面でもウイークポイントをつかれておりまして、仙台がキーパーやアンカーを利用してフォワードのプレスを外すことに成功すると、鳥栖の中盤が4-3でのブロックにならざるを得ず、センターバックからウイングバックへ早い展開でスライドが追い付かずに、蜂須賀からダイレクトに縦へのパスを出されたり、蜂須賀が吉田を引きずり出すようなドリブルで鳥栖のセンターバックーサイドバック間を空けてそこに仙台のセカンドトップが飛び込むという攻撃を仕掛けられていました。今回はセンターバックーサイドバック間が空いてしまった時には、原川や福田がしっかりとカバーリングできていたため、決定的なピンチとはまでは至らなかったのですが、早い展開でボールをゴールライン近くまで運ばれるのは気持ちよいものではありません。守備を4-4-2にして、仙台最終ライン3人に対してフォワード2人と数的不利を生んだとしても、ウイングバックの攻撃に対する守備アクションを早めるという修正は良かったと思います。



このように、鳥栖にとっては仙台の陣形は
「自分たちの攻撃時にはミラーゲームのようにプレスを受ける」
「守備時にはミスマッチをつかれて3センターの脇をつかれて早い攻撃を受ける」
という決して自分たちの望むような展開とはなっておりませんでした。この状況を察知して、マッシモは前半途中から小野を下げたり、池田に代えて義希を入れたりしつつ、4-4-2システムへとシフトしていきました。結果的にはこの変更が奏功して段々とイニシアチブを握れるようになり、後半の猛攻に繋がったと思います。
前半と後半のシステムの違いによる成果ですが、前半の30分頃から、前からのプレスを少し抑えて、小野を下げてミドルサードから4-4-2で構えるようになり、また、後半に入って池田に代わって義希が入ると4-4-2でビルドアップを試みるようになりました。この変更が良かったのは、サイドハーフ(福田、義希)を高い位置にポジショニングさせてウイングバックをピン止めさせることができた事です。ウイングバックが上がれない仙台はサイドバック(藤田、吉田)にボールが入った時には仙台のセカンドトップがプレスに入る仕組みに変わりました。この鳥栖のシステム変更による仙台のファースト守備の変更によって、最終ラインの前にスペースを作ることができ、そのスペースを利用してフォワードがボールを受けたり、ドイスボランチ(高橋秀、原川)がボールを運べるようになりました。後半の方が鳥栖の攻撃が機能するようになったのは、ビルドアップにおけるパス回しのルートを確保することができたからということです。



実は、前半も4-3-3のまま少し形を変える事によってビルドアップがうまく行く仕組みも構築できていました。それは、ボランチの高橋秀が鳥栖の最終ライン(高橋祐の脇)におちてビルドアップを実施した時です。ミラーゲームのような形になって右サイドで詰まってしまって左サイドに展開したシーンですが、高橋秀が最終ラインに降りることによって、仙台のツートップのプレスに対してひとり余らせることができました。また、センターバックの脇でボールを受けたタイミングで、吉田と原川が高い位置でポジションを取ることにより、仙台のディフェンス陣が高橋秀にプレスをかけるのを躊躇させます。高橋秀はそのスペースを狙ってボールを運び、吉田にボールを預けてサイドの裏のスペースへ走り込みます。この状況を作ることによって、高橋秀が中野を引っ張り、原川は奥埜のポジショニングを引きさげて吉田が前を向いてボールを持つことに成功しました。その後は3人のパス交換で原川がスルーパスを出すチャンスまで演出しています。




この形は仙台のウイングバックのプレスでブレーキがかかっていた右サイドに比べると非常にスムーズにボールを運ぶことができていました。この形を繰り返すと面白いなと思っていたのですが、高橋秀がサイドに出て行ってしまうので、ネガティブトランジション時(攻から守への切り替え時)のリスクを考えると、前半でもありましたし、多用するのを躊躇したのかもしれません。
※ ちなみに、試合中にこのビルドアップの形についてツイートしたのですが、そのツイートが消えてしまっていました。どこに行ったのだろう?(笑) 観客が多くて通信状況が悪かったのかな。
前半から攻守ともに良くもないけど悪くもないという4-3-3ベースの戦いだったのですが、システムを4-4-2に切り替えた結果、試合のイニシアチブを握ることに成功しました。マッシモのこのシステム切り替えの判断としては非常に良かったと思います。(ただし前編で語っていますが、最後の選手交代で藤田を外して安在を投入した上での全体の配置変更は疑問が残るところではあります。)あとは得点を取るだけという状況だったのですが、その1点が本当に遠く、逆に仙台にショートカウンターから決められてしまうという、本当に残念な試合結果に終わりました。なお、失点シーンに関しては、前編に記載しているので本編ではふれません。
さて、今回の目玉は何と言ってもフェルナンド・トーレスですよね。トーレスのプレイの良かったところをまとめました。
1.スペース認知
トーレスのアシスト未遂やゴール未遂に終わったシーンは、上記で述べた、仙台の最終ラインのスペースが空きがちであるという事を察知したトーレスが、上手にそのスペースを使うプレイが絡んでいます。トーレスと言えばスルーパスに対して裏抜けしてゴールというシーンを想像してしまうのですが、裏に使えるスペースがあるかどうかというのは相手の陣形あっての事です。今回の仙台の守備組織では最終ラインの前のスペースを活用した方がより良いという戦術的思想が働いたのだと思います。




2.味方の位置の認知
トーレスが入って最初のボールアクションだったでしょうか。スローインを受けてバックヘッドで小野の下へパスを送ったシーンがありました。ゴール前の場面でも、ハイボールに対して早いタイミングのジャンプで相手を制して、バックヘッドで味方に送り込むというシーンがありました。(義希の飛び込みが僅かに及ばず得点には繋がりませんでしたが、コーナーキックのチャンスを得ました)。トーレスは自分のポジション、そして味方のポジションを常に把握しています。これが、自分も生きる、味方も生きるというプレイの大前提です。味方の認知ができているプレイヤーなので確実にチャンスメイクを遂行することができます。


3.シュートコースの認知
右サイド、左サイド、双方ともに1度ずつ見せてくれたのですが、ペナルティエリア付近でボールを受けた際に、カットインしてシュートというこのスピードが非常に速かったです。どちらもキーパーセーブやディフェンスのスライディングで入りはしなかったものの、確実にシュートというアクションを取れるのは非常に大きな武器です。ゴールのにおいは確実に充満しています。


改めて言う話でもないのですが、トーレスはまだコンディションが上がらない中でも十分にその実力の片鱗を見せてくれました。分かりきったことですが、鳥栖としての課題は、如何に良いクロスをトーレスに上げるかという所ですよね。それがかなえば豊田を囮にしてトーレスが決めたり、トーレスを囮にして豊田が決めたりという事もできるのですが、いかんせん、この試合でもクロスがトーレスまで行かずに手前でカットされるというシーンが多かったです。トーレスのストロングポイントを生かすためのプレイヤーという意味でも、金崎の加入は非常に大きいかもですね。
ここの所めまぐるしく環境が変わっているサガン鳥栖ですが、現実的には降格圏内にあえいでいます。次節ホーム磐田戦は、一戦必勝の構えで必ず勝ち点3を奪って欲しいと思います。
<画像引用元:DAZN>
Posted by オオタニ at
12:29
│Match Impression (2018)






